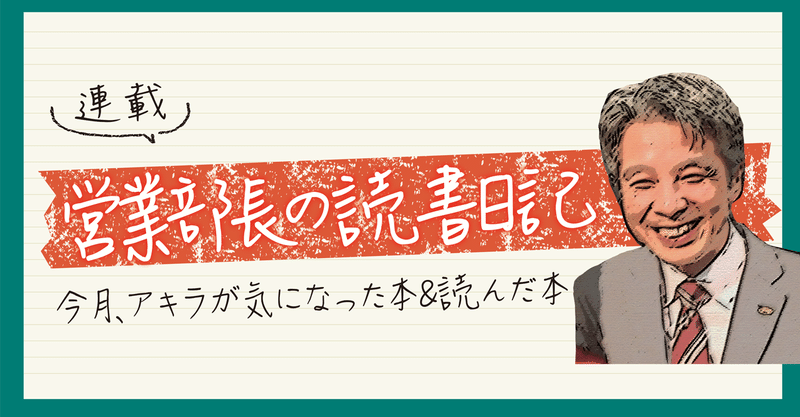
<第9回&10回・合併号>「聖地」巡礼に始まった2022年・読書の旅
2022年、気づけばもう2月中旬に。無事に新年改まり、「さてさて、今年はどうしようかな」と思っていたところ、おやおや、流行り病が再び猛威を振るい、いっこうに収まりそうもありません。「まん防」解除は3月に持ち越しだそうで、困ったものですね。とはいえ、2022年が未来へつながる希望に満ちた年になることを、心より願ってやみません。
思い返せば、年末の大掃除(結局、ちっともできませんでした)の合間に本棚からあれこれ引っ張り出し、そして大晦日、正月は幕の内も過ぎ、果ては1月いっぱいまで、なんやかや読み散らかしてしまいました。この読書日記(備忘録)も前回のアップから2カ月弱経ってしまい、まことに申し訳ありませんが、今回は合併号(!?)とさせてください。
北京五輪のスノボーの逆転金メダルに、素直に心が躍らされる今日このごろです。
≪この2カ月の購入リスト≫
『LISTEN~知性豊かで創造力がある人になれる』ケイト・マーフィ(日経BP社)
※1月20日、紀伊國屋書店あらおシティモール店(熊本県荒尾市)のプレオープン挨拶時に購入
『永守流~経営とお金の原則』永守重信(日本経済新聞出版)
※大垣書店イオンモール桂川店で購入
『京都かがみ』濱崎加奈子(MdN新書)
※2月5日、大垣書店イオンオール京都店で、裏千家・伊住禮次朗さんとの対談イベント参加時に購入
『千年の読書』三砂慶明(誠文堂新光社)
『これからの本屋』北田博充(書肆汽水域)
※ともに、梅田蔦屋書店で購入
『密約~外務省機密漏洩事件』澤地久枝(岩波現代文庫)
※丸善博多店にて、お勧めに応じて購入
フィルディナント・フォン・シーラッハ著『カールの降誕祭』(東京創元社)、『犯罪』『禁忌』(創元推理文庫)
※読書会参加のため、急ぎネット書店で購入
『哲学者・木田元~編集者が見た稀有な軌跡』大塚信一(作品社)
※ふたば書房京都駅八条口店にて購入
『読者はどこにいるのか 読者論入門』石原千秋(河出文庫)
※大垣書店ビブレ店で購入
■12月18日
『アースダイバー 神社編』⇒伊勢神宮の起源は、海民の聖地だったそう
お正月を迎えるので神社関連の勉強をしようと、本連載の初回に購入した中沢新一の『アースダイバー 神社編』(講談社)を繙きました。『週刊現代』に連載されていた「聖地」探索の試みで、読みやすいのですが、けっこう論旨の飛躍や牽強付会な点もあるようで、要注意。ただ、日本人の精神史の古層をはるか縄文時代から説き起こし、日本中あちこちを旅するものなので、やむを得ない移動制限のなかでは十分に楽しめます。家にいながら貴重な取材旅行に同行しているようなものです。
著者によると、人類最古の「聖地」は、いまから10万年ほど前の旧石器時代にまで遡ります。それは入り口が鬱蒼とした樹木に覆われた「洞窟」からだ、といいます。そこで人間の「祭儀」の萌芽が始まったとされます。なぜ暗い洞窟に、人類は哺乳類事始めの聖地を見いだしたのでしょうか。
ここで最新の脳の知見、科学的構造が説き明かされます。人間型サピエンスの始原は、脳と中枢神経を形づくるニューロン接続網の変化だと説く著者は、真っ暗な洞窟に長時間閉じこもることで、脳につながる視神経が内部から励起しはじめ、自ら光を放つように体験され(内部光学=entoptic)、それこそ「光あれ」の体験となり、さらには神の発見だと説きます。神の起源論の一つのようです。
同じく「洞窟」は、世界を生み出す「大いなる母」の体内だと見なされる、と続きますが、これはわかりやすい説明です。そこから、「聖地」は山中に存する「大岩(磐座・いわくら)」に移り、エルサレムの「岩のドーム」にまで地理的に飛躍します。アブラハムがヤハウェに対峙する以前から鎮座ましましていましたので、「岩のドーム」は旧石器時代からの由緒ある聖地となります。聖地構造の最下層を説きながら、このプロローグでは、突如として「人間の内なる聖地は滅ぼすことができない」と終えます。
中沢新一さんの不滅の内なる聖地とは、いったいどこにあるのでしょうか? それははるか遠く、チベット山中のどこかなのかな、と思いながら読み進めました。地球最高峰のエベレスト山頂8,848mは、いろんな意味で至上の聖地だと思います。現代では700~800万円で可能な民間山登りツアーもあるようですが、とても生命を懸けてまで登攀する気にはなれませんね。
以後、縄文、弥生の神道の系譜を探り、象徴的な文物やお祭りの伝承をたどりながら東北・秋田の鹿角から諏訪大社、出雲大社、三輪神社、対馬神道と日本列島を南下します。うっかり読んでいると、地図的・地理的に混乱してしまいそうです。
さらに、もう一度、信州・安曇野や九州・博多を往ったり来たりしながら、最後は海民系神社の系譜から、日本人は海人として自らの心象を形づくってきたと説き、自らの奥深くに眠っている海民の記憶を呼び覚ますべきだと説きます。そうして最後に、ようやく短いエピローグとして伊勢神宮に至ります。
著者は伊勢神宮を、大化の改新、壬申の乱後に、急速にヤマト王の権力が天皇家とその周辺に集中してきたことから、皇室の祖神であるアマテラス神をまつる国家神宮の必要性に応じて、地方豪族の渡会氏(起源は北九州の海民・磯部氏)の聖地を改変してできたものだと説きます。
これが国譲りの神話によって、古層の起源神話と新層(天孫降臨など王権神話による階層社会の定立)の建国神話へと結びつけた端緒だそうです(溝口睦子著『王権神話の二元構造~タカミムスヒとアマテラス』吉川弘文館、『アマテラスの誕生~―古代王権の源流を探る 』岩波新書)。内宮、外宮の二所権現も、もととも古来の聖なる力が現れる際の二元論としてあったものを改変したものだ、と説きます。
そもそもヤマト王権以前から、伊勢の渡会氏はいまの内宮、外宮の位置する2カ所で太陽神アマテラスを祀っていたが(世界の秩序と生命循環の二つの意味で)、中央集権政府の悲願で、天武天皇のころに内宮を皇室の聖地として祭祀権を得たといいます(その目論見は、早くも4世紀の崇神天皇のころから芽生えはじめていたそう)。
著者は最後に、「人間の心の構造に進化などが起こらないように、聖地にも過去とのつながりを断ち切った進化などは起こらないのである」と主張します。ふむふむ。
■12月26日
『夫婦善哉』ほか⇒関西の作家・織田作之助から映画監督・川島雄三へ
年末大掃除の際、ついつい読んでしまった小説について書きます。引っ張り出したのは、以下の4冊でした。
・織田作之助著『六白金星・可能性の文学』(岩波文庫)
・織田作之助著『夫婦善哉 正続 他十二篇』(岩波文庫)
・織田作之助著『猿飛佐助』(旺文社文庫)[『日本文学35 織田作之助』(ちくま文庫)]
・藤本義一著『鬼の詩/生きいそぎの記』(講談社文庫/河出文庫)
大阪・天王寺生まれの作家に織田作之助(1913~47年)がいます。坂口安吾、太宰治、石川敦、椎名麟三(『PHP』本誌・創刊初期の寄稿者の一人)、野間宏とともに「戦後無頼派」と呼ばれて久しいですが、織田作之助の活動は、戦後ではなく、戦前・戦中がほとんどでした。26歳ですでに『合駒富士』を『夕刊大阪』に連載していましたが、若くして亡くなっています(享年33歳)。
つい寝そべって年末の大掃除も進まず、『夫婦善哉』(九州・大分が舞台の続編が近年、発見されました)を読んで、『世相』や『アドバルーン』『競馬』から『猿飛佐助』、そして『可能性の文学』というエッセイまで、改めてたどり着きました。織田作之助の小説は、戯作者としての面目躍如、ストーリーテリングとして最高だと思いました。
エッセイの『可能性の文学』は、「坂田三吉が死んだ。」で始まります。自身、病を抱え(結核。二十歳で血を吐く)、つねに死を意識していたであろうことを微塵も感じさせず、ひたすら未来の文学への可能性に賭ける、織田作之助の気概を高らかに謳ったものでした。長く生きていればいったい、どんな小説を書いていたことでしょう。残念です、もっと読みたいものだと思いました。
織田作之助は二十歳前に両親を亡くし、さらに無二の親友や最初の妻を亡くし、死に抗うためだったのか、『可能性の文学』では、将棋棋士・坂田三吉(1870~1946年)の一世一代の大勝負で二局とも初手から端歩(はしふ)を突いて敗れるという、「青春」の生きざまに全面的に共感を表したものでした。
織田作之助による坂田三吉の紹介が傑作なので、長くなりますが、そのまま引用します。
***
坂田は無学文盲、棋譜も読めず、封じ手の字も書けず、師匠もなく、我流の一流をあみ出して、型に捉えられぬ関西将棋の中でも最も型破りの「坂田将棋」は天衣無縫の棋風として一世を風靡(ふうび)し、一時は大阪名人と自称したが、晩年は不遇であった。いや、無学文盲で将棋のほかには何にも判らず、世間づきあいも出来ず、他人の仲介がなくてはひとに会えず、住所を秘し、玄関の戸はあけたことがなく、孤独な将棋馬鹿であった坂田の一生には、随分横紙破りの茶目気もあったし、世間の人気もあったが、やはり悲劇の翳(かげ)がつきまとっていたのではなかろうか。中年まではひどく貧乏ぐらしであった。昔は将棋指しには一定の収入などなく、高利貸には責められ、米を買う金もなく、賭(かけ)将棋には負けて裸かになる。細君が二人の子供を連れて、母子心中の死場所を探しに行ったこともあった。この細君が後年息を引き取る時、亭主の坂田に「あんたも将棋指しなら、あんまり阿呆な将棋さしなはんなや」と言い残した。「よっしゃ、判った」と坂田は発奮して、関根名人を指込むくらいの将棋指しになり、大阪名人を自称したが、この名人自称問題がもつれて、坂田は対局を遠ざかった。が、昭和十二年、当時の花形棋師木村、花田両八段を相手に、六十八歳の坂田は十六年振りに対局をした。当時木村と花田は関根名人引退後の名人位獲得戦の首位と二位を占めていたから、この二人が坂田に負けると、名人位の鼎(かなえ)の軽重が問われる。それに東京棋師の面目も賭けられている、負けられぬ対局であったが、坂田にとっても十六年の沈黙の意味と「坂田将棋」の真価を世に問う、いわば坂田の生涯を賭けた一生一代の対局であった。昭和の大棋戦だと、主催者の読売新聞も宣伝した。ところが、坂田はこの対局で「阿呆な将棋をさして」負けたのである。角という大駒一枚落しても、大丈夫勝つ自信を持っていた坂田が、平手で二局とも惨敗したのである。
坂田の名文句として伝わる言葉に「銀が泣いている」というのがある。悪手として妙な所へ打たれた銀という駒銀が、進むに進めず、引くに引かれず、ああ悪い所へ打たれたと泣いている。銀が坂田の心になって泣いている。阿呆な手をさしたという心になって泣いている――というのである。将棋盤を人生と考え、将棋の駒を心にして来た坂田らしい言葉であり、無学文盲の坂田が吐いた名文句として、後世に残るものである。この一句には坂田でなければ言えないという個性的な影像があり、そして坂田という人の一生を宿命的に象徴しているともいえよう。苦労を掛けた糟糠の妻は「阿呆な将棋をさしなはんなや」という言葉を遺言にして死に、娘は男を作って駈落ちし、そして、一生一代の対局に「阿呆な将棋をさし」てしまった坂田三吉が後世に残したのは、結局この「銀が泣いてる」という一句だけであった。一時は将棋盤の八十一の桝も坂田には狭すぎる、といわれるほど天衣無縫の棋力を喧伝(けんでん)されていた坂田も、現在の棋界の標準では、六段か七段ぐらいの棋力しかなく、天才的棋師として後世に記憶される人とも思えない。わずかに「銀が泣いてる坂田は生きてる」ということになるのだろう。しかし、私は銀が泣いたことよりも、坂田が一生一代の対局でさした「阿呆な将棋」を坂田の傑作として、永く記憶したいのである。
坂田の端の歩突きは、いかに阿呆な手であったにしろ、常に横紙破りの将棋をさして来た坂田の青春の手であった。
***
このように坂田の姿と、当時、権勢を誇っていた文壇のオーソドックス(志賀直哉や小林秀雄)を否定し、乗り越えようとした自身の姿を重ね合わせた、感動的なエッセイでした。たぶん、埃まみれの『改造』(『可能性の文学』の初出誌)が横浜の自宅のどこかにあるはずですが(昔、古本市で購入しました)、ここではスケールが小さい美術工芸品のような私小説・心境小説を、次のように完璧に否定しきっています。
***
しかし、最近私は漸くこのオルソドックスに挑戦する覚悟がついた。挑戦のための挑戦ではない。私には「可能性の文学」が果して可能か、その追究をして行きたいのである。「可能性の文学」という明確な理論が私にあるわけではない。私はただ今後書いて行くだろう小説の可能性に関しては、一行の虚構も毛嫌いする日本の伝統的小説とはっきり訣別する必要があると思うのだ。
***
ちなみに、この破れかぶれのようなエッセイを書く直前、織田作之助は銀座のバー「ルパン」で(写真家・林忠彦の写真で有名な文壇スナック)、坂口安吾と太宰治と一緒だったそうです。さらに、その「ルパン」に向かう前には、すでに夕方から(?)酔っぱらってグダグダになった同じメンバー(坂口、太宰)と、評論家・平野謙が司会する実業之日本社主催の座談会に1時間遅れで出席しています。
当時、奈良に住む織田と太宰とは初顔合わせでした。翌年、太宰は織田の死後、激烈な追悼文を認めます。いわく、「織田君を殺したのは、お前じゃないか」(「織田君の死」)とありますが、これも戦後の時代に困惑した太宰の心境を現したもののようです。
この座談会では、しきりに太宰が未婚の坂口にからみ、乞食女と恋愛したいとか、妻を寝取られた話をしたがっていたという妙な対談でした(いまでは、その座談会の全文をネットでも読むことができます)。
この座談会については、織田作之助の通夜の晩に坂口安吾が認めた追悼文「織田の死」という2019年の新発見記事(『日経新聞』2月15日付け)もあります。
それは、終戦翌年の1946年11月22日のことでした。織田作之助は、翌12月に大量喀血し、現・東京慈恵会医科大学付属病院に入院、1月10日に死去しています。結局、この日に書かれた『可能性の文学』は、亡くなる直前の所信表明となりました。墓は大阪・天王寺の浄土宗・楞厳寺(りょうごんじ)に。何でもない一日だったのかもしれませんが、織田作之助にとっては未来へ繋がる一日だったのだと思います。
さて、織田作之助についての伝記小説は、同じ大阪・堺市生まれの作家・藤本義一の『わが織田作』4部作(中央公論社)がありました(残念ながら古本屋に処分したので、手許にはありません)。そこで、つい藤本義一で思い出したのが、映画監督・川島雄三との決定的な体験を描いた小説『生きいそぎの記』(河出文庫『鬼の詩/生きいそぎの記』所収)。日活で織田作之助の『わが町』(1956年)を映画化した監督です(未見)。
『生きいそぎの記』は、藤本義一が井伏鱒二原作の川島雄三監督作『貸間あり』(1959年/東宝映画)の脚本を書いていたころの話です。フランキー堺と淡路千景主演の、本当はずいぶん脚本に手間暇かけているのに、一見そうとは思わせない軽妙洒脱な映画。「サヨナラだけが人生だ」のラストで有名です。
そこで、どうしても観たくなって、『幕末太陽傳』(1957年/日活)をAmazonプライムで再視聴してしまいました。日本映画特有の流れる時間密度の濃い、まごうことなき傑作です。労咳を病み、明日をも知れぬ命のフランキー堺演じる「居残り左平次(落語の主人公)」の、性根が座りながらも飄々とした土壇場での人間味の強さや、最後には尻端折りで逃げ出す映画の主題「積極的逃避」というものが、いまなお新鮮に思えました。
映画の最後では、墓場から父親(?)に叱責されて逃げ出す左平次に、川島雄三は自身の出身地・青森<下北半島の恐山=死>からの逃避を重ね合わせたといいます。あり得たシナリオでは、フランキー堺の左平次は撮影当時の現代の街中を駆け抜けるシュールなラストシーンもあったそうで、興味深いです(「川島雄三」[森田信吾著『栄光なき天才たち 大合本2』ゴマブックス]所収)。
さらに脱線ついでに、川島雄三による漢詩意訳を次に載せます。
雑詩 其の一/陶淵明(とう えんめい)
人生無根蔕(にんげん ねもなくへたもない)
飄如陌上塵(みちにさまよう ちりあくた)
分散逐風轉(ときのながれに みをまかすだけ)
此己非常身(しょせん このみは つねならず)
落地成兄弟(おなじ このよにうまれりゃ きょうだい)
何必骨肉親(えにしは おやより ふかいのだ)
得歓当作楽(うれしいときには よろこんで)
斗酒聚比鄰(ともだち あつめて のもうじゃないか)
盛年不重來(わかいときは にどとはこない)
一日難再晨(あさが いちにち にどないように)
及時當勉励(いきてるうちが はなではないか)
歳月不待人(さいげつ ひとをまたないぜ)
となると、つい思い出すのは、次の有名な井伏鱒二の翻案です(『厄除け詩集』講談社文芸文庫)。
勧酒/于武陵(う ぶりょう)
勧君金屈巵(コノ サカヅキヲ 受ケテクレ)
満酌不須辞(ドウゾ ナミナミ ツガシテオクレ)
花発多風雨(ハナニ アラシノ タトヘモアルゾ)
人生足別離(「サヨナラ」ダケガ 人生ダ)
こんな調子で続けていると、ほんとうにキリがありませんね。ともあれ、コロナ禍が落ち着き、みんなで一日も早く心おきなく祝杯をあげることができる日を、心より願っています。
■1月3日
『平家物語』ほか⇒大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に誘われて、古典の森へ
年末に伊勢神宮の外宮、内宮その他にお参りし、年始は、伏見稲荷大社、石清水八幡宮に初詣をしました。神社仏閣を訪れると、つい悠久の歴史に思いを馳せてしまいます。これまた読み出すとキリがありません。
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」もあって、つい保元の乱から鎌倉時代末期まで、武士の時代についてあれこれ読み直し、果ては『証言・桜花特攻 人間爆弾と呼ばれて』(文藝春秋編/当事者の証言が胸に詰まりますが、巻頭の山岡荘八のルポルタージュが秀逸です)、「武士道裁判」(岩川隆著『神を信ぜず BC戦争犯の墓碑銘』[立風書房]所収)まで読んでしまいました。ほかにも小説や翻訳本やなんやかやを読んでいるのですが、ここでは武家台頭の時代についての備忘録にします。
武士の時代の端緒である保元の乱(1156年)は、私の現在の住居からほんの数㎞、丸太町通り先の鴨川辺で戦われたそう。いまの住居の場所も応仁の乱(1467~77年)初発の戦いでは、紅白合戦の中間にあたるようです。いやはや、かつての京都は戦乱の場だったのだなと改めて思いながら、結局、引っ張り出してしまったのは、次の書籍です。
・『木下順二集8「子午線の祀り」とその世界』(岩波書店)
・木下順二著『古典を読む 平家物語』(岩波書店同時代ライブラリー)
・嵐圭史著『知盛の声がきこえる』(ハヤカワ演劇文庫)
・數江教一著『日本の末法思想』(弘文堂)
※このほか、『新版 平家物語 全訳注』(講談社学術文庫)、『太平記』(岩波文庫)、『吾妻鏡』(角川文庫)に加えて、新たにお正月に、五味文彦著『鎌倉と京 武家執権と庶民世界』(講談社学術文庫)を大垣書店烏丸御池店で購入しました
まずは、『夕鶴』で著名な木下順二の『子午線の祀り』についてです。
じつは私、1999年に長男を身籠った家内と、野村萬斎(知盛)主演・観世栄夫演出の4時間あまりの舞台を新国立劇場に観に行きました。圧倒的なノーカット版です。
一の谷(1184年)から壇ノ浦(1185年)の合戦までの平家物語を題材にした舞台作品でした。平家物語は、日本の文学に「運命」の概念を主題として持ち込んだ先駆といわれます。「自分の明日の運命を知らず、あるいは多少の豫覚はあっても、なお戦い、傷つき、敗れればそれを運命と享受して“いまはかう”と死んでいく人々である」(村松剛著『死の日本文學史』中公文庫)。
たしかに『平家物語』は、日本人の哀歓を誘う古典です。平家を題材としたお能では、静謐な世阿弥作の『清経』を思い出します。秦恒平著『清経入水』(角川文庫)という小説もありました。
清経(1163~83年)は『子午線の祀り』では重要な役割ではありませんが、平清盛の孫であり、21歳の若さで平家都落ち後に大分・宇佐八幡宮のお膝元、柳ヶ浦で入水自殺しています。平家一門衰退の端緒だったと建礼門院はのちに語ります。『平家物語』では、壇ノ浦に至るまで自裁の記述は少ないのですが、これが『太平記』になると、親子兄弟差し違え、腹切り(切腹)ばかりとなります。凄惨ではありますが、ここまでくると、ある意味、爽快な死にざまに思えたりもします。とはいえ、これが江戸時代、昭和の戦中まで続く「武士道」として、生命を軽んじる思想に曲解されていくと思えば、危ういものです。
『子午線の祀り』の主人公は平相国(清盛)の四男、文武に優れた知盛(1152~85年)が主人公です。すぐ上の兄である優柔不断な棟梁・宗盛(1147~85年)を助け、最後には「見るべき程の事は見つ。今は自害せん」と、壇ノ浦の海に自ら鎧を重ね着して沈んだ西国一の武者です。この知盛に源平武士たち、影の内侍(清盛の弟で囚われの身の重衡の思い人)という魅力的な巫女をあてがい、阿波の民部重能という、これまた日本国にこだわらないスケールの大きい人物を絡めた脚本でした。また、ところどころで『平家物語』原文を朗読する、「群読」という新たな表現形式を背景にした壮大な舞台演劇でした。
なかなかに長大な本戯曲の要約は難しいのですが、日本における武家の台頭の先駆者である平家の没落とダイナミックな源平争乱を描いた見事な作品であることは、間違いありません。本書は、宇宙の「天の子午線」を通過する月の引力の記述を前後に置き、壇ノ浦の合戦の勝敗の分け目になった潮の満ち引きを想起させるところが、スケールが大きくてユニークです。
また、残念ながら佐殿(=源頼朝)は登場しませんが、義経(舞台では市川右近でした)の縦横無尽な活躍は楽しめます。
作者の木下順二は、上記『全集8』をはじめ、さまざまに本作品について語っているのですが、最初に戯曲を書き上げた直後の文章(『毎日新聞』1978年2月6日付け)では、あろうことか毛沢東が人民解放軍を率いて1949年に南京から国民党軍追い払った際の七言律詩(『毛主席詩詞墨跡』)を引き、「天若有情天亦老(天もし心あらば、天もまた老いん)」という句を紹介しています。
そこで、竹内実(中国文学&現代中国社会・研究者)の解釈では、「逃げ場なき敵を撃破し尽くせとはいかにも残酷で、天にもし情(こころ)あらば天も感傷のあまり老いこむだろうが、宴会や婦人の手芸ではない革命の遂行をためらうのは、天の法則=事物の変化の法則にそむくことだ。とあって、甚だ納得が行く」と書いています。う~ん。当時は、どうしても暴力革命を容認する傾向があるのは否めません。“敵は、すべからく殲滅すべし”というのは、現代ではナンセンスですね。
ところで、山崎正和著『鴎外 闘う家長』(新潮文庫)は、「日本人の劇的な生き方」を考える上で欠かせない一冊です。特に「Ⅲ勤勉なる傍観者」の章は、学生時代の初読から、いまだに気になってやみません。
***
「己は己だ」というこの自覚を表現するために、やがて弥一右衛門は主君の許しなく腹を切り、嫡子・権兵衛は主君の霊前で髻を切って出家する。足もとから崩れる運命に抵抗するのとは反対に、むしろそれをみずからの足で踏み崩すことによって、彼らは自己の存在を証明しようとする。こうして結局は一族全滅の道をたどった阿部家の顛末は悲惨だが、しかし、その悲惨さはあくまでも厳密な意味での悲劇とは無縁のものというほかはない。なぜなら、彼らはつねに迫って来る非運の先廻りをしているのであって、ある意味で、その非運のあり得べき大きさを徹底的に験(しる)したとはいえないからである。真に悲劇的な人間は目前の非運にどこまでも抵抗し、にもかかわらず、ついには力尽きることで逆に運命の大きさを身をもって証明する人間だということは、周知の定義であろう。
***
たとえ、どんな状況に陥ろうと、たとえ義がどこにあろうとも、「己は己だ」と最後の最後まで意志的に生き抜いた『子午線の祀り』の平知盛は、まさに悲劇的人間の嚆矢だと思います。感動させられました。
■1月16日
『往生要集』⇒日本のホラー文学の極致!?
続いて、和辻哲郎のお弟子さんである倫理学者・數江教一著『日本の末法思想』(1961年刊の古書です)に手を伸ばしてしまいました。漢文が随所にあって、つい高校の古文の授業を思い出して目が眩みます。とはいえ、頑張って読み進めると、ずいぶん勉強になり、面白いものでした。
鎌倉時代の慈円(1155~1225年)の『愚管抄』から始まり、日本の末法(法滅尽)思想の系譜を文献によりたどっています。難しいです。字面を追っていると眠くなります。授業でも読んだこともない、幾多の貴族日記(『小右記』『春記』『玉葉』などなど)が参照されます。
本書で今回、勉強になったと思えたのは、源信(恵心僧都/942~1017年)の『往生要集』(第五章:往生要集の罪責観)の説明でした。『源氏物語』の「宇治十帖」などで有名な比叡山・横川の僧都の著作についてです。
本書で、『往生要集』が浄土思想の始原だと理解できました。この書から日本全土を席巻する浄土教が始まったとも言えそうです。『往生要集』原書は、地獄の諸相(等活・黒縄・衆合・叫喚・大叫喚・焦熱・大焦熱・無間地獄。しかも、それぞれ眷属別処が用意されています)の描写から始まります。筆を尽くした圧巻のようで、とても怖くて読めそうもないです。おそらく日本のホラー文学の極致かもしれません。これが欣求浄土の前提なのであれば仕方ありませんが、極楽より地獄のほうが豊かな想像力を駆使できたというのは、現実を反映しているからでしょうか(出典があるにしても)。
当時はいまと違って(?)国家・行政組織の整わない平安、鎌倉時代であり、迫りくる天災人災になす術(すべ)がありませんでした。飢饉、地震、洪水、落雷、疾病、強盗、放火、殺人、南北無頼僧徒の横暴などなど、ついに貴族日記は諦観のあまり、記載する文章も殺伐とした事実の羅列のみとなります。挙げ句の果ては阿弥陀仏にすがり、いまわの際に五色の糸を仏さまと自身の指につないで極楽往生を願うに至る、というのも、心情的には理解できますが、どうなんでしょう。
当時の貴族たちが現状打破の気力が持てないまま、現世の欲望あらわな武家の台頭を許してしまったということになります。とはいえ、当時の貴族社会トップを牛耳る後白河法皇(「日本国第一の大天狗」信西)は、現世に執着した飽くなき思惑を持ち、さらに社会不安を増大させていたようです。まさに末法の乱世であり、浄土教の興隆も宣(むべ)なるかなです。いまだ本書の「選択本願念仏集」と「正法眼蔵」の記述に達していませんので、もうちょっと頑張って読んでみることにします。
■2月11日
『ドラッカー わが軌跡』『傍観者の時代』⇒直訳すると「Adventures of a Bystander=傍観者の冒険・探検・探索」ですが?
翻訳書のタイトルの付け方は難しいと思います。何でもありと言えばありなのですが、大事なタイトルなので、著者(編集者)の主張は明確にしたいと思います。
今回、最後に採り上げるのは、P・F・ドラッカー著/上田淳生訳『ドラッカー わが軌跡~知の巨人の秘められた交流』(ダイヤモンド社/2006年)です。自伝としてわかりやすいタイトルに魅かれ、ずいぶん昔に購入しました。著名人の自伝は、どれを読んでも学ぶところが多いものです(本当のところはさておき、出来事に対する受け止め方のいいケーススタディとなります)。
本書は2008年に、『傍観者の時代』(ドラッカー名著集12/ダイヤモンド社)とタイトルを変えて刊行されています。第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけての時代を指すという意味なら、本書の時代区分には合っていますが、「Adventures of a Bystander」を直訳すると「傍観者の冒険」ですから、改題タイトルとしては、ちょっと違うかなと思ってしまいます。勝手な一読者の感想ですが、『ドラッカー わが軌跡』のほうがまだしも内容に即していいように思えます。
では、なぜいま本書を引っ張り出したかと言えば、2月5日に丸善ジュンク堂のオンラインセミナーで弊社役員の講座を視聴し、そこで紹介されたからでした。講座のテーマは「渋沢栄一・稲盛和夫・ドラッカー~3人のビジネスカリスマと松下幸之助」(テキストは、渡邊佑介著『ドラッカーと松下幸之助』PHPビジネス新書でした)。
本講演で説かれたドラッカーと松下幸之助の共通点は、①物の見方として「現実を受け入れること、その本質・因果関係を考え抜く」、②人間観として「人間が中心である」、③経営観として「すべては経営である」とのこと。及ばずながらも努めたいものです。
ピーター・ファーディナンド・ドラッカーは、恵まれた生まれのユダヤ系オーストリア人経営学者です。少年時に育ったウィーン実家のサロンでは、経済学者シュンペーター、精神医学者(文学者)フロイトと面識をもち、かの偉大な音楽家アルトゥール・シュナーベルのピアノレッスンにも立ち会って、「教える」ということの奥義を成人前につかんでいます。すごいです。著名人に混じって、ドラッカーの愛すべき素敵なおばあさんの逸話が一緒に記載されるのも微笑ましいです。
ドラッカーはこれまで何冊か読んでいますが、その出自や、人生における「人との邂逅」を知ると感慨がいや増します。自らを「傍観者」と規定するのはどうなんだろうとも思いましたが、ただ見るだけではなく積極的に社会に発信し、大学では学生に教授してきたということは、ただの「傍観者」ではあり得なかったということでしょう。冒険者(探求者)の著作として、もう一度、いくつかを読み返してみたいと思いました。
さて弊社は、今年4月に『PHP』本誌が創刊75周年という記念すべき節目を迎えます(創刊号は1947年5月号)。会社としては昨秋(11月3日)、創業75周年を迎えており、京都に本社をもつ百年企業の仲間入りができるまで、四半世紀を切りました。
弊社の創設者・松下幸之助の最新刊は今月、『松下幸之助 日々のことば~生きる知恵・仕事のヒント』が装いを新たに刊行されます。ぜひ書店店頭で、お手に取ってご覧ください。いまに生きる、物事の本質を衝いた短い言葉の数々がまとめられています。
プロ野球広島カープの元監督・緒形孝市さんは、監督に就任されてから3連覇を果たす数年間、つねに本書を鞄に入れて持ち歩いたといいます。自身の野球観を明確に選手に示し、偉業を達成した原動力になったそうです。これを機会に、さらに多くの方の夢をかなえる必携の書となることを心より願います。
