
フィリピンのおすすめNPO・NGOインターン10選【留学の出口】
追記:2019年8月7日
2015年には年間約35,000人の日本人がやってきたというフィリピン留学。東京オリンピックを控え、その勢いは今後もしばらくおさまりそうにありません。そんなフィリピン留学を経てみなさんはどんなことに挑戦してみたいですか?
ここではワーホリや2カ国留学とともに関心を集める国際協力インターン、ボランティアをフィリピン国内で募集している10のNPO・NGOについてご紹介します。
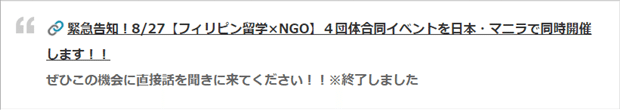

![]()

実はフィリピンは日本のNGO活動が特に盛んな国で、無数の団体が支援活動に励む様子から「NGO先進国」と呼ばれることもあります。
日本から直行便でわずか4時間程度という地理関係はもちろん、7,000を超える島々には今なお多くの問題が孕まれているため、多くの人々にとって協力の余地があります。
青年海外協力隊の国別累計派遣先でもフィリピンは第1位となっています。
目覚ましい経済成長を遂げるマニラ首都圏におけるスラム問題、ミンダナオ島の終わらない紛争、ルソン島北部山岳民族の若者の伝統離れなど地域によって違った問題を抱えているのがフィリピン。
最近では2013年に台風Yolandaがレイテ島に上陸し、沿岸部に壊滅的な被害をもたらしました。今日においても現地の復旧作業は終わっていません。話は戻りますが、そんなことからフィリピンでは多くの日本のNGOが活動しているのです。
NPO・NGO団体の定義は以下になります。

※ただし「主に」であって、国内・国内でその役割が分かれるわけではありません。
![]()


一人の会社員がフィリピンを旅する中で目にしたストリートチルドレンの惨状に対して「何かできないか」と、1994年に資金5万円でスタートしたのが認定NPO法人アイキャンです。旧名はアジア日本相互交流センター。
事業は多方面に及びますが、紛争や貧困など危機的状況下にある子どもたちに対して特に注力されています。ミンダナオ島の紛争に巻き込まれた子どもたちを、マニラでは路上生活を余儀なくされたストリートチルドレンに働きかけています。
現在では70名超の有給スタッフ、200名のボランティアという大所帯で活動しており、フィリピン以外にもイエメンやジブチなど紛争地で被害を受けた子どもたちのケア、技術訓練などに励んでいます。


創始者で代表の横田宗氏が高校3年のときにフィリピン・ピナトゥボ火山噴火によって被災した子どもたちの孤児院に訪問したことがきっかけで活動がスタートしました。「こども達が持っている可能性を発揮できる社会づくり」を目的にかかげ、ストリートチルドレン支援、盲聾学校サポートをしています。


日本を含むアジア各地での「農を軸にした地域自立」実現に向けて活動しています。主な事業地は西ネグロス州、ヌエバビスカヤ州、イサベラ州。現在はインドネシアや東ティモールにもパートナー関係を構築し、アジアの農家同士の交流も図っています。

「日本人とフィリピン人が国境を越えて協同し、環境保全活動を通して友情を育てていくこと」をビジョンに、マングローブの植林活動を展開しています。主な事業地はバコロドのある西ネグロス州、ボホール島ウバイと比較的日本からは馴染みの薄い場所で行われています。


「すべての人々がさまざまな違いを乗り越えて共存し、地球上のあらゆる生命の基盤を守り育てようとする世界」の実現を目指し、1961年に設立されたオイスカ・インターナショナルは現在34の国・地域で活動している国際NGO団体です。
フィリピンではヌエバビスカヤ州の植林、北カマリネス州のマングローブ林再生支援、パナイ島の森林再生と生活向上、西ネグロス州のシルク産業振興、レイテ島沿岸部の海岸林再生など多様な活動を展開しています。


人間活動によって引き起こされる環境問題の解決、そして持続可能な社会の実現のために尽力している団体です。フィリピンにおける日本の大型開発事業の環境・社会・人権について、現地住民・NGOとともに調査・提言活動をしています。


ルソン島北バギオを拠点に活動する環境NGO団体。今なお先住民族が伝統的暮らしを営むコーディリエラ地方で環境教育や植林活動、さらには現地農家の生活向上のためコーヒー栽培も指導しています。現地に20年在住する反町眞理子氏が代表として指揮。
2011年には「親子で滞在できる空間」をコンセプトにTALAシェア&ゲストハウスもCGNの協力のもとオープン。


国際協力分野で活躍できる人材を養成するため、実務研修と学術研究の機会を創出しています。フィリピンではヌエバビスカヤ州にて「環境にやさしい暮らしを継続する」ことを目標に、有機・減農薬野菜を販売し、農民の生計向上と環境保全の両立を目指したプロジェクトを実施。
「Vizcaya Fresh!」では農産物の販売・ブランディングにも取り組み、環境・農民・消費者ら全者が満足できる体制を構築しました。


マニラ首都圏のケソン市パヤタス地区でのスタディツアーで出会った二人の女性をきっかけに1995年に設立された団体。ゴミ拾いをして生計をたてる子どもや貧困の連鎖を目の当たりにする中で根深い貧困構造に対する理解、学校や地域で活躍できる人材育成の必要性を感じ、啓発・研修事業をしています。


日本とフィリピン間の人々の交流を促進するNGO団体です。単に「もたらす」「助ける」のではなく、「共に学ぶ」ということをコンセプトにワークキャンプや環境活動など多方面で地域・コミュニティに貢献しています。



言葉の方が先行して、実はどんなことをしているのかよくわからないということも多い「国際協力」。その実は地道で、決して楽なことはありません。しかし、人々が直面する困難を共に克服し、人や地域に貢献することにやりがい・生きがいを見つけられることも少なくはないでしょう。
「何をすればいいのかわからない」「どうしたら幸せになれるだろう」先のことを考えては、出口の見えない不安に自分を迷子にする人々。今いる場所と自分への執着からちょっと離れて、誰かのために尽力してみませんか?
人の役に立つことで自分を認められる。幸せや喜びのヒントはそんな「つながり」や「貢献」から見つかるかもしれません。
PHILPORTAL編集部
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
