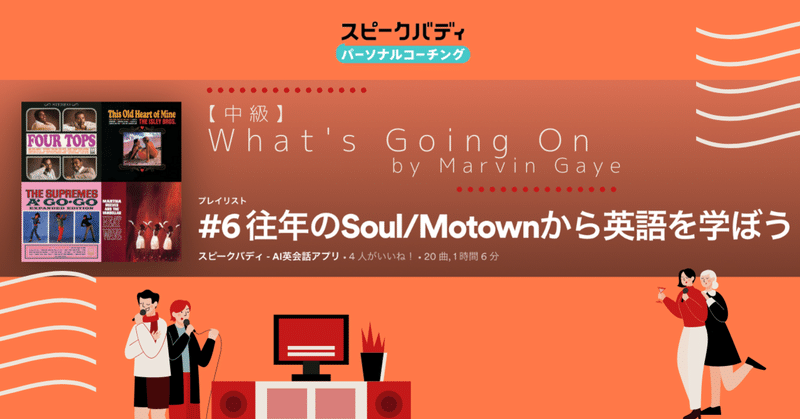
スピークバディの「音楽から英語を学ぼう」Soul/Motown編 【中級】What's Going On (by Marvin Gaye)
みなさん、こんにちは!
オンライン英語コーチング「スピークバディ パーソナルコーチング」のコーチ、Motohiroです!
今回は「音楽から英語を学ぼう!」のプレイリスト第6弾「往年のSoul/Motownから英語を学ぼう」のご紹介と、その中から What's Going On を紹介していきますよ!
・プレイリスト「往年のSoul/Motownから英語を学ぼう」について
まず今回のプレイリスト「往年のSoul/Motownから英語を学ぼう」についてご紹介させていただきます。
これは1960年代から70年代までのアメリカにおけるソウル音楽、そしてモータウン・レコーズ(アメリカ・デトロイトを本拠地としたレコード会社)が輩出した音楽の中から代表的な20曲を選んでまとめたものになります。当時は黒人音楽と言われたりもしていましたが、アメリカの黒人文化が作り上げた、音楽史の中でもとてもエモーショナルで深みのあるジャンルとして、今なお人々の心に根付いているのです。
・絶大な影響力を誇ったモータウン・サウンド
Diana Ross & The Supremes(ダイアナ・ロス&スプリームス)や The Four Tops(フォー・トップス)、The Isley Brothers(アイズレー・ブラザーズ)を始めとした、今回のプレイリストの前半を占めているモータウン・レコーズのサウンドは、比較的アップテンポかつキャッチーなポップ音楽が主体を成しています。
このモータウン・サウンドは60年代のロック音楽の誕生にも大きく関与しており、The Beatles(ビートルズ)や The Who(ザ・フー)といったロックの礎を築いたバンドが、初期に度々モータウンの楽曲をカバーして演奏していたことからも、それをうかがうことができるのではないでしょうか。
・時代を反映したよりシリアスなソウル・サウンド
そんなモータウンの中からも、幼い頃から天才と謳われた Stevie Wonder(スティービー・ワンダー)や看板スターの Marvin Gaye(マーヴィン・ゲイ)らは、1970年代に入るあたりから、より時代に対するダイレクトな思いを聴衆に訴えかけるような、シリアスな曲作りに入っていきます。
1960年代から1970年代のアメリカはアフリカ系アメリカ人公民権運動やベトナム戦争などの時代背景から、とても大きな時代のうねりの中にありました。そしてその時代に生まれた音楽も、必然的にその背景を色濃く反映させているものが多く目立ちます。
1950年代から活躍したソウル音楽の原点とも言える Sam Cooke(サム・クック)が、1963年に作った「A Change Is Gonna Come」がアフリカ系アメリカ人公民権運動の象徴であるように、ベトナム戦争の真っ只中である1971年に Marvin Gaye が作った「What's Going On」は、ソウル音楽としての代表作であることはもちろん、近代音楽史の中でも最も重要だと言われてさえいます。
そして今回は、その Marvin Gaye の代表曲「What's Going On」をご紹介していこうと思います。
⦅楽曲の背景⦆
まず簡単に Marvin Gaye についてお話ししましょう。1939年にアメリカのワシントンD.C.で生まれた彼は、1960年にモータウン・レコーズの本拠地であるデトロイトに移住し、モータウン・レコーズ創業者から才能を見初められたことからプロの歌手としてキャリアをスタートさせます。
・Marvin Gaye のモータウンでの成功、そして方向転換
モータウン・レコーズとの契約以降、最初はくすぶる期間があったものの、62年あたりからヒットを生むようになり、64年には「How Sweet It Is (To Be Loved By You)」、67年には「Ain't No Mountain High Enough」といったヒット曲で彼の人気は確固たるものとなっていきます。そして68年には「I Heard It Through The Grapevine」で初の全米1位を獲得するまでに至るのです。
しかし、レーベルの操り人形のように使われていると感じ始めた Marvin Gaye は、この成功を手放しで喜ぶことができず、また、自身の離婚や盟友の死などを受けて精神的にもかなりの低迷時期があったため、一旦音楽から少し距離を取るようになります。
・世紀の傑作「What's Going On」誕生
そして1970年、ベトナム戦争への反戦デモが繰り返される最中、警察によるデモ参加市民への残酷な暴行を目の当たりにしたことをきっかけに、Marvin Gaye は再び音楽の世界に戻ってきます。ベトナム戦争に駆り出された自身の弟が無事帰国できたタイミングであったことも重なり、もともと提案された曲に、彼自身もさらに歌詞とメロディを書き加え完成されたこの「What's Going On」は、あまりにも政治色が強すぎるということから、モータウンから即座に却下されてしまいます。
しかし、彼は「僕は音楽で戦うんだ」と意を確かに、会社に対してこの曲がリリースされるまでは一切新しい楽曲の作成はしない、というストライキを起こします。そしてついに71年にリリースされることとなったこの曲は、最終的にはR&Bチャートで1位を獲得し、全米でも2位を獲得するという成功を収めるのです。
・史上最も偉大なアルバム「What's Going On」
楽曲のリリースを受けて Marvin Gaye は同名のアルバム制作にも取り掛かりました。今までのモータウン・レコーズのアルバム制作過程とは一切異なる、レーベル初の自主制作というスタイルで作られたこの作品は、環境問題へのメッセージを歌う「Mercy Mercy Me (The Ecology)」や、貧困問題に焦点を当てた「Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)」といった楽曲を含むプロテスト・アルバムとしてリリースされました。
アルバムは全米6位を獲得し、1年以上にも渡ってチャート入りする快挙を成し遂げましたが、後年になってその評価はさらに盤石なものとなり、楽曲「What's Going On」は米ローリング・ストーン誌が選ぶ「史上最も偉大な楽曲500選」で第4位に、アルバム「What's Going On」は同誌が選ぶ「史上最も偉大なアルバム500選(2020年最新版)」で The Beatles の「Sgt. Pepper's Lonely Heart Club」や The Beach Boys(ビーチ・ボーイズ)の「Pet Sounds」を差し置いて堂々の第1位に選出されています。
それでは、そんな偉大なこの曲がどういったことを歌っているのか、早速歌詞を見ていきましょう。
⦅歌詞と和訳⦆
Mother, mother
(母よ、母よ)
There's too many of you crying
(泣いているあなたたちが多すぎるよ)
Brother, brother, brother
(兄弟よ、兄弟よ)
There's far too many of you dying
(死んでいくお前たちがあまりにも多すぎる)
You know we've got to find a way
(どうにかしないといけないのがわかるだろ)
To bring some loving here today, yeah
(今日ここに愛をもたらすためにね)
Father, father
(父よ、父よ)
We don't need to escalate
(激化させる必要なんてないんだよ)
You see, war is not the answer
(わかるだろ、戦争は答えなんかじゃないんだ)
For only love can conquer hate
(愛だけが憎しみに打ち勝つことができるんだから)
You know we've got to find a way
(どうにかしないといけないのがわかるだろ)
To bring some loving here today, oh
(今日ここに愛をもたらすためにね)
[Chorus]
Picket lines (Sister) and picket signs (Sister)
(デモの監視線(姉妹よ)そしてプラカード(姉妹よ))
Don't punish me (Sister) with brutality (Sister)
(僕を罰しないで(姉妹よ)暴力をやめて(姉妹よ))
Talk to me (Sister), so you can see (Sister)
(話してごらん(姉妹よ)そうすればわかる(姉妹よ))
Oh, what's going on
(ああ、何が起きているんだ)
What's going on
(どうしたっていうんだ)
Yeah, what's going on
(何が起きているんだ)
Oh, what's going on
(どうしたっていうんだ)
Mother, mother
(母よ、母よ)
Everybody thinks we're wrong
(みんな僕らが間違っていると思っているんだ)
Oh, but who are they to judge us
(でも誰が僕らを批判できるというんだ)
Simply 'cause our hair is long?
(単に僕らの髪が長いからって)
Oh, you know we've got to find a way
(どうにかしないといけないのがわかるだろ)
To bring some understanding here today, oh-oh
(今日ここに愛をもたらすためにね)
[Chorus]
Picket lines (Brother) and picket signs (Brother)
(デモの監視線(兄弟よ)そしてプラカード(兄弟よ))
Don't punish me (Brother) with brutality (Brother)
(僕を罰しないで(兄弟よ)暴力をやめて(兄弟よ))
Come on, talk to me (Brother), so you can see (Brother)
(話してごらん(兄弟よ)そうすればわかる(兄弟よ))
Oh, what's going on
(ああ、何が起きているんだ)
Yeah, what's going on
(どうしたっていうんだよ)
Tell me what's going on
(何が起きているのか教えてくれ)
I'll tell you what's going on
(そうしたら何が起きているのか教えてやるから)
(Music & Lyrics by Marvin Gaye, Al Cleveland & Renaldo "Obie" Benson)
⦅英語のポイント⦆
なぜ争わなければいけないのか、世の不条理さを嘆き「なぜこうなってしまったんだ、どうにかしないと世の中がダメになってしまうよ」と歌うこの曲、歌詞の内容と比較するとだいぶ明るい、キャッチーなメロディに乗って軽やかに歌われています。
歌詞の英語は難しい文法や表現は少ないのではないかと思います。今回は英語のポイントを2つピックアップしました。
(1)接続詞で使われる for
For only love can conquer hate. という文章は For から始まりその後に主語、動詞が続いていますが、普段よく目にする for は前置詞として名詞表現の前に置かれることがほとんどですよね。ここで使われている for は「というのは〜だから」という意味の接続詞として使われています。
このように聞くと「because とどう違うの?」と思われる方もいるかもしれませんが、この for は and や but のような等位接続詞というもので、前後の文が対等な関係として使われます。because は従位接続詞と言われ、主文に because 以下が従位節としてかかっているので、主文と従位節が対等ではないという関係になるのです。なので場合によっては And 〜 や But 〜 のように、この For から文章を始めることができるんですね。
今回の文は前文と対等に接続されており、You see, war is not the answer. For only love can conquer hate.(わかるだろ、戦争は答えなんかじゃないよ。というのも愛だけが憎しみに打ち勝つことができるんだから。)という意味になるわけですね。
(2)who are they to judge us
これは疑問文 who are they に to不定詞が続いている文ですが、要は「be動詞 + to不定詞」という用法です。この用法は以下に示す5つの意味があるとされています。
① 可能:「〜できる」 can と置き換えると成り立つ意味合い
② 義務:「〜すべきだ」 should と置き換えると成り立つ意味合い
③ 予定:「〜する予定だ」 be going to とすると成り立つ意味合い
④ 意図:「〜するつもりだ」 will と置き換えると成り立つ意味合い
⑤ 運命:「〜することになっている」 be supposed to とすると成り立つ意味合い
しかし、今回の文では they を主語に据えている限り、どれもしっくりこないのでは、と思われるかもしれません。この they というのは複数形の代名詞になりますので、単数で言うところの it に相当しますね。これは誰かを特定して言っているものではないこともあるため、今回もそれが当てはまると思います。1人に限らず複数の人を想定しているときに、便宜的に置いている代名詞主語というところでしょうか。なので、この文では they を取ってしまって who are to judge us. と考えてみるとわかりやすいのではないかと思います。今回は「誰が僕らを批判できるというんだ」という①の意味合いが反映されていると考えることができるのではないでしょうか。
ちなみにこの文の後ろには Simply 'cause our hair is long? が先程の従位接続詞としてくっついていますね。これは「僕らの髪が長いからという理由だけで」という意味になります。この髪の長さが意味するのは当時ベトナム戦争に反対していた人々は長髪のヒッピーが多かった、という背景からきているものと考えられます。なので「ヒッピーだという理由だけで批判されるのはおかしい!」ということを言っていると解釈できますね。
さて、いかがでしたでしょうか。今回の楽曲が誕生するきっかけとなった一般市民への、特に黒人に向けられた警察の残酷な暴行は、この曲が作られてから50年以上経った現在のアメリカでも今だに頻繁に起きている、根深く残っている大きな社会問題です。
2020年においてこの楽曲を主体とするアルバムが「史上最も偉大なアルバム」と位置づけられた背景には、人種差別を含めた様々な社会問題への解決策を今一度考えてほしい、という思いが強まっていることの表れなのかもしれませんね。
次回は、プレイリストの第7弾「60年代ROCK/POPから英語を学ぼう」を紹介しますよ!
今後も続々と新しいプレイリストの紹介とその中の楽曲についての解説もしていきますので、ぜひお楽しみに!
【関連記事はこちらのマガジンに↓】
--------------------
「続けるため」のオンライン英語コーチング
スピークバディ パーソナルコーチング
https://speakbuddy-personalcoaching.com/
━━━━━━━━━━
■無料カウンセリングお申込みはこちら
https://speakbuddy-personalcoaching.com/counseling
■Twitter
https://twitter.com/SBpersonalcoach
■AI英会話スピークバディ(アプリ)
https://www.speakbuddy.me/
━━━━━━━━━━
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
