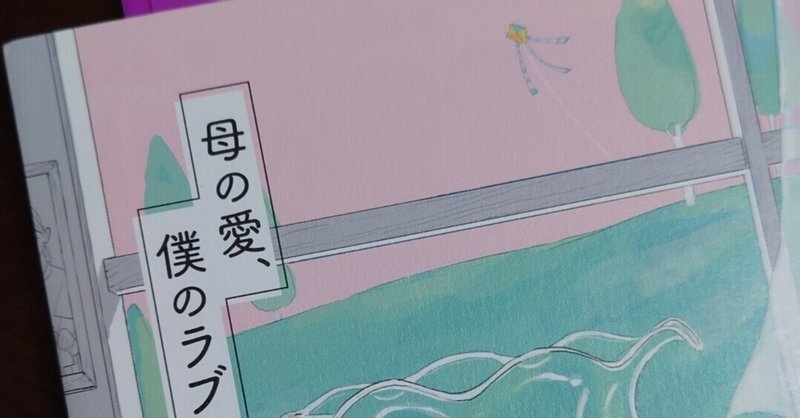
柴田葵「母の愛、僕のラブ」を読む
タイトルが強烈で、一度聞いたら二度と忘れない。「母の愛」はものすごい正しさを秘めていて、それに対する「僕」はきっと同じ愛を持たない。「僕」が抱くのは「ラブ」、それは「母の愛」ほど正しくも美しくもないかもしれないけど、「僕」になくてはならないもの。そんな主体の決意めいたものを、このタイトルから感じた。
恋人はふたりで勝てばいいと言う プリキュア我らはきっとプリキュア
連作「ぺらぺらなおでん」より。恋人が「ひとりで勝とうとしなくていい」と言ってくれる心強さは、戦友のようでもある。主体も同じように思っているからこその下の句である。プリキュアはいつもふたりで(みんなで)勝つ。しかも、正々堂々、肉弾戦で。
プリキュアになるならわたしはキュアおでん 熱いハートのキュアおでんだよ
帯にも載ってるしこの歌集で最も有名な歌だと思うけど引かざるを得ないパワーのある歌。「熱いハートのキュアおでん!」って口に出したくなっちゃう。相方は「冷静沈着キュア冷や汁!」だろうか。もし設定があるなら教えてほしい。
おでん しかも大根として生きてゆく わたしはわたしの熱源になる
おでんの大根は花形ではない。煮すぎれば出汁に溶けてぐずぐずになってしまう。でも大根のないおでんは少しあたたかみに欠けているようでさみしい。そんな「誰かをあたためる」大根ではなく、「自分自身をあたためる」大根になるという主体の強さに憧れる。
捨てられたバケツなみなみ雨を飲みわたしはそれを見て満たされる
連作「不在通知」より。「なみなみ雨を飲み」のリズムが楽しい。捨てられたバケツと自分を重ねているのか、「おまえもそうやって満たされるなら、わたしも」と思う主体の切実さが迫る。
カロリーメイトメイトが欲しい雨あがり駅のホームでほろほろ食めば
こちらもよく引用される歌だ。カロリーメイトを食べる時、だいたいひとりぼっちだということに気づかされたゆえの面白さだろうか。「ほろほろ」という言葉は涙があふれる時にも使われるから、余計にひとりぼっちのさみしさがある。でもたとえカロリーメイトメイトがいたとしても、特に盛り上がらず黙って一本食べきっちゃうんだろうな。
きみは私の新年だから会うたびに心のなかでほら、餅が降る
連作「冬と進化」より。「きみは私の新年」!すごいいいたとえ!!めでたくてあかるくてうれしくてたのしくて、全身がふわふわするかんじがめっちゃ伝わってくる。わたしも今度からすきなひとに「きみは私の新年」って言いたい。
海は必ず海だからいい目を閉じて耳を閉じても海だとわかる
わたしは永遠に海を見ていられる人間なんだけど、それって視覚や聴覚を失ったとしても存在を認識できる安心感ゆえのことなのかな、とこの歌を読んで気がついた。この連作の海は冬の海、夏とおなじにおいの海。
まぼろしをまたほろぼして 進化して 鳥にも草にも戻れずわれら
「まぼろし」と「ほろぼし」のリズムがいい。二つの一字空けも読むリズムを邪魔せず存在している。進化することはポジティブなように見えて、不必要な部分を削ぎ落とすことでもある。削ぎ落としたものは元には戻らない、というかなしさと、前半のひらがなの可愛らしさのコントラストが印象に残る。
「動く歩道は動いたらだめ。考えて、コンベアーから落ちるってこと」
連作「より良い世界」より。大阪の人は動く歩道上を歩くからみんな積極的にコンベアーから落ちてるなあ、と想像したところで、コンベアーから落ちることはそんなに悪いことなのかな?という疑問がふと浮かんだ。「落ちる」わけだからそりゃ痛かったり怖かったりはするけども、コンベアーって決められたルートにしか乗せていってもらえないから、そこから外れてしまうことは必ずしも悪いことではないはずだ。とすればこの発言の主は、決められたルートしか歩ませないように、コンベアーから落ちる恐怖を説いていることになるわけで、型通りの人間を量産することで「より良い世界」にしようとしているのだとしたら、恐ろしい歌だなあと思った。
目を閉じてボールを握る想像をしてみてそれが父さんの愛
いわゆる「休みの日にキャッチボールをしてくれるお父さん」像なんだ、いいなあと思って付箋を貼った歌だけど、上の歌の解釈に気づいた今読み返すと「そういう父親像を望め」「そういう父親たれ」と押し付けてくる存在を感じてぞっとする。そういう父親こそが「より良い世界」に必要だと誰かに決めつけられているとしたら、そんな恐ろしいことってないよな。キャッチボールが苦手なお父さんも、料理が嫌いなお母さんも、外遊びが得意じゃない子どももいるはずなのに。
マーガリンも含めてバターと言うじゃんか、みたいに私を恋人と言う
連作「さよなら」より。それはいい意味でか悪い意味でかと言えば、この連作を通して読むにあんまりいい意味じゃないんだろうな……つらい……マーガリンはバターじゃないし、恋人だったら何もない海じゃなくてちゃんと水族館に連れてってくれるだろう。でも相手にとって一緒にいる意味が少しでもあるんなら、「私」にとってそれでじゅうぶん、っていう、胸の奥を捩じ切られそうな痛さを感じてつらい。この連作を通してずっとそんなかんじ。
生きている元気な母よもう一度いっしょに夏のドリルを解いて
連作「七月のひとり」より。こちらの連作は一転ノスタルジーにあふれていて、こんなの全部泣いちゃうよ。母が元気で生きていたら他にもやりたいこといっぱいあるはずなのに、主体は夏のドリルをいっしょに解きたいんだね。新しいことをするのではなく、ただ過去をもう一度なぞりたい。「なんでもうちょっと早く始めなかったの!」って小言を言われながら、それでも終わるまでそばにいてくれた一日があるんだね。こういう歌を読んだとき、どうしても今は母側にも感情移入してしまって、涙が止まらなくなっちゃう。
「あかるいね、性格」「まあね(本当は自分をちぎって燃しているだけ)」
連作「強いとんび」より。中高生のぴんと糸を張った状態で生活しているような緊張感は、普段そばで見ててハラハラする。誰ともトラブルにならないように上手く明るく立ち回っている子は結構いて、そういう子たちは「自分をちぎって燃しているだけ」なんだろう。それが苦にならなければいいんだけどなあ、と思いながら、大人は見てるしかできないんだけども。
しんだら嫌、しあわせにならなきゃ嫌、ずっと器のままでいようか
連作「カレンダーを繰る」より。妊娠中がテーマの連作と思われるので、やっぱり自分と重ねてしまって涙なしには読み進められない。この世界に生み落としてしまうことの恐怖は、わたしも確かに感じていたからだ。人と比べてしんどさは少なかった妊娠期間だったから余計に、「このままずっとお腹にいれば、この世のしんどいことに触れさせずにいられるだろうか」と思ったこともあった。だって生まれたら死ぬ。嫌な思いだってする。生まれてこなきゃよかったと思うこともあるかもしれない。とてもとても自己中心的な考え方だったと今なら分かるけどもね。
産まれたらなんと呼ぼうか春の日にきみはきっぱり別人になれ
でもやっぱり、産んだら上のような考えはまったく思わなくなってしまったな。今はもう「自分とは別人であること」の驚きと楽しさをこどもたちから日々感じている。
僕らはママの健全なスヌーピーできるだけ死なないから撫でて
【戦争にいかせたくない わたし自身が戦争になってもこの子だけは】
連作「母の愛、僕のラブ」より。ひりひりする連作だ。「母の愛」と「僕のラブ」がこんなにも違ってしまっていて読んでいて苦しいくらいなのに、それでも目を離せない。栞文にもあったが、ものすごく作り込まれている、読まれることを1首目から最後まで意識し続けている連作だと感じた。それでいて、作りもののような嘘っぽさがない。自分が母であり、子であるから余計にそう思うのかもしれない。この作り込みは連作を通して読まないとじゅうぶんには感じられないと思うので、ぜひまとめて読んでほしい。
その上で、「母の愛」と「僕のラブ」が交差していると感じた2首を引いた。【】書きの歌は「母」が主体と思われる。めっちゃ分かる、今まさに世界がこんなだし我が子に戦争には行ってほしくない、そのためには知識を身につけて人の上に立つような人になってお金を稼げる人になってメンタルを鍛えて、って思ったら自分が我が子にとっての戦争になってしまうこともありうるよな。それが母の愛だ、って思えるようになるまでに子どもの方は戦線離脱してしまうよな。それでも「できるだけ死なないから撫でて」ってギリギリまで思ってしまうの、本当につらい。そこまで思わせてしまいたくない、とは思うけど果たして。
以上、17首を引用して感想を添えました。普段いい歌には「いいなあ……」としか言えないので、上手いこと感想になってるか不安ですが、めっちゃ好きな歌集のひとつです。挙げた歌以外も本当にいいです。読もう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
