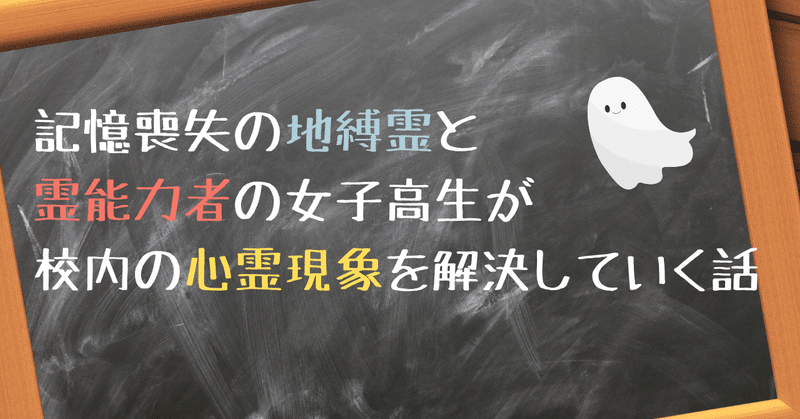
【長編小説】陽炎、稲妻、月の影 #21
第4話 天秤に掛けるもの――(2)
翌日。
普段、特別に呼び出しがかからなければ、放課後近くに出現している俺が、自発的に十時半には出てくることに成功した。アサカゲさんが可能な限り授業を受けられるよう、早起きできたら良いと念じてはいたが、まさか成功するとは思わなかった。生前の記憶は一向に戻らないが、最近、なんだか身体の調子は良い気がする。
さて、と一息ついて、俺は行動を開始する。
アサカゲさんやハギノモリ先生と違い、俺は校内の異変には気づけない。それを補う為には、とにかく足で稼ぐしかないのだ。幽霊である俺は、アサカゲさんよりかは楽に校内を巡れるとはいえ、時間がかかることに変わりはない。だから、早起きできて本当に良かった。
まず向かうのは、ハギノモリ先生が常駐している、第二特別教室棟一階の第二国語科準備室である。
先生からアサカゲさんの成績についての話を聞いたとき、俺と先生とで巡回と対応を強化することは即座に決定した。となると、俺と先生との間で使える連絡手段が必要となってくる。今までなかったことのほうが不思議に思われるかもしれないが、如何せん機動力のあるアサカゲさんと連携が取れていれば、これまでなんの問題も起きなかったのだから仕方ない。
アサカゲさんのくれたリストバンドと似たような仕組みのものを、先生も作ってくれるらしい。腰を痛めていて現場に急行できないことも考慮し、万が一の場合に発動する防衛機能等をつけてくれることになっている。それが昨日の遅い時間に完成したらしく、先生から、都合の良いときに受け取りに来てほしい、と連絡を受けた。いつ何時なにが起こるかわからないし、早めに受け取りに行って損はないはずだ。
「あ! ろむ君じゃんっ!」
第二国語科準備室を目指して移動しているうち、二限目の終わりを告げるチャイムが鳴り、教室から続々と生徒が出てきた。どうせすり抜けてしまうから意味はないのだけれど、通行の邪魔にならないようにと廊下の端に寄って歩いていたら、背後から聞き覚えのある声が飛んできた。
振り返って声の主を確認してみると、以前に第二視聴覚室への道順を尋ねてきた女子生徒が立っていた。
「しばらくぶりだね。この間はちゃんと第二視聴覚室に行けた?」
小走りに近寄ってきた女子生徒に、俺は尋ねた。
「行けた行けた! あのときはマジ助かったよ~」
「それは良かった。学校にはもう慣れた?」
「ん~、まずまずかな。勉強はとりあえずって感じだけど、校内で迷子になるんだもん」
「ほとんどの子は三年生になっても道に迷っちゃうからなあ。また気軽に声かけてね、道案内なら俺にもできるから」
「ろむ君頼りになるぅ~! それに、思ってたよか話しやすいしっ!」
「え、俺、話しかけづらそうな雰囲気でも出てた?」
俺は、春先にアサカゲさんから、警戒心を抱かせない見た目をしている、と評されたことを思い出しながら、首を傾げた。
「んん、ろむ君自体は全然怖くなさそうだったんだけど。なんかこう、ほら、声かけにくいじゃん、いろいろとさ。ねえ、それよりさ、あたしの名前ってまだ教えてなかったよね? あたし、高橋千華っていうの」
半ば話題を逸らすように、女子生徒――タカハシさんは、自らを指差して自己紹介した。
俺が、よろしく、と言おうとした刹那、タカハシさんは遅れて教室から出てきた女子生徒に向かって、おーい、と手を振る。元気な子だなあ。
「ねね、あたしの友達も紹介させて! この間道を教えてもらった話をしたら、その子もろむ君と話してみたいって言ってたんだ」
「良いけど、時間は大丈夫?」
「うん。次は自分のクラスだから、すぐ行けるし」
そんな話をしているうち、タカハシさんが声をかけた女子生徒がこちらに向かって歩いてくる。
と。
その後ろから、アサカゲさんも姿を現した。
まだ二限目終わりだというのに、よほど授業内容が難しかったのか、いつになく表情が暗い。
「もう、遅いよ麻美~」
「ごめんごめん、最後の小テストに手こずっちゃって」
この子たちは、アサカゲさんと同じクラスであるらしい。それなら、アサカゲさんを自然な流れでこの会話に巻き込んでみるのも良いかもしれない。
そう思って、俺はアサカゲさんに気づいてもらおうと、彼女に向かって小さく手を振った。タイミング良くアサカゲさんがこちらを向き、しばし視線が交錯する。
しかし、次の瞬間。
アサカゲさんは繋がっていた視線を乱暴に切ると、そのまま立ち去ってしまった。
全く予想できなかったアサカゲさんの行動に、俺の身体は思わず硬直した。
え、俺、今アサカゲさんに無視された? 今まで、俺を見つけたら向こうから話しかけてきてくれたのに。俺から声をかけようとしたら無視されるの?
何故だろう、自分でも驚くくらいショックを受けているのがわかる。
俺は、今は忘れているだけで、昔、この感覚を嫌というほど味わっていたのだろうか。そう思わせるほど、底の見えない絶望だった。
「それでさあ、ろむ君。この子、あたしの友達の佐藤麻美ちゃんっていうの」
「わあ、すごい、本物だあ。よ、よろしくね、ろむ君。……ろむ君?」
「え? あ、ああうん、こちらこそよろしくね、サトウさん」
動いていない内臓がきゅうきゅうと音を上げるような感覚に陥りつつ、俺は平静を装いタカハシさんとサトウさんとの会話を続けた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
