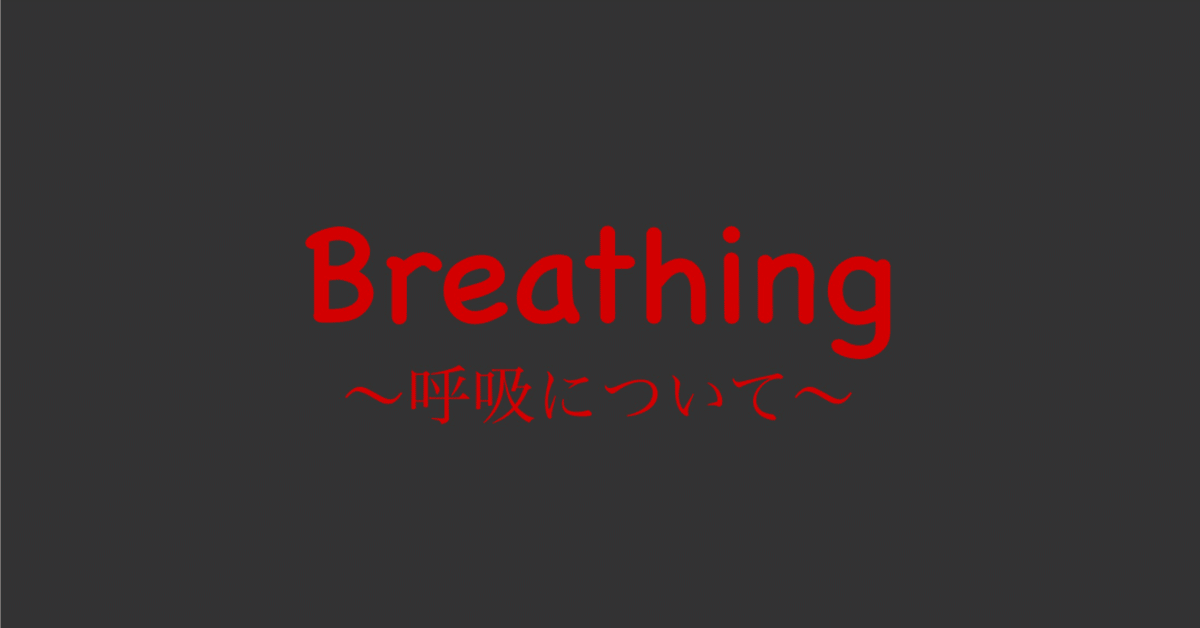
呼吸について
【サマリー】
・息を吸う=吸気とか吸息、息を吐く=呼気とか呼息
・肺はガス交換の場ですが、肺自体が動いて呼吸運動をしているわけではありません。胸腔が運動することにより吸気・呼気が行われています。この胸腔の運動に関係しているのが呼吸筋です。
・主な呼吸筋について
横隔膜と肋間筋です。横隔膜は胸腔の下端にあるドーム状の骨格筋で脊髄神経である頸神経叢から出る横隔神経(C3〜C5)に支配されています。横隔膜が収縮すると胸郭が広がり、胸腔内圧が下がるため吸気が行えます。肋間筋は肋間にある3層の薄い筋で外肋間筋・内肋間筋・最内肋間筋からなっています。外肋間筋は吸気時、内肋間筋および最内肋間筋は呼気時に、それぞれ肋間神経(Th1〜Th11)の働きで収縮します。 ※ パワーブリーズHPより
・呼吸補助筋について
外肋間筋の働きを補助する吸気補助筋には、斜角筋、胸鎖乳突筋、僧帽筋、肩甲挙筋、肋骨挙筋、大胸筋、小胸筋、上後鋸筋があり、これが吸気時に収縮して肋骨を持ち上げる働きを補助します。また、脊柱起立筋群により脊柱を後方に反らせると、肋骨の挙上を助けます。
呼気時の呼気補助筋としては内肋間筋、最内肋間筋、肋下筋、胸横筋、下後鋸筋と腹筋(腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋)があります。腹筋の働きは内肋間筋に比べて非常に重要。 ※ Arai LaboratoryHP&イラスト解剖学&人体の正常構造と機能より



【安静時呼吸】
・安静時呼吸はその大部分が腹式呼吸(=横隔膜呼吸)
・安静時呼吸は70-80%を横隔膜が担っていて、外肋間筋よりも大きく働いている。
・肺は膨らんだゴム風船のように自分で収縮する性質をもともと持っています。従って、横隔膜と外肋間筋により胸郭を広げ、この筋肉が弛緩すると、肺は自らの縮む力で収縮して、息を吐き出す。その為、安静時呼吸では呼気時に働く筋肉はない。もしあったとしても内肋間筋は安静時呼気には作用わずか。※Arai LaboratoryHP&人体の正常構造と機能より
【腹式呼吸】
・腹式呼吸を意識せずとも、安静時呼吸はその大部分が腹式呼吸
・ドーム状の横隔膜を下げること=横隔膜収縮(これを横隔膜呼吸とも言う) ※プロメテウスより
・腹部の動きが著明な呼吸法
・男性の呼吸型とされているが、女性でも横隔膜が全く働かないわけではない※理学療法士市川先生講義より
・吸気では横隔膜が強く収縮して胸郭を縦方向に大きく拡げます。このとき、横隔膜が押し下げられる事で腹圧が上昇し、腹全体が膨らみます。呼気時では横隔膜は弛緩し、腹筋が収縮してお腹をへこませる事で腹圧を上げて横隔膜を強く押し上げ、呼気を助けます。※パワーブリーズHPより
【胸式呼吸】
・肋骨を上げることによる呼吸(肋骨呼吸とも言う) ※プロメテウスより
・女性に胸式呼吸の傾向強く、衣服による腹部の締め付け、妊娠時に特に著明 ※理学療法士市川先生講義より
・運動時では胸式呼吸の割合が大きい。※人体の正常構造と機能より
・努力性呼吸(深呼吸)の場合は外肋間筋やそのほかの吸気補助筋による胸式呼吸量が増大する。※プロメテウスより
・吸気時には外肋間筋と複数の吸気補助筋が強く収縮して、肋骨を大きく前上方に引き上げ、吸気を助けます。呼気時には内肋間筋が収縮して胸郭を縮めて、呼気を助けます。※ パワーブリーズHPより
・吸気時には斜角筋群が第1肋骨を固定・挙上、外肋間筋が収縮して第2肋骨以下を挙上(肋骨は前上方に挙上)して、胸郭の拡大が起こる。一方、呼気時には腹壁筋群が第12肋骨を固定、内肋間筋が収縮して肋骨を下制すると,胸郭の強制的な縮小(努力性呼気)が起こる。※人体の正常構造と機能より




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
