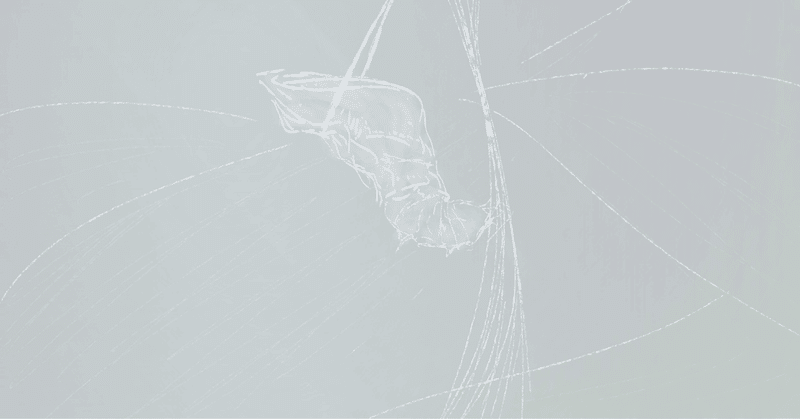
とにかく変態は今日も変態
時代によって呼び名が変化することは特に珍しい現象ではございません。そして、それは科学の言葉もまた同様です。
例えば、遺伝学には以前、「優性」「劣性」という言葉がございました。使われなくなった理由は誤解を招きやすい表現だったからです。
遺伝子はしばしば身体に特徴を出す働きがございます。子供の顔がどこか両親に似ているから、人は両親から遺伝子を引き継いだと理解する。ただし、遺伝子には出やすい特徴を持っているものと出にくい特徴を持っているものがあります。その「出やすい特徴を持つ遺伝子」が「優性遺伝子」と呼ばれ、「出にくい特徴を持つ遺伝子」が「劣性遺伝子」と呼ばれてきました。
しかし、優劣は「優れる」「劣る」のイメージがどうしても強いために、優れた特徴を持つ遺伝子が優性遺伝子、劣った遺伝子を持つ遺伝子を劣性遺伝子だと勘違いする人が続出したんです。優性劣性は単に特徴として出やすいかどうかだけであって、特徴の優劣は全く関係ありません。誤解のされやすさは以前から知られていたようで、私が優性劣性を授業で習った際にも「優れているかどうかの意味じゃないから気をつけるように」と注意されたものですが、いつまで経っても勘違いはなくならない。そこで、いよいよ名称変更となりまして、「優性」は「顕性」、「劣性」は「潜性」と呼ばれるようになりました。
生物の名前が変更になったこともあります。以前、日本魚類学会は差別用語が入っている生物名を別の名前に改める決定を下しました。調べたら、変更された名称の一覧らしきものを見つけました。
そうやって、様々な名称が様々な理由で時に変化する。科学も例外ではありません。変わる時はもう、いきなり一気に変わってしまう。
その中において、いつか変わるんじゃないかと思い続けていても、一向に名称変更の兆しが見られないものもございます。個人的に筆頭として挙げたいのは「変態」です。
生物学的な意味での変態は、生き物が生まれて成長するに従い、「形態」、すなわち体の形を変える現象を指します。形態が変わるから変態なわけですね。
一言で変態と言ってもいろいろございます。例えば、虫が卵から幼虫となり、蛹を経て成虫となる過程を「完全変態」と呼び、チョウやハチなどが該当します。一方、蛹を経ず、幼虫からそのまま成虫になる過程を「不完全変態」と呼びます。セミやトンボなどが該当します。
他にも「過変態」「多変態」「小変態」「新変態」「前変態」「半変態」「不変態」「無変態」「増節変態」「改形変態」「整形変態」など、様々な変態が存在しています。
これらはあくまで生物学的な意味での変態であり、世間一般に広く言われている変態とは意味が異なります。だから、理科や生物の教科書にも載っていますし、授業でも習います。
そうすると当然の流れで、ニヤニヤしはじめる男子中学生や男子高校生、男子大学生、男子社会人が出てくるわけです。そんな男子をにやつかせ続けている「変態」ですから、いつかは違う言葉に取って代わるんじゃないかと思い続けているんですが、変態はずっと変態なんです。
科学者としても「やっぱ変態は変態だよな!」と思ってるのかもしれません。それに「変態」は生物学においては基本的な概念のため、名称を変更してしまうと膨大な教科書や専門書などで表記の変更を強いられる。かなりのお金と手間と時間がかかるんです。
改名が大変なことを考えれば、男子をニヤニヤさせるほうが遥かにマシだと考えても不思議ではありません。とにかく変態は今日も変態です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
