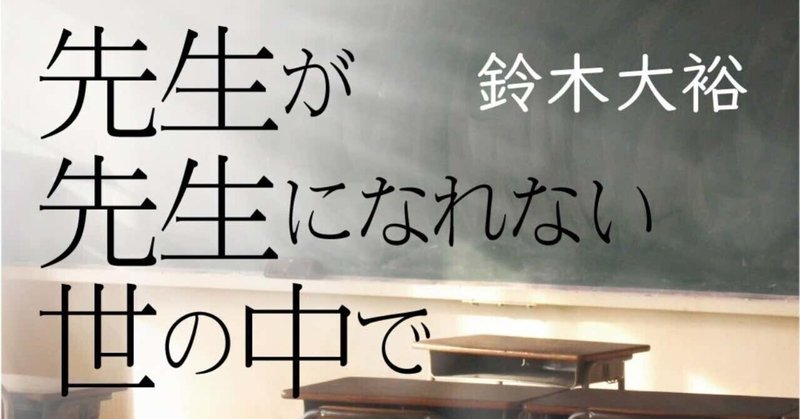
先生が先生になれない世の中で(12)教育現場における 「構想」と「実行」の分離②
鈴木大裕(教育研究者・土佐町議会議員)
1983年の『危機に立つ国家』以降、国を挙げて教育の合理化と標準化の道を突き進んできたアメリカだが、1990年に出版された論文で、アメリカの教育現場における「構想」と「実行」の分離について考察したアップルら(*1)は、「何のための教育なのか?」の定義が変われば、当然「何が良い教えなのか?」も再定義されると指摘する。そして、そのような教育目的の再定義は、日本でも確かに起こってきた。
2003年、日本が常に上位にいたOECD(経済協力開発機構)の学習到達度調査(PISA)で急に失墜した、いわゆる「PISAショック」で、「脱ゆとり教育」や「グローバル人材の育成」が叫ばれるようになった。「PISA型学力」の追求に加え、40年以上おこなわれていなかった全国学力調査が復活し、「学力向上」を掲げた業務の効率化が進み、「学習スタンダード」や「ゼロトレランス」の名の下に授業や生徒指導のマニュアル化が広まった。
また、「何を学ぶのか」というカリキュラムの基準であったはずの学習指導要領は、「何ができるようになるのか」というパフォーマンスの基準へと姿を変えた(*2)。教育条件整備の一環として、学びのインプットの基準だけを定めていたはずの政府は、学習指導要領の改訂によって、学びのアウトプット、つまり学習到達度の基準を定める役割を手に入れた。
その結果、政府は教育現場を評価し、教員に結果責任を求める主従関係の強化に成功したのだ。
それはまさしく、学校教育における「構想」と「実行」の分離の表れだった。「指導方法、教材、テスト、そして結果はますます、それを実行しなければならない人々の手から奪われている(*3)」というアップルらの指摘には、教室において保障されていた教員の自由が、徐々に教員の手を離れていったアメリカの社会的背景がある。しかも30年以上前からだ。
今日では日本でも当たり前となったスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーはもちろんのこと、アメリカでは授業計画の作成を専門とする「カリキュラムスペシャリスト」なる職も設けられているし、テスト産業も教育現場に深く食い込んでいる。テスト会社との契約で、教員が自ら作成した期末試験やクイズなど、テスト会社が作成したもの以外のいかなるテストの実施も禁止している地域もあるのだ。
アップルらは、「疎外感とバーンアウトを生み出すのに、労働におけるコントロールの喪失以上に有効な方法は他にない(*4)」と指摘している。新自由主義教育改革が猛威をふるっていたアメリカのニューヨーク州で、早期退職する一人のベテラン教師の辞表に綴られていた言葉を思い出す。
「私が教師の職を去るのではなく、教師という仕事が私を去っていった。」(*5)
それはまさしく、かつてマルクスが指摘した、労働からの「疎外」だったのだ。
しかし、マルクスにとって労働は、「忌避すべきもの」ではまったくなく、「むしろ、『労働が魅力的な労働、言い換えれば個人の自己実現であるための主体的および客体的な諸条件』を獲得し、創造性や自己実現の契機になることを目指していた」と斎藤幸平氏は指摘し(*6)、現代を生きる私たちに向けてこうも問うている。
「労働はもっと魅力的で、人生はもっと豊かであるべきではないのか。このマルクスの問いは現代にもあてはまります。へとへとになるまでつまらない仕事をして、帰宅してからは、狭いアパートで、コンビニの美味くもないご飯をアルコールで流し込みながら、YouTubeやTwitterを見る生活はおかしいんじゃないか。そして何より、『月曜日が憂鬱』、『日々の生活がしんどい』という感覚は、私たちの実感に合致するのではないでしょうか。」(*7)
教員はどうだろうか。教員は月曜日を楽しみにしているだろうか。「早く子どもたちに会いたい!」と感じているだろうか。
教員の働き方改革は、業務や勤務時間の削減という単純な問題ではない。逆に、業務の効率化はさらなる分業につながりかねないからだ。
どうしたら教職をもっと魅力的で、代替不可能な仕事にできるだろうか? 教職における「構想」と「実行」を結合し、教員の仕事における「疎外感」を解消することなしに、真の働き方改革はありえない。
【*1】Apple, W. M. & Jungck, S. (1990)“ You don’t have to be a teacher to teach this unit: teaching, technology, and gender in the classroom.”
American Educational Research Journal, vol. 276, no. 2, pp. 227-251.
【*2】鈴木大裕(2017)「結果責任の支配――カリキュラム・スタンダードからパフォーマンス・スタンダードへ」『世界』2017年3月号、岩波書店。
【*3】Apple & Jungck, op.cit., p. 231.
【*4】Ibid., p. 233.
【*5】鈴木大裕(2016)『崩壊するアメリカの公教育――日本への警告』岩波書店、141ページ。
【*6】斎藤幸平(2020)『人新世の「資本論」』集英社新書、307 ~ 308ページ。
【*7】斎藤幸平(2021)『100分 de 名著 カール・マルクス『資本論』』NHK出版、72ページ。

鈴木大裕(すずき・だいゆう)教育研究者/町会議員として、高知県土佐町で教育を通した町おこしに取り組んでいる。16歳で米国に留学。修士号取得後に帰国、公立中で6年半教える。後にフルブライト奨学生としてニューヨークの大学院博士課程へ。著書に『崩壊するアメリカの公教育――日本への警告』(岩波書店)。Twitter:@daiyusuzuki
*この記事は、月刊『クレスコ』2022年5月号からの転載記事です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
