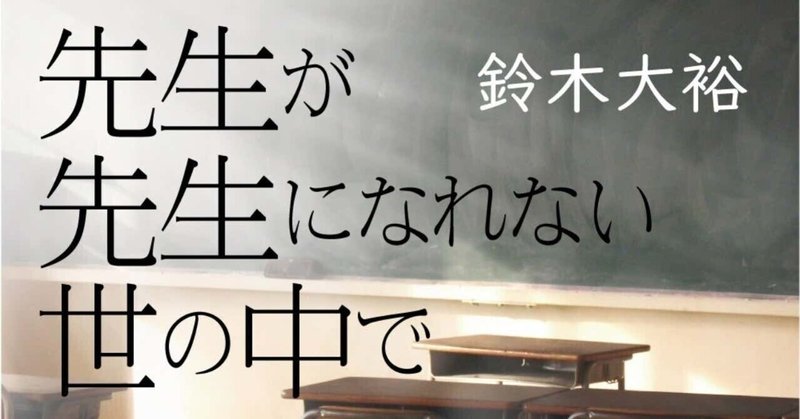
先生が先生になれない世の中で(6)学校における「免許外教科担任」の解消を求めます!
学校における「免許外教科担任」の解消を求めます!
そんな意見書を、わが土佐町議会の総務教育厚生常任委員会は3月の定例会に提出し、採択された。免許外教科指導という、教職員には珍しくもなんともないこの問題だが、裏を返せばそれだけ慢性的な問題であり、実は他の様々な問題にも飛び火する破壊力を秘めたテーマだと思う。
追記: 同様の意見書が、高知県大月町(3月4日)と芸西村(3月11日)でも採択された。
たとえば、子どもの学習権の問題。担当する教科の専門知識も免許も持たない教員が教えても、子どもの学習権を保障できていると言えるのだろうか?
次に、学習指導要領の「法的拘束力」の問題。もし本当に法的拘束力があるならば、そのなかで正規の教科と位置づけられている美術や技術・家庭科などの技能教科の免許を持つ人間が圧倒的に不足している実態はなぜ許されるのか? それは全国学力調査を中心とする貧弱な「学力」観と関係があるのか?
文科省以上にGIGAスクール構想の推進に鼻息の荒い経産省は、タブレットは「文房具」と言うが、専門の教員も足りていないのに高価な「文房具」に巨額の予算(2019年度と2020年度だけで約4600億円)を投じている場合なのか? お金はある。優先順位の問題だ。
教員免許制度のゆがみもある。「免許外教科指導」の常態化で、教員が専門性を発揮しにくい環境がある一方で、彼らは10年おきに専門教科の免許更新を強いられている。それと同時に「外部人材」の積極活用が謳われ、教職課程を通ってきていない人々に臨時免許が乱発されている矛盾を、私たちはどう理解したらよいのだろうか?
子どもたちのために十分な教育環境を整えるのが政治の役割だ。地方議員なら、手始めに過去5年間の免許外教科指導の実態を教育委員会に問い合わせてみるのはどうだろうか。保護者なら、地域の議員に調査するようアプローチしたっていい。免許外教科担任を強いられたことのある教員が声をあげ、経験を語ることも大事だ。
「改革」や「イノベーション!」を叫んで答え探しに走る前に、まずは最低限の教育条件整備をしていこう。当たり前のことを、ひとつひとつ着実に。
* * * * *
学校における「免許外教科担任」の解消を求める意見書
我が土佐町では、長年にわたり、中学校美術科および技術・家庭科の免許を持つ教員が配置されていません。特に美術に関しては現在記録が残っているだけで、少なくとも平成16年度以降続いている問題で、過去17年間、土佐町の子どもたちは専門的な美術教育の機会を一度も享受できていないことになります。しかし、文科省は平成30年に出した「免許外教科担任の許可等に関する指針」の中で、免許外教科担任制度は一年以内に限る臨時的な特例措置と明言しており、本制度の恒常的な活用は、免許状主義を定める教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の下でも問題があります。
また、これは土佐町だけの問題ではありません。高知県教育委員会によると、美術科教諭が配置されている学校は、県内108の公立中学校のうち48校に過ぎず、県内の大半の子どもたちが専門的な美術教育を享受できておりません。教員にとっても、専門ではない教科を一から学び、教えることは多大な負担であることは言うまでもありません。
そのように深刻な状況にもかかわらず、高知県における今年の美術科教諭の募集は「2名程度」とされていることから、免許外指導は構造的な問題であることがわかります。また、問題は県が定める教員の配置基準にもあります。土佐町中学校をはじめ、中山間地域などの過疎化が進む自治体では、地域唯一の学校でも各学年1学級の小規模校が多くあります。高知県は平成6年度に小規模中学校への教員配置を1名増やして7名(校長、教頭除く)とする改善を行いました。しかし、それでも県の配置基準では、各学年2学級の中規模校になってようやく9教科全ての教員が揃う基準になっており、県内の全中学校の約68%に当たる中学校でそもそも全教科分の教員を配置できないことになっています。
AI時代の到来を目前にして、人間的な感性を育むことが急務であることはもちろん、何よりも美術は学校教育法施行規則に定められた正規の教科です。したがって、これは憲法で守られている子どもの学習権の保障に関わる重要な問題であり、財政の状況に左右されて良い問題でもありません。中山間地域からの子育て世代のさらなる人口流出を防ぐためにも、地域の要である学校における教育の質を、待遇の悪い非正規雇用などに頼らない持続可能な形で保障すること、そして教員がそれぞれの専門性を発揮できる教育環境を整備することが喫緊の課題です。
よって、県・県教育委員会においては、以下を実行することを求めます。
1. 一刻も早く免許外教科担任の解消に着手すること
2. 中山間地域等の小規模校でも9教科全ての教員が揃うよう、県の教員の配置基準を是正すること
3. 各教科ごとの免許外指導問題の現状把握と問題の要因分析(県内における各教科ごとの免許取得者数の推移、教員採用審査受審者数の推移、離職者数の推移など)に基づく対策を取ること。必要に応じて国の支援を求めること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和3年3月2日
土佐町議会
高知県知事 浜田省司 様
高知県教育長 伊藤博明 様

鈴木大裕(すずき・だいゆう)教育研究者/町会議員として、高知県土佐町で教育を通した町おこしに取り組んでいる。16歳で米国に留学。修士号取得後に帰国、公立中で6年半教える。後にフルブライト奨学生としてニューヨークの大学院博士課程へ。著書に『崩壊するアメリカの公教育――日本への警告』(岩波書店)。Twitter:@daiyusuzuki
*この記事は、月刊『クレスコ』2021年4月号からの転載記事です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
