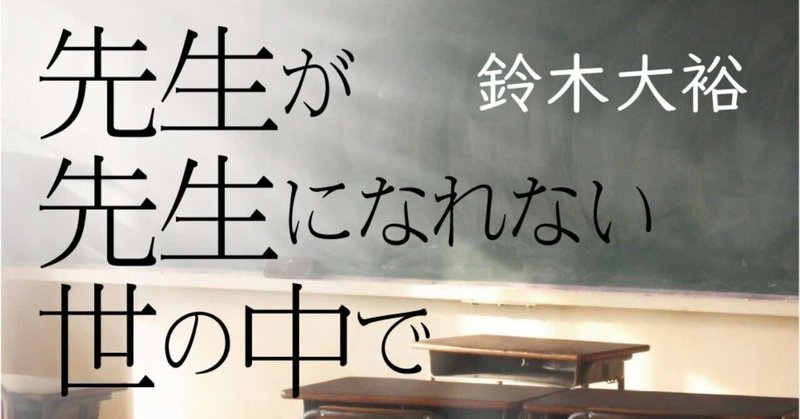
先生が先生になれない世の中で(15)「学校部活動の地域移行」~教職員の分断を絶対に認めない~
鈴木大裕(教育研究者・土佐町議会議員)
9月6日に開会する土佐町議会にて、「学校部活動の地域移行」に関する意見書を提出する。このような形で国に対して意見を表明することは、地方自治法第99条にて地方議会に認められた大事な権利だ。いま国が進めようとしている「学校部活動の地域移行」も課題が山積みで、多大な影響を受ける地方自治体として黙っているわけにはいかない。
この意見書は、4月から月一回程度、「教職員の働き方改革」と「学校部活動の地域移行」をテーマに、高知県内の教育関係者で激論を重ねてきたものが土台となっている。参加者には、教員の過重労働の観点から部活動の顧問になることを拒否している教員、逆に部活の顧問として指導を続けたい教員、「地域移行」の実現性を疑問視する総合型地域スポーツクラブの代表などの様々な立場があり、たいへん難しい議論を続けてきた。そこで積み重ねた議論をもとにこのたびの意見書のたたき台をつくり、8月中旬に全国から土佐町に集まってきた教員、校長、教育委員、地方議員、教職員組合役員らとともに最終版を作成した。
議論のなかで大事にしてきたことがある。それは、部活の地域移行をめぐって、教職員同士の間で分断を生まないことだった。部活指導が教職員の長時間労働の大きな要因であるとして、SNS上で部活顧問拒否の運動を展開している教職員も少なくない。同時に、部活動の教育的意義を感じ、学校からの切り離しに危機感をもつ教職員もまた少なくない。「部活を学校から切り離すのか、それとも維持するのか」――そんな二項対立で議論をすれば、教職員間の分断は免れない。
議論の終盤、折衷案として「部活指導をしたくない教職員が顧問を強要されず、部活指導を続けたい教職員が自由に続けられる環境の整備を」という一文について議論していたときだった。それまで口数の少なかった山口の教員が、強く反対した。「私たちがそこに乗っかってはいけないと思う。」教職員の分断を絶対に認めない。そんな一体感が生まれた瞬間だった。
そうして出来上がった意見書は、実にシンプルなものだった。部活の地域移行に向けた様々な課題に関しては、今年6月に全国市長会が国に突きつけた「運動部活動の地域移行に関する緊急意見」が見事に網羅していたので、地方議会としてそれに賛同の意を表明するとともに、文化系部活動に対しても同様の措置を求めることにした。そして、部活動をめぐって教職員同士、そして教職員と保護者や子どもらとの間に分断を生まないよう、部活動の切り離しには一定の理解を示しつつも、もう一つの選択肢を提案した。
「『人格の完成』に値する豊かな学校教育を守り、教職員の負担軽減を進めるためにも、部活動を含む教員のすべての業務を勤務時間内に収める取り組みも推進すること。」
「地域移行」という名の下で安易に部活を民営化すれば、次にねらわれるのは授業だろう。ただでさえ、深刻な教員不足に便乗した特別免許状の乱発が進んでいるなか、授業さえもが「副業先生(*) 」に持っていかれるのは目に見えている。学校はますます「塾化」して、そのうち教員免許はもういらない、授業はカリスマ講師のビデオを一斉配信すれば十分、なんなら生徒一人ひとりタブレットを用いた「個別最適化」プログラムで対応させればよい……。そんな方向に向かうのではないだろうか。
子どもたちにとって豊かな学校教育を守るために、今一度立ち止まって考える必要がある。子どもたちの教育は、教育基本法が定める「人格の完成」に値するものなのか。国は、地方自治体は、その崇高な目標を実現しうる教育条件を保障できているのか。この意見書が、一つでも多くの地方議会で採択されることを願う。
*追記:この意見書は9月13日に土佐町議会で、15日には本山町議会にて、ともに全会一致で採択された。
「学校部活動の地域移行」に関する意見書(案)
先般、スポーツ庁と文化庁の有識者会議は、持続可能な部活動と教職員の働き方改革に対応するため、公立中学校の休日の部活動を皮切りに、令和7年度を目処に段階的な「地域移行」を実施する内容の提言をまとめた。
スポーツ庁の有識者会議の提言後まもなく、全国市長会は、『運動部活動の地域移行に関する緊急意見』(添付)を取りまとめ、多くの自治体に広がっている懸念の声に応えるよう、国の責任、移行期間、部活動の教育的意義、費用負担のあり方、スポーツ団体等の整備充実、スポーツ指導者等の人材の確保、保険のあり方などに関する具体的な項目を挙げ、政府に措置を求めた。
日本の教職員の長時間労働の実態は世界的に見ても異常であり、早急な対応が求められることからも、この度の「地域移行」は一つの選択肢としては理解する。しかし、国は、これまで部活動を学校教育の一環である教育活動として位置付けてきた。それは、生徒の自主的な活動である部活動が、教育基本法が教育の目的として定める「人格の完成」において重要な取り組みだからである。
本議会は、全国市長会の緊急意見書に賛同の意を表明すると共に、文化系部活動に関しても同様の措置を求めると同時に、国において、下記事項について特段の措置を求める。
記
1. 部活動の地域移行に関しては、当事者である子ども、教職員、保護者等の声を十分に聞き、それぞれの地域の実情に合わせて進めること
2. 「人格の完成」に値する豊かな学校教育を守り、教職員の負担軽減を進めるためにも、部活動を含む教員のすべての業務を勤務時間内に収める取り組みも推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
以上
令和4年9月6日
土佐町議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文科大臣
財務大臣
スポーツ庁長官
文化庁長官
【*】鈴木大裕「規制緩和による問題をさらなる規制緩和で解決!?」『クレスコ』2022年8月号

鈴木大裕(すずき・だいゆう)教育研究者/町会議員として、高知県土佐町で教育を通した町おこしに取り組んでいる。16歳で米国に留学。修士号取得後に帰国、公立中で6年半教える。後にフルブライト奨学生としてニューヨークの大学院博士課程へ。著書に『崩壊するアメリカの公教育――日本への警告』(岩波書店)。Twitter:@daiyusuzuki
*この記事は、月刊『クレスコ』2022年10月号からの転載記事です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
