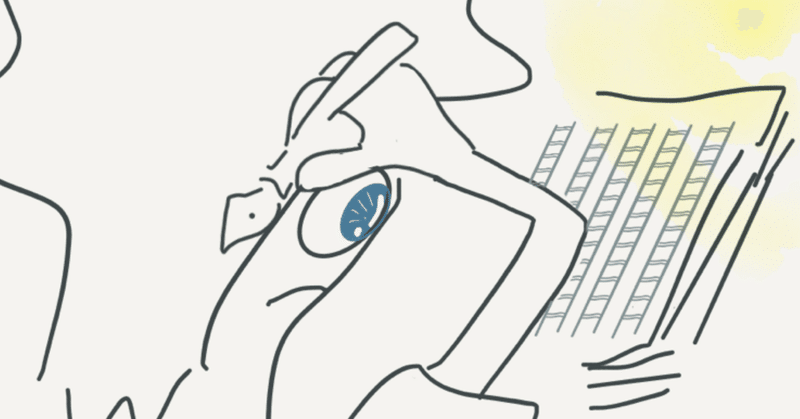
ライター、小説家もどきを演ずる。
あのとき僕は、京都の呉服屋で若旦那だった。卒業から不逢まに10年が経ち、それぞれに途切れた時間を縫い合わせようと、4人だけの同窓会話が持ち上がった。
現実的ではなかった。一人はデザイン関連の仕事でニューヨークにいたし、一人は海外1号店を開業させたばかりで上海にべったり張り付いていたし、京都の僕と東京のもう一人の事情を鑑みるに、せめて京都か東京での開催が現実のライン上にかろうじてしがみついていた。
僕は家族をつくり、安定と引き換えに足枷もできた。同窓会で家を空けるとなると、それなりの物理的な手順と機微の韻を踏まなければならない。ほかの3人と違って仕事の都合のやりくりでどうにかなるものではない。
それに、仕事にだってうねりの具合で抜け出せない波にとらわれることもある。上海のリュウは今が勝負どころだった。月面探査機を乗せたロケットが軌道を誤れないのと同じく、日々微調整を繰り返し、見据えた一点に着地させなければならない大事な時だ。小さな飲食チェーン店展開において、海外最初の花火は大輪の花を咲かせなければならなかった。彼とて譲れぬ大義を抱えている。
大人になってから対峙する問いは、一筋縄ライクな解答を導けない。縄は多岐に渡り、柔軟ゆえに絡み、きつい結び目をつくる。
事情は人の数だけ存在し、それぞれが複雑に絡まった糸を解いていくしかない。
個々の事情は割愛するが、3人は上海に旅立った。事情を述べると理屈っぽくなる。4人は共に言い訳は聞きたくないほうだったから、誰もが退屈な理屈を口にしなかった。訊いても話さないのだから、知る由もなかった。知りたいとも思わなかった。結果だけが、物事を前に押し進める。上海同窓会は、4人がおのおの誰が無理ができないかを考え、たどり着いた絞られた答えだった。
バンドの河畔を見下ろすラウンジ。夕日の残り火が消えてからの集合は会を始めるには遅めの時間帯だったが、ニューヨークから飛んでくる飛行機の到着時間に合わせると絶妙にフォーカスされた焦点といえた。
展望ラウンジから眼下に街の灯が蠢いている。蛇行する黒い影は黄浦江だ。川面を、甲板を己のライトで照らす船が気だるそうに行き来していた。ふと、トーマスの仲間に船が名を連ねていたことを思い出したが、何という名だったか、テレビに熱中していたわけでもないので、思い出すことはできなかった。見下ろす船はどれも三頭身の滑稽な玩具みたいだった。
アメリカ時間で飛んでくる飛行機は沖縄時間ほどではないにせよ遅れ、悪い悪いと頭を下げたハルキが心底申し訳なさそうな顔をして入ってきたのが、会開始予定の1時間後。言い訳はいらない。わかってる。
「10年ぶりだ。1時間なんて屁の役ほどもない」確かにリュウの言うとおりだった。
そんなことより、やっとそろった4人にチアーズ。待った1時間は、昔話に咲く花が瞬時に埋めた。
今夜は長い。振り返れば瞬く間で終わってしまう時間も、渦中にいれば永遠に続くようにさえ思える。その刹那刹那を刻み込んでいきたかった。
ーーーーーーーーーー
こんな物語をかつて描いた。依頼主は旅行関連のメーカーで、テキストの量からすれば小説には程遠かったけれども、活字として無料配布のパンフレットに載った。
広告としての効果はわからない。書き手はマーケターではないから。関わった者としては、商品の販促につながっていればいいと思う。
あれ以来、京都の呉服屋の若旦那は登場していない。あれから10年。そろそろ再会してもいい間合いかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
