
◆読書日記.《矢内原伊作『サルトル 実存主義の根本思想』》
<2022年11月28日>
矢内原伊作『サルトル 実存主義の根本思想』(中公新書)読了。
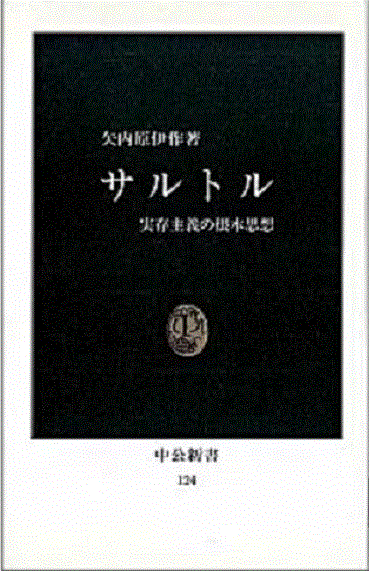
今年は年初に気まぐれに澤田直の『新・サルトル講義』を手に取ってしまったがために図らずもサルトルの思想を研究する年になってしまった。
本書で今年読んだサルトル解説本は7冊目。サルトル本人の著作は小説の『嘔吐』と『存在と無』全3巻の4冊。という事で本年はサルトル関係の本はこれで計11冊目という事となる。
さすがにもう今年はこれで最後にしたい。というのも、以前から言っているように、ぼくはあまりサルトルの思想は好みではないからである。
しかし、先日ふと馴染みの古本屋を覗いてみた所、ワゴンセールの棚にこれがポツリと置いてあったので、仕方ない、これも何かの縁だ、無視するのもどこか寝覚めが悪いという事で購入し、読む事となったのである。
◆◆◆
サルトルは晩年から没後しばらく、ほとんど「流行遅れ」的な扱いとなっていたという印象がある。
澤田直の『新・サルトル講義』にも以下の様に書いているほどである。
「ここ二十年ほどの間(※サルトル没年の1980年から後20年ほどの間)、サルトルは徹底的に否定されてきた、あるいは、無視されてきた。それに先立つ二十年間、あらゆる場面でサルトルの名前が口にされたことに反発するかのように、誰もがサルトルという名を避け、口にするときは、吐き捨てるように、あるいは気恥ずかしそうにそっとつぶやいた。まるで、追放した悪病神の帰還におびえるように……」
また、永野潤も『図解雑学・サルトル』で、学生時代にサルトルを研究していた時の事を次の様に書いている。
「個人的な話をさせてもらえば、1988年にサルトルについての大学の卒論を書いたのですが、当時から、「なんで今どきサルトルなんかやってるの?」と何度も言われました。私が大学生のころは、ドゥルーズやデリダといった哲学者の新しい思想がブームで、「サルトルなど前時代の哲学者、そんなものを読むのはダサい」というような雰囲気がありました」
『新・サルトル講義』の澤田によればフランスでは21世紀に入ってからサルトルの様々な遺稿が刊行され、再評価の流れがあったのだそうだが、日本ではどうだったのだろうか?
今年、澤田直『新・サルトル講義』を読んだついでといった形で書店でサルトルを探しまくったが、手軽に手に入る書籍は数冊程度しかなかった……という状況を考えても、さほど変わってはいないのではないだろうか。
今回読んだ矢内原伊作『サルトル 実存主義の根本思想』も今では絶版になっているようで、初版は1967年と、サルトルがまだ生きて活発に活動していた時期であったようだ。
という事で、本書は以前もご紹介した村上嘉隆『人と思想34 サルトル』と同じく情報が若干古いと感じさせてしまう所があった(因みに『人と思想34 サルトル』は1970年刊行されたものである)。
本書の著者は法政大の教授を務めていた人で専攻はフランス哲学。
という事で、本書の刊行された前年の1966年、サルトルがボーヴォワールと共に訪日した際は日本を案内したのだという。また、フランスにもしばしば行ってサルトルと交流を持っていたという事だから、半ばサルトルの知り合いのような人物である。
サルトルはこの1966年の訪日の際、三度の講演を行った他、著者と共に日本を精力的に見て回ったという。
という事で本書ではサルトルと著者との間で交わされたやり取りなども記載されているという点でなかなか貴重な記録でもあると言えるだろう。
そして、この時期はまだサルトルが活発に活動していた時期であり、その同時代を生きた学者である著者が、サルトルの書籍を読むだけでは窺い知れない当時のサルトルの活動のあれこれをもまとめているのが本書の特徴の一つと言って良いだろう。
サルトルは戯曲に文芸評論、時事評論、小説、思想と様々な文章を書いたが、特に後期は自らの思想である「アンガジュマン(社会参加)」のために、様々な場所に訪れて活発な発言をし、そういったあれこれは、本書の様に他人がまとめたサルトルの活動記録的な部分でないと、サルトル自身の著作だけでは把握しきれない部分もある。
という事で、本書は「入門書」的な書き方にはなってはいないものの、当時のサルトルの活動を当時の研究者が期待を持って書き紹介しているという点で、他のサルトル本とはまた違った価値のある内容だと思うのである。
◆◆◆
本書の内容は三部構成になっている。
第一部・サルトル
第二部・実存主義
第三部・年譜
このようにはなっているが、第三部の年譜は十数ページ程度の簡単な年譜なので、読み物ではなく添付資料といった所だ。
そのため実質は第一部と第二部の二部構成の内容と見ていいだろう。
第一部ではサルトルの「根本思想」としての実存主義の基礎を簡単に説明し、それが何故サルトルの「アンガジュマン」に繋がり、どうしてそこから様々な活動に繋がっているのかという事を説明し、そのスタンスでサルトルの関わった様々な事件を解説している。
第二部はサルトルの思想を踏まえ、基本的には著者なりに実存主義の立場から芸術について論じるという内容になっているため、サルトルに関する言及はわりと控えめであったりする。
内容としては第一部のほうが面白いし、サルトル思想の特徴が良く出ていると思う。
第一部では特にサルトル思想の中でも「アンガジュマン」をサルトル自身の実践に即して説明されているという点でも具体的で分かり易い。
まず著者は、1966年にサルトルが訪日した際に行った三つの講演の内容を紹介している。その内容が、その当時のサルトルの活動を裏で支える思想に繋がっていたからである。
この日本で行われた三つの講演はそれぞれ「知識人の位置」「知識人の役割」「作家の政治参加」というテーマで行われたという。
以前もご紹介した様に「普遍的知識人」といったイメージを作り上げたのはサルトルといってもいいだろう。
「普遍的知識人」というのは、自分の専門分野であっても専門外の事柄であっても、常に積極的に自らの考えを開陳して発言をする知識人の事を言う。
サルトルはこの講演によってそういった「知識人」というものは、どういった者なのかを説明したのである。
今回本書を読んで面白いと思ったのは、この「知識人」のスタンスが、サルトルとしては共産主義的な思想と結びついているという点を知った所にあった。
特に二回目の講演「知識人の役割」でサルトルは「普遍的なものとブルジョワ階級に特有なものとのあいだの矛盾を自覚した知識人が何をなしうるか、何をすべきか」を論じているというのだが、ここからもサルトルの共産主義への傾倒傾向がみられる。
明らかに後期サルトル思想の重要点は「共産主義」にあり、それは前期の実存主義からアンガジュマンへと発展して共産主義思想へと至る流れの結果としてあったのである。
サルトルの実存主義のキーワードには「自由」というものがある。有名な「人間は自由の刑に処されている」である。
キリスト教的な観念から解放された近-現代人は、「神」によって保障された固定された世界観からも解放された。
それは、更に言えば「生きる意味」や「死ぬ意味」からさえも解放され、キリスト教的な「人間の存在意義」というものを失った。
もう「生きる意味」や「人間の存在意義」などというものは、教会に行っても教えてくれるものではなくなった。
サルトルが言う所の「実存は本質に先立つ」である。
人間に元々備わっている「本質的な意味」などは、ないのである。人間は「何の意味があって存在しているのか」という「人間の本質」が出来る前に、もうこの世に生を受けて、人生を始めてしまっている。存在の意味が出来る前に「実存=現実存在」してしまっている。
何のために生きているのか? 何の意味もないのである。あえて言うなら、それを見つけるのは誰でもない、自分自身が、これからしなければならないのである。
だから、既に存在してしまっている「実存」が先行して、「人間の本質」やら「貴方のいる意味」というものは、その後に付いてくるものだ、というのがサルトルの言う「実存は本質に先立つ」という事なのだ。
人間が生きる意味は、自分が自ら探し出さねばならなくなったのである。生きようが、死のうが、君の自由だ。もうそれを「正しい」とも「間違っている」とも保証してくれる「神様」のような存在はいない。
それが宗教的な「意味」から解放された近代人の姿であった。
つまり、ここで言う「自由」はポジティブなものとも言えるし、ネガティブなものとも言えるのだ。
だからこそ「人間は自由の刑に処されている」のである。
人間は自由に生きられるが、その自由には「責任」がついて回る。
自分が何者であるのかという事が決められておらず、決まってもおらず、それを自分で決めなければならない。
決めなくてもいい。だが、決めなくて損したり得したりするのは自分だ。だからその選択の「責任」は自分がとらねばならない。
人間というものは、意味もなく既に生きてしまって「世界の-中に」放り出されている状態である。だから否応なく、その世界の「状況」に巻き込まれているというのが、人間なのである。
このような「状況」の中で、何をするのかは「自由」なのである。行動するもよし、行動しないもよし。だが、その結果責任も負わねばならないというのが、現実的存在としての人間なのである。
自分の国が戦争を始めた。自分をまきこむこの状況は一見、国を運営する政府機関の責任のようにも思える。
だが、サルトルの思想からしてみれば、この戦争に反対し、拒否し、抵抗運動をおこすのも兵役拒否して逃げるのも、「状況」の只中で生きねばならない現実的存在である人間の「自由」だと考えた。
だから、徴兵を強制させられたり周囲が全て戦争賛美の傾向にあったりしたとしても、戦争が起こってしまった「責任」は、「状況」の中で「自由」な選択ができる自分にある――と考えたわけだ。
人間は「世界-内-存在」であるのだから、「状況」に巻き込まれている自分はそれを変える力がある。
だとしたら、戦争に反対せずに望まない戦争に巻き込まれるのも自分の「責任」だし、例え犯罪者となって警察から追われる身となったとしても、兵役を拒否して逃げるのも自分の「責任」となるわけだ。
実際にサルトルは、フランス領アルジェリアがフランスに対して1954年から独立戦争を始めた「アルジェリア戦争問題」にて、兵役拒否をした学生を支持し、真っ先にFLN(アルジェリア民族解放戦線)への支持を表明している。
それが、サルトルの考える「実存主義」であり、だからこそ「自由の刑に処されている」人間としては、自分の望まぬ「状況」に介入してそれを変える「アンガジュマン」が必要だ――という流れになるのである。
そこからサルトルが共産主義的な思想に展開していったのは、サルトルがブルジョア階級を「抑圧」と見たからでもあった。
実存主義は人間を解放するという意味でヒューマニズムであった。人間が自分を解放し、自由を手に入れ、この世の「歴史」の流れは神でも仏でも王侯貴族でもなく、自分たちの手によって自分たちで作っていくものだ……だから人間の解放のために自らの手で歴史を作っていくのが、これからの「実存主義」の時代の解放された人間の姿なのだ、という考えがあった。
歴史や自由や平和といったものは、ブルジョワジーの独占物ではない。そういった普遍的価値を皆が手にする事が人間の解放であり、だからこそブルジョワジーを打倒する事が実存的な人間の解放にもつながる。
ここからサルトルの共産主義的な思想の道が展開していく事になるのである。
「実存主義のもっとも大きな意義は、従来歴史的政治的現実を離れて独立に存在すると思われていた理念とか自由とか文学とかの観念を破壊し、歴史と一体である人間の責任を明らかにし、その責任をプロレタリアの解放に見出した点にある。したがってそれが左翼的になるのは当然だったし、またそれが文学や哲学の領域をこえて実際政治の中にはいってゆくのは当然のことであった。個人と社会、理論と実践の不可分離こそ実存主義の中核だったのである」
◆◆◆
本書が刊行された当時(1967年)、世界で革命運動の機運が高まっていた。
1968年5月のパリの五月革命に端を発する世界的学生運動の波。日本も60年代の半ばからベトナム戦争に対する反戦運動などがきっかけとなって学生運動が盛り上がっていた時期にあった。
そんな中で、当時の「思想家」や「小説家」としては非常に珍しく、個々の事件や問題に対して積極的にメディアに出て発言し、共産主義を擁護してきたサルトルはこの当時の若者の「知的アイドル」と化していたというのも頷ける話だと思う。
サルトルは共産主義者たちからしてみれば、マルクスの有名な「フォイエルバッハに関するテーゼ」の第11テーゼ「哲学者たちは、世界を様々に解釈してきただけである。肝心なのは、それを変革することである」を自ら体現した思想家でもあったのだ。
だからこそ本書でのサルトルの扱いは、期待すべき時代の寵児であり、その先見性を褒めてその当時世界を股にかけて大活躍していたサルトルを生き生きと描き、評価しているという点で、その後の低評価とは隔世の感がある。
そのためぼくからしてみれば本書は、当時の共産主義の盛り上がり、サルトルに期待する人々の熱意を記録し閉じ込めたタイム・カプセルのような読後感があった。
強制収容所などがありながらも、共産主義への道を考えればソ連を擁護すべきだとし、共産主義の運動にのめり込んでいって友人、知人らと袂を分かったサルトル。
構造主義、ポスト構造主義と、次々に思想トレンドが移り変わり、学生運動も下火になって、すっかり若者からも愛想をつかされたサルトル。
そういった晩年のサルトルの凋落ぶりを知っているからこそ、「何故あの当時、サルトルはあんなにも支持されたのか?」というのは、自分としては感覚的にもなかなか理解できにくいものがあった。
学生運動など自分たちの生まれる遥か昔の話だ――そう感じていた自分としては、その当時の人びとからのサルトルに対する生き生きとした期待感に触れられたというのは、この当時の思想潮流や時代感覚や、そしてサルトル思想の明暗をハッキリと示してくれるという意味で、なかなか得難い読書であった。
そう考えれば、本書がひょいと古本屋で発見し、今年最後のサルトル本になったというのは、割と悪くない縁であったとも思うのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
