
◆読書日記.《陳舜臣『玉嶺よふたたび』》
※本稿は某SNSに2021年4月20日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
陳舜臣『玉嶺よふたたび』読了。
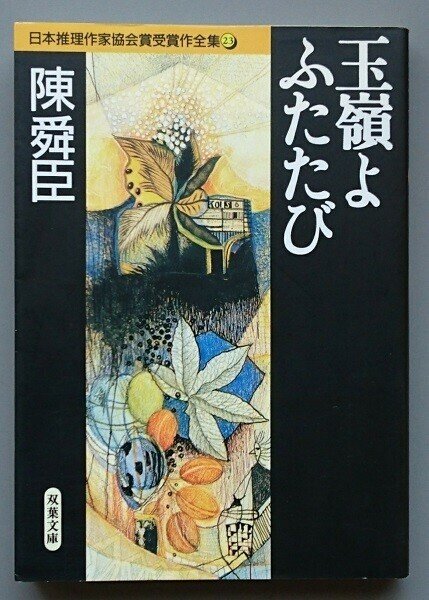
江戸川乱歩賞出身の小説家で、どちらかと言えばミステリよりも後年の『阿片戦争』『太平天国』『小説十八史略』等の中国歴史小説のほうで有名ではあるが、推理小説の名手でもある。
本作はその陳舜臣が長編『孔雀の道』と共に日本推理作家賞を受賞した長編ミステリとなっている。
<あらすじ>
大学教授8名からなる訪中視察団の内の一人であった東洋美術学者である入江章介は、ダメ元で申請した玉嶺への訪問があっさり許可された事に、彼は動揺していた。
実は彼は25年前の戦時中、まだ学者の卵であった時代に2年ほど玉嶺にいた事があったのだ。
玉嶺には名もない庶民が絶壁を削って作った磨崖仏があった。
仏像の美の源泉はことごとくギリシアの美を源流とする、という当時の支配的な見方に反発心を抱いていた入江は、ギリシアの表現のかけらもないそのアシンメトリで素朴な味わいのある造形に興味を惹かれていたのだった。
果たして戦時中の入江は、まだ抗日ゲリラが出没していた玉嶺に一か月ほど滞在する事となった。
玉嶺では日本の駐留軍指揮官の将校を嫌って地元一の物知りという李東功の家に逗留する事となる。
李には美しい姪がいて、名を映翔といった。彼女はその村の行われる行事である「点朱」に参加するのだという。
「点朱」とは、ある絶壁に彫られた巨大な磨崖仏に女性が登り、その仏の唇に紅をさすという行事であった。
この祭事で紅をさす巨大な磨崖仏には言い伝えがあり、昔一人の娘を巡って二人の男が絶壁に磨崖仏を彫ったという伝承が残っていた。
より美しい仏を彫ったほうを、娘の婿とするというものであったが、磨崖仏を彫っている最中、片方の男が崖から転落して落命した。これは、もう片方の男の奸計であった。
しかし、この謀は、当時の司直にすぐ見破られ、彼は捕らえられた。
男は、仏を完成させてから縄につく事を司直に約束し、自分の磨崖仏を彫り続けた。男は自分の磨崖仏を彫り終えた後、崖から飛び降りて死んだ。
彼の血は磨崖仏の頭から伝い、その唇にまるで紅をさしたかのように吸い込まれていったという……。
「点朱」は、この故事に由来する祭事であり、女性がこれを担当するのは、娘のために落命した二人の男の鎮魂の意味が込められていた。
「点朱」当日、祭事服を纏って絶壁を悠々と上っていく映翔を見た入江は、彼女を「美しい」と思った。
しかし彼は、薄々彼女が抗日ゲリラと通じている事を知っていたのだった……というお話。
<感想>
あらすじの通り、これは真正面から「本格推理」といった感じのミステリではない。
ミステリではあるが、その扱いはかなり薄いと言って良いだろう。
殺人事件やトリックのようなものも出てくる事は出てくるが、あくまで日中を股にかけ過去と現在を繋ぐこの人間ドラマを彩るための添え物にすぎない。
陳さんのミステリはどれも読後感が良い。それは彼のミステリが最終的には人情噺に落ち着くからであろう。
犯人がトリックで欺こうとするのも、探偵役の主人公らが追う謎も、明かされてみればみな「人の情」である事がわかる――だからこそ、陳さんのミステリは殺人事件が起ころうとも、雰囲気は爽やかですらある。
しかし、この時代の作家の知識や取材力はすごいものだったのだなあとつくづく思う。
戦時中の中国の抗日ゲリラと日本の駐留軍との争いをこれだけしっかりと説得力を持たせて描けるというのも凄いし、東洋美術研究家である主人公の美術知識もしっかりとしている(キャラクターの言動がしっかり「美術の専門家」として説得力があるという事)。
普通は、これくらいの知識がなければ、自分の生きた時代でもなく、自分の住んでいた地域でもない場所を舞台にして、説得力を持たせる事などできない。
つまり知識があるという事は、それだけ自分の描くドラマの舞台の選択肢が増え、自分の書きたいテーマに最適な道具立てを選ぶ選択肢も豊富だという事である。
これがこの時代の作家の実力であったのだろう。
本作は「ミステリ」と言うよりかは、抗日ゲリラと通じている美しい娘に恋をした、素朴な日本人の物語だと言えるだろう。
入江は、過去の思い出をたどりながら玉嶺を巡る。この玉嶺で発生した殺人事件には、彼の人生と深く関わっているのである。
それは、一人の娘を巡って発生した、あの磨崖仏に関わる伝承と二重写しとなっている。
その殺人事件の顛末については、既に決着がついている事であるし、それを入江もわかっていた。だが、この物語で本当に重要なのは「そこ」ではなかったのである。
本作のラストで明かされる「真相」では、過去に起こった殺人事件の「本当の意味」が伝えられる。
あくまで「真相」でも「謎解き」でも「種明かし」でも、ない。
「あの殺人事件にはどんな意味があったのか?」という所――「そこ」に、この事件の肝心かなめの部分であったのだ。
こういう趣向は、出来すぎと言えば出来すぎと言えなくもないが、最後に本作の構成全てをきりりと引き締めて巧い。陳さんは小説巧者だ。
本作は陳舜臣が書く本格推理の定型を微妙に外してはいるが、最終的にはちゃんと陳さんらしいミステリとなっている。明かされる真相は、けっきょく人情なのであった。
本書のAMAZONレビューの中で、小谷野敦氏が「凡庸なスパイ小説」と評し「現代の推理小説読者ならすぐに先が見えてしまうだろう」と断じていたが、この指摘は野暮というものだろう。
確かにぼくも本作のネタはすぐ見抜けたが、これを「スパイ小説」と断じて評するのは視点がズレているように思える。スパイ小説の面白みを主眼とした作品ではない事くらいは、読めばすぐわかりそうなものだ。
これだけ巧みに道具立てを揃えてシチュエーションを整え、日中に渡る壮大な恋愛ストーリーを書ける作家というのはそういないだろう。これだけの構想を持った恋愛ドラマを称して「スパイ小説」と断じてしまってはもったいないというものだ。
小品ではあるがピリリと辛い、切れ味の良い仕掛けを持ったロマンではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
