
◆読書日記.《西岡常一『木に学べ 法隆寺・薬師寺の美』》
※本稿は某SNSに2020年7月8日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
西岡常一『木に学べ 法隆寺・薬師寺の美』読了。
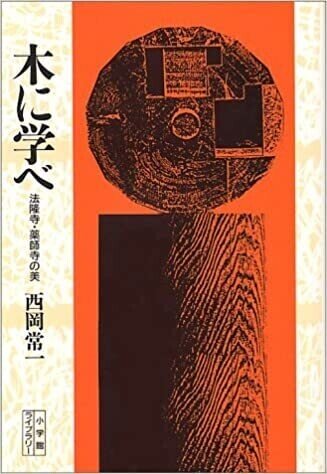
著者は法隆寺専属の宮大工であり、法輪寺三重塔、薬師寺金堂や西塔などの復元も行った、人呼んで「最後の宮大工棟梁」である。
文化財保存技術者であり文化功労者でもあった。その著者が長年の宮大工の経験を踏まえて古から伝わる日本の伝統的建築技術・技能を語り下ろした一冊。
著者は明治41年、奈良県は法隆寺の宮大工の棟梁の家に生まれ、小学生の頃から現場に出て働き、果ては法隆寺専属の宮大工の棟梁となった宮大工。
この方のノウハウの「語り下ろし」をしてベストセラーとなったのが本書。
一読、関西弁のおっちゃんが喋り散らかしている印象が強いが、この人の思想も知識も非常に頑健だ。
何しろこの人は戦時中から法隆寺の解体修理を担当し、古の日本建築のノウハウを「作り手」として理解してきた人間なのだから、文献学の考古学者や西洋建築の影響の強い建築学の言説にはビクともしない。
実際、法隆寺や薬師寺の修理・再建の際に考古学や建築史の学者と喧々諤々やりあって一歩も引かなかったと言われている。
そのために本書の著者・西岡常一は「法隆寺には鬼がおる」と恐れられたと言われるほどにまでなっていたそうで、学者についても「結局は大工の造った後のものを系統的に並べて学問としてるだけのことで、大工の弟子以下ということです」とまったく歯牙にもかけないほどだったと言われている。
「自らの手で作り上げる」というのはそれほどの事なのだろう。
事実、著者のノウハウは技術的なものだけではない。
農学校に学んで土壌や植物を知り、棟梁として設計から積算・人の手配・賃金・作業の進行まで担当する日本建築のスペシャリストなのである。
法隆寺の解体・修理に長年携わった経験から古代日本の建築法や建築思想を誰よりも知悉していたために「最後の棟梁」とまで言われた。
現代日本の建築学は西洋建築の様式に則ってガラス・鉄骨・コンクリの強度計算を行うが、古くから樹木のみを扱ってきた昔の伝統的な日本建築の構造力学とはまるで世界が違ってしまっている。
「木」というのは種類や樹齢だけでなく、育ってきた土壌や育成環境でも決まって来る。木は生物なので「クセ」があるのだ。
「堂塔の木組みは寸法で組まずに木のクセで組め」というのは、著者の家の棟梁らが代々口伝で伝えてきた教訓なのだそうだ。
普段の陽や風の当たり方によって木はねじれて「クセ」を持つ。
場所を移動できない環境でその時の環境に適応するために一本一本の木が捻じれ、根を張り、枝を張り巡らせて他の木と成長を競い合う。
だから、棟梁の口伝には「堂塔の建立には木を買わず山を買え」という言い伝えもあるそうで、切り出した木材から選ぶのではなく、山に入って実際に生えている木や土壌や周辺環境を直に見に行って選んでいる。
実際に著者は法隆寺に使うヒノキは国内にはなかったので、台湾の山に生えているヒノキを直に見に行ったという。
日本書紀にはスサノオの体から生えた木を材料にして「用うべくを定む」と書いてあったそうで、「ヒノキは瑞宮に使え、スギとクスノキは浮き宝(船のこと)にせよ。そしてマキの木は死体を入れる棺に仕え」等とあり、実際にもそれに従って法隆寺などの仏の伽藍はヒノキで作られているのだそうだ。
昔の職人というのは木の材質のクセや特徴というのを理解するのは必須の教養だったようで、実際に先日放映していたTV番組『ニッポンに行きたい人応援団』に出てきた伝統的なからくり人形師の玉屋庄兵衛氏なども、日本の茶運人形には7種類もの木材を使い分けて作っていると言っていたし、木工の伝統工芸師も作品を作る上で木材の種類や質にこだわる事のも割と普通にある。
特に建築は日本の風土の特性が大きく影響してくる。日本と西洋との風土の違いはほぼ真逆だ。
西洋は夏は乾燥していて冬の湿度が高い。それに対して日本は夏の湿度が高くて冬に乾燥している。だからこそ日本建築と西洋建築の考え方も大きく違っているのだ。
基本的には西洋でも東洋でも湿度の高い季節のほうが生活は厳しく感じられ、日本の建築では「雨が多く、暑くて湿気た夏をどう乗り切るか?」という考え方が設計上も反映されている。
暑さと湿気で問題なのはまず第一にカビが良く繁殖し、物が腐り易いという事。住空間を密閉するとこの条件はより悪化する。
だから日本建築は風通しを良くし、建物の構造体に直接陽の光や雨が当たらないように屋根を広げて軒を大きく張り出す設計が採用されるようになった。
西洋建築はこの点、逆だ。
住空間を壁で念入りに密閉して寒い外気を遮断し、軒を作らない事で陽の光を窓から直接部屋の中に導き入れようという考え方が採用されている。
西洋建築はそのように「寒くて湿気た冬をどう乗り切るか?」という考え方が強い。だから、西洋建築の考え方のままに日本に建物を作ると、錆びたり腐ったりカビたりしやすくなる。
本書の著者もそういった事を指摘している。
「建築基準法も悪いんや。これにはコンクリートの基礎を打回して土台をおいて柱をたてろと書いてある。しかし、こうしたら一番腐るようにでけとるのや。コンクリートの上に、木を横に寝かして土台としたら、すぐ腐りまっせ。20年もしたら腐ります。やっぱり法隆寺や薬師寺と同じに、石を置いてその上に柱を立てるというのがだいじなんです。明治以降に入ってきた西洋の建築をただまねてもダメなんや」
――西岡常一『木に学べ 法隆寺・薬師寺の美』より引用
また、日本は自然災害が多いので、建築物を長く持たせようと考えると地震や台風や雨に長年耐えられるような設計が必要となる。
つまりは地面の揺れや風による揺さぶりに耐えられる構造が必要となる。
西洋建築のように固く重くすれば地震で崩れてしまうし、建物が軽すぎれば台風で飛ばされてしまうという環境にある。
だからこそ日本建築には、柳のように揺れを柔軟に受け流す軟構造が必要だった。
強靭なゴムのような「柔軟な強度」を建築に持たせるには、木材を用いるのが適していたのだ。日本の環境からして、日本建築が木造になったのは必然だったのだろう。
構造上だけでなく、木材の扱い方次第で耐用年数も鉄筋建築とは違ってくる。
法隆寺に使われたヒノキは千年に渡ってこの建築をを支えてきた。
その耐用年数の秘密は、「樹齢」にありそうだ。
「ヒノキのええとこはね、第一番に樹齢が長いということです。法隆寺の伽藍の材料はだいたい千年か千三百年ぐらいで伐採されて材料になってるんですわ。で、台湾に行くと六百、二千四百年というのがあるんです。すると法隆寺の五重塔の心柱が、この日本に芽生えた時に、台湾にも芽生えたわけで、それが残ってるわけですわな。法隆寺は今まで千三百年たってますわな。薬師寺の東塔もそのとおり。ちょうど千三百年ですわな。こんな長い耐用年数のものはヒノキ以外にはありませんわ」
――西岡常一『木に学べ 法隆寺・薬師寺の美』より引用
それだけ育ったヒノキは幹の直径も2メートルを越えるものもあり、高さは数十メートルにもおよぶ規模となる。
それだけの大規模なおのれの質量を千年に渡って支えてきた幹だからこそ、上手く使ってやれば巨大建築を千年以上も支えていられるだけの耐久性があるのだろう。
こういった樹齢千年も二千年にも及ぶ樹木の材質を「構造材」として調べる研究があればまた建築における材木の再評価にもつながるだろうが、コンクリの耐用実験ほどそう簡単にはいかない。
先程も述べた通り、木材はコンクリとは違って一本一本に別々の「クセ」があるもので、なかなか得られたデータを標準化できるとは思えない。
千年や二千年にも及ぶ樹齢の木材をそうそう何度も耐用実験や耐用年数を計る研究に使う事も出来ないだろう。
宮大工というのは、こういった木材一本一本にある「クセ」を見抜いて、それぞれに適した仕事をさせようとするのだそうだ。
木が乾燥していく事で徐々に生まれていく「反り」を利用したり、木の反発性を利用したり、節の付き方や筋の入り方などのクセによって使われる場所や加工方法を変えていく。
そういった一本一本の「クセ」を利用するからこそ、例えば法隆寺の連子格子に使われる木材は太さや形がバラバラになっていたりする。
加工のあり方が材質によって変わるのである。
「木を割って作ったんですから、同じようにはなりませんわな。一本一本が違った性質なんやから、同じ形にしたら無理がでますわ。ですから、そうしないで、それぞれの特徴を見抜いて、一本ずつの個性を生かしてやってるんですな。そうして全体のバランスをうまくとってやる。(略)飛鳥の建築は、外の形にとらわれずに木そのものの命をどう有効に、生かして使うかということが考えられてるんですな」と著者も指摘している。
それでは、大きさや形を合わせずにバラバラに作るという事は、飛鳥時代の工人たちは建築デザインの美については度外視し、構造を優先させていたのだろうか?
著者によればどうやら、そうでもないようだ。
「なんでも規格に合わせて、おなじようにしてしまうのは、決していいことではないですな。人も木も大自然の中で育てられてますのや。それぞれの個性を活かしてやらなくちゃいけませんな。そのためには、個性を見抜いて、のばしてやる。そういうことが忘れられてますな。ごらんのとおり、全てが同じじゃおもしろくないし、美しくない」
――西岡常一『木に学べ 法隆寺・薬師寺の美』より引用
著者はこういう所に人や自然の有機的な温かみを感じているようだ。
つまりは用の美、機能美を自然的な美と捉える考え方なのだ。
「『人は仕事をしているときが美しい』といいますな。それは、人の動きや心に無駄がないからです。建造物も同じですな。機能美というんでしょうな。こういう美しさを。飛鳥の建造物にはこうした機能を第一とした美しさがありますな」
――西岡常一『木に学べ 法隆寺・薬師寺の美』より引用
こういう考え方も、西洋建築のシンメトリ構造や全体の部品の規格を合わせる人工美・装飾美的な思想とは真逆だ。
例えば著者は、装飾ばかりが華美になって「構造」の考え方が弱くなってしまった江戸時代の建築――日光東照宮などを批判する。「建築物は構造が主体」なのだと。
「建築物は構造が主体です。何百年、何千年の風雪に耐えなならん。それが構造をだんだん忘れて、装飾的になってきた。一番悪いのは日光の東照宮です。装飾のかたまりで、あんなんは建築やあらしまへん。工芸品です。人間で言うたら古代建築は相撲の横綱で、日光は芸者さんです。室町時代以降、構造を忘れた装飾性の強い建築物が多くなってますな。そやから、何回も解体せなならんのですわ」
――西岡常一『木に学べ 法隆寺・薬師寺の美』より引用
著者の主張のポイントは、装飾がダメだと言っているわけではなく「構造を忘れた装飾性ばかりの建築」がダメだ、と言っている点だろう。
何度も言う通り、その土地の風土に合っていて自然災害に対して耐性のある建築物でなければ、巨大建築など作る意味がないのだ。
著者は宮大工だからこそ、国のシンボル的な存在として伝統的な巨大建築を後世まで残さねばならない使命を持っている。だから「装飾ばかり」の建築などは「意味がない」のである。
本書を読んでいると、現代の日本の建築というのは、あまりに海外の様々な技術を無反省に取り入れてきた結果として、伝統的な工法の良かった所を総じてダメにしてしまっているのではないかと危惧してしまう。
「今の大工は耐用年数のことなんか考えてませんで。今さえよければいいんや」と著者は現代の大工を批判している。
「資本主義というやつが悪いんですな。利潤だけ追っかけとったら、そうなりまんがな。それと使う側も悪い。目先のことしか考えない」。
本書で著者の口を借りて語られる伝統的日本建築の考え方というのは、構造から建材論、美学に至るまで、古の工人の"思想"をもこの人は再現しているのだな、とつくづく思わせられるのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
