
◆読書日記.《乾正雄『夜は暗くてはいけないか 暗さの文化論』》
※本稿は某SNSに2020年11月14日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
乾正雄『夜は暗くてはいけないか 暗さの文化論』読了。
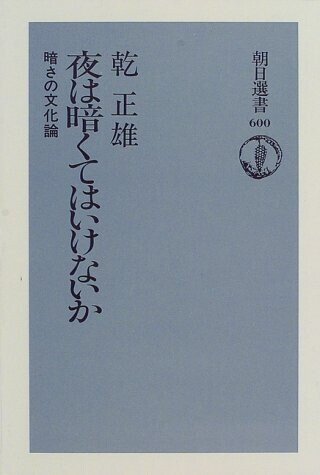
照明と色彩を専門とする建築学者による、人間の生活や文化や生理などあらゆる「暗さ」の価値について考える一冊。
本書の結論を先に言ってしまえば「照明は明るいばかりでなくとも良くて、省エネを考えるならばむしろ暗さとの共存を考えても良いのでは?」という提案を示して終わる内容となっている。
◆◆◆
この手の論文はメインテーゼがシンプルなものほど切れ味がいいものだが、本書の場合は若干「普通」という印象を受けてしまう。
というのも、日本は不必要なほどあちこちに照明を設置していて明るすぎる、というのはもう何年も前から言われていた事だからである。
それを象徴しているのが日本の歓楽街におけるネオン・サインの騒々しさで、これは高度経済成長期にはもう煩がられていたのではなかろうか。
本書でもしばしば取り上げられる谷崎潤一郎の随筆『陰翳礼讃』(昭和8年)の時代にも既に日本は急速に照明を普及させて街の隅々まで照らし上げたという記述があった。
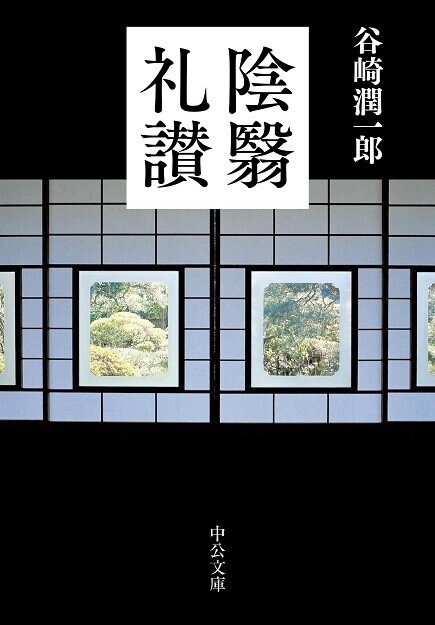
『陰翳礼讃』にもあるように、江戸時代の照明は明治維新の前までロウソクか種油だったし、街灯のような公共照明もなかったので、人々は夜は闇と共存していた。
それが、『陰翳礼讃』の時代の1933年にはもうヨーロッパを抜いてアメリカに次ぐほど照明が普及して街が一気に明るくなっていたのである。
日本の住宅照明の変化スピードは驚異的で、西洋では石油ランプが開発されてから現在まで200年以上かかっている上に、蛍光灯もそれほど歓迎されて取り入れられているわけではないそうだ。
それに対して日本は明治時代に石油ランプが輸入されてから蛍光灯が流行った昭和20年代までわずか80年という早さだった。
明治時代以降の日本というものは、それ以前に積み重ねてきた日本の伝統文化をことごとく西洋文化に塗り替えていった歴史であったが、その流れの中で失われたもの内のひとつが「暗さの美」であった、というのは『陰翳礼讃』でも言われている事である。
日本は「暗さ」と慣れ親しむ余裕がなくなってしまったようだ。
住宅照明でも、深い考えがあるわけでもなく「明るければ明るいほど良い」という方向で無尽蔵に部屋の中を隅々まで照らし出す考えで発展してきたために、谷崎の言う様に長い事「暗さを堪能する」という意識が抜けていたのではなかろうか。……というのが本書の著者の主張のひとつとしてあったようだ。
明治以後の日本の「明るさ礼讃」の傾向の要因の一つとしては、日本の近代化、近代化の手本としての西洋化という事もあった。
「電灯の明るさイコール文明開化」という、江戸時代の夜の暗さとの差異化としての照明というイメージがあったのだろう。
だが、著者が言うには西洋人は日本ほど電灯の明るさをありがたかったというわけでもなかったようである。
ヨーロッパなどでは、未だに室内でのロウソクの明かり=暗がりを事を好む人も多いと言う。
例えば、著者によると「接客時に室内が暗いことが、客に対して失礼であるという感覚は、欧米にはないようだ」という。
「それどころか、事務室のような明るさの下での食事を野蛮だという。電灯を消して、ろうそくの灯で食事の接待を受けた経験は、私にも一度ならずある」というように、西洋人は、日本人ほど室内の明るさにこだわってはいないようなのだ。
この東西の認識の差の理由の一つとして著者は人体生理学的な点を説明する。
ここら辺の事情は面白いので、本書の中から引用してみよう。
「蛍光灯が普及した一九五〇年ころから、欧米では、グレア(まぶしさ)の研究が盛んになった。高原の明るすぎによる不快なまぶしさは、「青い眼」には大きな問題である。光は、強くなると、瞳孔からだけでなく、虹彩を通しても侵入するからだ。ところが、不快なまぶしさの研究は、欧米の学者が熱心なのに比べて、日本ではあまり興味をもたれなかった。「黒い眼」では虹彩が光を遮断する能力が高いので、日本の研究者自身が、まぶしさをそう不愉快なものと感じなかったせいだろう。(略)それでも六〇年代に入ると、予想通り、「黒い眼」は「青い眼」よりまぶしさに鈍感であること、まぶしいかまぶしくないかの境目の輝度を測ってみると、「黒い眼」は「青い眼」の倍くらい高いこと、を示す研究が出てきた(市川宏、長南富男「まぶしさの快不快限界線に関する基礎的研究」)。まぶしいと感じ始める輝度が倍もちがうということは、「黒い眼」が「青い眼」よりも、まぶしさに対する耐久力が倍もあることを示す。たいへんなちがいといってよい」
つまり、西洋人と日本人では「まぶしさ」の感じ方が倍も違っていたのだ。これが東西の照明文化の差に出てきているというわけである。
著者は斯様に「明暗」についての欧米と日本との差について、生理学的な事情だけでなく建築思想の差や気候の差についても言及している、非常に興味深い比較文化論となっている。
◆◆◆
特に気候については和辻哲郎が『風土』でも指摘している東西の気候の差に起因する文化の差異についても興味深い比較が為されている。
日本の気候は「夏:湿気ていて暑い」「冬:乾燥していて寒い」であり、西洋は「夏:乾燥していて暑い」「冬:湿気ていて寒い」となっている。
この気候条件の差が「快適な住み心地の住居」のスタイルに差を生んでいるのである。大抵の場合、人は「湿気ている季節」のほうに「過ごしにくさ」を感じるようである。
なので、建築も「湿気ている季節」をどうやり過ごすか、という思想の元に作られるケースが多いようだ。
だから伝統的な日本建築は「蒸し暑い夏をどう快適に過ごすか?」という建築思想になる。
高床式で床下に風を通し、柱を立てて屋根を乗せる、という開放的な作りにして全体の風通しを良くする。また、屋根は軒を深くして、夏の陽の高い時期には陽光が直接部屋の中まで差し込まないようにしている。
日本建築は室内に空気が滞留して、湿気が建物内に籠らないようにしているのである。
このように考えれば現代の密閉性の高い日本住宅は、伝統的な日本建築の考え方とは真逆の構造をしている事が分かる。
それに対して西洋建築は「湿気た寒い冬をどう快適に過ごすか?」という建築思想となる。
西洋の湿気た冬は、日本より曇りが多くて日照時間も日本より短くなる。
寒さが肌に纏わりついてきて、湿気が多いと霧も発生する。暗く、寒い、生物の死に絶えた「氷の世界」となる。
こうなると住居は、家に対して「人の生活を自然の驚異から守る殻(シェルター)」という考え方が出るようになる。
断熱効果を考えた建築思想が発達する。
分厚い石壁で四方を囲う事で外の気温を中に伝えないようにするし、断熱効果を考えて窓はあまり広くは作らない。換気機能よりも「壁に空いた明り取り」が窓の考え方となる。
このように「外気をシャットダウンする分厚い壁」というのが住みよい住宅の条件となると、西洋人は自然と「うす暗い室内」と慣れ親しむようになっていくのである。
こういった各地の気候の差が、建築様式の差にもつながってくる。そして、その建築様式の要請に従って西洋人は「暗さ」と共に生活をしてきたのだろう。
西洋人が「明暗」に敏感なのは、生理学や気候だけでなく、東西の日照時間の差というのも関係しているのだという。
東京における夏と冬の日没時間の差は二時間二八分、それに対してロンドンの夏冬の日没時間の差は四時間二七分にもなるという。日の出時間の差も、日没時間の差と同程度あるというから、ロンドンの日照時間の夏冬間の差は八時間四九分もあるという事が分かる。
著者はある西洋人から「日本は四季の差があまり感じられない」という感想を聞いて「えっ?」と思ったそうだが、われわれ日本人が四季の差を「寒暑差」を基準に考えるのに対して、西洋人は「光の差」の基準で考えていたようなのである。
これを著者は、日本が「寒暑の文化」であるのに対して西洋は「光の文化」であると言っているのである。
このように生理学的、気象学的、建築学的、等々、西洋人とわれわれ日本人とでは「明るさと暗さ」の捉え方にこれほどの差があるのだ。
現代日本社会の照明が往々にして明るすぎるのは、われわれが西洋よりも光に対して鈍感だから、という事も言えるのかもしれない。
◆◆◆
さて、翻って現代のわれわれの建築物の傾向を反省してみたい。
ビルディングのような公共建築にしても、マンションや一軒家にしても、現代日本建築は密閉性がより進んでいる。
要は「すきま風」の入ってこない、断熱効果の高い壁に囲まれた建築スタイルが現代日本には多いのである。
これは上述したようにむしろ伝統的西洋建築の考え方に近い。
こういうスタイルの建築物というのは、日本の夏は湿気を室内に閉じ込めてしまい、冷房を効かせていないと蒸し風呂状態となる。
そのために日本の商業施設でも公共施設でも一般家庭でも、クーラーは欠かせない家電製品となってしまっている。
また、日本の伝統建築のように開放的な作りにはなっていないために電灯も必需品で、その上「光に鈍感」なためなのか、商業施設でも公共施設でも室内光は常に不必要なほど煌々と灯っている。
つまりは、省エネの観点から言って、現代日本建築はとてもエネルギー効率の悪い建築が多くなってしまっているのではないかというわけである。
この省エネとエネルギー効率の観点から、もっと光量も電気量も抑えながら、豊かな照明効果の得られる方法を考えるべきではないか、というのが本書での著者の最終的な結論になってくるのである。
本書は1998年刊と20年以上も以前の著書なので、著者の新たな「提案」は、若干貧弱な印象を受けてしまう。
当時オフィスではPCのディスプレイに蛍光灯の光が映り込まないように照明をデザインする事が重要となってきたという状況があったのだという。
しかしこれは西洋の照明デザインの傾向のようで、実際、日本のオフィスでは未だに蛍光灯がコンビニエンスストアの店内のようにかなり遠慮なく煌々と光っているものも多い。
やはり、日本人はそういった光の微妙な加減に関してはそれほど関心を持たない傾向にあるのかもしれない。
しかし、ぼく的に本書の価値はそういった思想や提案の部分ではなく、それを支える様々な「明暗についての東西比較データ」の面白さにあると思うのである。
上述してきたように日本人は景観環境や照明環境といったものに、どうやら鈍感にできているらしい。
そういう日本において「暗さの美」を再評価した谷崎の『陰翳礼讃』はけっこう優れた随筆であったと思うし、谷崎の提示した「暗さの美」の再々評価をするうえで様々なデータを提示してくれているという意味では、本書も今後の建築デザインや住環境デザインを考える貴重な資料の一つとして価値があるのではなかろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
