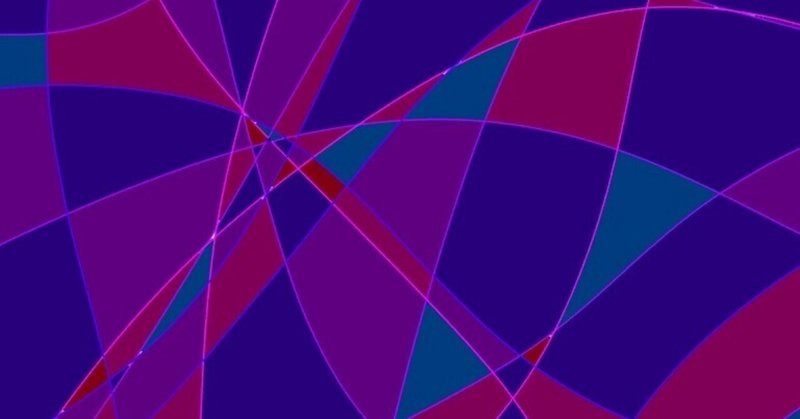
お金の仕組み1(歴史編)
こんにち殺法。(某作品に大きな影響を受けております。)今日から5日間かけてお金というものについてお話していこうと思います。今手元にあるお金とは何なのか、一緒に考えていきましょう。
そもそもお金とは。人間はその昔(縄文時代より前)ではお金は存在していませんでした。お金が存在しないなら何で物を買ったり売ったりしていたかというと、「物」(魚、肉、毛皮、木の実)なんです。「物」と「物」の交換すなわち物々交換というもので人々は経済活動(生活)をしていたわけなんですよ。今でもこの事例はありますよ。例えばトレーディングカードゲームなんかをやっている人は良くある話ではないでしょうか?カードとカードを交換する。これもまた、物々交換です。昔は「物」でなければ交換が成り立ちませんので、必ず「物」を自分で作りだしたり生み出したりする必要がありました。
貨幣制度の登場。貨幣というものは、縄文時代から既に存在していたという説があります。その時には紙や、金、銀、ましてや合金などはなかったので、自然界にあるもの。例えば貝殻や石などを貨幣として使っていた。しかし、貝殻や石はやがて朽ちてします。当時は銀行なんてものもなかったわけですから、貝殻に変えたらすぐに使おうとします。時代が進むにつれて、中国から青銅という合金の作り方を教わります。これからが速くて、貝殻に代わるお金、硬貨が誕生します。そして硬貨を作る時代は江戸まで続きます。しかし、この時点でもその硬貨に価値がありました。金や銀など。そして江戸時代からは皆さんおなじみの紙幣が流通するようになります。一番わかりやすいものでいうと藩札(江戸時代の藩ごとに作った紙幣)を世に出回らせます。これはなぜ行ったかというと、徳川幕府がお金を藩に蓄えさせないようにするためでした。お金がなければ反乱を起こそうと思っても起こしにくいですからね。(その時にお金を持つものは汚いという話も広まりました。)ですが、藩にもお金が必要ですので、藩札というものを発行して信用貨幣を初めて実現させました。ここから私たちの時代に入っていくわけです。
信用貨幣の登場と金本位制。明治時代に入ると、江戸幕府はボコボコにされて新しい明治政府ができます。その時に一番困ってしまったのが武士の後始末でした。武士たちはそのほとんどを明治政府が作った日本軍に入れたのですが、それでも各地には多くの武士がいました。それを一気に解雇すると反乱がおきてしまうので、こう考えるわけです。大きなお金を一回で渡して満足してもらおうと。そのため武士は武士ではなくなってしまいましたが、大金を手に入れ、商売や職人として生活をはじめました。和菓子職人なども多くが武士から派生しました。これで明治政府は安泰かと思いきや、外国が金を交易と偽って為替していくので金がどんどん流出していきます。そのため国内では金が不足し、暴動が多発します。その時にも多くの紙幣が発行されました。しかし、今とは違い金本位制というものに基づいて紙幣は発行されました。例えば1000円札を銀行に持ってきて金と交換してほしいといえば金が1グラムもらえるといった感じです。こうして紙幣は世の中に急速に広まっていきました。
金本位制からの信用貨幣制度。日本は戦後多くの資金を必要としました。それをGHQから借りていたわけです。しかし、日本にはもうお金(金)がありませんので国内で経済を回すことが困難になりました。そこで誕生したのが信用貨幣制度です。今皆さんの手元にある1万円札はファミチキが71個ぐらい買えるという信用によって成り立っています。(なんでファミチキやねん)ほとんどの国が今は信用貨幣制度を基軸にしています。お金とは人間が長い歴史から生み出したものということがお分かりいただけましたか?
それでは今回はここまでで、次はお金の仕組み2(銀行)でお会いしましょう。good bye
your support will support me
