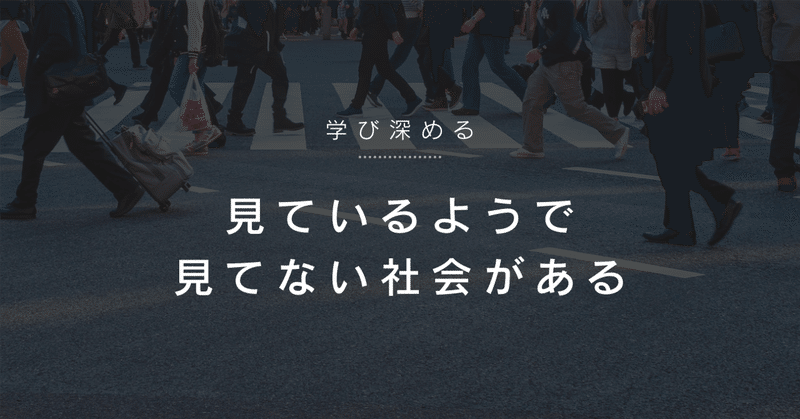
聴覚障害者向け「音が目でわかるプロダクト」を私たちがつくる理由
ONTELOPE(オンテロープ)代表の澤田です。私たちは、聴覚障害者向けの「音が目でわかるプロダクト」を開発していますが、「どうしてこのプロダクトをつくっているのですか?」「知人や家族に聴覚障害者がいるのですか?」とよく聞かれます。
今回は、なぜ私たちが「音が目でわかるプロダクト」をつくるのか、開発前の私自身の体験や当時の思いと合わせて、その理由を語ります。
プロダクト開発のきっかけ

私は音に関するさまざまな仕事をしていますが、その中に音をつくったり整えたりする仕事があります。例えば、映像に音を付ける仕事では、まったく音のない無音の映像から、一つ一つ音を付けて調整していくことがあります。
自然の音、街の音、人の声、電化製品の音、BGMや効果音。シーンの意図によって、無限のパターンから音をつくるのです。音がある状態とない状態、または音の世界のつくり方によって、出来上がる映像の意味はまったく変わります。
そして、長年このような経験をしてきたため、私は「音のゆたかさ」と「音の可能性」をよく知っています。
聴者にとって「音」は、情報を知るうえで役に立つものであり、時には心理状態に影響を及ぼします。その「音」をうまく利用し、自分の生活を整えたり、社会自体がつくられたりしています。そう、聴者は「音のゆたかさ」を浴びるように生活しているのです。
「この音のゆたかさを聴覚障害者の人たちとも共有したいなあ」
仕事をしながら、このようなことを度々考えていました。そして、音が目でわかるプロダクトの構想自体は、約5年以上前から頭の中にありました。
音のエンジニアリング的な仕事を進めるなかで、私の実装技術がいつの間にか身に付き、実験的にプロトタイプをつくったのがONTELOPEの始まりです。
見過ごされてきた人たち

音が目でわかるプロダクトの原型をつくったものの、私には聴覚障害者の知り合いが1人もいませんでした。聴覚障害者とのワークショップに参加したり、人に紹介していただいたりしながら、少しずつ聴覚障害のある友人が増えました。
ところが、ろう者・難聴者の友人や、ONTELOPEの研究・実証実験を進めていくなかで、これまでの社会と聴覚障害者との関係性を知り、誇張ではなく、幾度となく衝撃を覚えました。
聞こえに困難がある人と聴者との現実に、大きな違いがあること。
社会が聴覚障害者にとって良かれと思ってやってきたことが、ぜんぜん良くなかったこと。
聴覚障害者の文化や価値観、誤解を恐れずに言えば、人権が軽視されていること。
聴覚障害者は、社会に見過ごされてきた人たちだった——、ということです。
朝から晩まで、さらに寝ている間も聞こえないということがどういうことなのか。社会生活の中でどれほど多くのバリアが存在しているのか。社会は、人として同じ価値を持つ聴覚障害者の困りごとを見過ごしてきたのです。きっと、聴覚障害者に限らず、世界にはまだまだ見過ごされている人たちがいるのだと思います。
目に見えないものを共有するということ

この世には、目に見えないものがたくさんあります。例えば、音や価値観です。目に見えないものは、共有することが容易ではなく、時に労力を要します。
「CM音楽つくりたいんだけどさ、“かっこいい感じ”で頼むよ!」と言われたとしても、「あなたにとっての“かっこいい感じ”の音楽とは?」ってなりますし、相手もつくり手も、言葉で表したものが実体として目に見えない音の説明をするのはとても大変です。
同じように、価値観や困りごとも、本質的な感覚までをきちんと言葉で説明するのは容易ではありません。これが、聴覚障害者の困りごとがなかなか社会に理解してもらえない原因でしょう。
一見して聴覚障害があるとは分からない。
聞こえの状態によって内面の価値観や文化が違う。
言語に対する脳の使い方が違う。
言語コミュニケーションの隔たりにより深く対話する機会が少ない。
同じ社会で生活しながらも聴者と聴覚障害者との間では、このような目に見えにくい差異があり、なかなか共有しづらいものです。一方で、このような差異こそ、互いを知るうえで大切な部分だったりもします。
今の社会では、共有すべき聴覚障害者の困りごとをうまくキャッチすることができていません。存在の表面的な部分を捉えるだけではなく、目に見えないものを共有するためには、相互探求を行うことが必要です。
互いの価値観だけではなく、困りごとや目に見えない痛みも共有できて、初めて他者の人権を軽視することは少なくなっていくのではないでしょうか。
正しさとは何か
ONTELOPEは、プロダクトづくりだけではなく、相互探求の文化づくりをとても大切に取り組んでいます。たとえ、「音が目でわかるプロダクト」で多くのろう者・難聴者が、音をわかるようになったとしても、いわゆる少数派に対する社会の向き合い方が変わらない限り、社会を形成する人々の価値観や感覚は変わらないからです。
「正しい」と述べることはとても難しく、ある意味危険で怖いことでもあります。それでも人類は、共通の正しさの認識を積み上げてきました。
奴隷制度は間違っている、人の命を奪うことは間違っている、虐待は間違っている、人権軽視は間違っている。同じように、見過ごされてきた聴覚障害者の困りごとや価値観を、これからも見過ごし続けることは間違っていると私は考えます。
正しさとは、人類や社会が、自らが覚悟を持ち決定づけていく倫理的な共通概念なのだと思います。
目に見えない音、目に見えない聴覚障害者の困りごとに向き合うことは、人類社会がゆたかさを形成するプロセスにつながる大きな一歩になると私たちは信じています。
ONTELOPEは、プロダクトづくり、相互探求文化づくり、両輪でゆたかな現実をつくっていきます。
