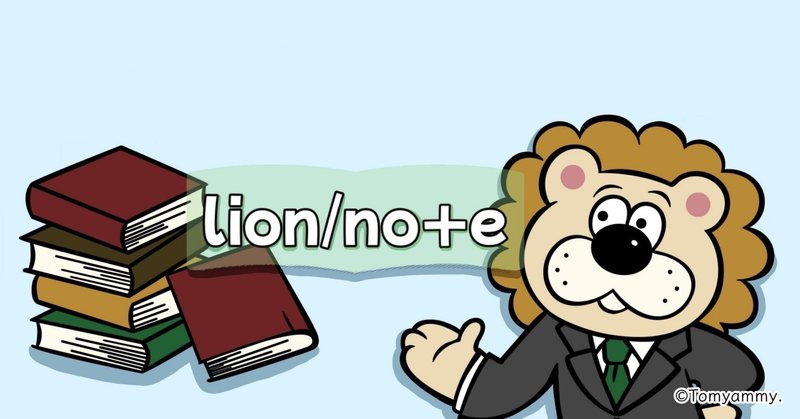
読んでいても読んでいなくても、「本を通したコミュニケーション」を。そろそろ、あの本の読書会をやってみたい
ヘッダーを変えてみました!
@Tomyammyさんにステキなヘッダーを作ってもらいました。
今日から66日ライティング×ランニング1日目ということで装いも新たに楽しみながら、今日一日を最高の一日にできればと思います。

ひさしぶりに読書会をやってみたくなってきた
ここ最近ちょいちょい「読書会」にお邪魔しました。
ひとりで読むのとはまた違う読書体験がありました。
とくに、デヴィッド・グレーバーらの「万物の黎明」は一人ではこういう読み方はできなかった。とりあえず今は、もう一回読もうって気にはならないけど(笑)
そんななか、きくちしんいちさんから、読書会をやってみましょーよというお話もありました。


実は、リアルでの読書会というのは数年前に何回かやったことがありました。
場所を借りて、私設図書館を作って、本を通したコミュニケ-ション空間を作るっていうのをやろうとしたことがあったんですね。
その試みは、いろいろあって辞めてしまったんですが、そのイベントでやった読書会は楽しかった。
そのときは、自分のオススメの本を持ち寄って紹介しあったり、課題本を決めて感想を言い合うみたいな感じでした。

当時、課題本でそれをチョイスするセンスがすごって思った(笑)
読書って一人で読むのも良いですが、一人じゃないパターンもいいなと思います。
ということで、読書会やりたい願望が湧いてきたので、今回は、今自分が読書会をやるんだったら、こんな感じがいいかなっていう願望を言ってみようと思います(笑)
オンラインの読書会を主催したことはないので、よくわからないことも多いですが。。。
課題本
まず何の本を選定したいかといえば、これは、明確に1冊あります。
本noteのコンセプト本でもある
「読んでいない本について堂々と語る方法」
です。
※Amazonのアソシエイトによる広告を含みます。
全部で第1章から第3章まであるのですが、なんとなく、分量的に前半と後半の2回に分けてやるのがいいんじゃないかと思っています。
テーマ
そして、あらかじめ本に対する話題を入れておくと、話が盛り上がりやすいんじゃないかと思いました。
実は、感想文を書いたのが2年前だったので、昨日、ちらっと本を見直したのですが、あれ?こんなこと書いてあったっけ?となりました(笑)新たな発見があった。大量にあった(笑)
それでもって、思い付いたトークテーマは例えばこんな感じ。
トークテーマ(案)
はじめに
・「読んでいない本について堂々と語る」ことはタブーなのか?
・<読まずにコメントする>という経験
・読書を難しく、偽善的にしてしまう3つの規範
・「読んでいない」とはどういうことなのか?
・バイヤールの脚注の略号の謎
第1章
・未読の諸段階(「読んでいない」にも色々あって・・・)
・本を読むことは、本を読まないことと表裏一体
・ムージルの司書が本をまったく読まないのはなぜか?
・書物について語る決め手は<共有図書館>
・読書の過剰は、アナトール・フランスから独創性を奪う
・いかなる本のなかにも入っていかないが、すべての本の間を移動する者
・本に対して適当な距離を保つ
・バイヤールは「薔薇の名前」を読んだのか?
・本が公にされた瞬間に、それが引き起こす様々な言葉のやりとり
・遮蔽幕(スクリーン)としての書物
・本を読んでも、読んだことは忘れ始める
・教養を到達できない高みのようにイメージしてしまう者たちに安心感を
第2章
・バイヤールは「サンタフェの孤独な騎手」を読んだのか?
・耳の聞こえない者同士の対話
・<共有図書館>と<内なる図書館>
・ティブ族は「ハムレット」をどう読んだのか?
・作家は、自分が書いた本を一番よく知っているのか?
・読んでいない本について、著者自身の前でコメントする場面。そして、このシチュエーションを考察する意図
・<内なる書物>を一致させることはファンタジーでしかない
・他人に関心をもつことで、フィルはリタを魅了した
第3章
・書物は、現実の書き手の延長線上にある。
・<共有図書館>の中で占める位置を知ること
・ハワード・リングボームの失敗と<ヴァーチャル図書館>
・<ヴァーチャル図書館>はあいまいさを保持し続ける必要がある
・欠陥なき教養という重苦しいイメージから自分を解放する
・書物も著者も読者も変わる
・<他者>は知っているという習慣を断ち切る
・ヴァーチャル図書館は不明瞭だからこそ、独創的な創造を生み出す
・<幻想としての書物>に生命を吹き込む
・書物は大事なものを語ろうとするときの口実に過ぎない
・重要なのは書物をつうじて自分自身について語ること
結び
・読んでいない本について語ることが正真正銘の創作活動
・誰にでも創造の世界は開かれている
・(番外)千葉雅也さんはこの本をどうとらえているのか
めっちゃ出てきた(笑)。でも、まだ拾い切れていない気がする。
いろいろトークテーマを妄想してひろってみて思ったのですが、やはり、この本は、「読んでいない本について聞かれたときに、うまく乗り切るためのノウハウを伝授する本」だと読んでしまって終わるのはあまりにももったいないような気がしてしまいます。
と、ここまで書いてみてこんなことを思いました。
これは、読んでいない本について語る場面だけの問題ではないのでは?
例えば、noteを書くことについては、何か生かせないか?
実際に、自分はこの本をコンセプト本にしたことによって、noteに生かせる学びがたくさんあったので、noteに生かせるという側面は多々あるような気がしています。
ということで、今やるんだったらこんな感じのテーマ
「読んでいない本について堂々と語る方法」を読んで、noteに生かす方法を考えてみる
明確な答えがあるわけではないんですけども、こういう接続みたいなのがあったほうが読書会が面白くなりそうな気がしています。
実際に、私はnote書いているときに、あ、こんな感じで「読んでいない本について~」にも書いてあったなあって思って、引用することが多いので、面白いなと思っています。

きくちさんやるんだったらいつがいいですかね?
てなわけで、7月に入ってから、x(旧twitter)のスペースでゆるゆる、上記のトークテーマから全部がっちりやると疲れそうだから、気分で選んでタラタラやりたいなあと思っています(願望)。
スペースだと聞き専もアリですし、また、読んでいなくても、開いてすらいなくても、買ってすらいなくても、参加できると思います。なぜなら、この本が「読んでいない本について堂々と語る方法」なのだから(笑)。
ということで、もし何か興味がある方、いやもっとこうしてみたらいいんじゃないかといった意見がある方はコメントいただけると嬉しいです。
そんなわけで、こいつまた同じ本のこと言ってるよって感じで、「今日一日を最高の一日に」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
