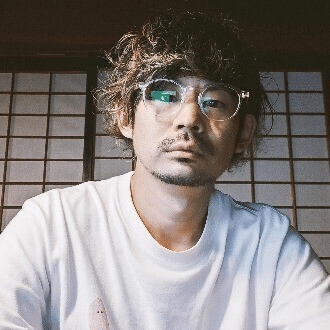企画はできるけど運営できない、が、未来を潰してる。
そんな話を、先日、立て続けに1日で2回もしてしまった(たのしかったなぁ)。それぞれ行政に頼ることなく、独自で鳥取県内でしっかり積み上げる取り組みをしている方たちだった。
そう、課題(的なもの)を見つけて、ビジネスモデルというか他地域事例をもとに机上の空論で組まれた企画を練るところまではそりゃできるでしょうよ。
一番大事なのは、その企画をちゃんと運営しきること。特に(ハードでもソフトでも)拠点をつくる企画こそ、そこで「何をするか」でなく「誰がするか」に重きを置いて、運営していかんくちゃいけない。
地域プロジェクトの初期フェーズでは属人性が重要になる。そこを考慮しないから、運営がうまく回らない。そういうとき、企画した人が運営に入らない場合が多く、口だけを出してるだけ。運営する人はふり回れ、現場はじょじょに蝕まれるように疲弊する。
また、都会からきた外部人材だけが企画をがつがつ進めているケースだと、地域住民からすれば蚊帳の外で「いろいろ進めているねぇ、で何が変わってるの?」とツッコミを入れたくもなる。ポーズで”やってる感”を見たいわけじゃなく、”やって何が変わったのか/変わっていきそうなのか”を自身もその場にまざって体感したいわけだからそりゃそうだ。
働き方改革だかSDGsだかリカレント教育だか国の指針だかわからないけど、地域の現状に合わせてはやってくれないのね。置いてけぼりよ。そういうふうに感じちゃうと、それが自治体の事業に対しては希望を抱けなくなる。「ここには何を言ってもムダだ」「ここでがんばって変えようとしても意味がない(から他のところでがんばろう)」と無関心になり、直接的なコミュニケーションをとろうとすらしなくなっていく。
だいたい一年くらいで事業が終わるとして、委託される事業者は毎年変わっていくものが多いだろう。1年目の印象が、2年目に引き継がれる。事業者が変わったとしても。だから、単年で関わることもじつはその数年後の未来につながっている。一度へんな先例をつくられると、似たようなことを任される次の事業者はたまったもんじゃない(これね、各自治体の地域おこし協力隊のマネジメントにも言えること)。
だから、それぞれに責任があると自覚しながら、事業者はプロジェクトが"持続可能になるように”企画して、ちゃんと運営もして、次の人たちが自走できるようにバトンを渡せるようにしたい。運営ができないなら、できるところでがっつり組めばいいじゃん。
そして何より、いい事業者に発注/コーディネートできるような眼力と胆力を自治体は持たないと、逆に事業者に消費されるだけで何も発展しないおそろしい未来が待ってるんじゃないだろうか。おそろかにしがちだけど、人事ってめっちゃ大事。
そんな未来予想をしながら、日々過ごしてます。ぼくは違った道から「小さく、じんわり変わる」をつくっていければと思っている。
いいなと思ったら応援しよう!