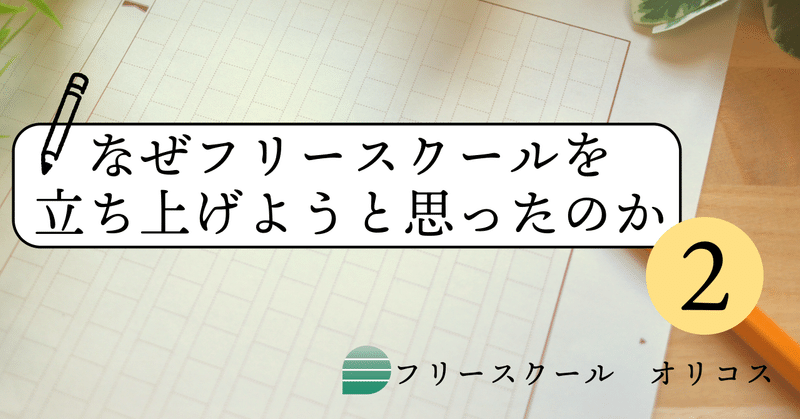
フリースクールを立ち上げようと思ったきっかけ(2)
前回に続き、教員時代での話です。
私は特別支援学級の主任をした経験がありますが、とりわけ発達障害についてはよく勉強していました。
発達障害の特にASD(自閉スペクトラム症)と不登校について疑問に思っていたことがあります。
本当にASD?
私が自閉症・情緒学級(特別支援学級は障害種別に分かれています)というクラスを担当していた頃、通常級で不登校となった子どもが新年度から転籍し、私の学級に来ることになりました。
ASDの診断があるとのことでした。
発達障害というのは、DSM−5という精神疾患の診断基準を使って医師が診断します。
このASDは自閉症はスペクトラム(連続体)となっていて、明確に分けられるものではないとして、現在の名称になりました。
私はASDの診断はありませんが、ASDの特徴の一つである「こだわりが強い」を少なからず持っています。
例えば、私はコーヒーに砂糖を絶対に入れません。
このことも「こだわりが強い」といえるでしょう。
ではどういった判断で診断されるかというと、特徴とされるものが日常生活に支障をきたすほどであれば、障害として診断されるようです。
ASDの診断があるその子は、何か生活に支障があるほどのASDの特徴がありませんでした。
生活に支障が出ているとするならば「学校に行けなくなったこと」くらいです。
つまり、不登校になったことが「日常生活に支障をきたしている」と判断されたのではないかということです。
もしくは、薬が必要だと判断されたために診断したのかもしれません。
いずれにしろ、医師は診断した方がその子のためになると考え診断しているはずです。
念のため誤解のないように言うと、医師の診断がおかしい、と言いたいわけではありません。
私がお伝えしたいのは、そういった診断を出さなければならないほど、これまでの学校教育は子どもたちを苦しめていた、ということです。
もしかすると、学校教育のあり方によってASDに限らず、発達障害と診断する必要のない子どももいたのではないかと考えています。
発達障害に対する理解が広まったとはいえ、自分が発達障害だと診断されて少なからずショックを受けた子どもがいたはずです。
教育のあり方によってそういった子どもを生まなくて済むのならば、やはり日本の教育のあり方はもっと変わらなければならないと感じました。
誰一人取り残さない教育
ここからは少し話が逸れてしまいますが、学校も当然のことながら、子どもを苦しめたいわけではなく、良かれと思ってやっていることが結果として苦しめていることがあります。
私も教員時代に良かれと思ってしていた指導によって子どもを苦しめていたであろうことが、今になればよくわかります。
また、構造上の問題で子どもを苦しめてしまうこともあります。
公教育に競争させ優秀な人材を選抜する機能があることや学び直しのできない履修主義となっていること、などです。
少なくとも、毎年必ず不登校になる児童・生徒を生み出しているのが昔からの学校教育のあり方です。
そんな学校教育でしたが、文部科学省も最近の不登校児童・生徒の急増を受け、対策に取り組んでいます。
以下に文科省のホームページのリンクをつけておきます。
対策の概要を見ると、学校教育を変えようと本気になっているように受け取れます。
しかし、多様な学びの場を確保することはそう簡単なことではないだろうと思います。
学びの多様化学校を全国の都道府県と政令指定都市に2027年までに300校の設置を目指すとありますので、千葉県ではまず千葉市に設置されることは間違いありません。
その他、どこの自治体に設置されるかはわかりませんが、全ての市町村に設置することは現段階では現実的ではありません。
必ずフリースクールが必要になるはずです。
しかも公立学校に劣ることのない教育を提供するフリースクールが必要になるはずで、私の目指すフリースクールがまさにそういったフリースクールです。
具体的にどういったフリースクールを目指すのかは、また記事にして公開しようと思います!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
