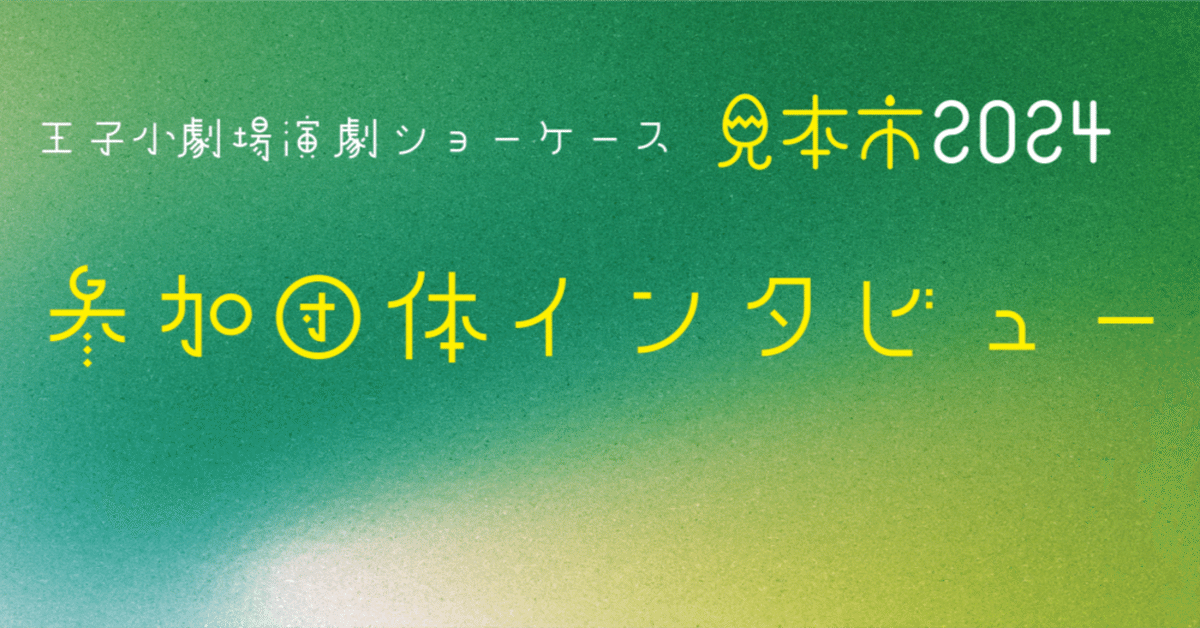
第2回ゲスト:飯田充さん(ヨルノサンポ団 主宰)「やっぱり演劇の根幹は演技で、「演技が面白いもの」を作りたい」 聞き手:山本真生
年始に王子小劇場で開催される『見本市』
活動最初期にあたる9団体を選出し、ショーケース型の公演を行います
【公演詳細】
「見本市2024」
2024年1月5日(金)〜9日(火)@王子小劇場
みなさん、はじめまして。インタビュアーの山本です。
みなさんが今回の見本市で、初めてお目にかかる団体の、
お芝居の魔法により染まっていただきたく思い、
「見本市2024」に参加する方へのインタビューをしてきました。
第2回目のゲストはヨルノサンポ団の飯田充さんです!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
【ゲストプロフィール】

飯田充
https://x.com/iida326?s=20
(ヨルノサンポ団 https://sites.google.com/view/yorunosanpodan)
1993年、千葉県生まれ。京都大学在学中に劇団ケッペキにて演劇を始め、卒業後会社員の傍らヨルノサンポ団を旗揚げ。過去12公演全ての演出を担当する。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
こういう瞬間を、なんとか演劇でもやれないか
飯田:ヨルノサンポ団と申します。3年前に旗揚げをしました。
元々京都大学の劇団ケッペキという演劇サークルの仲間と一緒に、演劇活動をしていました。今も働いているメンバーが多いんですけど、一回社会人になってから、4年5年ぐらい経った後に旗揚げをしました。
旗揚げ公演がコロナウイルスで中止になっているので、本格的に劇場で公演をしたのは2年前ぐらいかという感じです。
関西、特に大阪を拠点に活動しています。
僕は主宰で、全作品の演出をしています。僕の他に脚本を書く藤代耕平という者がいて、脚本と演出を分けて活動しています。
――どういった経緯で結成されたんですか?
僕がいた頃の劇団ケッペキは、既成脚本を演出して作っていくことが多い団体でした。卒業公演で初めて藤代が脚本を書いて、僕が演出するという形で演劇を作り、卒業公演ということで「これで演劇を辞めるつもり」でいて、実際に一回辞めたんですけど、それが楽しかったというのがあって。
団体を立ち上げた当初は僕が書こうとしたんですけど、上手く書けなくて、藤代に書いてもらったら、良い形にハマった感じでした。
僕も藤代のテレビ局に就職したのですが、やっぱり忙しい業界で、それで演劇を続けられなかったというのもありました。ちょっと仕事が落ち着いてきた中で、自分達が考えていたり思っていることが、大学生の頃とは違って、社会人になったことで、色々思ったことや考えていることが出てきて、そういうものを表現してみたい欲求が出てきたことで、結成しました。
今は転職して、演劇を続けやすい仕事に就きました。
演劇がある前提で働いているので、職場には、ご迷惑をおかけしつつ、ご理解を頂きながら続けられる所を選びました。
特に平日は長い時間を仕事で過ごすので、何かしら面白みを感じられるものを、と思っていました。
僕自身は仕事自体も楽しいなと思ってやっています。


――好きなものについてお聞かせください。
飯田:好きなものはたくさんあるのですが、僕と藤代は、特に音楽がめっちゃ好きです。藤代はKing gnuが大好きで、僕はLucky Kilimanjaroや、中学生のころから洋楽がめっちゃ好きです。フェスとかライブにもよく行きます。
大阪のTV局で働いていて、そこで知って、劇場に行くくらいお笑いも好きです。テレビも結構観ます。
あとはもちろん、演劇も好きです。
音楽ライブを観に行くと単純に大きな音が鳴っている。ただギターをかき鳴らしてるだけなのに、泣きそうになる瞬間が、ライブを観ているとある。生で観るエンターテイメントという意味では、演劇も音楽も一緒だと思っています。
こういう瞬間を、なんとか演劇でもやれないかと思ったりしています。
直接的なことで言うと、今年やった公演で、家族が喧嘩するシーンでラップバトルになる。音楽が流れて声が大きくなっていくみたいな強さもそうですし、恥ずかしいことや日常で言えないことを、いかに刺さる形で伝えるかみたいなことが一つあるかなと思っていて。
歌詞でも、多分日常生活で言ったら恥ずかしいことが、音楽に乗せるとすごく響くことがあると思っていて、そういうことを自分たちの作品でどうやってやるのかみたいなことを、好きなアーティストのライブを観たりしながら考えています。
その一つのやり方がラップかなと思って、やってみました。
藤代が描く脚本の暴力性だったり、わからなさ
――現時点での、見本市参加作品の構想をお聞かせください。
飯田:人間の一番本能的な感情は、恐怖なんじゃないかなと思っていて。
自分たちが動物として、生命を守るために本能的に備わっているものが、恐怖。
僕らが元々テレビを作っていたこともあって、編集できるものじゃないものを作りたいなとも考えています。演劇だからできるものを考えた時に、空間も人間も編集できないということ。
原始的で、恐怖みたいな感情。ただ、人が黙って目の前に立ってるだけで、すごく怖い。知らない人が立っていたら、すごく怖い。
そうしたことが立ち上がらないかと考えて、創作をしたいなと思っています。
今考えているタイトルが「パレイドリア」。
例えば「木目が人間の顔に見える現象」のことを言うんですが、つまり、何の変哲もない模様や景色が、人間の顔などの意味のあるものに見えてしまう現象のことなんです。
それをモチーフにして、「人や物の見方が変わることによって生まれる恐怖」を、演劇で描きたいなと思っています。
僕が出演していた過去の公演で、「今日が終われば明日が来る」みたいなことを急に言い出すシーンがありました。
俳優がある種、破綻したことを言うみたいな、ちょっと怖いシーンがあったんですけど、それをやっていた時の感覚で、お客さんの集中度が高いと感じたり、ハマっている感覚があったりして、その感覚は面白いんじゃないかと。
いろいろ観劇をしたり、自分たちが創った別の作品を見る中で、本格的に恐怖と演劇は相性が良いんじゃないかと感じました。
藤代が描く脚本の暴力性だったり、わからなさが面白いなと感じてもいて。
急におっきな音が鳴って怖いとか、ドーンみたいな怖さではなくて、ちょっと考えさせる怖さというか、家に帰った時に知らない男がめっちゃニコニコしていたら超怖いみたいな怖さ。
演劇はお客さんが想像力を使うものだと思うので、想像力を刺激する怖さが、今回、僕らがやりたい演劇なのかなと思っています。
ずっと死ぬことに対して恐怖が頭の中にある
――創作活動を続けていく上で、エンジンになっているものがあったら教えてください。
飯田:2つあるかなと思っていて――1つは、音楽もそうですし、テレビ番組や映画、マンガ、小説など、いろんなエンターテイメントであったり既にある創作物から受ける刺激が、エンジンになっているなと思います。
もう1つは、人は絶対に死ぬわけで、僕はずっと死ぬことに対しての恐怖が頭の中にあるので、生きている間に考えていることを表現しておきたい感覚が個人的には強いです。
わざわざ劇団を立ち上げて表現をやっているということには、死への恐怖みたいなものが根底にあって、そこで何か言いたいとか、何か表現したいというものが、ずっとある気がします。
表現媒体における拡散力の強さにはあんまりこだわりがなくて、テレビ局にいて何万人に届くものに関わっていたわけですけど、それよりも、目の前の1人とか2人に、ダイレクトに届けたい気持ちの方が、自分たちのやりたいことには近いのかなという感じがします。
――人生に一番影響を与えた作品はなんですか?
飯田:演劇を初めてすぐ、1カ月頃の大学生の時に観た大人計画『マシーン日記』という作品です。それを映像で観て、本当に衝撃でした。なんというか、ハチャメチャなんですよね。
猛烈に面白いし、感動するし、笑えるし、とてつもないものを観たなと思って、演劇という表現は面白いと感じて、自分でも創りたいなと思いました。
――最近すごいなと思った作品を教えていただけたらなと思います。
飯田:今年のキングオブコントがめちゃくちゃ面白かったです。全コンビ面白くて、ニッポンの社長の1本目のネタが特に好きでした。好きな女の子が海外に行ってしまう、となった時に、友達が「お前、空港に行かなくていいんか」「引き止めなくていいのか」と言って喧嘩するシチュエーションで、それが普通のドラマだったら殴り合うんですけど、片方が殴るんじゃなくて銃を撃ったりとか、もう滅茶苦茶やるけど相手も死なないっていう。片方が不死身という暴力的で変なコントなんですけど、それが面白くて。
今戦争が実際に起こっていて、銃社会に生きている人たちもいる中で、そのフィクションの軽やかさというか、コントとしてやることの強さを感じて面白いなと。
演劇では大前提として安全性を絶対担保しなきゃいけないなとは思うんですが、そこを犯すことによる快感みたいなものもあると思っていて。
それは当然誰かを傷つけるという話では全くなくて、ジェットコースターに乗るのと一緒で「あ、もしかしたら今死ぬかも」思うことが快感になり得るとも思う。ジェットコースターは「ジェットコースターに乗る」という前提があった上で、どんなものか分かった上で乗っているので、そこがなかなか現段階では難しいなと思いますね。
つまり客席に何かを働きかけるところまで「ヨルノサンポ団だったら、こういうことが起こるよね」と了解してもらった上で観られるということだと思うのですが、難しいなと思います。
今でも宣伝の段階で「こういったことが起こります」とシートを配ったりすることもありますし、僕らもやったりしますけど、そこはちょっと考えなきゃいけない問題だなと思います。
ほとんどの演劇が最終的に、客席に当事者性を投げかけるものにはなると思うので、どんなものでもそうした場面になり得るかなと思うと、創作の方向としてもそうなっていくのかなと思います。
もちろん、誰かを傷つけたりはしませんが。
理屈のない良さみたいなものが、演劇にはある
飯田:演劇サークルに入るとなった時に、京都大学にある西部講堂という木造のホールで新入生歓迎公演をしていて、そこで「脚本を読んでみよう」というイベントに参加しました。
野田秀樹の『贋作 罪と罰』を先輩方がバーッと走り回りながら読んでいて、その感じが僕はすごくいいなと思って。
当時18歳で野田秀樹の脚本も何が何だか分からなくて、しかも抜粋されているので、本当に何が面白いのか分かんないんですけど、素敵なセリフを素敵な先輩方か大きな声を出しながら走んで読んでいて、訳分かんなくていいなと思ったのが、多分僕にとって芝居初めだったかなという感じがします。
ああいう理屈のない良さみたいなものが、演劇にはある気がして、そういうものを作りたいなと思います。
それまで僕はずっと剣道部でした。中学1年生から剣道をやっていました。音楽が好きで音楽をやりたいなとも思っていて、高校の時にお兄ちゃんと一緒にちょっとだけバンドを組ませてもらって、ドラムをやらせてもらいました。ただ、あまりにもドラムが下手すぎて、これは向いてないなと思って、大学では演劇を始めました。
演出家と俳優が喋ることが大事
飯田:ヨルノサンポ団は脚本と演出を分けているので、何となく「こういうことがしたいたよね」と話しながら、脚本の藤代がいったん書いてくれて、それを基に、それをどう上演したら面白いかと話し合う形で、創ることが多いです。
基本的には前の公演の反省であったり、「これはちょっとワクワクするかな」みたいなものを軸に作ることが多いかなと思います。
「このシーンがあったら楽しそう」とか、そういったものを軸に、創っているような気がします。
さすがに脚本を書き出す前に話はするんですけど、結構藤代がバッと書いてくれて、そこから考えることも結構あります。
公演毎にちょっと違う気もしますが、「こういうことがやりたいよね」という話は、脚本を書く前にしていますね。
団体を立ち上げた時は、派手にプロジェクターの映像を投影することであったり、ビビットな瞬間や綺麗な瞬間を作りたい感覚が強かったんですけど、最近は「演劇って、状況とか感情を再現する実験みたいだな」と思っています。
「人間が怒っている時はこういうふうにもなるし、こういうふうにもなるよね」と考えるのが楽しいなと思っていて、その面白さというか、そういうことにこだわりたいなと思っています。
僕がもともと俳優の演技よりも、かなりスタッフワークにこだわってしまうところがあったので、最近はむしろ、やっぱり演劇の根幹は演技で、「演技が面白いもの」を作りたいという気持ちも強くなりました。
スタッフワークもものすごく大事だなと思うんですけど、それが「俳優の演技を引き出すもの」である方が良いなというのを、最近思います。
僕らはインスタ映えする劇団なんですけど(笑)
インスタ映えはするんですけど、演技の面白さにも、もっと色んな遊び方があるんだろうなと思っていて、今回の公演でもちょっとそれを突き詰めたいなと思っています。
また、ここ2公演では、毎回稽古場のメンバーとルールを決めています。
例えば毎回調子を聞いてほしいとか、終わった後にどうだったと絶対に感想を聞くとか。
やっぱり演出家と俳優が喋ることが大事なんだなと思います。
はっきり説明できないことや言葉にできない瞬間、解釈的なことであったり、何故この舞台美術になっているのかといった、抽象的なことを俳優に喋ることがあまり好きじゃなかったんですけど、それを喋った方が俳優の演技が良くなるような感覚が最近あって、目に見えないものを信じるというか、最初に出来るだけ喋るようにしようと思っていますね。
「分からんな」という時には劇団員の顔が曇ったりとか、さっとフォローに入ってくれたりもするんです。
出来るだけ周りの反応を見ようとも思いますし、「劇団員の顔が曇っているな」と思ったら、後で聞くというようにしています。

恐怖という感情を最終的にそういうものできたら
――見本市2024で、どう芝居染めしようと思っていますか?
飯田:僕らは怖い劇をやろうと思っているんですけど、根本には観てもらった人の世界の見え方を変えるようなものをつくりたいと思っています。新年早々世界の見え方が変わるような”芝居初め”に出来るように頑張ります。
――最後に記事を読んでいる方へ何かあればお願いします。
飯田:普段は関西で活動してますが、関東でも活動したいのでチェックしてください。ラジオを細々とやっているので、ちょっと気になったらラジオを聞いてくれたら嬉しいです。
初めての東京公演でめっちゃワクワクしています。楽しみです。
※次回は明日、山口綾子の居る砦の飯尾朋花さんと小澤南穂子さんのインタビュー記事です。次回もまたお会いしましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
