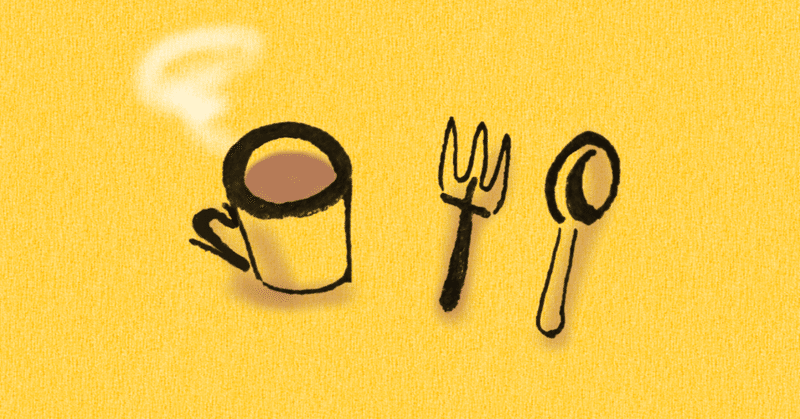
あずまきょうこと、申します。
「ちょっ、ちょ、ちょっとまって!」
まちこは冷や汗をかきながら駆け出していた。頭が状況に追いつかない。それでも駆け出さなくては。間に合わない。間に合わない。こんな早朝、わたし以外に誰も歩いてない。他の人には助けられない。
「はやまってはダメです!」
そう言いながら、歩道橋のうえ、手すりに手をかけていた初老の女性を後ろから抱きかかえた。ここで死んではだめです、そう言いたかったのに、言葉よりも先に、まちこは女性を抱きかかえたままバランスを崩して歩道橋の上に倒れ込んでしまった。やってしまった。そう思ったときにはもう遅かった。
抱きかかえられたまま転がった初老の女性は、ばっと身を起こすと、しばらくこちらをぼんやりと見つめていた。しかし、しばらくして、
「ふふふふふ」
と、小さく笑い出した。
まちこの心臓は早鐘のように鳴っているのに、このひとはなにがおかしいのだろう。まちこも呆然と女性を見つめ返した。
すると女性は、立ち上がりながら、こう言った。
「朝日の写真が撮りたかっただけなのよ。でも、ご心配をおかけしました。ごめんなさいね、ありがとう。」
そう言われてみれば、右手にはしっかりとスマホを握っている。まちこは自分の勘違いに気がついて、穴があったら入りたくなってしまった。
「こ、こちらこそ、すみません・・・。」
消え入りそうな声で謝りながら立ち上がると、女性はさらににこにこと笑った。まちこも笑うしかなかった。
女性はスカートの裾をパンパンと払った。その隙間に、すりむけている膝小僧を見つけてしまった。
やってしまった。まちこはそう思った。
「あの、膝、お怪我されてますね。本当に本当に、すみません。」
とにかく謝るしかない。
「ひざ?ほんとう?全然気が付かなかったわ。でもどうか、お気になさらないで。」
「いや、そういうわけには、いきません。わたしが怪我をさせてしまったんです、本当に申し訳ありません。」
まちこはただひたすらに頭を下げるしかなかった。もしかしたら、他にも怪我をしているかもしれないのだ。
「その、あの、怪我の治療代、わたし出します。」
「治療代?そんな・・・」
「わたしが怪我をさせてしまったんです!本当に申し訳ないことをしました。もしかしたら、足首とか、他にもお怪我があるかもしれないし。本当にわたし、治療代出します。出させてください!」
まちこは引き下がらなかった。さっきとは別の意味で冷や汗が止まらない。頭のなかでそろばんを弾く。たいしたお給料をもらっていないけれど、なんとか治療代を捻出しなければならない。もしかしたら慰謝料だって要るかもしれない。ああ、わたし勘違いしてなにやってんだろう。他人なんて、ほっとけばよかったのに。二人の間には、沈黙が流れている。まずい。多分慰謝料も請求される。
すると女性は、頭を下げるまちこを見ながら、こう言った。
「それなら、わたくしとおともだちになってくださらない?わたくし、あずまきょうこと申します。」
見上げた女性の顔は、いいこと思いついた!というひらめきで、いっぱいだった。
それから数日後、まちこは、彼女の自宅に招待されていた。
あの日、「おともだちになってくださらない?」の問いかけのあと、しっかりと彼女のスマホの電話番号を教えられていた。まちこのスマホの画面には、こうこうと「東 京子」の文字が光っている。
ー「東京の子」と書いて、あずま、きょうこ。字面だけみると、役者みたいだ。
「おともだち」って、どういうことだろうと考えながらも、どうしても怪我のことが気になって、彼女と番号の交換をしたのだった。まちこは、彼女が他にも怪我をしているんじゃないかと考えて、この数日はひやひやしていた。しかし彼女から怪我の報告はなく、代わりに届いたSMSは、
「明後日、お茶をしにいらっしゃらない?」
というお茶のお誘いと、彼女の住所だった。
仕事帰りにお茶をしにいく約束をしたものの、ただ一度会っただけなのに、自宅の住所まで教えてしまう京子のことを、まるっきり信じているわけではない。まちこは、新手の詐欺の可能性も考えて、法外な慰謝料をふっかけられたらとにかく逃げよう、そうするしかない、と考えていた。けれども、怪我をさせたのは事実だし、という思いが、まちこを彼女の自宅へ向かわせていた。
たどり着いた京子の自宅は、ちんまりとしたアパートだった。最近主流の警備会社がついているようなアパートではなく、昔ながらの、木造賃貸アパート。しかしそこまで古すぎるということもなく、彼女のイメージとアパートの佇まいが、まちこの中できれいにリンクする。しっかりと年月を重ねて、きちんと生活を送っている人々が、静かに暮らしているような佇まいだった。
まちこは、恐る恐る京子の家のインターホンを押す。インターホンだけは新しいものに付け替えてあるようで、防犯カメラがついている。
「はーい」
と、彼女がインターホン越しに答えた。玄関から顔を覗かせた京子は、相変わらずにこにことして、こう言った。
「いらっしゃい、まちこさん。」
京子の家の玄関に立つと、そこには、他の誰の姿もなかった。てっきりご主人もいるのかと思って、戦々恐々としていたまちこは、すこし拍子抜けした。京子の膝にちらりと目をやるが、長いスカートの下に隠れて、怪我の様子がわからない。これは上がり込む前に正面きって聞くしかないな、と思ったまちこは、思い切って、京子にこう問いかけた。
「お怪我の具合は、いかがですか?」
京子は一瞬、きょとんとした顔をした。それから、ああ、そんなこともあったわね、という調子で長いスカートをめくり、膝小僧を見せてくれた。そこには、ちょこんと絆創膏が貼ってあった。
「なんともないわ。ただのすり傷よ。ねんざもしていないし、こうしてぴんぴん歩いているでしょう。ご心配をおかけしました。」
と言って、深々と頭を下げた。
まちこは慌てて、
「怪我をさせたのはこちらですから!」
と訂正し、その勢いで、手土産を渡した。駅ビルの洋菓子店で買ってきた、ちょっとお高めのプリンだった。
京子はよろこんでプリンを受け取ると、
「じゃあさっそくいただきましょうよ!どうぞおあがりになって、そのへんに座っていらして。」
と、台所にいそいそと向かっていった。
「おじゃまします・・・」
と言いながら、まちこは京子の家に上がり込んだ。あらためて家の中を見回してみると、この部屋は、たくさんのもので溢れている。まちこは自分の祖母の家を思い出した。
ーおばあちゃんちも、こんなふうに、ものが溢れていたっけな。
京子の部屋は、まちこの祖母の家と同じように、たとえば健康食品のチラシ、たとえば走り書きのメモ、たとえば雑誌の料理ページの切り抜き、つまりは京子が大事に思うものが、そこかしこに積み上げられていたのだった。
「さあ、一緒にいただきましょう。おもたせで、すみませんね。」
と、京子がプリンとコーヒーを持ってきた。まちこは今更、自分がやります、と言わなかったことに後悔したし、不躾に部屋をじろじろ見ていたことにうしろめたさを感じたが、京子は意に介していない様子だった。
「おともだちとこうしてお茶できるなんてうれしいわ、ありがとう、まちこさん。」
「・・・その、おともだちっていうのなんですけど、」
と、まちこが切り出す。ここははっきりしておかなくてはならない。新手の詐欺の入り口かもしれないのだから、慎重にいかなくては。まちこはこころの紐をきゅっと結び直した。
「わたしたち、まだ今日でお会いするのは二回目ですし、おともだちっていうことになるんでしょうか。」
すると京子は心底不思議そうな顔で、
「あら、おともだちになってくださるから、お茶に来てくださったんでしょう?だから今日で二回目だとしても、おともだちは、おともだちよ。まちこさん、改めまして、よろしくね。わたくしは、東 京子と申します。」
そう言うと、京子は深々とまちこに頭を下げた。この、「東 京子」なんていう嘘みたいな名前の人は、すぐ人に頭を下げるんだなあと思いながら、まちこも慌てて頭を下げて、こう言った。
「いや、いえ、こちらこそ、よろしくお願いします・・・?」
それからというもの、まちこは、京子と度々お茶をするようになった。
最初の一回目こそ、新手の詐欺なんじゃないかと訝しがっていたまちこだったが、二回、三回と京子の自宅を訪れるにつれて、その警戒心も薄れていった。
訪れる回数が増えるにつれ、まちこにはわかったことがあった。
それは、京子の旦那さんはすでに死別しているということ、京子には二人の息子さんがおり、遠方に住んでいること、そして、京子がここで一人暮らしをはじめてかれこれ八年は経っているということだ。
「主人が死んだときに、わたしは愛知県にいたの。ある日の朝、胸が痛いなあ、と主人が言うから、病院に連れて行ったら、そのまんま死んじゃったのよ。びっくりでしょう?それまで、なんの病気もしてこなかったのに、あっけなく死んじゃって。待合室に居たわたしは、呆然としちゃった。ああ、人ってこんな簡単に死んじゃうんだなあって、わかったの。それでね、そのまま愛知に居てもよかったのだけれど、なんだかつまらないな、と思ってね。愛知なら息子夫婦も近い場所に住んでいたのだけれど、わたし、昔、東京で働いていたことがあってね。主人と出会った頃の、自分がうんと若いときよ。それで、東京が大好きだったから、せっかく一人なら、好きなところにもう一回住もう!って思って、思い切って、こちらで一人暮らしすることにしちゃった。」
京子は茶目っ気たっぷりに自分のことを語った。
「わたし、東京のデパートで働いていたの。高円寺にあったデパートでね、販売員をしていたの。そのときは、とっても楽しかった!お店に立つのが嬉しくて、しょうがなかった。だからまた東京に戻ってきたのよ。まちこさんは、いまのお仕事はお好き?」
まちこは京子にこう問われて、ぐうの音も出なかった。今つとめている仕事は、区役所の清掃アルバイトで、好きか嫌いかと問われれば、「どちらでもない」としか言いようがなかった。生活のために、お金を稼ぐために、生きていくためにやっているけれど、嫌いなところもあれば、好きなところもある。だいたい仕事って、そういうもんじゃないの、と、まちこはこころの中で思った。
「まあ、どちらでも、ないですね。」
まちこはこれ以上仕事の話に触れられたくなくて、さらに言えば、自分のことに触れられたくなくて、なんとなしに話題をそらした。
「高円寺には、よく行かれるんですか?」
「それがね、実はまだ一度も行っていないの。まちこさんみたいに、わたしと一緒にお茶を飲んでくださるおともだちが他にも居るのだけれど、みなさん、高円寺なんて若者の街、今更行きたくないって仰って。せっかく東京に住んでいるのにね。」
京子がすこしさみしそうに、お茶を口に運んだ。
たしかに、京子が勤めていたという時代の高円寺と、今の高円寺とでは、街は様変わりしているだろう。
まちこはふと、なんとなくさみしそうな京子が気になってしまった。
せっかく東京に来たのに、行きたい場所に行けないっていうのは、たぶん、さみしいことだ。そう思ったら、つい、口にしてしまった。
「よければわたし、一緒に高円寺に行きましょうか?」
件の高円寺に一緒に行ってみると、京子は大はしゃぎだった。
純情商店街を興味深く観てまわり、
「せっかくだから他の商店街も全部観てまわりましょう!」
と、中通り商店街や、パル商店街にも足をのばした。
一緒に歩いているまちこのことは置き去りにして、あっちを観たり、こっちを観たりしながら、
「なんだか素敵で、ちょっとあやしげな看板があるわ!」
と叫ぶとそこは「シーシャ」のお店だったりして、まちこの胸はビクビクしっぱなしだった。
けれど、若い頃に戻ったようににこにこしている京子を見ると、まちこは、自分がなんだかとっても素敵なことをしているような気持ちになって、たいして知りもしない高円寺の街を、スマホを見ながら懸命に案内した。スマホを見て、かと思えば、先ゆくまちこの背中を見逃さないように姿を目で追ったりして、慌ただしいけれど、どこか愉快な時間を過ごした。
高円寺への旅を終えたその夜、まちこはくたくただった。
いつもの自分なら、休日はただひたすらにこんこんと眠るばかりなのに、お出かけして、あまつさえ観光案内までしたのだから、無理もなかった。
けれど、その疲れはどこか満たされているもので、悪い気持ちは全然しなかった。
「まちこさんとお出かけすると、とっても元気になるわ!ありがとう。またどこかご一緒したいですね!」
と、京子から送られてきたSMSを見て、ニマニマしながら、その夜は、眠った。
この「高円寺への旅」がきっかけで、京子はまちこの「街案内」を気に入ったようだった。
いつものように京子の自宅でお茶をしているときに、
「わたし、新宿にも行ってみたいの。昔ね、歌声喫茶があったのよ。」
だとか、
「うんと遠いところにも行ってみたいわ。海を見たりしてみたい。」
だとか、どこかに行きたい、という気持ちを、よく口にするようになった。
まちこはその度に、京子の行きたい場所を、こころの中でそっとメモした。
「高円寺の旅」は、まちこの中でも、良い思い出として刻まれていたから、またあんなふうに京子と出掛けるのも悪くないな、と思うようになっていた。
京子がよろこぶ顔を見たい、という気持ちもあった。
この人は、とっても素直によろこんでくれるから、よろこばせ甲斐があるなあ、と思っていた。
だからまちこは、こっそり京子の行きたい場所を覚えておいて、お茶を終えたその夜には、
「今度、新宿の高野フルーツパーラーに行きませんか」
だとか、
「今度、思い切って、江ノ島まで足を伸ばしてみませんか」
だとか、自分から京子のことを誘うようになっていた。
仕事から帰っても、仕事が休みの日でも、こんこんと眠るだけだったまちこにとってそれは、自分でもびっくりする変化だった。
その夏二人は、あちらこちらへの「旅」を楽しんだ。
まちこは、京子の体力も考えて、泊まることはしなかったとはいえ、日帰りで東京やその近郊をぽつぽつと出掛け歩いた。
そんな「旅」のひとつである江ノ島の海を見ているときに、まちこは、京子といると、不思議と自分が外に開かれていることを感じていた。
それは、仕事で毎日きたないものをきれいにして、またよごされてきれいにして、という繰り返しの日々に差し込んだ、あたらしい風のような感覚だった。
京子が、まちこ自身のことを根掘り葉掘り聞いてくることがないのも、よかった。
まちこは他人が自分のテリトリーに入ってくることを、極端に恐れいていた。
それは、ほんとうの自分、というものがあるとしたら、ほんとうの自分は、実に空虚だと常々思っているからだった。
からっぽだと、思っていた。
まちこは、京子がその「からっぽ」に足を踏み入れてこようとしないので、安心して、京子の隣でのんきに笑っていられた。
たとえばありきたりな質問、「どうして三十五歳になってもアルバイトなの?」だとか、「わざわざアルバイトっていうことは、なにか目指しているものがあるの?」だとか、「結婚してる?」だとか、「彼氏はいる?」だとか、そういうありきたりで、他愛ない質問を、なぜか京子はまちこに一切問いかけてこなかった。
まちこは、ただただ社会が怖くて、「社会人」というものに馴染めなくて、それでも生きてゆかねばならないから、今の仕事をしている。そこに大義があるわけでも、高尚な思想があるわけでも、ない。学生の頃から集団にうまくなじめずに、いつも「自分は不十分だ」と思って、生きてきた。それがつもりにつもって、「就職活動」という波にものれず、自分が「社会人」になって会社に勤めるという現実も受け止めきれず、ここまでずっと、アルバイトを転々としてやってきただけなのだった。
ただ流されるままに生きてきた自分は、まるでたまねぎみたいだな、とまちこは思う。
剥いて剥いて、剥いてしまえば、最後には何もなくなってしまう。
外の皮だって、時間が経てばみずみずしさを失って、中の身は反対に、腐ってしまう。
ほんとうにたまねぎみたいだ、と、まちこは日々思っていた。
だからそんなまちこにとって、京子は「あたらしい風」だった。
京子のことを、まちこは、蜜の詰まったりんごみたいだ、と思った。
中にたっぷりの蜜を秘めていて、外側はしゃりっとさわやか。
他人にずかずかと足を踏み入れない線引きがあって、でも、目の前のことを思う存分素直に楽しんで、蜜の濃度をあげていく。
京子はまちこのことを、おいしいりんごみたいな人だな、と、こっそり思っていた。
そんなことを考えていたら、自然と、ふふ、と笑みがこぼれた。
砂浜はひんやりとしてここちよく、視線の先では、京子が波打ち際で足をちゃぷちゃぷさせている。
「なあに?まちこさん、なにを笑っていらっしゃるの?」
ばっちり日傘をさしながら、波と戯れている京子が、振り返りながら笑った。
京子と連絡がつかなくなったのは、クリスマスも差し迫った十二月のあたまのことだった。
二人でお茶をしたり、お出かけをするようになってから、京子とまちこは毎日SMSでやり取りをしていたのに、ある日突然、それがぷっつりと、途絶えた。
最初まちこは、京子も京子で忙しいのだろうと考えて、とくに気にも留めていなかった。
けれどそれが一週間も続くと、こころの中で、不安が頭をもたげてくる。
ーおかしい。あの京子さんが一週間も返事をよこさないなんて、どうしたんだろう。何かあったのだろうか。
京子は若々しいとはいえ、七十代後半だ。
まちこは、出会ったばかりの頃に聞かされた、京子の旦那さんの話を思い出す。
『胸が痛いって言って、そのまま死んじゃったのよ。』
そう思うとまちこは居ても経ってもいられなかった。
ー今日、仕事帰りに京子さんのアパートに寄ろう。
そう決めた。ただ顔を見られればいい、わたしの勘違いだったらそれでいい、もしかして嫌われたとか、そういうことでもなんでもいい、とにかく京子が生きていてくれればいいと、胸がはやった。
京子のアパートにたどり着いたとき、まちこの胸は、早鐘のように鳴っていた。まるで出会った最初のときみたいだ。そう思いながら、京子の部屋のインターホンを押した。
ピンポーンと、間延びした音がして、中からの応答はない。そっとドアノブに触れると、鍵はかかっている。コンコン、と何度強めにノックしてみても、一向に返事がない。
いよいよまちこの不安は現実味を帯びてきた。
ーこういうとき、タイミングよく隣人が出てきて、何か教えてくれるもんじゃないの。
そう思いながらアパートを見遣っても、誰も出てくる気配がない。
ーどうしよう、どうしたらいい?
ふとアパートの外壁に目をやると、管理会社の電話番号が載っていた。
ーどうする?親族のふりをして電話をかける?でも今時、個人情報だとかで、何も教えてくれないんじゃない?いや、そんなこと言ってる場合じゃない、中で京子さんが倒れているかもしれないんだから。そうだ、電話をかけるべきだ。
まちこは頭がぐるぐるするのを感じながら、はやる気持ちを抑えて、スマホを取り出した。震える指で、ひとつひとつ番号を確かめるように押していく。かかった。
「はい、○☓不動産でございます。」
電話口に出たのは、若い女性だった。
まちこは京子のアパートの名前を確認して、畳み掛けるようにこう言った。
「あの、今、○区の、○○の、○丁目○番地の、みどりアパートの102号室に住んでいる、東京子の親族のものなんですけど。ちょっとここ数日、本人と連絡がつかなくて。なにかあったのかと思って、今、みどりアパートの前に来ているんですが、どんなに部屋をノックしても応答がないんです。もしかして、部屋で倒れているんじゃないかと思って。」
まちこは、ここまで一息に言い切った。
電話口の若い女性は、「ええ」とか「はあ」とか言いながら、こちらの勢いに気圧されたのか、
「少々お待ちください、担当者に確認します。」
と言って、逃げた。逃げた、と、まちこは思った。
数分の保留音のあと、再度同じ女性が電話口に出た。
「どうでしたか?なにかご存知ですか?」
と、畳み掛けるまちこに対して、その女性は怯えながら、こう言った。
「あの、みどりアパートに、そのようなお名前の方は住んでおりません。」
まちこは一瞬、固まった。
なにをいっているんだろう、この人。
その思いは、そのまま口をついて言葉になった。
「何を言ってるんですか?」
「いえ、ですから、みどりアパートには、東さん、という方は住んでおりません。住人の名簿に、そんなお名前はないんです。」
「いやいや何言ってるんですか、だってわたしは何度も東さんのアパートに遊びに来てるんですよ。どうしてそんなこと、」
「まちこさん?」
そう呼びかけられて振り返ると、後ろに立っていたのは、京子だった。
まちこは思わず二度見しながら、
「京子さん!」
と叫んでいた。
まちこは混乱する頭を抱えながら、
「とりあえずもういいです!」
と言って、不動産屋の電話を切った。
これで、不動産屋の中でわたしは完全に不審者の扱いになったな、とまちこは思ったが、それより今は、目の前に京子がいることにほっとしている自分がいた。
「京子さん、どこ行ってたんですか。返事がないからわたし、京子さんが倒れてしまったんじゃないかと思って・・・」
そう言いながら、まちこは、頭の片隅がちりちりするのを感じていた。
ーさっき、あずまさんなんて住んでないって、言われなかった?
「ごめんなさいね、色々あったのよ。そんなにご心配をおかけしてしまうなんて、ほんとうにわたしったら、ダメだわ。そうだ、お詫びに今からお夕飯をご一緒しない?ちょうど買い物に出たところなのよ。」
スーパーの袋を持ち上げて、京子は楽しそうに笑う。促されるままに、まちこは京子の部屋の玄関に立った。頭のちりちりがどんどん大きくなる。
ーさっき、あずまさんなんて住んでないって、言われなかった?
覆いかぶさるように、頭の中に響く、不動産屋の声。
『東さん、という方は住んでおりません。』
買い物袋から次々と冷蔵庫にものをしまっている京子を横目に、まちこは玄関から動けなかった。
京子が訝しげな顔でこちらを見ている。
「あら?まちこさん、どうぞおあがりになって。今日はカレーにしようかしらね。それならすぐにできるから!ごはんはもう炊いてあるし、」
「だましたんですか?」
まちこは下を向いたまま、蚊の鳴くような声で、言った。
「さっき不動産屋に電話して聞きました。このみどりアパートに、東さんなんて人は住んでないって、言われました。どういうことですか?」
京子は、まちこをじっと見つめたまま、黙っている。
なんで黙っているんだ、と、まちこは無性にイライラした。
「あなたは、東京子さんじゃないんですか?京子さん、嘘ついてたんですか?わたしがこんなだから、あたまがからっぽだから、騙しやすそうにみえました?」
「からっぽだなんて、そんな、」
「からっぽに決まってるじゃないですか!いい歳してこんなふうにあなたとほいほい遊びに行ける人間なんて、おかしいでしょう。おかしいと思いませんか。本当はおかしいって思ってたんじゃないですか?だから嘘ついたんじゃないですか?一体なんなんですか?」
まちこは自分の口が止まらないことに気がついていた。こんなに怒ることはない、怒る必要はないとわかっているのに、止められなかった。
「まちこさん、わたしは、」
「もういいです。金輪際わたしに連絡してこないでください。あなたが本当はどんな名前でどんな人生だったのかなんて、もう知らないです。もう結構です。嘘をつくのも大変でしょうから、わたしはここにはもう来ません。さようなら。」
「まちこさん!」
それからどうやって自宅へ帰ったのか、まちこは記憶がなかった。
ただ、次から次へと湧いていくる怒りの感情がどこから来るのか、そして、この目からこぼれ落ちるなみだの理由はなんなのか、そればかりを考えて、歩いた。
ーわたしなんでこんなに怒ってんの。あの人はただの「他人」でしょ。
ーわたしなんでこんなに泣いてるの。あの人はただの「他人」でしょ。
そうやって、ぐるぐる呪文のように唱えながら歩いていると、京子と出会った歩道橋に差し掛かった。
今度は、こころの片隅が、ちりちりと、した。
それから二週間。クリスマスの日がやってきた。
あの日以来、京子からの連絡はなかった。
まちこは、携帯電話から京子の電話番号を消すことができなかった。登録画面には、「東 京子」の文字がまだ光っている。
ーでもこの人は、ほんとうはこの名前じゃない。なんでわたしに嘘つくの。どこからどこまでが本当の話なの。
まちこは考える度に苦しくなるので、もう考えるのをやめていた。
いつものように、出勤のために家を出る。クリスマスだろうがなんだろうが、まちこにとっては関係がない。
仕事の日であれば、仕事場に行く。
そして帰ってきて、こんこんと眠る。
それが、京子と出会う前のまちこの「日常」だった。その「日常」に戻っただけに過ぎないのだ。あれはなにかの夢だったのだ、と、まちこは一人、こころの中で思っていた。
いつもの歩道橋に差し掛かる。京子と出会った歩道橋だった。
まちこは、京子との一件があってから、通勤経路を変えようかと思った。
けれども、自分は何も悪くない、この道が最短距離なのだからと、どこか頑なにいつもと同じ道を通った。
いつものように、下を見ながら階段を登る。
まちこはいつだって、下を見て歩いてきた。
京子と出掛ける時だけは、京子がどこかへ行ってしまわないように、そして京子が楽しめるようにと、いつしか視線をあげて世界を見る癖がついていた。
その癖だって、今はもう必要ない。
だからまちこは、その日も、下を見て、階段を登り続けていた。
「まちこさん。」
聞き覚えのある声。
驚いて顔をあげると、京子がそこに立っていた。
時間は朝の五時だった。
初めて出会った時は日が昇っていたけれど、今日はまだ、夜を引きずっている。
「京子、さん」
まちこは驚いたまま、思わずこう返してしまう。
この名前しか、自分はこの人の呼び方を、知らない。
「まちこさん、おはよう。これからご出勤よね?」
「そう、ですけど」
「お仕事のあと、うちに寄ってくださらないかしら。色々お話したいことがあって。ここならあなたに会えると思ったの。だから今日、ここに来ました。」
まちこは黙り込んだ。
この人と話すことなんてもう何もない、と思う気持ちと、どうして嘘をついていたのか、聞いてみたい気持ちがあった。
「今日は冷えるわね。帰りを待っているから、温かいお茶を飲みながら、もう一度だけでいい、わたしとお話してくださらないかしら。わたし、待っていますね。」
そう言うと京子は、くるりと踵を返して、歩道橋の向こう側へ歩いていった。
まちこはその場でしばらく立ち止まったけれど、すぐに京子に追いついて、
「わかりました。うかがいます。」
と、言った。
仕事を終えると、まちこはまっすぐに京子の家に向かった。
今日はクリスマスだから、街に人がたくさん出ている。人混みをかき分けながら、まちこは京子の家への道を歩いた。
何度も足繁く通った道だから、からだが勝手に道を覚えている。
まちこは、京子のアパートに着くと、扉の前で深呼吸した。
ー今日でさっぱりお別れしてやる。
どこかそんな気持ちがあった。
インターホンを押すと、すぐに、
「はーい」
という京子の声が返ってきた。自分のことを待っていてくれたのが、ひしひしと伝わった。
扉をあけた京子は、
「どうぞお入りになって。お仕事お疲れさまでした。」
と、笑いながら言った。
まちこは何も言わずに、玄関で立ち尽くした。
あの日と同じだ。
京子はそんなまちこを見ても、ためらうことなく声をかける。
「どうぞ、おあがりになって。今日はゆっくりお話しましょう。だからどうか、おあがりになって。」
そう言って見つめる京子の視線に負けて、まちこは渋々、京子の部屋に上がりこんだ。もう、こたつが出ている。
「こたつに入って暖まってちょうだい。このアパート、石油ストーブ禁止なのよ。だからエアコンをつけているのだけれど、それだけだと、どうしても冷えちゃうわよね。ちょっとお茶を用意するから、待っていてね。」
まちこは、京子に促されるまま、こたつに入った。とても暖かい。冷えて固まったからだがほぐれていくのがわかった。
京子に何か言葉をかけようと思うが、うまくできない。
いざ面と向かうと、言葉が何も出てこなかった。
ーわたしはこの人に、何を言えばいいんだろう。何を聞けばいいんだろう。そもそも、なんて呼んだら、いいんだろう。
まちこはそう思った。
「はい、あたたかいお茶をどうぞ。ケーキもあるのよ。今日はクリスマスだからね。」
そこには、温かい緑茶と、いちごのショートケーキがちんまりと並んでいた。
人が溢れるクリスマスの街で、京子が自分のためにケーキを買ってくれた姿を想像すると、まちこのこころは、きゅっとなった。
「・・・いただきます。」
京子の買ってきてくれたケーキは、いつもどおりの味だった。
いつもの、安心の、いちごのショートケーキ。
しっかり甘いクリームが、疲れたからだに染み渡った。
京子は、まちこが一口ずつケーキを口に運ぶのを、にこにこと見つめていた。
「よかったわ。まちこさんが喜んでくださると思ったのよ。」
まちこは、何も言えずにケーキを黙々と口に運んだ。
あっという間になくなってしまったケーキの代わりに、二人の間には、沈黙と、温かいお茶だけが残された。
お茶をすすりながら、京子が口を開いた。
「嘘をついて、ごめんなさい。」
まちこは、お茶の湯呑をぎゅっと握りながら、その一点を見つめていた。
ーやっぱり、嘘だったんだ。
「あなたのことを傷つけるつもりは、なかったの。でも結果的に、あなたを裏切るようなことになってしまった。わたしってほんとうにダメね。ほんとうに、ごめんなさい。」
「・・・どこからどこまでが嘘なんですか。」
まちこは、絞り出すようにそう聞いた。
名前から生い立ちから、何から何まで嘘に思えて仕方なかった。
二人で出掛けたことも、お茶を飲みながら話したことも全部、嘘みたいに消えてなくなってしまう気がした。
「名前だけが、嘘よ。あとは全部、ほんとう。主人が亡くなっていることも、息子夫婦が遠くに住んでいることも、高円寺で働いていたことも、ほんとう。それなのに、まちこさんに連れて行ってもらうまで、高円寺をもう一度訪れていなかったのも、ほんとう。それから、」
「それから?」
「あなたとおともだちになりたい、って思ったのも、ほんとうよ。」
京子はそう言うと、お茶をぐいっと口に含んだ。
「わたしね、東京に越してきてから、あたらしい自分になりたいと思ったの。主人に先立たれて、息子たちもとっくに巣立って、自分には何もない、って思ったわ。仕事を辞めて、主人と結婚して、こどもを二人産んで育てて、それは、一生懸命頑張った。頑張ったんだけれど、主人がいなくなって、気がついたら、一人だった。息子夫婦を頼っても良かったんだけれど、わたしって一体なんなんだろうって、思ってね。このタイミングでこどもを頼って暮らしていくには、早すぎると思ったのよ。今から八年前だから、そう、まだわたし、六十代だった。六十代なんて、まだまだ働いている方もいるでしょう。今のわたしの年齢だってそうよ、働いている方は、たくさんいらっしゃる。だけれどわたしは、たった一人になったときに、もう一回、あのきらきらとした東京で、生きてみたいと思ったの。そのまま愛知で一人ぼっちで暮らすのでもなくて、息子を頼って暮らすのでもなくて、なにかパートを始めるのでもなくて、わたしはもう一回、この東京に来てみたかった。人生最後のわがままだと思って、息子たちを説得したの。わたし、好きな場所で生きてみたい、って、一生懸命伝えたの。それで東京に来たわ。わたしには、もう一度東京に来てみたいという気持ち以外、なんにもなかった。今も、なんにもないわ。わたしには、なんにもないの。」
そう言うと、京子はもう一口、お茶を含んだ。
「息子もいるのに、変でしょう。でもね、昔から、そう、こどものときから、そう思ってた。わたし、からだがちょっと弱くてね、お嫁に行けるかわからなかったの。今はこんなにピンピンしているけれど、小さい頃は、それはもう、大変だった。だから、主人がお嫁にもらってくれると言った時、わたしの家族は驚いたのよ。こんな娘を嫁にしてもいいことはない、って父は言ったけれど、それでも主人は譲らなかった。『自分の娘だと思って大事にします』と、父を説き伏せたの。だからわたしは、主人と結婚できて幸せだった。その主人がいなくなってしまって、また、元の自分にもどってしまったと思ったの。自分というものには価値がない、なんにもない、からっぽな人間だって、思うようになってしまったの。それで、東京に来た。東京に来たら、なにもない自分でも、居てもいいんじゃないかって思ったの。こんなにきらきらしている街、働いていた自分が欠片でも残っている街に来たら、なにもないことを、隠せると、思ったの。」
京子は続けてこう言った。
「だからわたし、ここで生きていくために、あたらしい名前をつけたの。からっぽな自分じゃなくて、きらきらとした東京で生きていくために、あたらしい名前がほしかった。それで、うんとうんと考えて、『東 京子』にしたのよ。ちょっと自分にしては、名案だ!と思ったわ。東京に来て、こちらで出会った方々には、『わたくしは、東京子と申します』って、みなさんに名乗った。さすがに不動産屋さんには嘘をつくことはできなくて、本名だけれど、おともだちも全員、わたしのことを『東さん』だと思ってる。からっぽの自分じゃない、あたらしい自分の名前。誰かが『東さん』って呼んでくれるたびに、何かが満たされる気がしたの。まるで自分なのに自分じゃないみたいで、とっても嬉しかった。からっぽの自分じゃない、あたらしい自分になったんだって、そう思ったの。
でもね、まちこさんをひどく傷つけてしまって、やっぱりわたしってほんとうにダメだわって、思ったの。からっぽだから、こんな風にしないと、人と繋がれなかった。中身を見られてしまったら、わたしがからっぽなことがバレてしまう。わたし、自分のことを、たまねぎみたいだなあって思うのよ。剥いて剥いて、剥いてしまえば、最後には何もなくなってしまう。外の皮だって、時間が経てばみずみずしさを失って、中の身は、反対に腐ってしまう。からっぽだから、人を自分の中に入れることが、怖かったのね。だからあたらしい名前なんてつけて、自分はからっぽじゃないって、装おうとしてた。ほんとうにごめんなさい、まちこさん。」
京子はそう言うと、深々と頭を下げた。
まちこは、京子が今言った、『たまねぎみたい』という言葉に、胸を鷲掴みにされていた。
「傷つけてしまって、ほんとうにごめんなさい。あのね、わたしのほんとうの名前はね、」
「いいんです。」
まちこは京子を遮って言った。
「いいんです。もう、いいんです。」
「待ってまちこさん、わたしは、」
「違います、そういう意味じゃなくて、ええと、もうわかりました、って意味です。京子さんのことがよくわかったから、なんで嘘ついたのかも、わかったから、もう、本当の名前とか、どっちでも、いいんです。」
まちこは湯呑を見つめていた視線を、まっすぐ京子に捉え直した。
「わたしも、自分のことからっぽだと思ってました。たまねぎみたいだなあって、よく思ってたんです。剥いて剥いて、剥いてしまえば、最後には何もなくなってしまう。外の皮だって、時間が経てばみずみずしさを失って、中の身は反対に腐ってしまう。そういうのほんと、よく思ってたから、今、驚いてるんです。こんな気持ち、誰にもわかってもらえないだろうって思ってたから。だから京子さんも同じ気持ちだったなんて、なんだか、びっくりして。わたしから見ると、京子さんは、蜜がたっぷり詰まったりんご、って感じだったから。」
「りんご?まあ・・・」
そう言うと、京子は嬉しそうにほほえんだ。
「わたしたち、似た者同士だった、ってことですかね。自分のこと、からっぽだ、からっぽだって思って生きてきた二人。歳もうんと離れているのに、変ですね。でもわたし、今なんだか、ほっとしてます。ほっとして、気が抜けて、安心してる。いつも、京子さんの隣にいる時はそうだったんです。京子さん、わたしのこと、根掘り葉掘り聞いてこないから、すごく居心地がよかった。外の世界にいると、ぐんぐん自分が削られていくような気持ちになることが多くて。誰かの他愛ない質問、たとえば結婚しなんですか、とか、なんでアルバイトなんですか、とか、そういう質問、すごく普通の質問にうまく答えられない度に、傷ついてて。自分のからっぽさを突きつけられている気がして、みんなと同じようにできない自分は、何かが足りないんだって、ずっと思ってきました。京子さんは、そういうこと、一切聞いてこないから。わたしのテリトリーにずかずか踏み入ってこないから、こんなやつでも安心して隣に居られたんです。その安心が裏切られた気がして、勝手に傷ついて、ふてくされて、もう来ないなんて言って、こちらこそ、ごめんなさい。」
まちこは京子に向き直って、深々と謝った。
「わたしから見ると、京子さんは、蜜のたっぷり詰まったりんごなんです。中にたっぷりの蜜を秘めていて、外側はしゃりっとさわやか。他人にずかずかと足を踏み入れない線引きがあって、でも、目の前のことを思う存分素直に楽しんで、蜜の濃度をあげていく。そんな人だと思ってました。」
「わたしはまちこさんのこと、なんてやわらかい人だろうと思ってましたよ。まちこさんは、わたしの気持ちを一生懸命汲み取ってくださって、色々素敵なところに連れて行ってくださるでしょう。わたしが年甲斐もなくはしゃいでも、目くじら一つたてないで、一緒に笑ってくださった。まちこさんのこころは、とってもふわふわで、素直で、やわらかいんだなあって、ずっと思っていました。だからわたし、まちこさんの前だと、まるで昔に戻ったみたいにはしゃげるの。そんなこと、他のおともだちの前では、なかなかできないわ。人の悪口を言うわけでもなく、わたしのことを根掘り葉掘り聞くわけでもなく、まちこさんこそ、境界線をしっかり守ってわたしと接してくださった。だからわたしも、安心してまちこさんの隣に居られたの。まちこさんのこと、からっぽだなんて、一度も思ったことないわ。まちこさんがからっぽと呼ぶそれはきっと、わたしにとっては、ふわふわのクッションだったのよ。」
「・・・ふわふわの、クッション、ですか?」
「そう、ふわふわの、クッション。あたたかくて、やさしくて、やわらかい、クッション。」
京子はそう言うと、まちこの目をじっと見つめた。
まちこも、京子の目を見つめ返した。
「わたしたち、もっと早く、こういうお話ができたらよかったのね。」
「そうですね。でもわたしたち、似た者同士で臆病だから。だからこんなお話ができるのが今日で、よかったんじゃないでしょうか。これだけ時間をかけることで、やっと自分自身を開いていけるっていうのも、わたしたちらしくて、なんか、いいです。だから、」
「だから?」
京子がこちらを見つめている。
まちこは、お茶を一口含んで、こう続けた。
「これからも、わたしとおともだちで居てくださいませんか?」
と、まちこはまっすぐに言った。
「ええ、もちろん、よろこんで。」
京子はそう言うと、少女のようにはにかんだ。
「それはそうと、どうして一週間も連絡がとれなかったんですか?」
「それがね、わたし、新しい携帯電話に交換をしたら、操作がむずかしくって、なかなかうまくいかなくて。イライラしていじくるのをやめてしまったのよ。だから京子さん、もしよかったら教えてくださらない?」
そういたずらっぽく京子に問いかけられたまちこは思わず笑いながらこう答えた。
「ええ、もちろん、よろこんで。」
年が明けて、三月も下旬のころ。
まちこは、いつもの歩道橋の上で、五分ほど前から立っていた。
時刻はお昼をちょっと過ぎたくらいで、平日のこの街は、それなりに人が行き交っている。車の交通量も多い。
流れゆく車のテールランプを目で追いながら、まちこは、今日の予定を頭に思い浮かべる。
今日は、京子と少し早いお花見の約束をしている。
お互いにお弁当を持ち寄ろうという話をしており、まちこのリュックサックには、がらにもなく手作りしたサンドイッチが詰まっている。
紅茶を入れてきた水筒も、先程から背中でカランコロンと良い音を立てている。
「まちこさん!」
少しつばの広い帽子を被った京子が、向こう側から手を振ってまちこを呼んでいる。
その顔は、これからのお楽しみに胸をいっぱい膨らませた少女のようだ。
「今日はお弁当を交換し合うっていうから、はりきって作ってきたの。おにぎりと、タコさんウィンナーと、たまごやき。遠足みたいで、いいでしょう?」
「ほんとうに遠足みたいですね。わたしはサンドイッチを作ってきました。あとで京子さんのおにぎりと、サンドイッチ、交換しましょう。」
「わあ、それはいい、それはいいわね!とってもたのしみよ。改めて、今日はよろしくね。きっと早咲きの桜もきれいに見られるわ。」
「そうですね。きっときれいに見られるはずです。」
二人は桜の咲いている公園へ向かって、まっすぐに歩き始めた。
並んで歩く二人のからだを、真上に昇っているお昼の太陽が、さんさんと照らしていた。
(16,928文字)
投げ銭?みたいなことなのかな? お金をこの池になげると、わたしがちょっとおいしい牛乳を飲めます。ありがたーい
