
だまされない「学び」のために:公立高校から東大合格へ 小田切 秀穂(著)
- その「常識」を疑え -
タイトルに、だまされない「学び」のために、とあるように、著者は世の中で当たり前と思われている常識や慣習に対して、疑問を呈している。
「NASAの報告は本当ですか?」の項では、自ら実験しNASAの報告が科学的でないことを立証、雑誌掲載にまでこぎつけたエピソードが紹介されている。
その姿勢は、中学受験に対しても同様だ。
「お父さん、お母さんの時代とは違います」と言われる今の時代は、では何がどう違っているのだろうか。単純に考えてみれば、少子化が進んでいるわけだから競争は緩和されているというのが普通の見方ではないかと思う。
圧力が強まっているとすれば、それは小学校受験や中学校受験の話である。大学は以前に比べてかなり入りやすくなっている。
これらの記述は説得力がある。
ゆとり教育から始まった公立校への逆風
公立校への逆風は2000年代初頭の、ゆとり教育の中で強まった。
一般的に親は、私立校は公立校に比べて独創的なカリキュラムが組まれているとか、優秀な教師が多いと考えて子どもに中学受験を勧めていると思う。
ところが、著者の主張をふまえると必ずしもそうではないかもしれない、と思えてくる。
「公立校に行っていては駄目だ」と思い込まされた部分が多かったのではないかと思う。その結果、公立校が落ち込むと私立に生徒が流れる。ところが優秀な資質をもった生徒がすべて私立に流れるわけではなく、経済的上位層だけである。
さらに著者は、受験アドバイザー兼評論家の和田秀樹氏や、元文部科学省官僚の寺脇研氏の著書を引きながら「実は、東大進学者を毎年輩出している進学校でも、学校内での大学受験対策はそれほど優れたものとは言えない」と記す。
つまり、名門校が名門たりえるのは、教育カリキュラムや指導力が優れているからではなく、生徒自身の力によるところが大きいということのようだ。
さらに私立の中には、受験学力さえ身につけば、生活していくための基礎基本は身につかなくてもよいとする方針の学校もあるという。
著者は「いい教師に当たるかどうかは、公立も私立も運でしかない。そのため、公立校から東大に合格することは十分に可能だ」と主張する。
誰かが実態のないところで不安を煽り、競争がないところに不必要な競争を意図的に作り出しているように思えてならない。
ひょっとすると中学受験を過熱させているのは、ゆきすぎた市場原理や、選択と自己責任の論理といえるかもしれない。
リスキリング、どうすればいいのか
「選択と自己責任の論理」で思い起こされるのは、近年の学び直し(リスキリング)の過熱だ。人生100年時代と言われる中、ずっと同じことをしていてはダメだ。だから学びましょうということなのだが、実際にはどうしていいかわからない人も相当数いるのではないかと思われる。
そこで重要なのは、興味関心を持つことだろう。「好きこそものの上手なれ」というように、純粋な興味関心を注げる対象がある者は強い。興味関心を持ち得ることは、それ自体が幸運なことなのかもしれない。
しかし、興味関心に基づいた一点集中型の学びには危うさもある。
個性を伸ばす教育、創造性を育てるには、子どもが好きなことをやらせてやる。そこから個性は開花する。このこと自体は間違いではない。しかし、そのことは幅広い分野にわたる知識が不必要ということには決してならない。物事を総合的に判断していくには、個性云々の前に、豊富な知識が必要となるであろうし、そのことが個性をさらに伸ばしていくことになると思う。
一つの事柄も、それを深めるには多くの知識を必要とする。東大大学院で生物学を修めた著者流に言えば、生物学をするには、国語も必要、数学も必要ということになるのだろう。
価値観が多様化した正解がない時代を生き抜くには、ときに常識やこれまでの慣習に疑問を呈することが求められる。逆説的ではあるが、自分の興味関心を明確にするには好きなもの以外も学ぶ。長期的に見れば、それが好きなことを仕事にすることになり、主体的な生き方にもつながっていくのではないだろうか。
同じ著者が書いた『「教育」というアコギな商売』と本書をセットで読むと、より理解できる。
神奈川県の公立高校から京都大学に進学し、神奈川県の畜産課職員を経て、教員になった著者の体験談はユニークだ。特に畜産の体験談はめずらしいので、それだけでも楽しめる。
また、東京大学の大学院に進学し再び県立高校の教師になった経緯を知ることは、学び直し(リスキリング)に関心のある読者の参考となるだろう。
文・筒井永英
【著者プロフィール】
小田切秀穂(おだぎり・ひでほ)
1956年横浜市生まれ。1980年、京都大学農学部卒業。神奈川県立大野山乳牛育成牧場勤務を経て、神奈川県立高校の教師となる。1985年退職し、東京大学大学院理学系研究科へ進学。1987年修士課程を修了し、再び神奈川県立高校へ就職し、現在に至る。
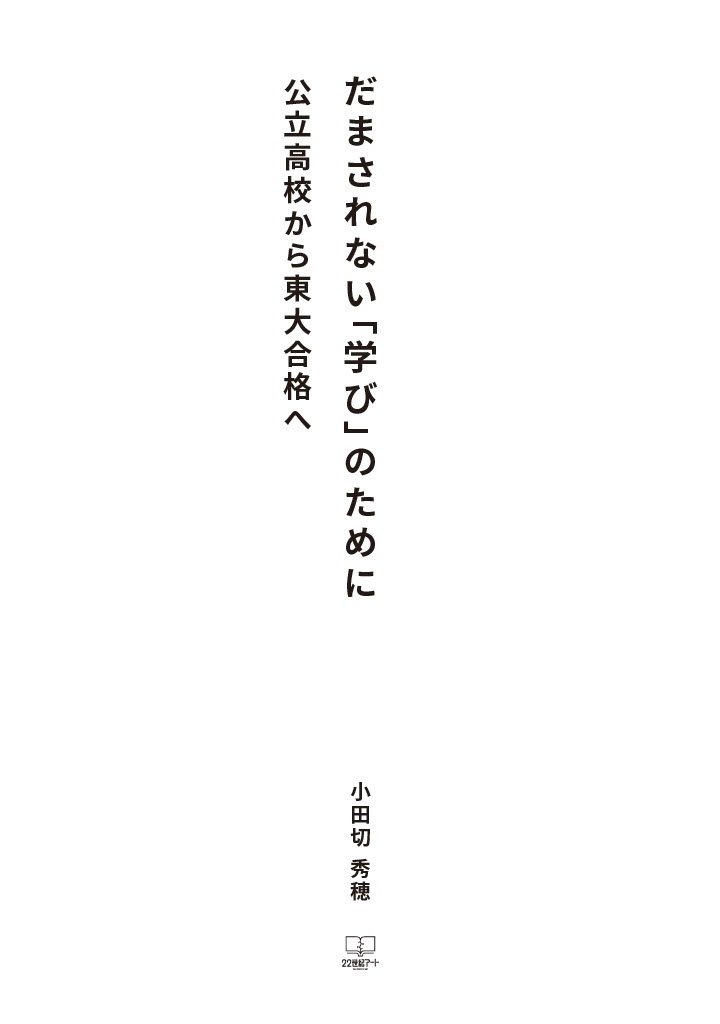
はじめに
本来みんなが持っている好奇心が、選択テスト、受験体制ですさんでいる、『教育汚染』だ」、ノーベル物理学賞を受賞された益川敏英さんが言っていた。こんな話を聞きながら、このノーベル賞学者達を生み出したはずの日本の教育は、いったい今、どうなってしまったのかと思う。つい数年前まで、詰め込み教育はいけない」と言われ、ゆとり教育」が推進されていた。06年9月に安倍内閣が誕生し、教育改革を重要施策に掲げて「教育再生会議」がつくられると、いつの間にか教育改革」はゆとり教育」からつめこみ教育」へと変わってしまったようだ。でもほんとうに、日本の教育は再生しなくてはいけないようなひどい状態なのだろうか。教育再生会議」がつくられた06年、この年は教育」に関して、実にいろいろなことが起こった。いじめが原因と思われる生徒の自殺が続出する。10月になると全国600を超える高校で、必修科目の履修漏れが露見して問題となった。まさに「受験による日本の教育の汚染」の現れだが、なぜ今さら」と思う。そして12月15日には、ついに教育基本法の改正へと辿り着いた。日本の教育の、あるいは社会の大きな転換点となった年であったのかもしれない。しかし振り返ってみると、戦後いつの時代にも日本の教育は「問題」があると言われ続けていたように思える。
過度の受験競争がわが国の教育をゆがめている」といわれ、詰め込み教育はいけないといわれ続けた。1980年代に「ゆとり教育」が推進されると、1990年代の中頃から、大学生の学力が低下している」といわれだしていたように思う。
1999年に『分数ができない大学生』、2000年には『小数ができない大学生』が出版され、日本のトップクラスの大学での学生の学力低下が指摘された。以来、学力をめぐっての論争が激しく交わされだす。論点は、実際に学力低下しているのか」、ゆとり教育と学力低下の因果関係」、02年改定の学習指導要領の是非」、親の社会階層と教育の不平等や学力格差の拡大」と多岐にわたっていった。それに対して文部科学省は、必ずしも学力の低下を示すデータはない」、学力は下がっているかもしれないし、そうでないかもしれない」と言って、ゆとり教育」による教育改革を推進し続け、02年には、多くの反対を押し切った」かたちで、3割削減」ともいわれてきた学習指導要領の改訂を行った。生きる力」の獲得を目指して、総合的な学習の時間」を入れた。そして、この02年という年は、数学が分からない子が日本から一人もいなくなる」記念すべき年となるはずだった。少なくとも当時の寺脇研文部省政策課長はそう言っていたように思う。
ところが一転して04年の秋あたりから、日本の子どもには確かな学力が必要」だと急にいわれだした。するとすぐに中山文科相の競い合いによる学びが必要だ」という発言がなされた。そして06年には教育再生会議がつくられる。いつの間にか日本の教育は再生」しなくてはいけないような状況になっていたらしい。07年になると「ゆとり教育」の見直しがいわれだした。文科省の役人も、学者も、評論家も、そして教師もそれぞれ思い思いのことを言い、教育政策はめまぐるしく変わっていく。過度の受験競争がわが国の教育をゆがめている」といわれた時代は、ゆとり教育」の流れの中で終わりを告げ、すると今度は学習時間の減少」と「学力低下」が問題とされだしてきた。1967年に学校群制度」を導入して以来、着実に東大合格者を減らしてきた都立高校は、ここへきて「都立の復権」という謳い文句の下、学区を撤廃し、進学重点校を置き、数値目標を掲げて東大合格者の増加を図りだした。40年のときを経て、振り子はまた逆の方向へ大きく振れだしたようだ。そのような状況の中で、実際に教育を受ける子どもたちは、いったい何をよりどころに学びを進めていけばよいのだろうか。少なくとも教育が再生」されるのを待っているわけにはいかないだろう。世の中の意見がどのように変わっても、左右されない学び」、子どもにとってのだまされない学び」とは何なのだろうか。きっとそれを考えることが、今一番大事なことなのだろうと思う。
じわじわと少子化が進み、大学は選びさえしなければ、誰でも」行ける結構な時代となってきた。ここは状況に押し流されることなく、学び」についてじっくりと考えてみる必要があるのではないか。
時々なぜ、僕は教師になったのだろうか」と思う。そんなことを言うと、お前のような奴が教員をやっているから、日本の戦後教育はだめになったのだ」といわれるかもしれない。時々生徒に「先生は、なぜ教師になったんですか」と聞かれることがある。そのたびに気の利いた答えができず、困ってしまう。きっと僕のような教師を「でもしか教師」というのだろうと思う。そんな教師がなぜできてしまったのか。僕の辿った「学び」の道のりを振り返ってみながら、そんなことも含めて、教育を取り巻く環境の大きな変遷の中での、学び」ということについて考えてみたいと思う。
第一章学び」の道のり
学びの始まり
1969年1月18日と19日、僕は、学校から帰ってくるとテレビの前に釘付けになっていた。テレビのブラウン管には、上空をヘリコプターが舞い、放水と催涙ガスで煙る東大安田講堂が映っていた。時々、時計台から火炎瓶が落ちてきて、地面に炎が広がっていた。19日の夕刻5時半を回っていたと思う。仕事から帰ってきた父と一緒に見ている中で、時計台の最上部で翻っていた旗が取り去られ、学生が機動隊員に逮捕されて、すべてに幕が下りたように記憶している。1956年生まれの僕は、小学校の6年生だった。そのとき初めて東京大学の存在を知ったわけでもないとは思うが、鮮烈な記憶となって「東大」は僕の中に残った。初めて「大学」という存在を明確に意識した瞬間だったようにも思う。
共働きをしている小学校の教師の家庭に生まれた。4歳違いの妹が生まれたとき、妹の体が弱かったこともあったと思う、母は教師を辞めた。母は、その女学生としての生活の大部分を戦争中に過ごした。勉強をすることよりも、勤労動員に駆り出され爆弾の起爆装置を作ることの多い学生生活を送ったようである。女学校を卒業して、そのまま代用教員として小学校の教壇に立った。自分自身が十分に勉強できなかったという思いもあってか、子どもの教育には熱心だった。学問することはとても大切なことだと思うよ。学歴はとても大事なものだから、学歴があったら私も教師を辞めなかったかもしれない」と時々言っていた。
母は小学生の頃、とてもよく勉強ができたらしい。自分の子どもは、それなりにできて当然」と思っているような節があった。勉強は、まず毎日机に向かうことを習慣づけることが大切なことだ」と考えていたようで、小学校に入学する頃からは毎日30分ほどは机に向かうように仕向けられていたと思う。初めの頃は、勉強をみてくれるのはいつも母だった。2年生の頃だったか、九九を習ったときには、母に時間を計ってもらいながらトレーニングに励んだことを覚えている。学年が進むにつれて、いつしか勉強をみてくれるのは父であることが多くなっていた。父は知り合いから頼まれると、時々中学受験をする子どもの勉強をみていた。僕は地元の公立中学に行くと当たり前のように思っていたが、その子どもと一緒に勉強をみてもらったりしていた。
僕が小学生だった頃、高校進学率は、まだ70%にも届いていなかったかもしれない。世の中では、1947年〜49年頃に生まれた団塊の世代がちょうど大学進学の年齢を迎えていた。大学受験は厳しく、四当五落」「受験戦争」とかいうようなことがしきりといわれていたように思う。少なくとも我が家では、母が時々そのようなことを口にしていた。
学校の勉強は、おしなべてできたと思う。でも、なぜ勉強するのかといえば、試験でいい点を取らないといけないから」ということになるのだろうか。家の中の雰囲気が、もう勉強ができて当たり前」、将来は、大学に行って当たり前」というようなものだったと思う。試験ができなかったときの母は厳しかった。自分が親となった今となっては、それほどでもなかったかな」とも思えるが、そのときの僕にとってはとても厳しく、怖い母がいた。僕は、とても気の小さな神経質な子どもだったと思う。自分の思っていることをはっきりと言うことができなかった。友達とケンカをしたこともなかったと思う。いつも大人の顔色を見ているような子どもだった。そんな僕にとって、怖い母はとても大きなプレッシャーだった。『勉強ができる子』であり続ける」こと、試験でよい点をとる」ことが、勉強するための最も大きな、そしてもしかしたら唯一のモチベーションとなっていたと思う。返ってきた試験の点が悪くて、とてもそのままでは見せることができず、点数を書き直して母に手渡したことは何度もある。戻ってきた答案の間違えていた答えを正しく書き直して、先生のところにもっていったこともある。5、6年の頃には、試験のときに分からない問題があると、隣の子の答案をよく覗いたりしていた。もちろんカンニングがいけないことだということくらいはその頃の僕でも分かっていたが、見たい」という誘惑の方が強かった。担任の先生は、個人的に僕を呼んで注意することをしなかったが、当然分かっていたと思う。
志水宏吉氏が提唱する学力の樹」というものがある。学力は3つの要素から成り立つそうだ。知識・理解」に関わる学力、思考・判断・表現」に関わる学力、意欲・興味・関心」に関わるもの。そしてこの3つはそれぞれ生い茂る葉」すっくと伸びた幹」「大地をとらえる根」として一体として一つの学力の樹」を形づくっている。知識という一枚一枚の葉っぱのない樹は光合成ができず枯れてしまう。大地にしっかりと根を張っていない樹は少しの風にも耐えることができず決して大きくなることはできないということだろうか。降りそそぐ陽光は指導に当たり、根からの水や養分の吸収は支援ということらしい。これを初めて聞いたとき、とてもよく「学力」を表しているモデルだと感心した。
この学力の樹」として小学生の僕を見てみるとどうなるだろうか。豊富に与えられる肥料を、ひ弱な根は十分に吸収することができず、ややもすると根ぐされを起こしそうになる。降りそそぐ陽光に葉を増やして、盛んに光合成をしようとするが、ともすると強すぎる光に葉は日焼けを起こし枯れかける。なかなか幹は伸びることも、太ることもままならない。思考は深まらず、判断力はなかなか育っていかない。そんな「学力の樹」がそこにあったのではないだろうか。
何のために勉強するの?
中学生になると、母は、自分ではもう僕の勉強をみることはできないと思ったようだった。知り合いに頼んで、東工大に行っている息子さんに僕の家庭教師として来てもらうことに決めてきた。その先生には高校1年まで、週2回数学と英語をみてもらうこととなる。そのおかげもあってか、学校の成績は、安定して良くなる。もう試験のときに隣の答案を見ることもなかったが、中学校の3年間を通して、国語・社会・数学・理科・英語の5教科で、通知票に5」以外の数字がついてきたことはなかった。陸上部に入った。選手としてはまったくだめだったが、とりあえず卒業まで部員ではあった。2年生のときは、生徒会の役員もやった。中学生の僕は、先生の言うことを素直に聞く、生真面目で、そして神経質ではあったが、とても「良い」生徒だったと思う。たぶん、勉強も毎日2、3時間はしていたと思う。しかしその中学生の僕に「なぜ君は勉強するのか」と聞いたら、きっと「Y高校に行きたいから」とぐらいしか答えなかったと思う。勉強する目的は、試験でよい点を取ること」。それ以外にはなかったように思う。たまには教科書以外の本も読んだが、取り立ててよく読書をしたという記憶もない。与えられたものからしか学ぼうとしない学力の樹」は、人工照明の下で効率よく光合成はしていたのだろうが、その光量は絶対的に少なく、幹は伸びても太ることはできず、その根は極めて貧弱なもので、大地に深く根ざすことはなかったと思う。少しの風が吹いただけで、倒れてしまったはずだ。
進学先は当然のことのように、家から歩いて20、30分のところにあるY高校と決めていた。いや決まっていたという方がよいのかもしれない。それはその高校が近いからという理由もあったとは思うが、たぶんそこが、その頃横浜で一番の「進学校」だったからだと思う。ところが3年生となり受験が目前に近づいてきた頃、なぜそうなったのか記憶ははっきりしないのだが、なぜか東京教育大付属の駒場高校(現筑波大付属駒場高校)を受けることとなっていた。当時教駒」は東大合格者数で、トップかそれに近い数字を残していたと思う。腕試しにちょうどよい」というようなつまらない理屈でも考えたのだろうか。あるいは、母の友人の息子さんが中学校から「教駒」に通っていたので、親の見栄もあったのかもしれない。
東横線に乗りそして渋谷で乗り換えて、1時間近くをかけて受けに行った。その後も含めて幾度となく、数え切れないほど試験を受けてきたが、あれ程できなかった試験はそうはない。かろうじて理科だけは、少しは解けたような記憶がある。大地にしっかりと根を張っていない学力の樹」に、受験勉強でつけた葉さえもそう多くはない「学力の樹」に到底歯が立つような問題ではなかったのだと思う。2月初め、東京は何年ぶりかの大雪だった。電車も止まりそうなくらいに降りしきる雪の中を、父と二人、渋谷から井の頭線に乗って発表を見に行ったことを覚えている。当然のこととして、掲示板に僕の受験番号はなかった。
ここまではまあ、身の程知らずに……」というぐらいのことで済んだのだが、その後えらい目に遭うこととなる。雪の中を発表を見に行ったからというわけでもないのだろうが、数日して40度以上の発熱をする。その頃から、体はかなり丈夫な方だったと思う。中学に入ってからは、ほとんど学校を休んだことはなかった。それが、それから2日しても3日たっても熱が下がらない。受験の前日になっても38度以上の熱があった。願書はもう公立にしか出していない。Y高校に落ちたら行くところがない。試験の朝、母親に付き添われ、子どもの頃からかかりつけの医者のところへ寄って、解熱剤を打ってから試験会場へと向かった。高校へ着くと、担任のS先生がわざわざ来てくれていて、玄関のところで心配そうに出迎えてくれた。その姿が今でも瞼に浮かぶ。ありがたい限りである。
そんなさんざんな高校の入試であったが、もう一つ記憶にしっかりと焼き付いている光景がある。Y高校に着いて、母に付き添われタクシーから降りると、正門の外で3人の少年がヘルメットをかぶり、手ぬぐいで顔を覆った姿で、登校してくる受験生にビラを配っていた。ビラを受け取って校門の中に入ると、一抱えはある大きな籠を間に置いて2人の先生が立っている。受け取ったばかりでまだ読んでもいないそのビラを、その籠の中に捨てていくように指示していた。この行為はいったい何なのだろうか。真面目な」中学生の僕には、何か腑に落ちないものが残った。
