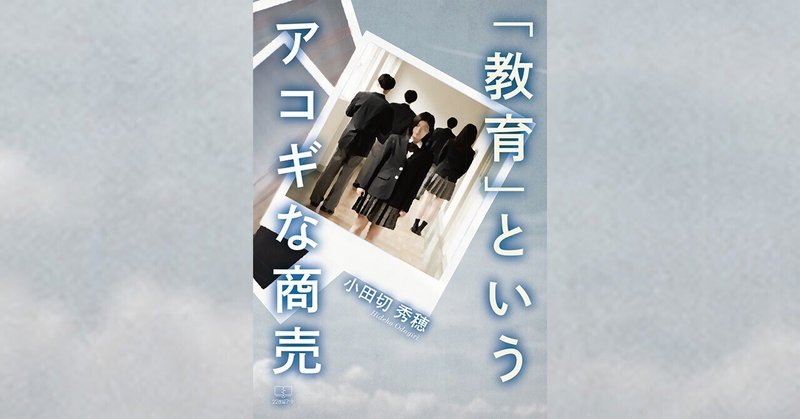
「教育」というアコギな商売 小田切 秀穂 (著)
なぜ週末に模試を受けないといけないのか
近年、校則の見直しが広がっている。髪の色や髪型はもちろん、下着の色までも指定する校則は人権侵害だ。
なぜ、そのような校則が存在し続けていたのか。問題はもっと根深いところにあるのかもしれない。
たとえば、運動会や文化祭、学芸会などの行事。本来は学校が一律に決めることではなく、児童や生徒の自主性に任せる事案なのではないかと思える。
本書は神奈川県の公立高校で模試が「強制されている」ことを取り上げる。生徒や保護者の同意を得ることなく、休日の土曜日に大手予備校の模試の受験を強制されたというのだ。さらに、納得はおろか必要性すら感じていない保護者がその費用を負担させられるのはいかがなものか、と。
模試の強制について、著者は、2000年代初頭のゆとり教育とそれに伴う学力低下からの揺り戻しであるとし、その結果「多くの高校で、特に『進学校』を中心に、『勉強』と『受験勉強』の区別がつかなくなっている」状況だと記す。
さらにまずいのは、PTAや生徒総会などの手続きが民主主義的でないことだ。本書では学校名が実名で登場するのだが、神奈川県下で有数の進学校でも、異議を唱える生徒や保護者に対して強権を発動している。この事実には驚かされた。
ゆとり教育で総合的学習の時間が導入されることとなった。著者の子どもが小学生のときに見た理科の教科書には、昆虫の写真と、わずか数行の文字があっただけだったという。
この教科書を使って、先生はいったい授業で子どもに何を語ってくれるのだろうか。すべてが教師の力量次第だと思った。
なぜ学校は強制したがるのか
ゆとり教育の理念はすばらしい。しかし「能力とやる気のある教師があまねく日本の小中学校に存在しているのか」と、施策を考える中央とオペレーションする現場のかい離を著者は指摘する。
なぜ学校は強権的になってしまったのか。
指導する側に、子どもたちに「アクティブに学びたい」と思わせるだけの力量がないから、強制することによってまずは見た目を繕おうとしている。
議論に耐えるだけの裏付けがないのか、強権をもっても黙らせる。
根底にあるのは、教育の資本主義化だ。「誰のために」「何のために」が欠けたまま、経済効果を求めた結果、いまの状態にたどり着いた、というのが著者の考察だ。
いつの時代も多くの親は子どものためならばと金を出す。それが教育投資となればなおさらだと思う。しかしそれは本当に子どものための生きた投資になっているのだろうか。
民主主義を機能させるための公教育
「我が家には子どもはいないから」「もう大きくなってしまったので関係ない」と思っている読者もいるかもしれない。
しかし、教育は子どものためだけのものではない。
社会を構成する最小単位は「人」だ。一人ひとりの思いがあって、社会はできていくのだろう。本書を読むと、民主主義を適切に機能させるには、公教育のあり方から問う必要があると感じる。
また、学校現場や教育委員会の事情が詳細に書かれている本書は、PTA改革を考えている人にとっても学びの多い1冊となるに違いない。
文・筒井永英
【著者プロフィール】
小田切 秀穂(おだぎり・ひでほ)
1956年横浜市生まれ。
1980年、京都大学農学部卒業。
神奈川県立大野山乳牛育成牧場勤務を経て、神奈川県立高校の教師となる。
1985年退職し、東京大学大学院理学系研究科へ進学。
1987年修士課程を修了し、再び神奈川県立高校へ就職。
2017年3月、定年にて退職。
はじめに
1980年、大学を卒業した。当時は景気もそれほど良くなく、就職もそれなりに大変だったように思う。特に女性の雇用条件は厳しいものがあり、この先この社会で家庭を持ち、子どもを育てていくのは途方もなく大変なことのように思えた気がする。ただ記憶の中に鮮明に残っているのは、きっと定年を迎えるころには日本の社会は民主的で自由な社会になっているのではないかと思っていたことだ。
2017年、定年を迎えた。微力を尽くしてきたつもりではいたが、残念ながら日本の社会がそのような良い社会になることはなかった。実感からすると、当時より相当程度悪くなっている。女性を、人間を大切にしなかった社会は当然のこととして少子化に向かった。国立大学の授業料は、僕が大学に入った1976年までは年額3万6000円だった。それからは上げ続けられ、最近落ち着いてはきたが、今では53万円を越える。その代わりに充実させると言っていた奨学金は、利子付きの教育ローンへと変わった。そして二十歳になれば学生であっても年金を払わせる。若者から収奪し続けた社会は、これも当然のこととして若者から夢を奪ったように思う。
1980年の日本の社会もあまり良いものではなかったと思うが、今よりは自由があったように思う。少なくとも若者は放っておかれた。それはそれで大変なことではあるが、アクティブであることを強要され、自分の将来を決めることを強要され、勉強することを強要される過干渉よりはよほど良いように思う。
若者が、そして一人ひとりの個々人が、希望をもって自由に生きていくことのできる社会の到来を願って本書を書くことにした。
第一章 「公立の復活」は誰のために
校長先生、「Be gentleman」です。
「崩れゆく機会均等〈格差〉の中の県立高校」、2007年12月11日神奈川新聞の朝刊社会面に「公教育の役割放棄に」という見出しで、次のような記事が載っていった。
進学校で有名な県立高校の今春の終業式でのことだ。淡々と終わるはずだった式が、生徒たちの校長への異例の直談判で一変した。「土曜日の時間の使い方を勝手に決めないでほしい」。2007年度から全生徒参加の補習を行う土曜日を〝部活禁止〟とする計画が生徒たちの耳にも伝わり、抗議をしたのだった。同校は有名大学へ進学実績を挙げる進学重点校の指定を5月に控え、布石を打つ構えだった。部活動が盛んな同校の1、2年生が相次いで校長の考えをただした。「受験勉強のためだけではなく部活や行事などさまざまな経験を積みたくて高校に入った」。その場にいた教員は生徒の思いをそう受け止めた。校長は回答を留保したが4月の始業式で「補習への参加は生徒の自主的な判断に任せる」と譲歩し、全員参加計画を引っ込めた。
同校教員は疑問を投げかける。「補習を望む生徒は確かにいて、希望に応える必要は確かにある。だが、学校を挙げて取り組むことで犠牲にされるものは多くはないか」
県教育委員会は進学重点校の10校の指定で、進学実績重視を鮮明にした。加えて、2009年度には全県学区の公立中高一貫校が2校開校する。県教委は一貫校について「新たな進学校をつくるわけではない」とのスタンスだが、塾関係者は「受験するのは私立中学を志望する層と重なり、有名大学への進学実績を問われる学校になるのは間違いない。早晩、進学校化する」と指摘する。
一方で、県教委は本年度から、申請者が急増している県高等学校奨学金(07年度予算額約14億円、国公私立高校の約4200人に支給)について、応募資格で生活保護世帯を除き成績要件を新設して貸与のハードルを上げた。返済免除の条件も同様に成績要件のレベルを上げた。県教委は応募資格の厳格化について「制度を安定的に運営していくため、成績優秀、原則返済という方針に立ち返った」と説明する。だが、約270人が選から漏れ、前年度まで支給されていた生徒に行き渡らないケースが出ている。学区撤廃、進学重点校指定、中高一貫校……。県教委が次々と打ち出す「改革」で選択肢が広がり、恩恵を享受しているのは誰なのか。経済的に恵まれ、教育投資が十分にできる層が結果として、有利になる制度になってはいないか。授業料免除の格差は、その一端を物語っている。
神奈川の教育事情に詳しい東京大学社会科学研究所の佐藤香准教授(教育社会学)は警鐘を鳴らす。「一連の動きは格差助長に結びつく可能性が高く、このままでは公教育の役割放棄と見なされても仕方ない。教育と福祉の連携を深めるなどして、格差を再生産しない取り組みを進めるべきだ」
(2007年12月11日神奈川新聞)
この記事にある終業式のその場に、うちの子はいたようだ。それまでにも、校長の部活動に対する対応についての不満は時々口にしていた。自分以上に、運動部の生徒は不満を持っているようなことも言っていた。終業式の日、帰ってくると式での出来事について興奮気味に語り始めた。
式も終わろうとしていたとき、壇上に一人の生徒会の生徒が上がった。「個人的なことではありますが、この場を借りて皆さんにお諮(はか)りしたいことがあります。賛同いただける方は拍手をしてください」という発言から、すべてが始まった。
突然に体育館の空気が揺れた。
普段はそんなことにまったく関心を示さないような生徒までもが拍手をしていた。
「4月から実施される土曜講習のために、土曜日の午前中の部活動は禁止になるのですか」という質問が校長先生に対してなされた。
「土曜講習への強制参加」「部活動の制限」に反対して、次から次へと生徒の発言が続く。
「禁止ではない。自粛だ」という校長先生の答えに対して、「自粛と禁止はどう違うのですか」。
すると「自分でよく考えてみなさい」と校長が答える。
「自粛は、私たちの主体的判断で、実施してもいいということだと思います」。
「もっとよく考えてごらん」。というようなやり取りが、2時間半に渡って、その後繰り返されていく。
うちの子も、自分も何か言わなくてはと思い、意を決して発言してきたようだった。それらの生徒の発言に対しての校長の対応は極めて不誠実、生徒を明らかに馬鹿にしたものに思えたという。
憮然とした口調で子どもの話は続いた。
そのうちに一人の1年生が手を挙げ立ち上がった。そして校長に向かって「先生、札幌農学校のクラーク博士の言った言葉をご存知ですか」と問いかけたという。
さらに言葉は続いた。
「クラーク博士は、生徒に向かって〈ルールなどいらない。Be gentleman〉と言われたそうです。先生、今のあなたの態度はGentlemanといえますか」
彼のニックネームはそれ以来、「Be gentleman」ということになったらしい。
生徒たちの懸命な質問が、校長によってのらりくらりとかわされていった。議論が全く深まっていかないことに若い高校生たちは焦れていく。2時間半余りが経過したとき、一人の女生徒が発言した。「先生はこの場で結論を出そうとする気はないですし、まともに私たちと向き合う気がないと思います。時間の無駄なので、帰りたい人は帰ることにしませんか」。老獪(ろうかい)な校長に生徒たちが敗れた瞬間だったかも知れない。結局その場では結論が出ず、散会となったという。
その春休み、運動部の新3年生を中心に、この問題に対する対策会議が何度ももたれていたらしい。うちの子どもは吹奏楽部員だったが、わざわざその為に、何度も学校へと出かけて行った。その成果があってか、記事にもあったように4月の始業式での、校長の「土曜午前中の部活動の自粛は、しないことにする」という発言へと至った。ただ、子どもの話からすると、顧問に圧力を掛けることで、なるべく部活動をやらせないように、校長は動いていたようだ。「立派な大人」のやることだ。
