
AIを利用し【非常識】な方法でQC検定2級に一発合格した話

*この記事は非常識な方法でQC検定2級に合格した追憶です。*
*途中の挿絵は私が1日で生成AIに創らせました*
*私の追憶はX(旧Twitter)で提供しています。*
*そちらもご覧ください。*
はじめに
QC検定2級をこれから学ぼうとしている方、もしくは学んでいる最中の方
試験で出題される範囲があまりにも多すぎて、どこから手をつけて良いか
悩んでいませんか?
かく言う、私が第36回(2023年9月)の2級試験に向けて
勉強を開始したときにそんな状態でした。
テキストを何冊か購入し、比較しながら学びを始めた時、
3級の範囲をはるかに超える数式の量に圧倒され、
さらにテキストや過去問に書いてある公式の表現違いに困惑し
【どちらが正解なのか?】
【どっちも正解なのか?】
それを調べるだけでかなりの時間を要しました
2級に合格した今では、公式は違っていても、
その違いは計算過程の違いで、結局たどり着く答えは同じであり、
どちらの説明も【正しい】という事がわかりましたが、
複雑な数式を学んだ事のない私にとっては、最初はそれすら分からず
暗記で乗り切ろうとしていたので、
暗記した公式と微妙に違う公式が、テキストや過去問に出てきただけで
すぐパニックになり、とたんに
【訳がわからなくなる】といった状態でした。
そこで過去問を分析した上で、テキストを読むという
非常識な逆転勉強法
を行うことにしました。
普通はテキストを読み込んでから過去問を解くと言うのが一般的ですよね。
でも私のように大学にも行っていない、数学も学んだ事が無い人間が半年で一発合格するには、常識的なやり方では太刀打ち出来ないと考えました。
そこでまず、過去問の分析を行う為、
テキストや過去問を10冊以上買い揃え(下画像)、

徹底分析しその結果からテキストを読むことをはじめました。
過去問を使う勉強方のメリットは以下のようになります。
過去問を使う勉強方のメリット
試験形式に慣れる:過去問を解くことで、試験の形式や問題の種類に慣れることができます。これにより、実際の試験での緊張を軽減し、効率的に問題を解くことができます。
重要なトピックの特定:過去の試験で頻繁に出題されるトピックや問題を特定することができます。これにより、勉強すべき重要な分野に焦点を当てることができます。
時間管理の練習:実際の試験と同じ時間制限の中で問題を解くことで、時間管理の技術を磨くことができます。これは、試験当日に時間内に問題を解き終えるために重要です。
自分の弱点の把握:過去問を解くことで、自分の弱点や理解が不十分な分野を特定することができます。これにより、効果的に勉強するための指針を得ることができます。
自信の向上:過去問を繰り返し解くことで、その分野に対する理解と自信を深めることができます。これは、試験本番で落ち着いて問題に取り組むために役立ちます。
過去問からテキストを確認するといった事を進めていくと、ある重要な事実に気がつきます。
それは
市販テキストは誤植だらけ
という事です。
【誤植とは?】
誤植とは、印刷物において、文字や記号に誤りがあることを言います。
例えば、本や雑誌、新聞などの印刷物で、正しくない文字が使われていたり、文字が抜けていたり、文字が重なっていたりする場合があります。 このような誤りは、印刷の過程で起こることが多く、校正や校閲で見つけて修正する必要があります。
いろんな書店で売っているテキストに書かれている公式は、
本によっては誤植があったり、公式が記載されていなかったりしています。
紙面の都合上出版社が判断し、【重要ではないところ】と判断したところを記載しないのでしょう。
でも過去問を分析して分かった事ですが、
例えば検定と推定では、試験では検定から推定の一連の理解度をもとめられます。つまりこの検定は何でしょうか?この推定は何でしょうか?
と問われますが、市販テキストでは、検定のみにフォーカスされ、その推定公式が端折られている(記述なし)こともありました。
試験に【良く出る】または【出る可能性が高い】ものを
正確な公式で一覧にし暗記しやすくまとめてあったものは、
市販本には無く、
1冊の市販本で学んでいる方は、誤植を暗記するリスク、
出題される可能性のある問題を逃してしまうリスクが高いと思いました。
そのリスクを極力回避出来るよう、
良く出る重要公式と出題パターンを記載した一覧を自作するしかない
と判断しました。
検定と推定の例を取って話しましたが、
他にも覚える公式は山ほど
さらに実践部分の概念、用語などの暗記も必要
こうなったら、手法、実践 両方を全て書き出し、まとめ
検索出来るようなデータベースを作ろう
でも・・・時間が限られています。
過去問&テキスト10冊以上の大量データを分析するには、
本を読み、ノートに書き起こし、または本に付箋を貼り何度も見返し
・・・なんて方法では時間がかかりすぎます。

2023年3月にQC検定3級が受かってから2級に取りかかり、
2023年9月の試験に挑戦しようと思っていたので、
半年しかありません
さて、なにから取りかかろうか?【重点指向】
どのようにすすめようか?【プランの作成】
どのようなツールを使えば、効率良く進められるのか【ツールの検討】
など、戦略をねり、
どのような手法で、どう実践したか?
を記載していきます。
まず
《手法》
過去問、テキストを多く揃える:
効果:広範囲の問題と情報に触れることで、試験の範囲を網羅的に学習できる。
手書きノートは取らない:
効果:デジタルツールの利用により、効率的な情報整理と迅速な検索が可能になる。
本に付箋は貼らない:
効果:情報のデジタル化により、必要な情報にすばやくアクセスできる。
パソコンを活用する:
効果:情報処理の速度と効率が向上し、複雑なデータも容易に管理できる。
ネットを利用する:
効果:最新の情報や幅広いリソースにアクセスでき、学習範囲を広げることができる。
暗記に重点を置く:
効果:基本的な事実や公式をすばやく思い出せるようになり、問題解決の速度が向上する。
生成AIを利用する:
効果:複雑な問題解決や概念理解のためのガイダンスが得られ、効果的な学習が可能になる。
学習データを持ち運ぶ:
効果:どこでも学習が可能になり、時間を最大限に活用できる。
では解説していきます。
過去問、テキスト、をできるだけ多くそろえる

これは、良く市販テキストに描いてあるうたい文句
【1冊だけで合格】などは私には無理でした。
2級の範囲は3級の数倍。
私のようにルートってなんだっけΣはなんて読むの?
っていう数式ド素人には、まず記号の読み方から学ぶ必要があったのです。
テキストは大抵解っている事を前提で書かれており、
基本中の基本に対する事は書いてありません。
この辺が、数式初心者には優しくない作りになっていました。
なので【1冊だけで合格】は不可能(私の場合)
1冊の本に書かれていない内容か解説は、別の本に書いてあることが
大型書店へ行き立ち読みで中身確認したところ判明したので
複数テキストが必要だと感じそこで、過去問、テキストを大量に購入しました。
手書きノートは取らない

これは、どうしてかと言うと
大量の情報をノートでまとめるには限界があり、
ノートだと見返すこと、
検索することが容易ではないという事です。
各社テキストや過去問の分析には、
同じ項目をまとめ比較検討をする必要がありますが、
手書きだと、データの並び替えをするため、
書き換える事が大変になりますし追記もしづらいのです。
ではどうしたかというと後で解説しますが、
パソコンを活用します
本に付箋は貼らない

これはというと、
本に色でグループ分けをした付箋を挟み、
あとで見返すといった事をする行為です。
しかし、大量になればなるほど付箋探しの森に迷い込むことになります。
限りある時間リソースを検索に使っていてはもったいないです。アナログ検索では、かかり時間がかかります。そこでパソコンの出番になります。
パソコンを活用する

これは手書きノートをやめ、
パソコンソフトにデータを記録すると言うことです。
先ほども言いましたが、
手書きノートだと編集、検索などがしづらいのです。
そこでパソコンソフトに入れると(私はエクセルを使用しました)
記録の編集、検索は用意になります。
ネットを利用する

これは、テキストや過去問で解りづらい箇所を
ブログやユーチューブを利用して学ぶ為です。
テキストは往々にして、
【読者がすでに解っているだろうと思われることを
省略してページ数を減らす】ように書かれています。
【30日で一発合格】
などとうたっている本などは
特に注意が必要です。
私も買いましたが、公式の意味、記号の意味、
記号の読み方、などの説明は少なく、
結果、ネットで調べる羽目になりました。
ですので、ネットやユーチューブを見て
学習する事は必須であると思います。
暗記に重点を置く

まず、手法部分では、公式を暗記しないと始まりません。
公式暗記
パターン暗記
これが必要となります。
深い理解は後回しにしました。
とにかく【受かる】ための学習に徹しました。
そして重要なことが1つ
ノートに手書きで何度も書くといったことはあえてしませんでした。
【頭の中の空想のキャンバスに公式を描く】

といったイメージでしょうか
描いたら、そのイメージを保持するようにします。
これは集中力が必要ですが、慣れると出来ます。
暗記は、記憶にたたき込む作業です。
手にしたシャープペンシルを動かすと行った、
動作への集中は必要無い。
むしろ暗記作業の邪魔になります
空想キャンバスへ書き込むと、通勤時間中、
会社の昼休み、お風呂の中、朝寝起きの布団の中でも、
公式がイメージでき、反復できます。
同じようにパターン暗記も行います。
生成AIを利用する

ただネットで解らない事を調べるのでは、
ネットの次元にあてもなく踏み入る行為です。
調べたい目的のものへ
瞬時にたどり着く方が効率的です。
なんせ時間がありませんので。。。

そこで、生成AIを利用しました。
特に回答の出典をおしえてくれる
マイクロソフトのBing を多用しました。
そこで出た出典元のサイトへ飛び、
学習しました。
学習データを持ち運ぶ
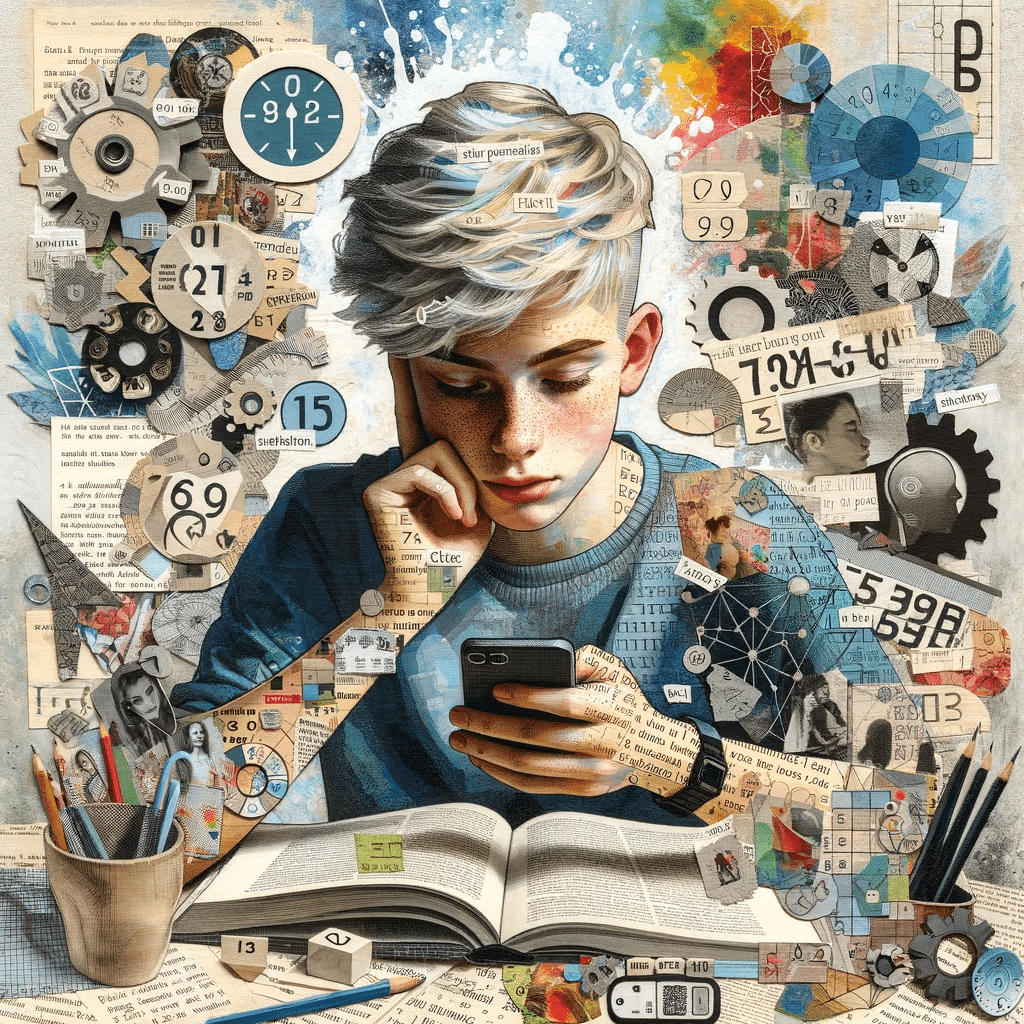
テキスト10冊を毎回出かけ先に持って行き、
隙間時間で勉強する、
なんて事は出来ないですよね。
なので、全てをデータ化し、PDFにし、
スマホに入れ
また、他のツールも使いながら
移動中でも勉強が出来るように仕組みました。
次に《実践》ですが
これらの手法をどのように実践したかは有料記事に記載しています
《実践》
生成AIに疑問を聞きまくる
生成AIにプログラムコードを聞きながら、パソコンでデータベース作成
生成AIに聞きながら、スマホでどこでも学習出来るようにする。
実践内容の解説は有料記事になります。是非ご覧頂き、参考にしてください。
このような方法で事実、2023年9月 私はQC検定2級に一発合格しました。
勉強時間、250~270時間
(仕組みの準備時間も含む)
でQC検定2級に一発合格出来ました。
恐らく、ここでシェアした経験、手法、
ツールを駆使した学習法は
私だけの特殊な方法だと思われます。
ですが、それに使用したツールや個々のやり方は
今後QC検定を受ける皆様に
役立つ内容であると思われます。
そのツール詳細は
有料部分にてシェアしますのでご一読ください。
この記事が皆様の資格取得に役立てれば幸いです。
*この記事は非常識な方法でQC検定2級に合格した追憶です。*
*途中の挿絵は私が生成AIに創らせました*
*私の追憶はX(旧Twitter)で提供しています。*
*そちらもご覧ください。↓*
https://twitter.com/octon_qc
別noteもご覧ください↓
ではどのように実践したかの解説です。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
