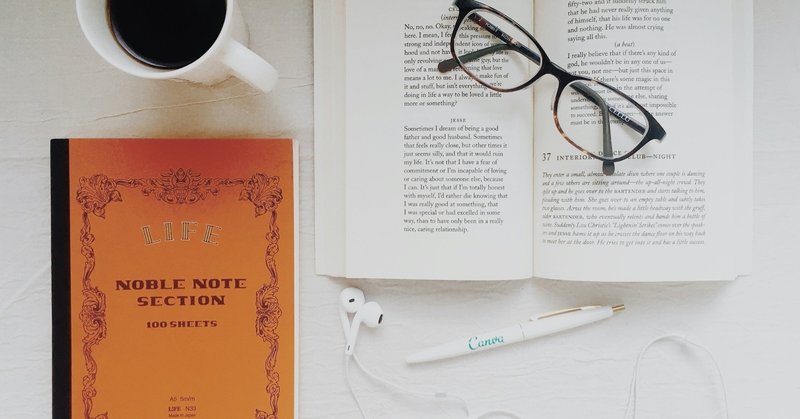
”人を動かす”を考える
こんにちは。
今週は”人を動かす”についていろいろなケースを経験しましたので、人を動かすについて考えてみたました。
その上で、Dカーネギーの”人を動かす”は読むべき本だと改めて思いました。
前提
人を動かす と言うと、上位層に自身が存在し、下位層に指示をすると取られてしまうかもしれません。
私の捉え方としては、”人に動いてもらうにはどうする??”と言うスタンスが一番しっくりきます。
雑談ですが、
本書はDカーネギーを受けての内容ではなく、ただ私の経験を元になっています。
本書の原書は
"How to Win friends &Influence People"です。
日本語訳タイトルと少しニュアンスが違うかもしれませんね。
(批判ではなく、当時の本書の捉え方の中で一番適したタイトルであり、少し時代の変化もあり、私の受け取り方も変わってしまったかもです。)
人を動かす
(人に動いてもらう・人が動きたくなる)には、様々なアプローチがあります。
特に我々30代後半になると、人を動かす能力と言うもを要求されます。
(いわゆる独立し会社を立ち上げたり、会社でも管理職となり)
成果をあげる事(だけではなく)より成果を上げる組織成形能力を求められます。
初めて、こういった新しい環境に対応する事に困惑するケースがあります。
それもそのはず、
今までは”求められる事”と”自分が動く事”は同義化する事が出来ました。
しかし、ステージが変わり”求められる事”と”自分が動く事”が変わります。
具体的には、営業担当なら売上を上げる事 営業課長は売上を上げる課を作る事を求められます。自身の数字ではなく組織の数字を求められます。
一昔前なら、課長が課のリーダーとしてプロジェクトの数字を追いかけ活動し、
部下のスタッフをアシスタント的に使う事で良かったかもしれません。
チームは1人のスーパースターの為のチームでも成立しました。
しかし、
様々な市場の価値観に対応する必要があり、1人の考えだけでは世の中に認められ続ける結果をあげる事が難しくなっています。
考え方1: 自分の考えを伝える
社会に出るという事は、年齢 出身 置かれてる環境が違う人達と関わる事です。
また、その違いが学生時代より多岐に渡ります。
学生時代なら
年齢も3つ違い程度のコミニティーを中心に先生 先輩後輩 バイト先 地域の知り合いくらいの中で活動します。
社会に出ると、まず軸となる職場のコミニティーでも年齢から大きく違います。
直属の上司の課長でも10歳近く部長となると15歳くらい違ったりします。
一番年齢が近い先輩でも3つくらい年齢が離れてたりするのではないでしょうか。
そして、初めて経験する顧客(クライアント)という存在も経験します。
このクライアントとという存在がまた難しくて、顧客の利益になるものを提案する事が顧客が求める仕事であり、一方で自社側で見ると自社の利益を求める事になります。と言うことは、最終的には利益の取り合いをしています。ここのバランスに悩む人も多くいます。
まずこのような社会という環境に適合し、
自分という存在を認めてもらい、その中で主体性を発揮する事が必要になります。
チームのエースとして数字を作る、または
チームのキャプテンとしてチームを統率する。
スタイルはそれぞれですが、
チーム内で頼られる存在になる事での価値を発揮します。
この時期は1番エッジが利く時期かもしれません。主体性を発揮する事が良い事になるので自分の想いを伝える事で、価値が高まって行く事を感じれます
少し調子に乗っているくらいが良かったりします。
しかし、この環境は長くは続きません。
この領域に来ると、次のステージを求められたり、求めたりします。
ここで一つのジレンマが生じます。
考え方2: 自分の考えが伝わらない
チームやスタッフ 得意先との商談の中で自分が思っているストーリー通りに物事が進まないケースが出てきます。
例えば、依頼した内容ができていない。 スケジュール通りに物事が進んでいない。 更にはその確認を自分が確認するまで認識されてない。。。。 など
出来るはずの事が、出来てない状況にある事が出てきます。
もっと言うと、出来るように段取りを取った事が、出来ていない状況にある。
なぜか、自分の思い描いた通りに物事が進みません。
どちらかと言うと、仕事を進める事より確認やフォローをする事が多くなってきたりします。
非常にストレスがかかる瞬間ですが、
ここは、成長ポイントなのでここを乗り越えてください。
最近こんな事がありました。
後輩がチームのメンバーにきつくあたっていまいした。
「なぜ、決めれれた期日通りに出来てないんですか?
出来ないは100歩譲っても、遅れるなら遅れると事前に連絡・相談頂く
べきではないでしょうか?」
なかなか、攻めた言い方ですね。
しかし、言っている事は何も間違っていません。
後輩としても
「はっきり意見は言うべきだと思っているので、僕も言わせてもらいました」
と言ってました。
いかがでしょうか、同じケースでなくてもよく似たケースはあると思います。
コーチング目線で彼に私が声をかけた内容は??
まず、彼の自己肯定をしました。
そうだよね。期日を守れないなら事前に連絡はもらいたいよね。
その上で新しい視点を考えるきっかけを提供しました。
なぜ、相手は納期を遅れてしまったんだろう?
相手はそんなにいい加減な人だったっけ??
このなぜ納期を遅れたかを遅れられた側が考える事に意味があります。
そして、その理由の対して相手でなく自分がどのようなケアを出来るか考える事が
後輩の成長につながると考えます。
相手を批判したり、相手に何かを求めるのは非常に簡単です。
しかし、解決策は相手に委ねられてしまいます。
もちろん後輩が行った、はっきり物を言う事で相手に緊張感(緊迫感)を与え
意識を改めてもら事も一つのアプローチだと思います。しかし、緊張感を与える事はできても意識を改めてくれるかは相手にかかってしまいます。
人を動かす と言うことは、
立場や緊張感で相手が動くのではなく、相手がどのように動くかを考えアプローチする事で人が動くようになる事だと思います。
今いる社会の中でいろいろな人と絡んでいくと思います。
人がどうすれば動いてくれるか?もっと深く言うと動きたくなるアプローチを絶えず考えてみててください。
あなたの仕事はよりいい仕事になると思います。
では、また次回
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
