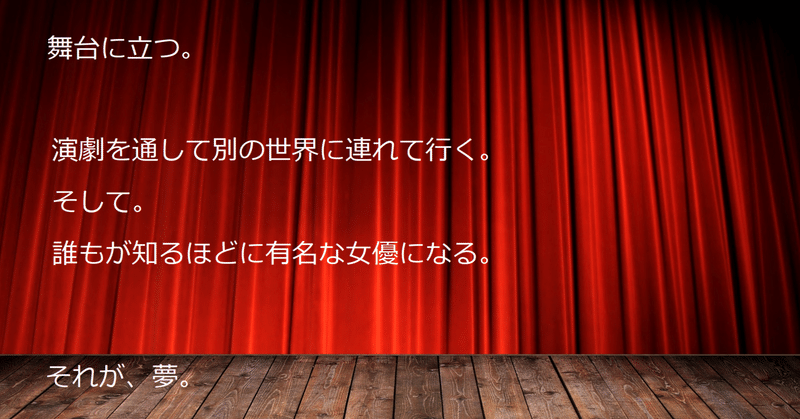
[短編小説]encore -アンコール-
***
劇団セカイズは、今最も勢いのある劇団だった。
セカイズが設立されたのは、今から八年ほど前。設立当初は知る人ぞ知る劇団だったのが、今では多くの人が知る劇団と化していた。
人々の琴線に触れるような脚本、生き写しのように鬼気迫る演技を見せる役者、演劇の世界に引き込むような演出、まるで座った瞬間に吸い込まれるようなふかふかとした座席。セカイズのステージは、全て舞台を盛り上げるためにあった。
セカイズの舞台を見た人々は、まるで別世界に導かれた気分だ、と口を揃えて感想を言っていた。そして、次に言う言葉も、お決まりとなっていた。
「セカイズでの主演を総なめしている北見多紀は、花形女優だ」
北見多紀は、セカイズに所属してから一度も主役を逃したことがなかった。
多紀はセカイズが設立されてから一年ほど後に入団したのだが、当初からその才能を発揮させていた。
多紀の魅力は、豊かな感情表現にある。それらを取り込めた演技、そして演技力の高さを決定的に裏付けるような整った容姿。多紀が舞台に立った瞬間、空気は一変する。
いつしか多紀を目当てにして、多くの人がセカイズに足を運ぶようになった。ネットニュースだけでなく、テレビのニュースの特集にも一回取り上げられたことがあった。それにより、多紀の人気に更に拍車がかかる。多紀のことを詳しく知らずに演劇を見た人々も、多紀の演技を目にすると、その鬼気迫る勢いに圧倒されてしまうことになる。気付かぬ内に多紀の虜になり、またセカイズの集客率も上がることはしょっちゅうだった。
多紀の噂は、大手の芸能プロダクションの耳にも届くようになっていた。実際セカイズの舞台を目にしたスカウトも、多紀の演技に惚れ込んだ。そして、多紀に対して、次の新作で更なる演技を見せるならば銀幕デビュー、更にはドラマにもヒロインとして出演させることを約束した。
その約束を聞いて、多紀の心は跳ね上がった。
「ようやく夢を叶えるためのスタートラインに立てる……っ!」
むしろ、スカウトに声を掛けられた日の帰り道は、スキップをしながら鼻歌を口ずさみ、家に帰ってからも興奮冷めやらぬで、全然眠ることが出来なかった。多紀には珍しいことだった。けれど、それも致し方ないことだ。
多紀の夢は、誰もが知る有名な女優になることだった。
道行く人に「今のご時世、日本で誰が有名な女優か」と問えば、百人中百人が北見多紀だと答えるほどに有名な女優。そういう世界的な女優になることを、昔から夢見ていた。出来れば、後世にだって名を残したいほどだ。
多紀がセカイズに所属するようになったのも、そのための布石だった。
将来インタビューを受けた時、まだ無名にも近かったセカイズの名前を堅固にし、更にはセカイズでスターとして歩んだことを伝えれば、多くの人の好印象に残ることはおろか興味の対象になることは間違いない。そして、多紀の過去を調べ、更に興味を抱いてもらえるだろうと踏んでいた。
だから、多紀にとって次の舞台が勝負だった。次の新しい舞台で最高の演技を見せることが出来れば、多紀の夢を叶えることが出来る。
そのために出来ることならば、多紀は何でもしてみせると心に誓った。
「ねぇ、志乃」
そんな最中の、ある日の公演後のことだった。
セカイズに所属する新人役者の西野志乃は、多紀に声を掛けられるや「はい、何でしょう。多紀さん」と人懐っこい笑顔を浮かべて振り返った。一方、志乃と違って、多紀の表情はかなり硬いものだった。
「あなた、今日の舞台で一か所セリフとちったでしょ」
「ん、そうでしたっけ。私、間違ってなかったと思うんですけど」
「『じゃあね、みんな……』が、幕間に入る前に言うべきセリフだったはずよ。でも、志乃は『またね、みんな』と言った」
多紀は志乃が言うべきだったセリフを諳んじる。脚本を読み込む際、多紀は普段から別の役者のセリフも覚えるようにしていた。特に、場の転換となるセリフの応酬は、今みたいに諳んじることが出来る。
志乃が演じた役は、しっかりと名前もあり、舞台の中で大事なキャラクターだった。今のシーンも、二度と会えない悲しみを彷彿とさせるべきところなのに、志乃の台詞回しだと再会出来るかもしれないと観客に思わせてしまう。
しかし、当の志乃本人はといえば、間違いを指摘されたにも関わらず何事もないように平然としていた。
前述の通り志乃は新人ではあるが、見る者を明るくさせるような笑顔は、すでに一定のファンから人気を博している。多紀とは別の意味で、セカイズの観客の目を奪っていた。
「あー、その件ですか。確かに、セリフは変えましたね。でも、私のセリフの方が、より先の展開を気にさせつつ余韻を残して幕間に入れると思うんです」
志乃は臆することなく自分の意見を言葉にした。
自分の意見を貫く期待の新人か、融通の利かない生意気の新人か。多紀が志乃に下した評価は、後者だった。
「いい? 私の言う通りにして、私を引き立たせるように演技すれば、セカイズの舞台は成功するわ」
志乃が何かを言う前に、多紀は志乃の前から去った。多紀の言葉が全く響いていないことは、志乃の表情を見れば容易く察することが出来た。次に見当違いのことを志乃が言ったら、多紀は自分の心がかき乱されることを察していた。
役者に大切なのは、平常心だ。
何でも受け入れられる柳のような平常心を持っていてこそ、そのキャラクターを理解する土台が出来上がり、そのキャラクターと一体化して感情を爆発させることが出来る。逆に心が乱されてしまったならば、邪心が入り込み、演じるべきキャラクターと一つになることが出来ずに平坦な演技となってしまう。
そう多紀は思っていた。
実際今までだって、そういう演技を貫いて来たから、結果もついて来たのだ。
だから、今この大事な時期に感情を乱されるわけにはいかない。
より一層、周りにも自身にもストイックにぶつかりながら、多紀は次の新作の脚本を渡されるまで胸を高鳴らせながら待った。
セカイズが新作の舞台を準備する期間は、およそ三か月だ。役者達は、普段の舞台をこなしながら、空いた時間では新作の稽古に臨むことになっている。
そろそろ脚本を渡されても良い頃だろう――。そう思っている内に、その時はやって来た。
脚本が配られる時、多紀は脚本家と二人きりで一番初めに脚本を読むことにしていた。何かあれば、すぐに意見を出すためだ。
だから、今回も同様だった。
次の舞台の脚本を手がけるのは、南条世宇。セカイズの人気を裏付けている実力が備わった脚本家であり、そして多紀のことを一番に輝かせてくれる脚本家だ。多紀は何一つ心配していない。
私は今回の舞台を通じて、もっと遥か高みに昇る――、多紀は一層決意を新たにした。
演劇のタイトルは、『私の世界を覆す魔法』。
多紀と世宇。二人きりの静謐とした空間に、紙を捲る音が小さく何度も響いた。
***
「ちょっと世宇。この脚本、どういうこと?」
脚本を読み終えた北見多紀の心境は、嵐が襲い掛かって来たように荒れていた。その乱れる感情を無理やり抑えながら、南条世宇に問いかける。
世宇はちょうど眼鏡についていた埃を拭っていたところで、掃除を終えてピカピカになったばかりの眼鏡を装着すると、
「どういうことって、今の私の心血を注いで書き上げた最高傑作のつもりだけど?」
「うん、分かった。確かに世宇の脚本を読んで、すごい心が踊らされたわ。純粋にワクワクもした」
今回、世宇が手がけた脚本の内容は、ある日魔法が使えるようになった女主人公であるナノの葛藤を描いたものになっていた。心の状態で周りに影響を与える魔法を持つナノ。ナノの気持ちを揺さぶった悪役の存在も、最初から最後までナノにきっかけを与えた叔母の存在も、そしてナノのことを陰ながら支えた幼馴染のチヒロの存在も、文字を見ただけでもみな活き活きと輝いていることが伝わって来た。
世宇の脚本は、現実とファンタジーを絶妙に掛け合わせた風潮が多く、まさに奇跡の賜物と表現しても過言ではない。その奇跡を役者として目に見える形に出来ることがどれだけ喜ばしいことか、長年一緒に活動して来た多紀なら分かる。
しかしながら――、
「だけどね、今回の舞台には相応しくない」
「……どういう意味?」
眼鏡越しでも、世宇が怪訝な視線を多紀にぶつけていることが伝わって来る。けれど、そんなことで動じる多紀ではない。
「この主人公、私の性格とはまるっきり別物よ。可愛らし過ぎるというか、少しあざとすぎる気がするの。この大事な時期に、私のクールな印象が崩れたらどうするのよ。分かるでしょ、私は今回成功を納めないといけない」
今まで多紀がセカイズで演じて来た役割は、容姿や雰囲気に似合った知的なものが多かった。クールでミステリアス、なのに感情が痛いほどに伝わって来る魂籠った演技に、見る人は惹きつけられて、その役柄を多くの人が願っている。そういうイメージが、多紀には根付いてしまっているのだ。
それを今更になって今回のような可愛いキャラを演じることは、周りの期待を裏切るようで演じることは出来ない。
「だから、書き直しよろしくね、世宇」
読み終えたばかりの脚本を、世宇に手渡そうとする多紀。しかし、世宇は多紀から脚本を受け取る素振りを見せることはせず、むしろ多紀を軽蔑するように、「逆だよ、多紀」と短く鼻で嗤った。
「私の脚本が多紀に合っていないんじゃないの。多紀が私の脚本に合っていないの」
世宇の言い方に、多紀は眉根をピクリと動かした。
「何を言ってるの、世宇。このセカイズは私の人気で成り立っていることは、あなたも重々承知でしょう?」
世宇の失礼な物言いに、怒り散らさなかった自分を、多紀は誉めてあげたかった。
次の新作の結果次第で、多紀の命運は分かたれる。活躍の場を広げられるか、このままセカイズに留まり続けるか。まさに多紀の一生を決める、大事な大事な公演になる。
だから、私に似合う脚本を作る必要があるのだ――、そう暗に含めて言葉にした。
しかし、多紀の主張を世宇は一笑に付す。
「それこそ何を言ってるの、なんだけど。周りにチヤホヤされて、思い上がってるんじゃない?」
多紀にとって痛い部分を、世宇は躊躇なく指摘してくる。
「いい、多紀。選ぶのは、あなたじゃない。ゼロから物語を作り上げる私なの」
迷いのない口調に、世宇が常々そう思っていることが分かった。
「確かに目立って見えるのは、表立って舞台に立っている役者だよ。でもね、役者は与えられる役割をこなすだけの存在。演じるための脚本がないと成り立たないし、更に言うなら、裏方に支えられたり、場を提供してくれる人がいなければ何の実力も発揮出来ない」
「……そんなこと、当然でしょ」
いの一番に答えられなかったのは、多紀自身の優先順位が、表立って立つ人間が一番上になっていたからだ。
世宇の言う通り、セカイズのスタッフに支えられていなければ演劇一つ作り上げることが出来ないのだが、最近の多紀は自分が有名になることだけに躍起になっていて、感謝の想いを失念していた。
しかし、多紀にも言い分はあった。
「裏で支えてくれる人達には、ちゃんと感謝してる。けど、演じる役者がいないと、物語は表舞台に出てこれない。違う?」
「うん。そうとも言えるし、違うとも言えるね。今は技術が進化して、プログラムだけで物語を動かすことが出来るし、文字でだって伝えることが出来る。言ってしまえば、個人で物語を作ることだって出来るんだよ。まぁ、そうしたら見る人を限らせてしまうかもしれないけど」
その時、もしかしたら世宇も脚本家という肩書きだけでなく、別の分野に進もうとしているかもしれないと、多紀は予測した。まさに今後活躍の場を広げようとしている、多紀のように。
「ちなみにね。メインの二人は、決まってるよ。まだ他は未定だけどね」
ぼんやりと別のことを考えていた多紀に向けて、世宇は配役表を手渡した。そこにある名前を見て、多紀は更に追い打ちを掛けられることになる。
「ナノ(主役):西野志乃、チヒロ:東谷八尋……?」
多紀は配役表を思い切り握りつぶした。多紀に合っていないキャラクターだったどころか、どうして主役の名前にすらも上がっていないのか。そもそも何故、新人の志乃が主役を演じていることになっている……。
「何よ、これ……。私の名前は?」
「今回の脚本を考えた時にね、残念だけど多紀の顔はメインで浮かばなかった。自然と志乃の姿で、動き出していたの」
多紀も同様だった。脚本を読んでいく内に、ヒロインに投影したのは志乃だった。志乃が浮かんでしまった時、多紀はすぐさま頭から消そうとしたが、世宇の文章力は凄まじく、志乃のイメージを覆すことはついには出来なかった。
そのことは頭で分かっていても、完全に受け入れることは難しい。
多紀は誰よりも努力している自信があった。感情を研ぎ澄ませ、心情を読み取り、空気を察知し、演技を磨く。その甲斐あって、多紀は舞台上で誰よりも光を放つ存在になり、セカイズの名前を更に世間に轟かせた。その自負が、邪魔をする。
多紀は先ほどの世宇のように、ふっと一笑に付した。もちろん、自分を誇示したいだけの見栄ゆえに、弱々しい。
「新人にあなたの脚本を委ねるなんて、練習台にでもしたいつもり? 世宇の脚本なら、ド新人でも輝かせることが出来るか試したいんでしょ」
そうでなければ、多紀を外すことなんて考えられなかった。先ほど脳裏に浮かんだ世宇の可能性が、多紀の中で現実味を帯びていく気がした。
世宇は落胆したように息を吐き、あからさまに肩を落とした。
「さっきも言ったでしょ。今回のイメージは、最初から志乃だった。ヒロインの天真爛漫さと、志乃の性格と若さから来る明るさが、このナノにはピッタリなの」
こうなったら、世宇の意見は変わらない。北見多紀という女優を輝かせるような修正を加えることなく、世宇は最後までこの脚本を貫き通す。
「話を振り出しに戻すけどさ。仮に、多紀にプロの役者だっていう自覚があるなら、どんな役にだって合わせてみせるのが多紀の仕事でしょ。それを役柄が合わないからって修正を強いるのは、お門違いなんじゃない?」
世宇の鋭い一言に、多紀は咄嗟に言葉を返すことが出来なかった。
そんな迷いさえも許さないように、更に世宇は多紀を問い詰める。
「今の多紀は何がしたいの?」
「……っ、私は――」
「あ、言わなくていいよ。私ね、コピペのように薄っぺらい言葉って嫌いなんだ」
一瞬の逡巡さえも見逃すことなく、世宇は容赦なく多紀の言葉を割り捨てる。
実際、世宇の言うことは事実だ。世宇の描く脚本は、いつも活き活きとして、そこには貼り付けられたようなセリフは存在しない。そして、脚本に関してだけではなく、世宇の性格もまさしくそうだった。
世宇は誰の意見にも流されることなく、いつも確固たる自分の意志を持っていた。だからこそ、人を惹きつける脚本を書くことが出来るのだ。
「意見があるなら、自分の言葉でいいなよ。そうしたら、耳を傾けてあげる」
多紀は拳を握り締めた。
言いたいことは、たくさん頭の中にあった。けれど、今何かを言ったところで、世宇は決して耳を傾けないことを多紀は分かっていた。互いの性格を知り合っているくらいには、多紀と世宇の関係性は長い。
多紀は何も言うことなく、部屋を飛び出した。せめてもの反抗に、扉を思い切り締める。けれど、そんな反抗さえも物ともせずに、澄ました表情を貫く世宇がありありと想像出来て、更に多紀の胸が焦がされるだけだった。
「あ、多紀さん」
大きな歩幅で廊下を進む多紀の正面に姿を見せたのは、志乃と八尋だった。
二人並んで歩く姿は、多紀にとっては悔しいことだけれど、先ほど読んだばかりの脚本の主人公達にピタリと当てはまっていた。
志乃はちょこちょこと小走りをすると、「私、楽しみです」と屈託のない笑みを浮かべながら言った。
「今回の世宇さんの脚本って、どんなものになるんでしょうね?」
「……私が知るわけないでしょ」
これ以上、志乃のそばにいたくなくて、多紀はつい強く当たった。そして、脇目も振らずに、廊下を歩いていく。志乃と八尋が多紀を呼び止めたけど、聞こえないふりをした。
苛立っていながらも多紀の歩き姿は、やはりと言うべきか、モデルさながらに整っていた。すれ違う人みなが足を止め、振り返る。いつもの多紀なら、愛想の一つでも振り撒くのだが、今日の多紀にそんな余裕はなかった。
今頃、世宇は志乃と八尋に脚本を渡して配役を伝えている頃だ。そして、志乃と八尋は無邪気に喜んで、最高の劇を作るために必死に稽古に臨むだろう。爪弾きにされた多紀は、嫉妬にまみれて眺めるだけ。
そんな想像をしてしまって、多紀は自分自身に嫌悪を抱く。
まさか夢の一歩手前で道が阻まれることになろうとは、脚本を読む前の多紀は予想さえも出来ず、配役を落とした後でも現実として受け入れることは出来なかった。
***
劇団セカイズが新しく公演する演劇『私の世界を覆す魔法』の稽古が始まってから、多紀の足はピタリと稽古場へ運ばれなくなった。
今日も、セカイズは休演日でありながら、他のメンバーは新作の稽古に臨んでいる最中だというのに、多紀は目的もなく散歩をしているところだった。
「はぁ」
何度目になるか分からない溜め息。
稽古に参加しないという事実は、セカイズに所属してから今まで毎日のように稽古場に残っていた多紀にとって、天変地異が起こったかのようだった。
また、多紀に変化が起こったことは、足を運ばなくなったことだけではなかった。
多紀は公演が終わった後、すぐに帰宅するようになった。もちろん、すでに割り振られている役割は、しっかりと演じている。主演を務める時は、ちゃんと主演としての振る舞いをした。しかし、演技の入り方は今までと明らかに異なり、見る者からしたら差は明確だった。更に、裏口に待ち構えるマスコミの対応にも、多紀はろくに言葉を返すことはなかった。
この変化の原因は、すべて多紀の心境にあった。
目の前の道が途絶えてから、多紀は目的を失くしかけていたのだ。いや、目的と言うと齟齬が生じる。多紀の夢は、ずっと変わらない。
「――皆間真奈美さん」
多紀はスマホの待ち受けにしている人物に目を落とした。そこに写っているのは、同性問わずに目を惹きつけるような、凛々しい姿の女優――皆間真奈美だった。
昔、多紀が住んでいた東京郊外の小さな商店街で、ロケが行なわれていた。そこのロケで一際目立っていたのは、当時から有名だった女優の皆間真奈美だった。真奈美を中心にして、ドラマが進んでいく。いつも慣れ親しんだはずの商店街は、いつしか自分とは掛け離れた世界の一部になっていく感覚を、幼い多紀は敏感に察していた。
真奈美の一挙手一投足は、世界に彩を与えていく。そんな人並外れた才能を持っているのに、演技が終わると、普通の人よりもへりくだって接する。
皆間真奈美は、そういう人物だった。
今は表舞台から姿を消してしまい、どこで何をしているのかは一切知られていない。けれど、彼女の名前を出せば、百人中百人が顔と名前とその功績を一致させることが未だに出来るだろう。それほど有名な女優だ。
その女優に、多紀の心は一瞬で持っていかれた。夢も目標もなく、ただ時間だけが虚しく過ぎていく退屈な多紀の世界が覆された瞬間だった。
一方的に憧れを抱くようになり、いつしか真奈美と一緒のステージに立つことを望み、多紀も演技の道を歩むようになった。
それからは、真っ直ぐだった。ひたすらに夢に向かって真っ直ぐ突き進んだ。普段から人に見られていることを意識し、凛とした佇まいを振るった。その全ては、真奈美のような有名な女優になるためであり、真奈美と一緒に同じ作品を作るためだった。
しかし、前述の通り、真奈美は演技の舞台から引退するようになった。
多紀の夢は叶わなくなったが、もう一つの夢までなくなったわけではない。真奈美の存在関係なく、多紀は演技の道に惹かれ、多紀の意志で有名になりたいと思うようになっていた。
演技の幅を広げたい、大勢の人に演技の楽しさを知ってもらいたい。
その想いの果てに、今の多紀が形成されるようになった。
「……なのに」
まさか、たった一度だけ主役を外されてしまうだけで、ここまで意気消沈してしまうとは多紀自身思いもしなかった。
今回のセカイズの新作『私の世界を覆す魔法』の主人公像は、多紀の性格とは百八十度異なっていて、たとえ主人公に抜擢されたとしても多紀は苦労を強いられたことだろう。
まだ現実を完全に受け入れることは出来ないけれど、新作の主人公は新人の志乃しかいないことは理解していた。
「お役御免、ってね」
呟いた言葉に、自分自身で嘲笑を漏らしてしまった。配役がなくなった女優の多紀に、なんとピッタリな言葉だろうか。
稽古場に行く必要がないとしても、ただ部屋でジッとしているというのは、多紀にとって苦行でしかなかった。
しかし、町に赴いたからといって、多紀の心が動かされることはない。
誰一人、北見多紀の存在に気付くことなく、己が道を進んでいる。セカイズでもてはやされ、テレビに出て、取材も受けて有名になった気でいたが、どれだけ高慢な考えに陥っていたのかを多紀は思い知らされていた。
気の向くまま真っ直ぐに進んでいると、一つの建物が――否、その建物の前にある看板が、多紀の目に映り込んだ。普段の多紀だったら看板になんて興味を抱かないが、その看板には「全国高校演技 地区予選」と書かれていた。演技と記されていれば、話は別だ。
「よかったら、どうですか?」
まじまじと看板を見つめる多紀に気さくに声を掛けて来たのは、「スタッフ」という腕章を左腕に付けた女子高生だった。
「今なら、まだ何校かは見れると思いますよ」
「私、保護者でも関係者でもないけど……」
「そんなの関係ないですよ。みんな、一人でも多くの人に見てもらおうと頑張って練習していたので、お時間に余裕があれば是非ご覧ください」
屈託なく笑みを見せる女子高生に、多紀は「じゃ、じゃあ……」と根負けするように会場の中へと入っていった。
一つの作品を作り上げるために費やされる時間というのは膨大だ。セカイズがこれから演じる『私の世界を覆す魔法』だって、相当な時間を費やしている。そして、その相当な時間を、作品に関わる人物みなが注ぐのだ。
エンタメの世界に関わる中で、努力の甲斐を感じられなくなる一番の瞬間というのは、見向きもされない時だ。
その事情も気持ちも知っている多紀は、高校生の想いを無下に扱うことは出来ない。
建物の中に入ると、男子生徒のスタッフが嬉しそうにプログラム表を手渡してくれた。多紀は一言礼を言うと、更に奥へと進んでいく。ホールに入った途端、観客たちによる雑談が押し寄せるように耳に響く。前の高校の演技が終わって、次の高校の準備段階に入っているのだろう。その間、観客たちは先ほどの演劇の感想や、次の演劇の推測を話し合っているわけだ。ということは、
「次の高校の演技は、最初から見れるのね」
途中から見るよりも初めから見る方が、当然のことだが好ましい。多紀は内心ホッとした。
ホールの中は思ったよりも広かった。その小さめの空間の中でも、空席がちらほらと目立っている。高校生の演劇、しかも規模も小さそうな地区予選だと、仕方のないことだろう。多紀は空席に腰を落とすことはせず、一番後ろの壁際に背を預けて観劇することにした。
この場所なら、高校生の演劇も会場の空気も、俯瞰的に見ることが出来る。そうすることで、多紀に必要なものを余すことなく吸収するのだ。
「……まぁ、高校生からは学べないと思うけど」
プロである多紀が、高校生の拙い演技を見て、今更何になるというのか。有名な劇団の舞台を観るというなら、話は異なるのだが。
こんなところまで来て、何をしているんだろう。私がいる場所は、もっと――……。
多紀の口から漏れた「……はぁ」という小さな溜め息を打ち消すように、ホール全体にブザーが鳴った。多紀は反射的に真正面へと意識を向ける。まるで多紀に倣うように、雑談に耽っていた観客たちも口を閉ざして、舞台へと顔を向けた。
幕が開ける前の、何が始まるんだろうという期待が籠った空気は、プロだろうと高校生だろうと変わらない。多分、観客であろうと役者であろうと裏方であろうとも、変わらない。多紀も同じ思いだった。
胸中を宿っていた感情は、舞台の前では水泡と帰す。そうしなければ、長い時間準備した人々に、失礼に値する。
それぞれの想いを籠めた眼差しが舞台に集まり、
「――」
幕が、開ける。
***
「――すまないね、世宇ちゃん」
脚本『私の世界を覆す魔法』を更にブラッシュアップ出来ないかと考えていた世宇の頭上から、男の声が降り注がれた。世宇はパソコンから目を離すと、そのまま視線を上に移した。
そこにいたのは、劇団セカイズの総支配人となる田井中奏汰だった。まだ三十代後半で若い年齢だというのに、よくやっている。
奏汰は手に持っていた缶コーヒーを、世宇のパソコンの隣に置いた。缶コーヒーのプルタブは既に開けられていて、周りに気を遣える奏汰らしい配慮だった。世宇は缶コーヒーをそのまま仰いで飲む。少しだけ頭がスッキリとした。
「んで、何を謝ったんですか?」
「君には辛い役目を振ってしまったと思ってね……。その、多紀ちゃんの件で。怒っていただろう?」
多紀に脚本を渡した日のことを思い出した。その場にいなかった奏汰の言う通り、多紀は物凄く動じていて、珍しく声を荒げていた。あの日の多紀を頭に浮かべると、多紀には申し訳ないながら、世宇はいつも思い出し笑いをしてしまう。今もそうだった。不可解なものを目の当たりにするかのように、奏汰は首を傾げる。
「まぁ、多紀には良い薬になったんじゃないですかね」
主役ばかり務めて来た多紀には、俯瞰する目が必要だ。
「それに、私は慣れてるから大丈夫ですよ。物語を盛り上げるためには、どこかで悪役の存在は必要になりますから。嫌なことから目を背けていたら、世界は変わらない」
「……悪役が板についているね、世宇ちゃんは」
奏汰の言葉に、世宇は薄ら笑いを浮かべるだけだった。
***
多紀が己の夢を自覚してからは、夢を叶えるための努力をずっと継続して来た。
たとえば、だ。多くの劇を生で見たり、流行のドラマも多く見た。自分の中で演技の引き出しを幾つも作ろうと、すれ違う人の人生を想像し、空想で演じてみたりもした。学生時代にクラス内で演劇をしたこともあったが、その時は多紀主導で行ない、妥協を許さなかった。
いつもレベル高く演技が出来る環境に身を置き続けていた。
だから、世間一般の高校生が作り上げる舞台を目にするのは、多紀にとって初めての体験だった。
「セリフ嚙んでるじゃない……」
舞台に立つ高校生が、顔を赤らめながら、舞台を進めていく。下手すると、小道具を持つ手が震える始末だ。
「緊張してるのが、こっちまで伝わって来る」
場面の暗転が、少しだけ早く、演者の台詞と重なってしまった。
「演出も、プロからしたら伝わらないわよ」
残念ながら、この高校が予選を突破することはないだろう。
プロの立場である多紀が見たら、足りないところが多すぎる。その足りなさを見逃すような真似を、審査員がするとは思えない。他の周りの学校の演技と比べて、五十歩百歩だったら話は別だが、その可能性もそうそうないはずだ。
最近の部活のレベルがこのくらいだとは、多紀は予想だにしていなかった。
やはりプロである多紀が、今更高校生の拙い演技を見たところで、学ぶべきことなんて何もなかったのだ。
そう冷静に分析する一方で――、
「どうして、目が離せないのかしら」
舞台で蠢く一挙手一投足すべてに、多紀は魅せられていた。
高校生の演技は、拙い。本当に大会に臨むつもりがあるのかと問いただしたくなるほどの、まさにお遊戯会同然のものだ。
しかし、舞台に立つ高校生は、真摯に演技に向き合っている。緊張も伝わって来るが、何よりも楽しそうにやっているのが、見ていればすぐに分かる。
その高校生の、幼く純粋な気持ちが、ホール中に伝播していた。
ここにいる人が、息を呑んで見守っている。多紀も自分がその一員になっていることに、ようやく分かった。
ここ最近、多紀はそんな純粋な演技をしただろうか。等身大の演技をする高校生の姿を見て、多紀は自問自答する。
いつも真摯に向き合って来たつもりだったけど、追い求めるベクトルが異なっていた。完璧に演じないとならないという思いと、楽しくやりたいという思い。最近の多紀が真摯に向き合っていたのは、前者だった。
楽しそう。
久しく向き合っていなかった感情が、ふつふつと多紀の心に湧き上がる。
その想いによって、多紀の胸の熱が燃え盛っていく。熱によって、心の中で何かが作られていく。おぼろげだった何かは、感情という炎で、何度も形を変える。何度も何度も。
そして、炎によって形が完成された時――。
「――ぁ」
多紀が胸の内の存在に気付いたと同時、ホール中に拍手が鳴り響いた。舞台上に立つ高校生は、全てを出し切ったような清々しい笑みを、くしゃくしゃに浮かべている。演技者だけでなく、舞台に関わった裏方の高校生まで表に立って、頭を下げて拍手を浴びている。
舞台は生き物だ。舞台を構成する要素が複雑に絡み合って、完成される。その完成形は誰にも分からない。まさか、あの拙い演劇が、このように拍手喝采で終えるとは誰が予想しただろうか。
けれど、その一方で、高校生たちのひたむきで楽しそうに演技をする姿を見ていたら、何となく予想を覆してくれるような気がしていた。
惜しみない拍手を浴びながら、幕が閉じていく。
拙いハッピーエンドを見届けた多紀は、急いで会場を後にした。
***
「――世宇!」
稽古場の扉を大きく開けた多紀に、稽古場にいた人々が振り返る。
唯一動じていないのは、多紀に名前を呼ばれた当の本人だけだ。いつも傍から俯瞰して見届けている世宇には珍しく、脚本を片手に役者に混ざって中央に立っていた。
「何? 今こっちは忙しいんだけど」
劇団セカイズの新作『私の世界を覆す魔法』が開始されるまで、残り一か月ほどだ。多紀はたくさん舞台を経験したから、今がどれほど大事な時期なのか分かっている。
「ごめん、世宇」
素っ気なく答える世宇に、多紀は誠心誠意を込めて頭を下げた。「それに、みんなも」と頭を下げながら、多紀は周りへの配慮を忘れない。
「私、自分の夢を叶えられると思って、自分の実力が認められていると思って、高慢になってた……。世宇に指摘されて、自分一人で考えるようになって……、そこで、私の身勝手な行動でセカイズにどれだけ迷惑を掛けているのか、痛いほどに分かった」
世宇も、志乃も、稽古場にいる人は、息を吞んで多紀の動向を見守っている。
「私の夢は、誰もが知る有名な国民的女優になること。けど、どうしてそうなりたかったのか、初心を忘れていたわ……」
そして、先ほどの高校生の演技を見ながら気付いた想いを、多紀は口にしていく。
多紀が演技の道を歩み出したのは、皆間真奈美という女優に魅せられたからだ。
初めて皆間真奈美に心を惹かれたのは、彼女が別の世界へと多紀を連れて行ってくれた。同じ世界でも、役者が演じれば、別の世界を作り出せることを知った。ありふれた多紀の世界を、彼女の演技が覆してくれたのだ。
もし真奈美に出会わなければ、多紀はずっと退屈な人生を歩んでいただろう。
「私は、可能性を知ったの。演技を通して、人の運命も覆せるんだっていう可能性を」
世界を広げてあげられる人になりたい。
辛い現実にいたとしても、多紀の演技を見ることで、別の世界もあるんだと考えを転換してほしい。劇を見るだけでは現実は変わらないかもしれないけど、せめて観劇している間だけは、現実を忘れてほしい。
そんな影響力を持った役者に、多紀はなりたかった。
存在そのものが光り輝いていた、元国民的女優の皆間真奈美のように。
――これが、多紀が役者を続ける理由だ。
だけど、そのことを忘れて、いつしか名声だけを追い求めるようになっていた。好きだった演技も、有名になるための手段と化していたのだ。
「演技が巧いだけの役者になりかけていたって、今気が付いて良かった。私が目指すのは、人の心を動かして、その人の世界を少しだけでも変えて上げられるような、そんな女優なの。……これが、あの時言えなかった答えよ、世宇」
ゆっくりと顔を上げる多紀。顔を上げた多紀を、咎める者は誰もいなかった。世宇も、静かに耳を傾けている。多紀は想いを噛み締めるように、一度だけ胸に手を当てた。大丈夫、多紀の内に宿る火は消えていない。むしろ、今言葉にしたことで、更に火が燃え盛っている。
「――だから、ね。私、何でもする!」
役者を目指すようになった初心。今度は消さない、決して。
「主役も脇役も、裏方も関係ない! 演技に関われるなら、何だってする! それが今の私がしたいことよ!」
高らかに、堂々と宣言する多紀は、冷静沈着な北見多紀が持つイメージとは全く掛け離れていた。しかし、この場にいる誰もが、その姿が一皮むけた後の多紀だということを、言葉なくとも察していた。
「……ふふっ」
真っ先に静寂を裂いたのは、世宇だった。いつも物静かな世宇には珍しく、声を上げて、肩を震わせて笑っている。眼鏡の奥の目じりに、涙まで浮かべるほどだ。「やっぱ面白いわ、多紀は」と目じりに浮かんだ涙を、人差し指で拭う。
「じゃあ、新しく生まれ変わった多紀に相応しい役をあげる」
そう言うと、世宇は手に持っていた脚本を多紀に渡した。
「ありがとう。どんな端役だって、私はこなしてみせるわ」
「違うよ。多紀に任せたいのは、端役よりも――、ううん、どんな主役よりも難しくて大切な役」
脚本を捲ると、すぐにマーカーが引かれている台詞が出て来た。次へ次へと捲る内、また彩られていく。マーカーが引かれているのは、全て叔母の台詞。大事な場面で何度も何度も登場するため、彩られている数はあまりにも多い。それが多紀に与えれた配役だと理解するまで、時間は必要なかった。
今回の多紀が演じる役は、主人公ナノに多種多様に変化を与える叔母。
今まで演じて来た役とは、違う。
主役として舞台を引っ張って来たけれど、今回は脇役として舞台を支えなければならない。
この叔母がいなければ、ナノは間違った道に進んでいた。あまりにも重要な役だ。
まさか、世宇がそんなに大切な役を多紀に割り振ってくれるとは思いもしなかった。
「文句があるなら、別の役にするけど?」
世宇の言葉は、更に多紀の心を焚きつけていく。その全てを見透かしたような不敵な顔、絶対に覆してやる。
多紀は全身を武者震いさせてから、音を立てて脚本を閉じると、
「――最高ね。やり甲斐があるわ」
迷いのない瞳で、堂々と口にした。
そして、多紀は稽古場に立つ。すると、稽古場の上には、多紀と同じ背格好――、けれど明らかに多紀とは異なる女性が姿を見せた。
多紀の姿は、演技をする度に与えられた役へと何度も何度も転じていく。
まさしく女優と呼ぶに相応しい姿だった。
<――終わり>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
