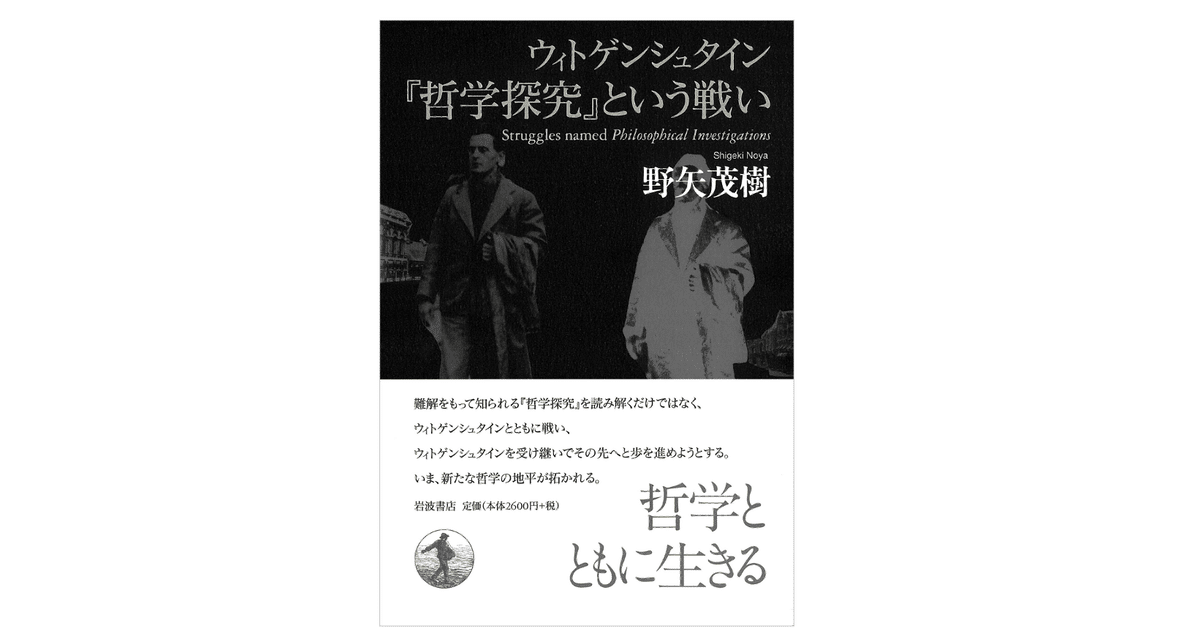
野矢 茂樹『ウィトゲンシュタイン 『哲学探究』という戦い』
☆mediopos2667 2022.3.6
ウィトゲンシュタインの
『論理哲学論考』と『哲学探究』に出逢ったのは
二十歳のころだったが
それ以来なんだかんだと
いまにいたるまで細く長くつきあってきている
『論理哲学論考』は
「語りえぬものについては、沈黙せねばならない」であり
『哲学探究』は「言語ゲーム」だったが
その後ウィトゲンシュタインについてふれるたびごとに
それまでとは別の文脈を加えながら
じぶんなりの理解と誤解を繰り返してきた
今回野矢茂樹氏が『哲学探究』と格闘している記録を
読み進めることでまたあらたなウィトゲンシュタイン像が
「問い」というかたちで姿をあらわしてきた
ウィトゲンシュタインへの関心が持続するのは
まさにその哲学が「問い」を喚起するからだろう
ウィトゲンシュタインは
「私の書いたものによって他の人が
自ら考えないで済ますことを、私は望みはしない。」
「可能ならば、この著作によって読む人が
その人自身の思考へと促されることを望んでいる」
と『哲学探究』の序に記しているが
重要なのはまさにウィトゲンシュタインが
哲学問題と格闘しているように
われわれもまた格闘するということなのだろう
そうでなければ「探求」の意味はない
そこにあるのは「答え」ではなく
病気をみずから治療するようなものだからだ
じぶんの罹患している病気に気づき
その病気をみずから治療しようとすること
それは哲学における目的が
「蠅に蠅とり壺からの出口を示すこと」
であると示されていることでもわかる
『哲学探究』の到達点は
『ラストライティングス』で示唆されているように
「言葉はただ生の流れの中でのみ意味をもつ」
という言葉に集約されるということだが
それは「言語の文の理解」は
「音楽におけるテーマの理解に似ている」
ということにも通底しているように思われる
言葉は特定の何かを表象しているのではなく
それを理解するにはその背景にある
「われわれの生き方の理解」が必要であって
言語をとらえるためには
時間のなかで音楽を享受するように
それとともに生きなければならない
つまり言葉を用いるということは
言葉とともに生きるということにほかならない
こう記してしまえば
あたりまえのことのようだが
はたしてわたしたちは
ともに生きるようなかたちで
言葉とともにいることができているだろうか
ノヴァーリスはすべての学問は
哲学になったあとにポエジーになるといったが
言葉とともに生きることそものが
蠅とり壺から出た蠅としての哲学者の
向かうべき場所だということもできるのかもしれない
そう考えるとウィトゲンシュタインの著作は
一節一節がまるで詩のようにも思えてくる
あるいは詩になろうとしている哲学断章・・・
■野矢 茂樹『ウィトゲンシュタイン 『哲学探究』という戦い』
(岩波書店 2022/2)
(「はじめに」より)
「ウィトゲンシュタインの哲学はおおまかに前期と後期に区分される。前期の著作は『論理哲学論考』であり、後期を代表する著作は『哲学探究』である。というよりも、『哲学探究』はウィトゲンシュタイン哲学の全体を代表する主著と言ってよいだろう。しかし、私を含め多くの人が−−−−非哲学者はもちろん、哲学の専門家たちでさえ−−−−『哲学探究』を読もうとして跳ね返されてきたのではないだろうか。晦渋な表現は何ひとつないのに、そこに何が書かれてあるのか、なぜそんなことを言うのかが分からない。断片的な考察が並べられ、それらがどうつながるのかもはっきりしない。ところがそうして読んでいるとはっとするような言葉に出会い、それに惹かれながら、『哲学探究』を手放せないでいる。いや、これまでの私自身のことである。だが、そんなつまみ食い的な理解ではなく、『哲学探究』そのものを捉えたい。私はそう思った。」
「注意すべきことがある。
私の書いたものによって他の人が自ら考えないで済ますことを、私は望みはしない。可能ならば、この著作によって読む人がその人自身の思考へと促されることを望んでいる。(『哲学探究』序)
『哲学探究』のすべてのページにおいてわれわれが目の当たりにするのは、哲学問題と格闘しているウィトゲンシュタインの姿である。」
(「第1章 語は対象の名前なのか」より)
「彼は一貫して哲学を「治療」として捉えていた。
哲学者は問題を治療する。そう、病気を取り扱うように。(第二五五節)
この哲学観は前期・後期を通じて一貫していた。哲学問題に対して、答えを与えようとするのではなく、そもそもそこには問題などなかったのだと示すこと。いわば問題を「解消する」こと。それがウィトゲンシュタインが哲学においてめざしたことだった。」
「 哲学問題は、「私は途方に暮れている」という形をとる。(第一二三節)
哲学における君の目的は何か? −−−− 蠅に蠅とり壺からの出口を示すこと。(第三〇九節)
哲学においてウィトゲンシュタインは「完全な明晰さ」を求めている。もちろん多くの哲学者がそうだろう。しかしウィトゲンシュタインにとって「それはただ哲学問題が完全に消滅すべきということを意味するにすぎない」(第一三三節)。それゆえ哲学はけっして何かありがたい真理を手渡してくれるようなものではない。壮麗な学説を打ち立てるようなものでもない。いわば、まがまがしいものに取り憑かれた人を祓い清める活動なのである。蠅とり壺というのは入りやすく出にくい構造になっている。しかし、入ってきたところから出ていきさえすれば、蠅も自由になれるのだ。
『哲学探究』はそんな治療の報告にほかならない。」
(「第12章 言葉は生の流れの中で意味をもつ」より)
「ウィトゲンシュタインはノーマン・マルコムとの会話において、「表現は流れの中でのみ意味をもつ」という趣旨の意見を述べたという。マルコムはその発言をウィトゲンシュタインの哲学を凝縮したものと受け止め、感銘とともに思い出している。マルコムはその意見を口頭で聞いたのだが、われわれはそれを『ラストライティングス』に見出す。
言葉はただ生の流れの中でのみ意味をもつ。(『ラストライティングス』第九一三節)」
「 言語の文の理解は、ひとが思っているよりもはるかに音楽におけるテーマの理解に似ている。(第五二七節)
(・・・)
第一に、音楽は基本的に何かを表象したものではない。
(・・・)
第二に、そうした音楽によって引き起こされた反応を「結論のよう」とか「挿入句のよう」という相貌で捉えるには、言うまでもないが、「結論」や「挿入句」といったことを理解していなければならない・そして、あるフレーズが一つの曲において結論や挿入句として聞こえるには、相応の文化的背景が必要だろう(・・・)言語もまた、言葉を理解するには。その言葉を用いて人びとが何をするかを理解しなければならない。それは『論理哲学論考』や過渡期のような人間不在の言語体系ではなく、われわれの生き方の理解を背景にもつのである。
第三に、私はなによりも音楽が時間の内に展開するものではることを強調したい。(・・・)われわれは言葉とともに生きることによってしか、言語を捉えられない。」
(「第14章 意志する・意図する・意味する」)より)
「「意味」という概念がまさに『哲学探究』の中心的な問題であったことは疑いがない。では、なぜウィトゲンシュタインは「意味」を問題にするのだろうか。「意味」が哲学的に問題になる概念だから。もちろんそれもある。言葉が意味をもつというのはどういうことか。それは言語哲学の根本問題である。だが意味をもつのは言葉だけではない。私がいま腰かけているのは「椅子」という意味をもち、窓の外を見れば「雲」という意味をもつものが「垂れこめている」という意味をもつ状態にある。世界は意味に満ちている。そして人間たちの行為もまた。だから「意味」はけっして言語哲学だけの問題ではなく、哲学の全体に及ぶ問題なのである。言葉が、世界が、行為が意味をもつというのはどういうことなのか。哲学はそのことを問い続けてきた。
しかし、それは『哲学探究』が「意味」を問題にする動機の半分(おそらくはより少ない方の半分)にすぎない。哲学が「心」「自我」「時間」「行為」・・・・・・等々を問題にするとき、「意味」という概念が哲学を誤った方向に導くのである。本書の冒頭近くで引用しておいた言葉をもう一度読もう。
第一節の事例をよく見れば、言葉の意味という一般的な概念がどれほど言語の働きをもやで覆い、明瞭に見てとることを不可能にしてしまっているかがおそらく感じとれるだろう。−−−−言語の諸現象を、語の目的と働きが明瞭に見渡せるような原初的な言語使用において検討するならば、そのとき霧は晴れてくる。(第五節)
そして私はこれに対して、いったいどういう霧に包まれているのかさえまだはっきりしないと率直に述べた。だが、こうして『哲学探究』を読み通してきたいまでは、ウィトゲンシュタインを、いやわれわれを覆う霧が何であるのかが多少なりとも見えてきたのではないだろうか・例えば「私」という語が意味する自我という実態を考え、それがこの世の中に存在するのか、それとも世界を超越しているのかと問う。あるいは、「意志」という語が意味する心的状態を考え、それが身体という物理的なものの運動をいかにして引き起こしうるのかと問う。こうした問いはなるほど哲学の難問であろう。しかし、それはそもそも「意味」という概念に誤動された疑似問題だったのではないか。哲学は、哲学が問題にする「心」「私」「行為」等々の語が意味する何ものかの正体を明らかにしようとする。『哲学探究』はその哲学的姿勢を突き崩し、新たな哲学の方法を提案した。『哲学探究』が「意味」を問題にするのは、「意味」という概念そのものが問題であるという以上に、それが哲学の方法に関わる概念だったからに違いない。
そして、「意味」についての『哲学探究』の到達点をひとことで述べるならば、『ラストライティングス』の言葉になるが、先にも引用した「言葉はただ生の流れの中でのみ意味をもつ」に集約されるように私には思われる。
だが、注意しなければならない。これは『哲学探究』が到達した哲学的テーゼなどではない。哲学は生の流れの中にあるものごとを説明しようとして、逆に生の流れを断ち切り、立ち止まり、目を凝らし、内面を見つめ、超越者を求め、はるかに深みをめざそうとしてきた。もう一度水面に顔を上げ、生の流れへと戻っていかねばならない。哲学はむしろそのリハビリテーション的な活動なのである。どうすれば、哲学問題に悩まされず、霧が晴れ、憑き物が落ちた状態で晴れやかに生きることができるのか。哲学とは、われわれを、とりわけ哲学問題に悩まされる哲学者たちを、本来の生の流れへと呼び戻すための技術の集積なのである。
ではウィトゲンシュタインはどうだったのか。『論理哲学論考』は「語りえぬものについては、沈黙せねばならない」として哲学を捨てて、沈黙の内に生きることをめざした。それに対して『哲学探究』は哲学とともに生きることをめざしている。哲学問題は一度やっつければそれで終わりというようなものではない。何度も何度もそこに繰り返し立ち向かっていくウィトゲンシュタインの姿をわれわれはこれまで見てきた。(・・・)大団円を迎えて幕を降ろすのではなく、ふっと緊張を解き、短く息を吐いて、「ちょっと休もう」とつぶやく。それが『哲学探究』の終わり方なのだ。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
