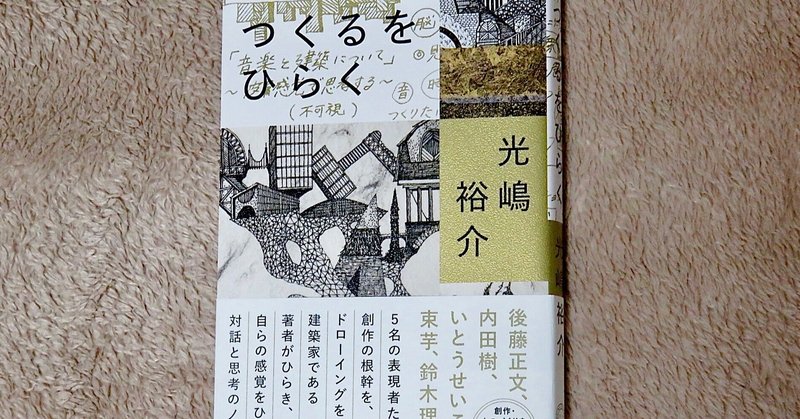
光嶋裕介『つくるをひらく』
☆mediopos2270 2021.2.2
じぶんをつくる
そのために
じぶんをひらく
閉じたじぶんをひらく
見る
じぶんは
なにを見ているのか
じぶんが見ているものを見る
見えていないものがあることに気づき
見たいものだけを見ていることに気づく
じぶんが見ている世界を
少しずつひらいていく
感じる
じぶんは
なにを感じているのか
じぶんが感じているものを見る
感じていないものがあることに気づき
感じたいものだけを感じていることに気づく
じぶんが感じている世界を
少しずつひらいていく
考える
じぶんは
なにを考えているのか
じぶんが考えていることを考える
考えていないことがあることに気づき
考えたいことだけを考えていることに気づく
じぶんが考えている世界を
少しずつひらいていく
いま見ている世界の外へ
いま感じている世界の外へ
いま考えている世界の外へ
じぶんをひらき
世界をひらく
じぶんをつくり続け
世界をつくり続ける
■光嶋裕介『つくるをひらく』(ミシマ社 2021.1)
(「第5章 目で思考する」〜「余韻 偶然を捉え世界を愛でるおおらかな写真」より)
「(鈴木)理策さんと話していると、自分のなかの世界をつくるうえにおいて「見る」ことがいかに決定的であるかを再認識させられた。この内なる世界は、それぞれの価値観と言い換えても良い。自分の価値観とは、自分がどのように世界を見ているのか、あるいは、どのように世界を解釈しているのかを意味する。だからこそ、見える世界とその向こうにあるかもしれない、見えていない世界に対する意識、想像力をもつことがたいせつになってくる。
自分が見えていると思っている世界というのは、じつのところ、自分が切り取っている有限の世界でしかないということをまず自覚しなければならない。自分の見たい世界だけを見て、それこそが外の世界のすべてだと都合よく思い込んでしまうことは危険であり、そうならないように、どうしたらいいのか。世界をより広く捉えるための余白を意図的に残しておくこと。つまり自分が捉えている世界がつねに不完全な世界であると認識し、断片的な世界でしかないにもかかわらず徹底的に「見る」ことを通して、思考する時間を持続させることに尽きる。そのために写真を撮ること、写真を見ることをセットで考えることがたいせつであると、昨日改めて感じた。
一九世紀初頭にカメラ・オブスキュラが発明されてまだ二〇〇年も経たないのだが、いまでは形態電話に高性能なカメラがついていて、写真を撮ることがあまりにも手軽で身近になり、わたしたちは日々の生活における記録を写真という媒体に残すことがものすごく容易になった。それにより、人間は感動した瞬間という忘れたくない時間を少しは忘れないで記憶に留められるようになったと考えられる。
しかし、本当にそうだろうか。怪しい。
むしろ、写真を撮るという行為があまりにもイージー(簡単)になってしまったが故に、感動を閉じ込めるという意識がめっきり薄れてしまっていないだろうか。忘れたくないという気持ちの発露からシャッターを切るのではなく、記録という手段がすっかり目的になり下がってしまい、撮ることだけで満足してしまいがちになった。要は、せっかく撮られた写真が、あまり見られなくなってしまったのである。プリントされることもなく、ほとんど見られることもない膨大なデータだけが携帯電話のなかやパソコンのハードディスクに亡霊のようにみるみるストックされていく。」
「わたしたちは写真、つまりイメージを見ながら考えて、世界を少しずつ自分なりに知っていく。そう考えると「写真を撮ることと、写真を見ることをちゃんと分けて考えないといけない」と理策さんが言ったのは、写真を撮るという行為が目に見える風景から「考える」という時間を写真を見るときまで「先送り」していることに対する違和感というふうにも受けとめられる。」
「わたしたちの眼はつい見たいものだけを見てしまう傾向がある。見えないものは、どうしたって見えない。自分が立っている場所から見るという視点が絶対に存在し、そのため死角という見えない場所がつねに存在する。つまり、世界全体を俯瞰的に捉えることは、理論的に不可能なのだ。
そんな眼の延長としてカメラを考えると、写真に収めることができるのも、もちろんレンズに収まる範囲だけということになる。意識的にせよ、無意識的にせよ、写真に写っているのは、いつだって切り取られた世界の断片である。しかし、撮ることと同様たいせつなのが、撮った写真を徹底的に見るということであるのは、見ることを通して写真を理解し、偶然を捉え、世界に暫定的な解釈を与えることが可能になるからだ。ゆらぎ続ける不確実な世界を透明な目でなるべく正しく認識し、不完全な自分をつくり変えることができるようになる。」
「写真を「撮る」と「見る」というのは、文章を「書く」と「読む」の関係に似ている。
撮ると見るも、書くと読むも、どちらが上位にあるという関係ではない。ただ、撮らないと(書かないと)見られない(読めない)し、見ること(読むこと)によって撮ること(書くこと)も変わっていくから、質と量の問題が発生する。たくさん撮らないと上手に撮れないという技術の問題になっていく。しかし、理策さんは「ダメな写真はない」と断言した。
この発言にわたしは心から感動してしまった。理策さんの写真というものに対する深い眼差し、絶対的な信頼のようなものを感じたからだ。創造に対する忠実な想いがあふれ、優しく肯定されたことにわたしは救われる思いがしたのである。
これを読むと書くに換えると、「ダメな文章はない」ということになろうか。
なるほど、写真も文章も質のことを考えると「良いか悪いか」という判断基準の問題が浮上する。けれども巧拙を問うことよりも、写真そのもの、文章そのものをそのまま受け止めることのほうがよほど豊かな可能性にひらかれていて、たいせつなのではないかといく理策さんの問題提起には全力で賛同する。」
「写真の良し悪しを恣意的に判断するのではなく、ただただ見ること。この原初の状態をわたしは身体的に「ひらかれている」ように感じている。
自分の世界観や価値観に静的に閉じこもることなく、つねに動的に自己を更新するためには、新しいことにひらかれた自由な場所を自分のなかにつくり続けなければならない。その余白としての自由な場所で持続的に思考する時間をもつことで、想像の選択枠が増えていく。そのとき、外の世界と内の世界の境界線にいる自分の身体感覚を信頼するという至極当たり前なことに思い至った。それは、自分の内側を丁寧に観察するということと地続きなのである。」
「自分の感覚をひらくことで、余白が生まれて未知の世界との接触面が拡張する。脳だけではなく、皮膚感覚だったる、遠くの音に耳を澄ましたり、目で見えるものを徹底的に見て、見えないものを心の目で眺めること。目先のこともわからない不確実な世界でも、肺の奥まで深くきれいな空気を吸い込んで、心身を整えながら、このひらかれた身体がキャッチするシグナルに対してつねに創造的であれたら、毎日をゴキゲンに過ごすことができるのではないかと思っている。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
