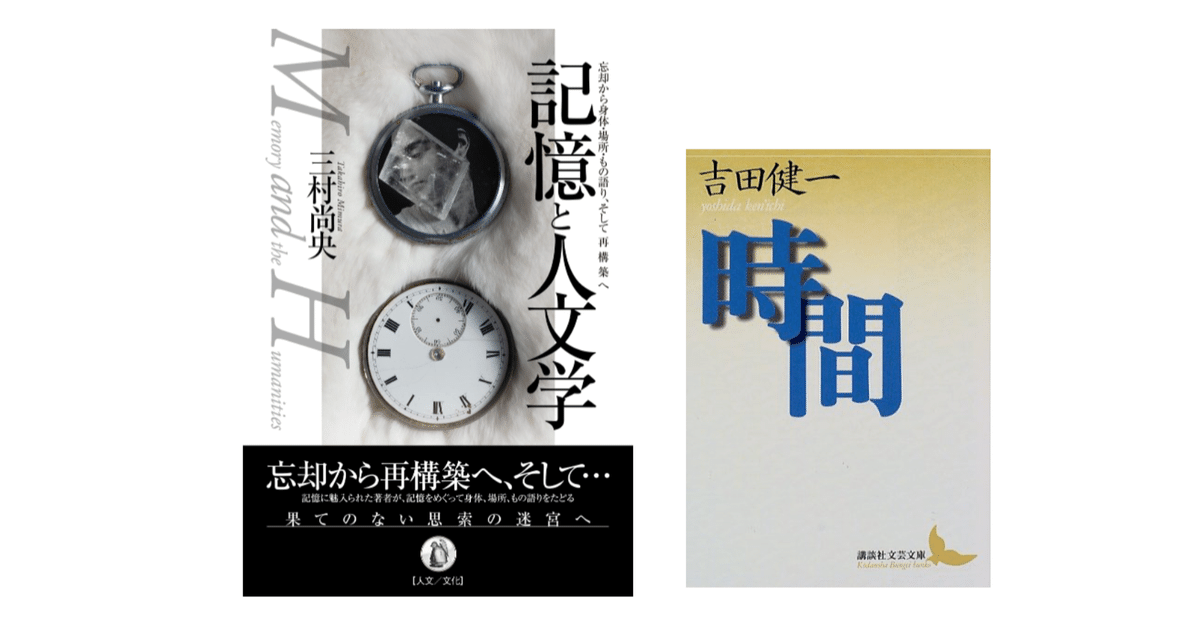
三村尚央 『記憶と人文学』 ・吉田健一『時間』
☆mediopos-2397 2021.6.9
記憶は
過去の単なる記録ではない
記憶は常に現在において働き
想起されるときに再構築され
その際さまざまに姿を変えて現れる
また記憶は個人的に現れるだけでなく
共有され伝わってゆく側面もあり
その際の記憶は集合的な姿をとって現れる
上記は『記憶と人文学』の主題だが
重要なのは
抽象化された物理的時間や
計測されるときの時間と
生きられている時間とは異なるということだ
生きられている時間は常に現在である
記憶も記録としてのそれではないとき
現在において生きられている時間として現れる
吉田健一の語る『時間』は
まさに常に現在という生きられている時間のことである
時間が生きられているときどんな過去も過去ではない
それはまさに現在において流れている時間である
逆に物理的に現在であったとしても
それが生きられていないとき
現在という時間のなかにはいないといえる
歴史に関しても
過去を記録した歴史データは
生きられている時間における歴史ではない
過去に起こったことでも
それが生きられているとき
それは常に現在である
たとえ「体験していない記憶」だとしても
それが真に生きられているとき
みずからの現在において
ともに生きることも可能となるといえる
時間を神秘学的な視点で試みに捉えてみると
時間が生まれたのは土星紀
物質の萌芽が生まれたときでもある
それまでは時間は持続という状態だったともいう
その意味では時間を生きるということは
「からだ」とともに生きるということでもあるだろう
常に現在である時間を生きるということは
からだとともに
つまりは物質世界のなかにおいて
意識を働かせるということでもある
そしてそこに記憶も生まれる
記憶には忘却がつきものだが
顕在的であるとはかぎらないが
記憶はすべて意識の奥行きにあるととらえたほうがいい
生きられた時間はすべて記憶として蔵されているのだ
仏教的にいえば阿頼耶識とでもいえるかもしれない
それが現在という意識のなかで
さまざまに姿を変えながら立ち現れてくる
■三村尚央
『記憶と人文学/忘却から身体・場所・もの語り、そして再構築へ』
(小鳥遊書房 2021.5)
■吉田健一『時間』(講談社文芸文庫 1998.10)
(三村尚央『記憶と人文学』より)
「本書を貫く三つの主題を次のように示すことができる。
①記憶は過去についての記録というだけでなく、さまざまな印象や感情と絡みあう情緒的なものでもあり、私たちの現在にも影響をおよぼす(記憶の現在性)。
②記憶は想起される際に再構築され、その過程で変容や補正を被る可能性がある(記憶の再構築性と可塑性)。
③記憶は個人的なものである一方で、人々のあいだで共有され、伝播してゆくものでもある(記憶の個別性と共同性、および集合性)。」
「第一章では、写真を題材に過去の想起が私たちの現在に与える影響を考察してゆく。写真加工技術が進みフェイクまで簡単に作れるようになった現代においては、過去の一瞬をありのままに記録して、それを事実として後に伝えるという、写真がかつてもっていた意義はほとんど風前の灯火である。だが、写真技術の誕生期から、著述家たちの思索の対象となってきたのは過去の正確な再現としての写真だけでなく。むしろそこにつねに含まれる加工や再構築の可能性でもあった。」
「第二章では、身体と記憶との結びつきを取り上げる。記憶の想起は脳内で起こる現象にすぎない、という主張にある程度の理は認めながらも、私たちにとっては、それ以上の身体的感覚と切り離せないものとしても立ち現れる。思い出に残るほどの強い身体的刺激をともなう記憶は、それを味わう舌や握り合う手自体が思い出すかのようにも感じられる。」
「第三章では、記憶と「場所」および「建築物」とのつながりを取り上げる。かつて行ったことのある場所に足を踏み入れると、そこにまつわる個人的な記憶が生き生きと蘇ってくることは日常的に経験される。このような記憶と「場所」や「建築物」との関連づけを利用していたのが、古くからおこなわれてきた記憶術であり。古代の弁論術においても用いられていたこの技法は、覚えたい内容を見知った場所と結びつけて、頭の中に強く印象づけるというものであった。」
「第四章では「記憶の物品」を取り上げる。幼少期の品を思いがけず見つけ出して、久しぶりに取り出したときには、しばしば強いノスタルジックな情緒が喚起される。ときにそれは非常に強力で、あたかもその物品から記憶があふれ出てくるように感じられ、懐かしさと不安の入り交じった戸惑いすら覚えることもあるが、そのようような取り戻せない過去へのノスタルジアは、あまたのフィクション作品の題材ともなっている。この章で注目したいのは、思い出の品々とそれらが喚起する記憶との結びつきは、極めて私的である一方で、遺跡の遺物や、博物館に陳列される証拠物のように、それが置かれていた「文脈」あるいは「物語」を他者とのあいだで共有することが可能な点である。また、記憶の物品を介して、記憶が個人の枠を超えて人々のあいだで伝達・共有されて集合的記憶へと拡張されてゆく現象も取り上げる。」
「第五章と第六章では、記憶と忘却の関係、およびそれに伴う記憶の倫理の問題に焦点を当てる。伝承や文書、書籍、写真そして近年のデジタル化にいたるまで、さまざまな形で個人のライフスパンを超えて私たちは記憶を継承してきたが、それは忘却に対する記憶の勝利などではなく、本質的にはつねに勝ち目のない後退戦である。(…)過去の歴史の重みから個人を救う「幸福な忘却」(ニーチェ)の可能性がある一方で、適切に忘却することの困難も私たちはしばしば体験する。「覚えておくべきこと」という何気ない言表にも、「覚えていかなくてよい」「あるいは「忘れた方がよい」とされうRものとのあいだでの線引きあるいは選別がセットされていることを思い浮かべれば、それらがつねに「誰に、あるいはどの集団にとっての」という限定の問題でもあることが理解できるだろう。」
「実際に経験した当事者にとっては辛すぎて、自分ではとてもそのまま表に出すことができず、別の人へと不完全な形で託すことでしか表現できない(向き合えない)記憶がある。そしてその記憶を受け取る者は、実際には経験していない出来事を自分のものとして「思い出す」ことで、その「手触り」を絵画として物質化する。このような警官は、私たちがいかにして自分のものではない物語----それが他者の実体験であれ虚構的なものであれ----深く関与することができるのか。という謎を考えてゆくきっかけにもなるだろう。他人の物語を我慢強く聞くどころか、それを自分のものとして引き受けて経験し直し、享受することさえできる、人間だけがもつ驚異的な能力である。」
(吉田健一『時間』より)
「時間はただ経過している。それに就いて過去その他の区別を設けるのが信用に値しないのはその過去に該当する時間の一部が意識の対象であってもこれに意識が向けられている間は過去の観念を伴わないからで我々が歴史を読んでいてそれが過去のことだと思うのは読んだ後で我に、或は俗に我と呼ばれているものに返って何かと分別してかたらのことである。」
「時間はただ経過する。その経過を意識する時に我々はそこにいてそれ故にそこにいることを自分とその周囲の状況に即して間違いないことに感じるのがその状況を満たすということが生じてそれが現在である。それが生じない時に我々の意識、或は精神は全面的に働かなくてそのように働ければいつでもどこでも現在があるということからすれば例えばロオマ時代の記念碑、貨幣の類いを点検しているその方の専門家がいる場所、その現在が今日のでなくてロオマ時代のであってもその専門家が現在にいることに変わりはない。又そこまで行くのでなければ専門家のロオマ時代に就いての知識は生きて来なくてこのことから今日の我が国に歴史家がいなくて歴史学者ばかりである理由も解る。それは歴史が過去のもの、従って今にはないものと考えられていることで歴史が既にないものならばそれに就いて知るには信用出来る文献に頼る他ないことになり、それはそこに記された事実にであってその事実が何を語るかは文献に記されていないから事実に再び戻るということが繰り返されて我々に歴史ということで与えられるものは文献の二番煎じでしかなという結果になっている。
幾ら文献が揃っていて事実を並べるのに不足しなくてもそこに現在がなくて従って人間の世界がないことは歴史が今はないものと決めた前提通りである。併しそれならば今日の一日前の昨日もなくて事実にしか頼らなくて破綻を来さないのが科学という一つの限定された領域でだけであることがここでも示されている。寧ろ天平時代の屋根の勾配を見てその時代には屋根がこうだったと考える代わりにそこにこの時代を摑むことがそこにいることなのでこれは見れば見る程そこにいることになる。そこから先が問題の眼目である。」
「そこにいなければ我々には何もない。もしいればそこにあるものが我々にもある。それが認識の根本であるようであって上の空というのは自分は対象の所まで行かなくてそれをしなくても解ることは解る積りでいることでこれが更に自分は別であることにもなれば少しでも立ち入って考えるのが損であることにもなる。」
「我わらは自分の体がある場所にだけいるのでなくて寧ろそうでないことの方が多い。併しそこが世界という一つの観念であってもそこに我々がいなければそれがその時の現在であってそうでなければこの観念が我々に何かを伝えるということもない。こうして我々がどこかにいるというのは我々の意識が充足して或る対象と向き合っているということで従ってその対象を場所、時代、観念という風に分類することはない。或は分類してもそれが区別することにならないのである。
それならばそれぞれの現在はどうだろうか。その何れもが現在であることに変わりはなくて我々は、或は我々の充足した意識が現在というのがどういうものか知っている。これは現在が数えられないことでそこにあるのはただ一つの現在であり、それ故に我々の一生も現在の連続、或は断続であってこれをただ一つのものと見ることが出来る。又当然これは我々の、或は人間の一生に止るものでない・我々が歴史でもある世界のどの一点に眼を向けてもそこにあるものを確実に摑むに至ればそこにいるのでその摑むというのがそこで自分の廻りを見廻すことになるまでに対象に習熟すること以外のどういうことでもないと考えられる。もしその状態にあったことを完全に思い出せば我々は再びそこにいる。」
「我々は物質に頼ることに限度があることを知らねばならない。(…)それが起こって時間のうちにその場所を占めるに至るのが我々の精神に訴えて来るには、これを別の言葉で言えばそれがそこにあることを我々が認めるにがその出来事が精神の領域での出来事でなければなたなくてその出来事が物質の領域に残した跡は消滅しても精神の領域では時間が過去になることがない。或は時間が過去になるというのがもともとあり得ないことなので物質は消滅する形で時間の経過を現す類のものである。」
「レダが白鳥に犯されたんのがトロヤ戦争の遠因をなしているというのは神話である。併し我々がアポロドロス、或はオヴィディウスを読んでいてこれを過去にあって後世に伝えられた捏造とは考えなくてそれ故にこれが歴史であることにならなくても我々がそこに確かにあると感じるものはそこにある。それが何であるか解らなければならないということはない筈であって我々の目の前で起こっていることでも我々に解らないことは幾らもある。その解るということに執着するのが我々に言葉をその意味と思わせて自分の感覚よりも解説に頼らせるので確実にあることを知ってそこに自分もいることを知ってそこに自分もいることを認めるのはその意味を取ることでもなければそれが解説の種になることでもない。併し世界を見廻してそこに間違いなくあると認められるものがそこにあり、それがあったのでないのはその感覚を生じさせるものがないからであって我々がものを見る時の眼を世界に向ければそうなる。そこにあるものがあって我々に語り掛けるがこういうことが曾てあったと語るものはなくてそこにも流れる時間というのは常に現在である。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
