
前川淳『空想の補助線――幾何学、折り紙、ときどき宇宙』
☆mediopos3335 2024.1.4
折り紙作家で
その数学・科学・歴史等に関する研究者である
前川淳の月刊『みすず』での連載が刊行されている
話題は紙飛行機・パスタの形の機微・巨大望遠鏡・
数学の難題の折り紙による解法・「無限」の御幣など
興味深いものが多々あるのだが
そのなかから「吾に向かいて光る星あり」を
「吾に向かいて光る星あり」という言葉は
正岡子規の
真砂なす數なき星のその中に吾に向かひて光る星あり
という句からのもので
芥川龍之介の『侏儒の言葉』の中で引用され
(なぜか作者名はそこでは伏せられているが)
「明滅する星の光は我我と同じ感覚を
表はしてゐるようにも思はれるのである。
この点でも詩人は何ものよりも先に
高々と真理をうたひ上げた」と評されている
星が宇宙の一部でもある自分と
対面しているというのだが
前川氏はみずからの
「闇の中に光る星の明かりは、
変わらないことがあるという安心感を与えてくれ、
それを見上げていると無力な自分を恥じることはない
という思いにもなった」という経験から
その歌について
「大いなるものと対比して無力の自覚があり、
それゆえの祈りがある」とし
「この無力の自覚は、逆説的に
自由や解放ということに結びつくこともある。」という
夜空に燦めく圧倒的なまでの無数の星々を見上げるとき
あまりにもちっぽけな自分を感じるのはだれしもだろうが
その無力さゆえにこそ
あまりにも小さなことに拘っている自分の自我が
大宇宙を前に解放されるように感じるのはたしかだ
しかもそんな星々の中に
「吾に向かひて光る星」があるというのである
前川氏は「自分が選ばれた者のように星に照らされていたり、
星に導かれているという考えには滑稽なところもあるが」
としているが
そんな「滑稽な」とみなされた考えは
ただ「滑稽な」ものではないのではないか
じぶんだけが選ばれたという感覚は錯誤しているだろうが
だれしも自分の魂は「星に導かれている」
そう感じることは決して錯誤ではないと思われる
導かれ方はさまざまだが
たしかに天空の星々はわたしたちの
内的な真実を映し出していると感じられはしまいか
都会の空の下ではそうした星空の神秘の姿を
意識することはほとんどなくなっているだろうが
みずからの魂に燦めいている星々を
天空の星々の前で実感することはかけがえのない経験となる
さてこのエッセイでは
芥川龍之介+子規の話題に続いて
若山牧水の第四歌集にある
かの星に人の棲むとはまことにや晴れたる空の寂し暮れゆく
ややしばしわれの寂しき眸に浮き彗星見ゆ青く朝見ゆ
という歌がとりあげられている
1910年5月に最接近したハレー彗星を詠んだ歌のようだが
牧水は火星や彗星の存在を自然主義的な感覚でとらえていて
「星に導かれている」というような感覚はなさそうである
前川氏は芥川が
「火星の住民の有無を問ふことは
我我の五感に感ずることの出来る住民の有無を問ふことである。
しかし生命は必しも我我の五感に感ずることの出来る
条件を具へるとは限つてゐない」と述べていることに対し
その考えは「わたしにはむしろ面白くなく、
火星人に関しては、若山牧水の次の歌のほうが響く。」
としている
その違いは
科学者と文学者の違いを表しているのだろう
科学者は「我我の五感に感ずることの出来る条件」のもとで
世界をとらえないと「面白くな」いのかもしれない
しかし私たちはどちらか一方だけというのではなく
その両者の違いをできうる限り踏まえながら
どちらをも許容できる魂であるほうが豊かになれるのではないか
■前川淳『空想の補助線――幾何学、折り紙、ときどき宇宙』
(みすず書房 2023/12)
(「吾に向かいて光る星あり」〜「真砂なす数なき星のその中に」より)
「地上での理不尽や、自分の日々の愚行からくる憂鬱が、星空を見上げることで解消するというのは甘い話だが、空気が澄んで人工の光の少ない土地で、星空が見分けられないぐらいに星の数が多い夜空の下に立つと、はじめ胸がざわついて、しばらくして静かに落ちつくということがある。少なくろもわたしにはそんなことがある。東日本大震災のさい、停電し暗闇となったなかで仰ぎ見た星空のことを語る人は多かった。わたしもあの日、全域停電となった山梨県の北部で、いつにもまして鮮やかな星空を見上げていた。
あの日は月齢も6ぐらいのそう明るくない月で、10時過ぎにはそれも沈んだ。闇の中に光る星の明かりは、変わらないことがあるという安心感を与えてくれ、それを見上げていると無力な自分を恥じることはないという思いにもなった。この感覚は、大いなるものを前にした絶対的な無力の自覚に基づくものなのだろう。この無力の自覚は、逆説的に自由や解放ということに結びつくこともある。
(・・・)
わたしは、ときどきこんな思いで星空を見上げている。自分は無力だ。それでも、無力の自覚ゆえに無力に抗しうるし、自由でもありうる、と。そしてときに、人がどんな思いで星空を見上げてきたのかということを考える。たとえば、正岡子規に次の歌がある。
真砂なす數なき星のその中に吾に向かひて光る星あり 子規
芥川龍之介はこの歌を、なぜか作者名を伏せて、警句集『侏儒の言葉』の中で引用し、「明滅する星の光は我我と同じ感覚を表はしてゐるようにも思はれるのである。この点でも詩人は何ものよりも先に高々と真理をうたひ上げた」と評した。芥川の論旨は、よくある、宇宙のことを思えばあなたの悩みは小さいという話とは違っていて、それとはむしろ逆に、星の世界も地上の世界も、「(同じ)運動の方則のもとに、絶えず循環している」というものだ。彼は、天体と地上の存在を普遍性で結びつけて「変わりない」といった。
芥川がこの文章を書いたのは、天文学の歴史において、われわれの棲む銀河のほかに多数の銀河が存在することが明らかになり、宇宙の大きさの認識が飛躍的に広がった時代に対応している。
(・・・)
ただ、こうした科学的発見の細部が芥川の見解に大きな影響を与えたのかというと。必ずしもそうでもないようだ。彼は宇宙の広さに目をみはるのではなく、その拾い宇宙もまた地上と同じ法則で存在していると考えた。彼は、19世紀のフランスの革命家ルイ・オーギュスト・ブランキの『天体による永遠』に書かれた、起こりうるすべてのことは起こりうる、あるいはすでに起こっていてその繰り返しであるという、一種の多世界宇宙説のような考えに惹かれたようで、これを『侏儒の言葉』の中でも紹介している。それは、新しいことなどなにもない、すべては退屈であるというペシミスティックな思想にも通じ、フリードリッヒ・ニーチェの永劫回帰説も思わせる考えである。
子規の歌をそうした思想に結びつける芥川のレトリックはややアクロバティックにも思える。多くの人は、この歌からもっと素朴な感慨を読み取るだろう。自分が選ばれた者のように星に照らされていたり、星に導かれているという考えには滑稽なところもあるが、わたしはこの歌から、高揚ではない、慎ましい祈りの響きを聞いた。宇宙の一部でもある自分と宇宙の対面という意味では芥川の考えと通底するのだが、そこにはやはり、大いなるものと対比して無力の自覚があり、それゆえの祈りがあるのではないか。」
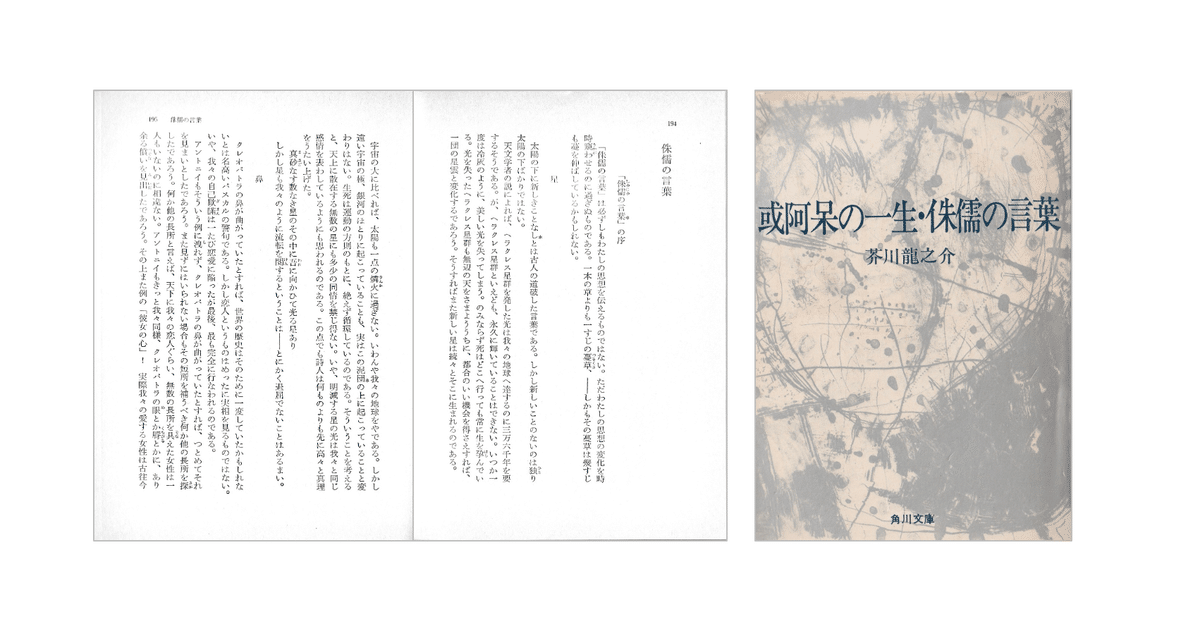
(「吾に向かいて光る星あり」〜「かの星に人の棲むとはまことにや」より)
「芥川の「星の世界も地上の世界も」同じ法則に従うという考えは興味深いと述べたが、『侏儒の言葉』の中においても、芥川の考えが一貫しているわけではない。『火星』と題された文章では、「火星の住民の有無を問ふことは我我の五感に感ずることの出来る住民の有無を問ふことである。しかし生命は必しも我我の五感に感ずることの出来る条件を具へるとは限つてゐない」と、地上の理屈では量れないものは火星にあるかもしれないようなことも述べている。この考えは、わたしにはむしろ面白くなく、火星人に関しては、若山牧水の次の歌のほうが響く。
かの星に人の棲むとはまことにや晴れたる空の寂し暮れゆく 牧水
これは、天文が記者パーシヴァル・ローウェルの火星人説やH・G・ウェルズの『宇宙戦争』が話題を呼んでから約10年後の1910年に火星を詠んだ歌であると考えられる。(・・・)
まず作歌の日付だが、正確な同定は難しいが、これは、「自 明治四十三年一月 至 同四十四年五月」とある歌集『路上』(1911年)の収録歌である。同歌集内で、この歌のほぼ直後に配された次の歌が、時期特定の参考になる。
ややしばしわれの寂しき眸(まみ)に浮き彗星(ほうきぼし)見ゆ青く朝見ゆ 牧水
これは1910年5月に最接近したハレー彗星を詠んだ歌として間違いがない。夕方ではなく朝に見たということなので、近日点(太陽に最も接近する点)通過前の4月下旬から5月上旬と考えられる。『路上』の収録歌は、つくられた淳に編まれているとは限らないが、読みとおすと、そうした入れ替えは最小限のように思える。前後の歌から読みとれる季節からも、「かの星に」は、4月ごろの歌と推定できる。その歌は、注釈として「戸山が原にて」とシルされた五首の五番目であり、ほかの歌も「摘草」「梢あをむ木陰」など、春から初夏を思わせる。
年と月がわかれば火星の位置は特定できる。問題なのは、そのときの火星がそれほど明るくないということだ。火星は地球のすぐ外側の惑星なので、その軌道における位置により明るさが大きく変わる。(・・・)牧水は、いわゆる自然主義なので、自分の目で見ていないものや経験していないことを歌う人でもないだろうとも思う。
ちなみに、天文学では、太陽の中心位置と地平線の角度による「薄明」が定義されている。角度が小さい順に、常用薄明(市民薄明)、航海薄明、天文薄明の三種で、それぞれ、1等星が見える。水平線が確認できる、6等星が見えるということに相当する。よって、この歌の「暮れゆく空」は、常用薄明と航海薄明の間ということになる。
1910年のハレー彗星の回帰は、尾の中に地球がは要ることで毒ガスの危険ありの流言も生んだことで知られるが、これは一面で一種の天文ブームでもあったということで、人びとが星空を見上げる機会は増えていたに違いない。牧水は、1910年の4月のある日、陽の暮れた戸山が原(現新宿区戸山)で、ハレー彗星を見る予行演習もかねて、天文に詳しい誰かを伴って、あれが火星だと赤い星を見たのではないだろうか。そしてそれは、恋に悩む25歳の青年に向かって光る星でもあったのだろう。」

□目 次
・折り紙と数学
高次元化した一筆書き/折り目に関する定理
・幻想の補助線
日時計の天使/奇跡を計算する
・パスタの幾何学
帽子、貝殻、百合の花/二重螺旋と驚異の定理
・解けない問題
デルフォイの神託/三大作図問題
・解けない問題を解く
折り紙による角の三等分/自分自身が定規になる/並列する世界
・単純にして超越
ただし角はない/どこまでも続く
・すこしずれている
幅のある線/正確さと美しさ/菱餅の菱形
・五百年の謎
デューラー・コード/デューラー予想
・吾に向かいて光る星あり
真砂なす数なき星のその中に/かの星に人の棲むとはまことにや
・四百六十六億光年の孤独 あるいは、四十三京五千兆秒物語
20億年の理由/20億光年の測りかた/追記
・管をもって天を窺う
宇宙電波観測所/毒をもって宇宙を解す
・遠くを見たい
巨人の肩/電波のプリズム/より精密に見たい、そして古い幾何学
・折り紙の歴史に関わるあれこれ
『子供の遊戯』と風車/『風流をさなあそひ』と折り紙
・あやとりの話
猫のゆりかご/手順と構造
・紙飛行機の話
飛行機より古い紙飛行機/よく飛ぶイカと飛びにくい鶴
・無限の御幣
堀辰雄と数学者/横光利一と御幣
・字余りの歌と長方形の中の円
字余りの歌/長方形の中の円の作図
・千羽鶴の話
千羽鶴の象徴性/千羽であることと糸で繋ぐこと
あとがき
参考文献
○前川淳(まえかわ・じゅん)
1958年東京都生まれ。折り紙作家、折り紙の数学・科学・歴史等に関する研究者。東京都立大学理学部物理学科卒業後、ソフトウェアエンジニアとして天文観測および解析に関わる仕事のかたわら、折り紙の創作と研究を続ける。著書に、『ビバ!おりがみ』(笠原邦彦編、サンリオ、1983)、『本格折り紙――入門から上級まで』(日貿出版社、2007)、『本格折紙√2』(日貿出版社、2009)、『折る幾何学――約60のちょっと変わった折り紙』(日本評論社、2016)ほか。ブログ「折り紙&かたち散歩」
