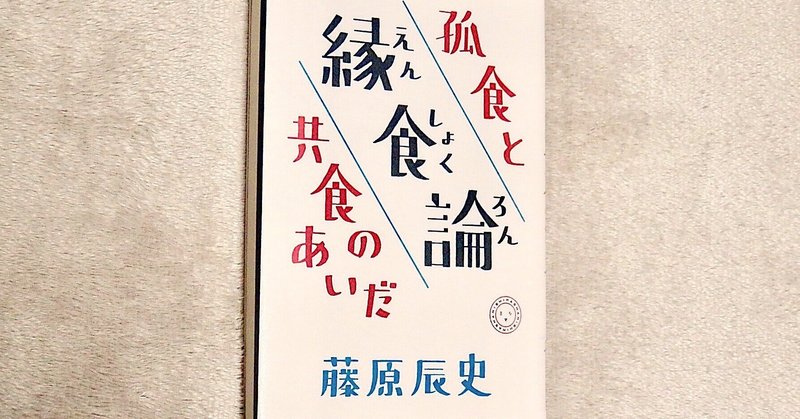
藤原辰史『縁食論/孤食と共食のあいだ』
☆mediopos-2287 2021.2.19
食への問いは
生きているあいだ
終わることはない
食物連鎖のなかで
わたしたち人間は
どうあるのがいいのか
少なくとも
食べられる食物が捨てられているにもかかわらず
飢えている人がいるという現状は
解決していく必要がある
また食の自由は
精神の自由にもつながってくる
食の自由は
飢えないこと
そして
どういうかたちで食べるかに
縛られないことが
必要条件になる
幸い小さい頃から
飢えるという経験だけはなくて済んでいるけれど
じぶんでなんとかやっていけるようになるまでには
いつ食べられなくなるかという不安はいつもあったから
その不安をもたずに生きられる安心感があればどんなにいいか
だれかといっしょに食べる楽しさはあるけれど
ひとりで食べるのが孤独だというのはとくにない
むしろ会食的なものはできるだけ避けたいと思っているし
本書でも言われている家族絶対主義のようなものの縛りは
少なくとも外したほうがいい
またおいしいものを食べられるに越したことはないけれど
グルメ志向なるものが特段あるわけではないから
からだに負担なく安心して食べられるものがあればいい
人間というのは業が深い
食への執着が生み出してしまうものもあるが
食へのあくなき追求があることで
それがある種の文化を生み出してくれることは否定できないけれど
飢えた人がいるという悲しい現実がある
そういうこともひっくるめながら
食への問いはおそらく終わることはないだろう
だれもが食べなくても生きていけるならばいいのだが
■藤原辰史『縁食論/孤食と共食のあいだ』(ミシマ社 2020.11)
「縁食とは、孤食ではない。複数の人間がその場所にいるからである。ただし、共食でもない。食べる場所にいる複数の人間が共同体意識を醸し出す効能が、それほど期待されていないからである。
縁とは、人間と人間の深くて重いつながり、という意味ではなく、単に、めぐりあわせ、という意味である。じつはとてもあっさりした言葉だ。めぐりあわせであるから、明日はもう会えないかもしれない。場合によっては、縁食が縁となって恋人になったり、家族になったりするかもしれないが、いずれにしても、人間の「へり」であり「ふち」でもあるものが、ある場所の同じ時間に停泊しているにすぎない。これは「共存」と表現すると仰々しい。むしろ「併存」のほうがよい。そんなゆるやかな併存の場こそ、出会いも議論も、ますますSNSに回収される現代社会のなかで、今後あると助かる人が多いのではないか。子ども食堂のユニークさも、この縁食にあるのではないか。ちょっと立ち寄れる。誰かがいる。しかし、無理に話さなくてもいい。作り笑顔も無用。停泊しているだけなので、孤食を存分に楽しんで、ちょっと掲示板を眺めて、月でも眺めながら帰ってもいい。そんな食のあり方をきちんと説明してこなかったのは、概念いじりを生業とする研究者の怠慢だと私は思うのである。」
「食べものを商品化するとは、食べものを数値化することであり、食べものが値段と一対一の対応をすることである。けれども、その場合、食べものが作られすぎると値段が急落するので、市場に出回る前に廃棄処分になる。この余剰は、飢えた人びとには届かない。
けれども、もしもその処分される農作物が、商品になる前に、市場とは別のルートで直接、調理場に運ばれ、そこの料理が直接、人びとによってほどこされるのであれば。もしも、その調理場では大量のカレーや豚汁が作られて、たまたま近くに立ち寄った人にも無料で振る舞われるとすれば。いや、そもそもすべての食材が商品化を断念して、直接、無料食堂に運ばれるような国があれば。その国にももちろんレベルの高い優れたレストランがあって、そのレストランは、この無料食堂のあまりものの食材を購入するとすれば、それでもあまったものは、燃やすのではなく、家畜に食べてもらったり、土壌微生物に食べてもらったりできるとすれば。社会の競争からもれた人たちがふらっと立ち寄れる食べる場所が増えるとすれば。いったいそれはどんな社会だろうか。
別にそうなったからと言って、政府公報のポスターのように、人びとの笑顔が突然溢れだしたり、希望に満ち溢れたり、太陽光線が若者を照らしたりはしないだろう。ただし、自殺も、過労死も、食品ロスも、飢餓も、減少することは否定できない。弁当を作れない親の罪悪感も、シングルペアレントの罪悪感も、栄養たっぷりの朝ごはんを作れない親の罪悪感も、本来抱く必要のないはずのこれらの感情もまた、不必要な社会になることも間違いないし、それゆえに女性の社会進出も、女性の閣僚の数も、女性の大学教員の数も、増加することは想像できるだろう。家庭の台所に特定単数の性のみを貼り付けない、という未完のプロジェクトや、食の前の平等という歴史上ほとんど例をみない事業が人間の内面の何を変えるかは、シミュレーションに値することだと思う。
このような食の究極的なあり方を、私は縁食と呼んできた。もちろん、現在の食の形態が縁食の完成型に到達することは不可能に近いだろう。それほどまでに、食は激しく商品化され、オートメーション化され、硬直した所有権観念に侵犯されているからだ。だが、食を商品化することの無理は、多くのシステムを機能不全にしている。この国で賞味期限前に食べものが捨てられることが、その証である。
農業をすることは、植物が合成したブドウ糖のあまりをもらした場所に集まってきた無数の生きものたちとともに、土で生きものの死骸を耕すことである。食べることは、人間が集まった栄養をもらした場所に集まってきた無数の生きものたちとともに、腸で生きものの死骸を耕すことである。性の営みは、交流のなかで高まる感情によってもれでる物質および非物質の交合である。昌益はそれらを「直耕」と表現した。この流れのなかに食の営みを置くことができれば、世界中の農村で問題化している土壌の劣化も、腸内の癌の増加にも、解決の糸口が見えてくる。では、そんな食の営みとは何か。答えはもう明らかだ。
自然の耕した食べものがもれでた場所。そこに集まり、食らう人間たちやほかの生きものとともに、地球社会を耕すことである。」
「パッケージ、賞味期限、広告、ビニールラップ、防腐剤、パーテーション、強制、イニシエーション、家族絶対主義、そういったもので満たされる経済システムが制度疲労を起こすなかで、弱目的性、多機能性、もれ、あまり、にぎわい、言葉屑、食べ心地、無料、微生物、死者、祭りといったもので満たされる縁食の存在を示す本書の試みがどこまで成功したのかはわからない。論じ切れていない部分も多いと思う。ただ、縁食の形態、事例、思想などの検証を通じ、最終的には、家族絶対主義を解きほぐし、「根圏無料食堂」と「腸内無料食堂」、そして「人間無料食堂」をつなぐ種を超えた縁食のラフスケッチまでは描けたと思う。こうして、「オープンである」ということ以外に深い目的のない食堂が、炊き出しのリアカーを引く今村さんのかざぐるまのように、現代社会の凍った空気に色と熱を与えるのならば、いまよりは多少居心地のよい社会が実現したっておかしいことではないと思いたい。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
