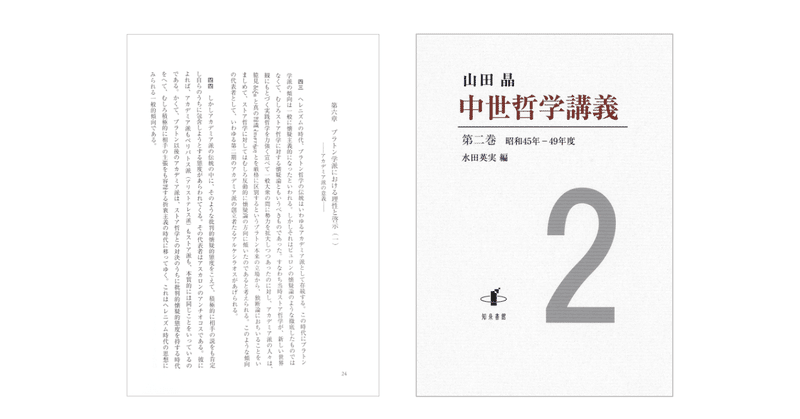
山田晶(水田英実 編)『中世哲学講義 第二巻: 昭和45年―49年度 』
☆mediopos2774 2022.6.22
アウグスティヌスやトマス・アクィナスの研究で知られる
山田晶(1922年 - 2008年)が昭和41年から58年まで
18年に渡って行った「中世哲学」講義が
全五巻に記録されている(現在は第三巻まで刊行)
以前このmedioposでも第一巻をとりあげたことがある
(mediopos-2501 2021.9.21/mediopos-2514 2021.10.4)
第一巻に続いて第三巻が先に刊行されたが
(第三巻についてはまたいずれ)
昭和45-49年度までの5年間の講義がこの第二巻であり
ヘレニズム世界とプラトン学派に見られる
理性と啓示の様相が考察されている
そのなかから
「プラトン学派における理性と啓示」
とくに巫女の神託とミュトス
そしてロゴスについて
「啓示」とは
神のような超越的な存在から
人知を超えた知識が開示されることだが
理性的であることを事としている哲学に
「啓示」は無縁かといえば
決してそうではない
そもそもプラトンから
その哲学は「啓示」に満ちていた
「神話(ミュトス)」も「啓示」のひとつであり
プラトン哲学ではさまざまな神話が引き合いにだされる
(だから新プラトン派は極めて神がかっている)
それにもかかわらずプラトンは
「ポリティア」において理想国からミュトスを追放する
ミュトスを盲信するがゆえに
ロゴスの力をおざなりにする危険性の故であった
知を超えたところからしか得られない
いわゆる神智なくして人は生きられないが
人間は経験的な知に基づいて発見されるロゴスを
得ることをめざさなければならない
ソクラテスもまた「神託」を得るが
その言葉どおりの意味を信じることはできず
「神託の意味するところを理解するために」
「人間吟味の遍歴」を始める
そしてその意味するところが
「知らないことを知っている」のは
ソクラテスのみであることに到る
とはいえソクラテスもまたダイモンような
超越的なものからの声とともにあり
「啓示」的な認識に支えられている
じぶんが何を知り得ているか
ということを突き詰めて考えていくと
たしかにぎりぎりのところまで
ロゴスによる知の重要さは否定できないが
それだけで生きていけるかというと決してそうはいえない
ロゴスを得ようとする知にしても
その得ようとするという衝動は
ある意味「啓示」のようなかたちでしか得られない
もちろんそれは巫女から聞くような
あるいはミュトス的なものから得るような形ではないが
真理を得たい!という衝動そのものは
決して経験知からくるようなものではなさそうだ
どうしてそれはそうなのか
ということを状態としては説明できるが
なぜそれがそうなっているか
という理由はどこからか「啓示」のように訪れている
おそらく重要なのは
そうしたどこからかやってきたものを
そのまま受けとるのではなく
ソクラテスのように
どこまでもロゴスによって吟味しようとすることなのだろう
そうでなければ「啓示」は
自由を失わせる命令になってしまうから
■山田晶(水田英実 編)
『中世哲学講義 第二巻: 昭和45年―49年度 』
(知泉書館 2022/5)
(「第七章 プラトン学派における理性と啓示(二)/プラトンにおけるミュトスの意味」より)
「四六 人間の通常の認識をこえながら、しかも人間にとって無関心でありえず、かえって人間の救済がそれにかかわっているようなことがらが、何らかの仕方で、人間をこえたところから開示されること、それを広い意味で「啓示」と呼ぶことが許されるとするならば、そのような意味での「啓示」は、プラトン哲学のうちに豊かに見出される。プラトンの理性的な思惟はそのような全き受容のうちに動いている。プラトンにおける「啓示」はまず「神話(ミュトス)」という形であらわれる。
四七 プラトンの著作の中には、非常にしばしばミュトスが語られる。プラトンの諸対話篇における議論(ロゴス)は、まずミュトスを語ることから始まり、ミュトスを語ることにおわる。なぜこのようにしばしばミュトスが語られるのであるか。いかなる場合にミュトスが語られるのであるか。このような点に注意しながら彼の対話篇をよむと、われわれは次のことに気がつく。
四八 すなわち、プラトンにおいてミュトスが語られるのは、問題が、人間の通常の認識をこえながらしかも人間にとって無関心でありえず、かえって人間の救済がそれにかかわっているようなことがらにふれてくる場合である。そのようなことがらのうち最大のものはおそらく「死」にまつわる問題であろう。この世に生きているわれわれにとって、この世のことがらがいかに在るかは、この世において可能な経験によって知ることができる。しかしながらこの世の生が終わったのちにわれわれがいかになるかについては、この世に生きている人間のうちの誰一人として、この世における経験にもとづいて答えることができない。なぜなら死はこの世の生の否定に他ならないからである。」
(「第八章 プラトン学派における理性と啓示(三)/プラトンにおけるミュトスの意味(続き)」より)
「五七 「死の問題」とは、「われわれはどこに行くか」という問題である。これに関連して「われわれはどこからきたか」という問題が生じてくる。この世に生を受ける前に、われわれはどこにいたのであろうか。それともこの世に生を受ける以前に、われわれはどこにも存在せず無であったのであろうか。もしもこの世に生きるとは、魂が肉体と結びつくことであり、魂は肉体をはなれて存続するとすれば、同じ理由によって魂はこの世で肉体と結びつく以前にも、すでに魂として存在していたとは考えられないであろうか。もしそうだとすれば、魂はこの世にきたる以前に、どこにどのようなあり方で存在していたのであろうか。これらの問題に対しても、われわれはこの世の生の経験からは何一つ答えることができない。すべては謎である。しかもそれは人間にとって決して無関心ではありえない問題である。
五八 プラトンはこれらの問題にふれるとき、そこに再び「神話」をもちだしている。「メノン」や「シュムポジオン」において、人間がこの世に肉体をもって生まれる以前、純粋な魂であった時の状態が述べられ、この状態からこの世に肉体をとって生まれたことが或る意味で人間の悲劇の始まりとして語られる。人間はこの世の条件の中で、無知と忘却のうちにありながら、なお前世におけるさいわいなる状態を全く忘却するには到らず、真の善、真の知、真の幸福に対する記憶を有しており、いったん失われたものを再びえようとする熱情にかり立てられる。これらのことはすべて「神話」によって語られる。それによって、現実の生における人間のあり方は、「エロス的」として特徴づけられる。」
「六〇 (…)プラトンが神話によって語るのは、人間の生死、世界の起源等のように、人間のこの世における経験をこえたことがらが問題になる場合である。しかもそれはわれわれにとって無関心ではありえず、それどころか、もしわれわれがこの動揺する生の中で動揺することなく生きてゆこうと願うならば、何人も回避することを許されない根本的な問題である。プラトンはそれらの問題に対する解答の手掛かりを「神話」からえている。「神話」はプラトンにとって「啓示」として受けとられているのである。」
(「第九章 プラトン学派における理性と啓示(四)/プラトンにおける神託の意味」より)
「六一 プラトンにおける「啓示」の第二の形態は「神託」である。ギリシア人は神殿において神託をうかがう週間があった。アテナイの市民はアポロをまつったデルフォイの神殿にしばしば趣重大な事件について神にうかがいをたてた。神殿には巫女がいて、神と人との間をとりついだ。すなわち神の意志は神がかりの状態になった巫女の口を通して人々に告げ知らされるのであった。人間の通常の認識をこえながら、しかも人間にとって無関心ではありえず、かえって人間の救済がそれにかかわっているような重大なことがらが、何らかの仕方で、人間をこえたところから開示されること、それを広い意味での「啓示」と呼ぶことが許されるとするならば、「神託」も啓示の一形態であったということができる。」
「六四 ソクラテス、プラトンはこのような神託をきわめて真面目に受けとっている。決して単なる迷信として軽んじてはいない。それどころかこの神託はソクラテスにとって、彼の哲学の出発点となるのである。すなわち、この神託を聞かされたとき彼は非常に深く思い悩んだ。彼は自分が智者であるとは信じない。しかるに神託は彼以上の智者はないという。神がうそをいわれるはずはない。とっすれば、神はこの神託をもって何をいわんとしているのであろうか。この神託の意味するところを理解するために、ソクラテスの人間吟味の遍歴が始まるのである。」
(「第一〇章 プラトン学派における理性と啓示(五)/神託の解釈」より)
「八二 その結果ソクラテスは神託を反駁するどころか、かえってその真実性をあらためて確認せざるをえなくなった。彼は世に賢いと称せられている人々を次々に訪問し話し合った結果。その人たちは「賢くない」ことを発見したのである。彼らは何かを知っているように見えるが問いつめてゆくと何も知らない。だから結局においてはソクラテスと同様に賢くない。ただソクラテスは自分が知らないことを知っているのに彼らは自分が知らないことを知らない。それゆえソクラテスは少なくともこの一点において、すなわち「知らないことを知っているように思いもしない」という点において、彼らよりも賢いといわねばならない。」
(「第一二章 プラトン学派における理性と啓示(七)/ミュトスとロゴス(一)」より)
「一〇五 われわれは以上において、プラトンにおける啓示の一形態としての神託と、それに対する理性のかかわり方を考察した。神託は巫女の口を通じて外からきこえてくる神の声である。そのことばは音声として発せられた側面、即ちφήμη(ペーメー)において受けとられるかぎり、理性にとって不可解である。しかしそのうちに何らかの意味を含んでいると考えられる。その意味の理解にまで到達するために、理性は或る道程をへなければならない。その道程はすなわち思惟の方法であり、その方法にしたがって動きついにφήμη(ペーメー)の含んでいるその真なる内容の完全な把握にまで到達する理性の運動がロゴスである。神託に対して理性はその意味内容を理解してゆくロゴスとしてかかわるのである。」
「一〇七 ところでプラトンにおける啓示の他の一つの形態はミュトスである。そこで次に問題となるのは、ミュトスに対してロゴスはどのようにかかわるか、ということである。神託とミュトスとは、いずれも人間の通常の経験をこえたことがらについて神の側から開示される知識であるという点では共通している。しかしその他の点では大きな相違がみとめられる。神託は或る人、或る事件についてその都度、巫女の口を通して語られることばであり、それは個別的なことがらにかかわっている。それに対してミュトスは、世界の起源とか人間の運命とか死後の世界とかいうような、世界および人間一般にかかわる普遍的なことがらについての啓示であって、単なる或る特定の人や事件にのみかかわるものではない。」
(「第一四章 プラトン学派における理性と啓示(九)/ミュトスとロゴス(三)」より)
「一三四 (…)経験的世界においてわれわれが経験にもとづいて発見するロゴスが、経験を超えた世界にまでこの世におけると全く同じ仕方で妥当するかという問題になるお、われわれは明確な答えを与えることができない。なぜならばわれわれがロゴスを発見したのはあくまでも経験的世界であって、それをこえた世界ではないからだる。それゆえわれわれは、経験的世界において発見したロゴスを、そのまま死後の世界に妥当すると主張することはできない。しかし法則としてのロゴスは、本来「比」を意味し、それは一定の関係を意味する。ゆえに経験的世界の諸事物のうちに見出された、関係ないし法則としてのロゴスが、この世界をこえる世界においてmこの世界に内在するロゴスとの何らかの関係において妥当すると考えることは、少なくともロゴスに反しない。経験をこえた世界に及ぶロゴスは、アナロゴスである。」
(「第一五章 プラトン学派における理性と啓示(一〇)/ミュトスとロゴス(四)」より)
「一三八 プラトンにおいて、ロゴスはミュトスに対しいかなる意味を有するものであったか。逆に、ミュトスはロゴスに対しいかなる意味を有するものであったか。既に見られたように。プラトンはミュトスから多くのものを学んでいる。経験によっては絶対に知ることのできない人生や世界に関する重大事について。彼はロゴスによって語るよりもむしろミュトスをして語らしめている。」
「一五六 哲学とはプラトンにとって、真理への愛であり、真理へのたえざる上昇であった。ロゴスとは、人間の魂を真理に向かって上昇させてゆく魂の能力である。プラトンが「ポリティア」において、理想国からミュトスを追放したのは、まず人々の心に真実に対するロゴスをやしなうためであった。その意味においてロゴスはミュトスにまさるものとされている。しかしそれはミュトスそのものを斥けるためではなかった。かえってミュトスの包蔵する真理が正しく理解されるために、まずロゴスの錬磨が必要であると考えられたのである。しかしミュトスの包蔵する意味が、少なくともこの世においてわれわれの有しているロゴスによって完全に理解されつくすとはプラトンは考えていなかったように思われる。ロゴスは再びミュトスに服するべきであった。ミュトスからロゴスへ、ロゴスあらミュトスへ。これがプラトンの道であった。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
