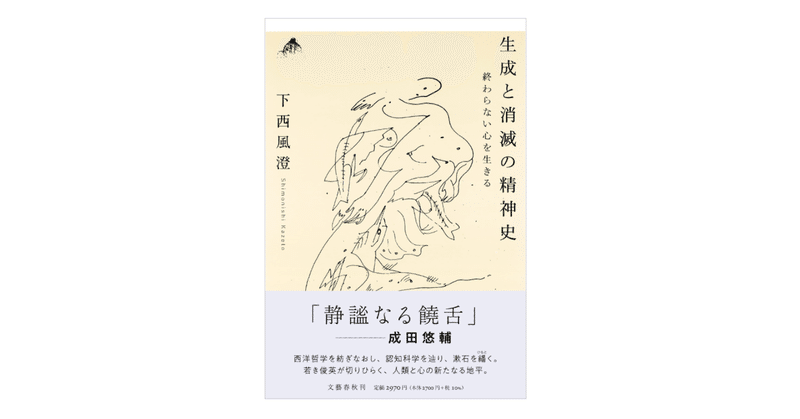
下西 風澄『生成と消滅の精神史/終わらない心を生きる』
☆mediopos2967 2023.1.1.
下西風澄の名を知ったのは
「月刊たくさんのふしぎ」(2018年6月号)の
絵本『10歳のころ、ぼくは考えた』でだった
(このmedioposでもとりあげている)
それ以来アカデミアの世界を離れ独り思索する
その哲学者のことばに魅せられてきた
独り思索するといえば
かつて池田晶子という
独り思索する方の著作に
魅せられて以来のことかもしれない
本書『生成と消滅の精神史』は
人類の3000年にわたる「心」の歴史を描いた
思想書といえるのだろうが
それよりも読み進めながら
一冊の詩集のように感じられた
そこで語られている内容は
神秘学とも深く通じあっている
中国でもかつて孔子の時代でさえ
「心」という漢字は使われていなかったそうだが
それはホメロスの時代の心が
「世界と意識の渾然一体となった在り様」だったように
《拡散》した在り様の「心」だったからだろう
シュタイナーは現在のような人の心は
かつて神々が外から人に働きかけたものであって
やがてそれが人の内的な魂の働きと
なっていったと示唆しているが
そのエポックとなったのが
ソクラテスだったということでもあるのだろう
ソクラテスは神々から離れてはいなかったが
心をその神々から切り離したのだ
本書の表現でいえば
《拡散》していた心を
ソクラテスは「《集中》させて自己の内に収めた」
ということでもある
その後時代を経てデカルト以降
《拡散》から《集中》へ
あるいは《拡散》と《集中》の分離
というように西欧では
かつてのホメロスのような時代の心から離れていったが
やがてメルロ=ポンティが
「心と世界の《拡散》と《集中》の緊張関係が
拮抗しながら運動するプロセスを描」くようになる・・・
本書で注目したいのはこの心の歴史について
日本の心のそれをも射程においていることだ
そして現代に通じるありようとして
夏目漱石の作品をとりあげている
日本の心のありようはかつて
「身体的感覚を中心に自然と融合する」ものだったが
奈良・平安では中国から
明治では西欧から
「意識の支配性やその形而上学」が
「矯正的に導入」されることになり
夏目漱石もまたそこで混乱をきたすようになった・・・
わたしたちはこれからも
《集中》して閉じた「心」を持つと同時に
《拡散》して開かれた「心」をも持ちながら
その往還や相互浸透による「緊張関係」に
どのように向き合っていくのかを
模索していくことになるのだろう
■下西 風澄『生成と消滅の精神史/終わらない心を生きる』
(文藝春秋 2022/12)
(「プロローグ」より)
「本書は、あらゆる局面で引き裂かれてゆく心の問題をその原初から考え直してみようという目的で書かれている。民主主義は自律した個人の意識の連帯が可能にする契約であるよりも集合生物のように蠢き、自然は人間の知性による制御をひっくり返そうとしているようなこの時代に、どのような心の在り方がかつてあったのか、そしていかにしてこのような時代に辿り着いたのか。その変遷をはじまりから考えてみたい。そうでなければ、私たちはこれからの時代の心について、延々と無自覚なまま進んでゆくだろう、」
(「第4章 認知科学の心」〜「メルロ=ポンティ 切り結ぶ心」より)
「私たちは本書で、ソクラテス以前のホメロス時代の意識の在り方から出発した。神話時代の意識は、世界という海のなかから生起する起伏のようなものであり、世界と意識の渾然一体となった在り様こそが意識のモデルならざるモデルであったことを確認してきた。そのような曖昧模糊とした意識を世界からはっきりと区別し、単位体とした独立させ、その機能を確定させていくプロセスこそ本書の読んできた意識の哲学史であった。そして二〇世紀に至り、意識の哲学を標榜する現象学はフッサールからハイデガーに引き継がれていくなかで、徐々にそれを巻き戻すように意識の強い機能を解除したのではないかという道も辿ってきた。このような文脈において、終にメルロ=ポンティに至って、再び意識は最初の地点にまで回帰してしまったのではないかと思われる。しかしメルロ=ポンティは意識を世界を「俯瞰」する機能とも考えなかったし、かといって世界へと「融合」するものとも考えなかったのである。
このメルロ=ポンティが注意を促している、世界をすべて超越論的主観のもとに捉えようとする誤謬と、世界そのものと溶け合ってしまうという誤謬を一人で同時に抱えてしまった哲学者こそパスカルであったと言えるだろう。私たちの意識は世界を包み込むこともできないが、世界に呑み込まれてしまうこともないのである。メルロ=ポンティが媒介する身体に注目し、意識と環境の弁証法を行為に求めたのも、また触れることと触れられることの両義性にこだわったのも、意識と世界の絶えざる「拮抗」、その緊張関係の持続、不断の交渉、行為によるズレの生成にこだわったのも、それこそがメルロ=ポンティが描こうとし意識のモデルの中心であったからだ。別の言い方をすれば、パスカルの、宇宙と意識の釣り合いを取ろうとする欲望と恐怖の両方を同時に抱くことによる狂気はたしかに不可避だ。しかしその欲望は決して完成してしまうことはなく未遂であり続けるし、むしろ未遂であることによって意識は世界へと参加できるのである。
また、パスカルが宇宙との拮抗を「思惟」という人間の尊厳ある能力によって捉えたのに対して。メルロ=ポンティは視覚や触覚など複数の「知覚」や、手や脚など複数の「身体行為」という多次元的で複雑な交雑の培養地から捉え直していた。メルロ=ポンティにおいては、宇宙と心という単純な二項対立では捉えられず、宇宙との結構はより複雑な世界との関係性から捉え直される。メルロ=ポンティが肉における知覚の表現として語った「交叉配列(キアスム)」、あるいは「含み合い」や「相互内属」といった事態は、まさに意識が世界を包み込むと同時に、世界に包まれるというパスカルの苦悩を肯定的な立場から語った思想である。ただしキアスムは、あらゆる存在者が他の存在者を含み合う関係、すなわち私と他者や、私とモノ、モノとモノ、などあらゆる関係性の相互的な帰属を示す概念である。したがってパスカルの「私が宇宙を包み、宇宙が私を包む」というような相互包含の関係性は。メルロ=ポンティにとっては無数の相互包含のバリエーションの一つでしかないのだ。
(・・・)
メルロ=ポンティにとって、あらゆるものがあらゆるものを包み込む世界はひとつの肉である。しかし肉は固定的な関係ではなく、あるものがあるものを含んだと思うそばから、また逆に包み返されるリヴァーシブルな転換である。」
「あらゆるものが、この肉という世界のなかで裂開し、裏返り、転移して無数の小さな宇宙を創り、繋がってゆく。私は世界と同様に肉でありながら、行為によって亀裂を生じ、知覚の生成に立ち会う。それゆえ私の心は世界に消え去ってしまうわけではないし、主体が世界へと溶けてしまうわけでもない。」
「終わらない会話、終わらない揺らめき、終わらない心。独立して完結することのできない滅びた心は、終わらない会話を続けるように、世界と心を共に切り結ぶ。私たちはメルロ=ポンティの心の情景を、このように想像する。」
(「第6章」〜「漱石・バタイユ・江藤淳」より)
「漱石は『明暗』で久しぶりに「山中」を書いた。それは、山中と呼ぶには中途半端な山の中腹にある温泉宿屋である。初期の『倫敦塔』を思わせる、自然もないが人間もいないような、迷宮のごとき宿屋としての桃源郷ではない。そこは、意識が捕まえようとしても消えてしまうヴァーチャルワールドのような世界である。
この中途半端な山中への温泉旅行は、漱石がこれまでずっと桃源郷としてきた「自然」への回帰ではなく、訣別を意味する。
(・・・)
津田にとってこの山中はほとんど夢の景色であった。しかし、津田はこの夢=桃源郷に再び「逃避」しようと訪れたわけではない。注目すべきことに『草枕』、『二百二十日』、『坑夫』などで、男たちが例にもれず全員が「歩いて」山中に入ったのに対し、『明暗』では津田は「汽車」で山へ向かっている。漱石は、身体を徐々に失い、魂を融合させる「歩く」という桃源郷に入るための儀式を省略したのだ。その代わりに漱石は、一見すると不自然なほど長く、何節にもわたって汽車で山に向かう様子を描写する。(・・・)津田は汽車を乗り継いで当地に着いても、歩かずに「馬車」に乗って宿に向かう。そうして最後まで歩く姿は描かれず、唐突に山中の宿へたどり着くのである。
津田は漱石が近代文明の象徴として忌み嫌いさえした汽車に乗って、自己を保ったまま、訣別のために山中に向かった。このような明確な決意を持って山中を描こうと挑む漱石は最初で最後であった。」
「津田は幻想の襲う山中にあって、ちゃんと眼を覚ましていた。もはや夢に飲み込まれることもない。だからこそ山の自然は『草枕』で描かれた紅い椿の乱れ咲く山のように、美しくないどころか人工的で陳腐ですらあった。」
「漱石は相手を眼差しながらも他者の身体と向かい合うなかで一瞬の和解を見た(・・・)。そして本書で見てきたように、西洋の心の思想史と比較しても、日本の心の思想史は明らかに身体的感覚を中心に自然と融合するというモデルが中心にあって、そこに侵入してきた意識の支配性やその形而上学というのは、奈良・平安では中国からの、明治では西欧からの、矯正的に導入されたガジェットのようなものであり、その拘束具に混乱をきたすというのが日本の典型的なパターンであったように思える。意識の支配性を引き受けてコントロールすることもできないし、かといって跳ね返すこともできない。この中途半端な態度は悲劇であると同時に可能性でもある。あるいは問題の突端であると言ってもいいかもしれない。」
「私たちは神でもなく、神の似像でさえなく、陳腐な人間であること、しかし、かといって樹々や飛ぶ鳥のような自然や生命でもないこと。そしてまた、時計じかけの機械でもないこと。それを近代は、漱石は、受け入れることができなかった。」
(「終章 拡散と集中」より)
「本書がこれまで辿ってきた精神の歴史は、心の《拡散》と《集中》の往復の歴史であると言いたい。人間の心はあるときは世界へと拡散し、あるときは自己へと集中した。
《拡散する心》は私の身体に囲われることはなく。樹々や水や夕陽や虫たちと、あるいは空の神々と、心を分散して共有した。心はネットワーク上に分散されており、私一人が意志を決定したり、感情を専有する必要はなかった。私が一人で世界全体について理解する必要もなく、鳥のことは鳥に任せ、海のことは海に任せ、心はそのようなネットワークに触れることでたしかめられた。世界を理解することは、世界に触れ、世界に成り、世界と交流することだった。
他方で《集中する心》は世界に分散された意識の切片をこの一個の身体のなかに凝縮し、すべてを一人の心に束ね上げた。意志はこの私という小さな箱の中で独立し、感情は何者とも分かち難いアイデンティティを構成した。鳥のことも海のことも、私の表象/対象としてはじめて理解可能なものであって、心は複雑なネットワークを切断して世界を俯瞰することでたしかめられた。世界を理解することは、世界を対象化し、記号化し、再配列することだった。
心のモデルは、この拡散と集中をくり返してきた。その往復、あるいは緊張、あるいは相剋の歴史こそ本書が捉えたかった精神の歴史である。あるいはこれを運動として捉えれば、《発展(develop)》と《内包(envelop)》をくり返してきたと言ってもよい。「velop(包み)」を開いて(de)、世界へと伸び拡がってゆく運動と、世界を心の「velop(包み)」の内(en)へと内包してしまう運動。
(・・・)
ホメロスの心は風のように世界へと《拡散》していたし、ソクラテスはこれを《集中》させて自己の内に収めた。デカルトはこの《集中》する心の中に「我」という原点と「考える」という機能を与え、パスカルは《拡散(develop)》と《集中(envelop)》を同時に実現しようとして引き裂かれた。カントは世界と心を分離し、《拡散》と《集中》を分割統治する方法を考案した。フッサールは《集中》の束を一つずつ手に取りながら緩やかにほどき、ハイデガーは《拡散》する心の可能性を持ちながら、その裏側で極度に《集中》する心を論理化してしまった。
初期の認知科学は《集中》する心を記号と推論によって強化させたが、「情報」という世界との交通路を開き、媒介することで容易に心を世界へと《拡散》する可能性も加速させた。自然現象はコンピュータによってシミュレーション可能な存在となり、同時に意識もコンピュータ上でシミュレーション可能な現象に思われた。意識と世界を、情報という同じプロトコルで処理することが可能なのではないかという期待は、歴史的にも革新的なものであった。すなわち情報技術は《拡散/集中》の方向性そのものを無化するような《媒介》という新たな心の可能性を開いた。一方で私たちは情報を通じて世界へと《拡散》することも容易であり、他方で世界を情報を通じて回収して《集中》することも容易になった。情報技術を媒介にした私たちの心は、むしろ世界へと拡散しているのかあるいは集中しているのか、そもそもが区別不可能な媒介的な接続状態を創り出した。
現代の情報技術が無際限に世界へのアクセスを切り開いたことで、意識と世界の交流はなだらかで終わらない手続きであることがリアルなものとなった。その意味で、はじめから出発点も終着点もないメルロ=ポンティの思想の重要性は際立ってくるように思える。
(・・・)
メルロ=ポンティは、心と世界の《拡散》と《集中》の緊張関係が拮抗しながら運動するプロセスを描いた。この終わりなき運動がメルロ=ポンティにとっての哲学の出発点であり、終着点はなかった。ヴァレラもそれを強く自覚していたからこそ生命という次元にまで溯ったし、逆に夏目漱石は、この意識と世界の分断と拮抗を生き抜くにはあまりに繊細で過敏すぎた。世界に心を《拡散》すれば私は消えてしまうし、世界を心に《集中》させようとすれば、すべてを渦のように絡め取ってしまおうとするほど激烈であった。
汲み尽くしえない世界、それは豊かさであると同時に恐怖でもある。人類の歴史は、この豊かさと恐怖のなかで心を構築してきた。私たちの心は、この汲み尽くしえない世界に対してどのように生きるのかということに賭けられている。この恐怖と豊かさを同時に与える世界に描く「心」という人間の自画像。決して完成することのない自画像にどう向き合うのか。それだけが重要な問いであると本書は考えている。」
(「エピローグ————あとがきにかえて」より)
「僕は、誰かのために何かを書こうとしたことはない。深く自己の問いに向き合うことでしか書けないものがあると、そう信じてきた。しかし同時に、僕は時代の風を感じ、歴史に潜ってこの本を書いた。そうして書き終わった今、誰かに何かが、ささやかな手紙のように届くなら、それはうれしいことなのかもしれないと思うようになった。それはこの本を手にとってくれた人ばかりではなく、過去の自分や未来の自分、あるいは過去の哲学者や未来の哲学者たちに、あるいは何かを考えることを手放さないと思う誰かに。書くことは、望むと望まざるとに関わらず、誰かに何かを届ける行為なのだろう。僕が、過去の哲学者たち、文学者たち、芸術家たち、数多くの死者たちにどれほど支えられて生きてきたか、言葉にすることさえできない。
だから僕は、僕の思索のなかに多くの人々のメッセージが込められていることを知っている。むしろ僕の思索は、人類の思索の海に溺れる、ひとつの小さな波紋にすぎない。けれどその波紋は、過去と現在と未来を区別することなく揺れている。死者も生者も、思索の海で響き合っている。」
「僕は大学院の博士課程で研究をしていた。図書館で論文を読み耽ったり、学会で世界の研修者らと議論したりする日々は、刺激的でもあった。だけど僕は、アカデミアの研究者への道を選ばずに、大学を離れ、独りで思索する道を選ぶことにした。ただ一人の、知を愛するという生。フィロソフィアを生きる人間であることが、僕は好きだったのだろうと思う。どこの組織にも所属せずに、独り野ざらしで息ながら、こうした本が書けたのは、メールマガジンを読んで、小さなパトロンとして支えて頂いた人々のおかげだった。この方々のお名前は、僕のウェブサイトに記載させて頂いている。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
