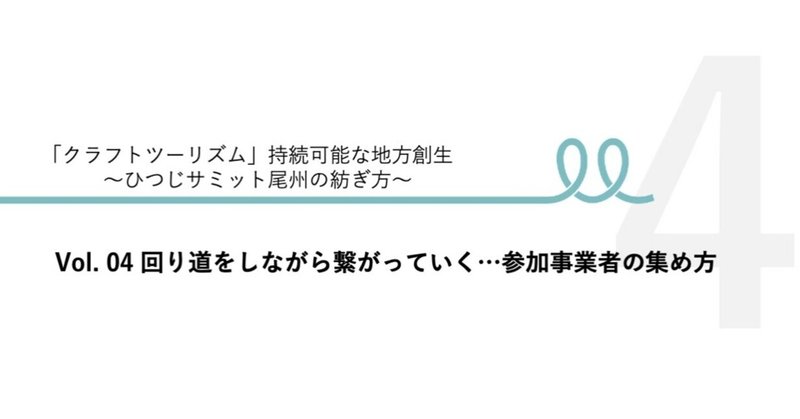
Vol.04 回り道をしながら繋がっていく…参加事業者の集め方〜「クラフトツーリズム」持続可能な地方創生
【はじめのご挨拶】
*前回から読んで下さっている方は飛ばしてね!
ひつじサミット尾州の発起人/実行委員会代表の岩田真吾です🐑
2021年10月30日(土)〜31日(日)開催予定の「ひつじサミット尾州」というクラフトツーリズム・イベントのPRも兼ねて、
「クラフトツーリズム」持続可能な地方創生
〜ひつじサミット尾州の紡ぎ方〜
と題してnoteを10回連載します!
【連載目次】
01. クラフトツーリズムって何?ひつじサミット尾州のケース
02. 始まりはいつも誰かに想いを伝えるところから
03. 類は友を呼ぶ…実行委員会の作り方
04. 回り道をしながら繋がっていく…参加事業者の集め方◀︎今回の記事
05. 夢を語ると助けてくれる人が現れる…協賛&協力者の集め方
06. 時流のどこに位置づけるか…メディアを仲間化する方法
07. 工場を「人」に変える…インフルエンサーの活かし方
08. わかりやすさと奥深さの両立…デザインのチカラ
09. 堅い後援を入れることでしっかりと…コロナ対策
10. やって終わりにしない為に…レガシーの残し方
遊びに来てくれるゲストの皆さんにはイベントをより深く楽しめるように、他産地でクラフトツーリズムをやりたい/やっている方には事業の参考になるように、未来の自分たちにとっては甘酸っぱい思い出(笑)として…頑張って書こうと思いますので、背中を押す感じでぜひハートマークお願いします!
想いを紙に落とし込む
発起人を募るところまでは、企画書はおろかメモ書きも何もなく、口頭で構想を語るだけでした。
ただ、そこから輪を広げていくには、目的や内容が具体的にイメージできるような企画書が必要になります。
構成を決め、詳細ページを作り込み…なんとか完成させた初版をプリントアウトして、参加事業者集めを始めました。

<企画書の構成>
説明はすればするほど上手になりますし、対話を通して企画自体もパワーアップしていきます。
その後、何度もアップデートを重ね、最後は19版となりました。いやー、頑張ったね、自分(笑)この資料は結構いろんな人に褒められたので、良いイベントは良い企画書から…と言えるかもしれません。
*実物の企画書が見たい!という方は
https://instagram.com/hitsujisummitbishu?utm_medium=copy_link
をフォローの上、ダイレクトメッセージでお問い合わせください。
一筋縄ではいかないもの…でも、諦めなければ最後は繋がりあえる
後述しますが、市の100周年記念事業に選ばれたり、商工会議所の後援をもらったり、地元新聞の一面に載せていただいたりしたので、「これで向こうからじゃんじゃん応募が来るに違いない」と思っていたんですが、実際にはそういう会社はあまり多くはありませんでした(汗)
待っていてもしょうがないので、地元大手のある企業さんにお声がけすると「新聞見たよ。いつ声掛けてくれるか待ってたんだよ〜。」とすぐに快諾してくれたり…地方のオジサマはツンデレなのかもしれません(笑)
また、別の事業者さんに説明に行くと「僕らには僕らのやり方があるので」と微妙な反応。地元を盛り上げたいって気持ちは一緒なはずなのに…と熱っぽく語り、通うこと計3回。最後には「協力するよ」と言ってくれました。良かったぁ〜。
もちろん、コロナで工場見学を一律禁止している会社さんや、キャパいっぱいで余力がないという会社さんなどなど、参加を見合わせた会社さんもあります。ただ、そういう方々とも将来繋がる可能性はあると思って、丁寧なコミュニケーションを心掛けました。(とか言って配慮不足のところがあったらごめんなさい💦)
こうやって、回り道をしながらも、参加事業者の縁が繋がっていきました。
相互工場見学や工場見学マニュアルなどで切磋琢磨
最終的に集まった参加事業者は50社超、発起人11人の約5倍まで広がりました。(参加事業者として登録してくれた数は53社、同一場所での開催等もあるので会場としては37箇所の予定です。)
もともと工場見学を受け入れている企業もあれば、今回が初体験の事業者もいます。ひつじサミット尾州では、個々の参加事業者が開催する工場見学やワークショップはあくまでそれぞれの企業が考えて作り込むのが前提なのですが、クオリティアップの為にも丸投げで放っておくわけにはいきません。
そこで、事前に相互工場見学を行ったり、工場見学の時に気をつけるポイントをまとめたマニュアルを共有したり、ブランドコンサルタントさんへの無料相談なども行いました。
特に、コロナでなかなか難しい状況ではありましたが、相互工場見学は具体的なイメージが持てるのと同時に、熱量も共有できて良い準備になったと思います。

<相互工場見学>
まだ開催してないけれど、反省点はたくさんある!
まだ10月開催をしていない現段階でも、反省点はたくさんあります!
まず連絡網をどのように作成・運用していくかは課題が残りました。最初はLINEグループで済むかな…と思ったのですが、そもそもLINEやっていない/仕事では使っていないという方もある程度いたので、メールとの二重運用となってしまい、実行委員会の連絡担当者の工数が倍増。
またLINEはどんどん流れていってしまう、単にアップしただけの写真だと保存期限が過ぎて見れなくなる、役割ごとの分科会グループがどんどん増えていってしまう、など運用に工夫が必要な点がいくつかありました。(数えてみたら、ひつじサミットだけで16グループもありました。)
Slackの導入も検討してベンチャーの人にレクチャーをお願いしたりもしたのですが、導入工数の多さにビビって諦めたり…この辺りはよりよいツールや工夫があれば、ぜひ他産地のクラフトツーリズム担当者と情報交換したいところです!

それと、開催曜日をどうするのが参加事業者にとってベストだったのか…も答えが出ていない課題です。
集客を考えると土日がベストだろうというのが実行委員会での結論でしたが、土日休みの工場が多いのも事実。
振替休日を活用したとしても本来休みの日に社員さんに出てきてもらうのは簡単ではありませんし、見学の為だけにエネルギーをたくさん使う機械を稼働させるのもエコではありません。
今回も「なんとか1日だけは稼働させる」という工場も多く、土曜日と日曜日でイベント数が偏ってしまいました。この辺り、最適解は試行錯誤していかなければならないだろうなと思います。
===
次回の「Vol.05 夢を語ると助けてくれる人が現れる…協賛&協力者の集め方」では、イベント開催の大切な一要素であるお金と、イベントの魅力を増すお金以外の協力をどのように募っていったのかについてお話します!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
