
「商品へのこだわりを発信しつづけ顧客に愛される老舗」中川政七商店とIKEUCHI ORGANICのSNSのつづけ方
さまざまな分野で活躍しているゲストをお招きし、noteやSNSとの付き合い方をひも解いていくトークイベント企画「ビジネスに役立つnoteやSNSのつづけ方」。
第2回目のゲストは、1716年創業の中川政七商店で取締役CDO(取材当時)を務められている緒方 恵さんと、創業68年目をむかえた今治タオルメーカーのIKEUCHI ORGANICで営業部長をされている牟田口武志さん。おふたりとも歴史ある企業で、ECサイトや実店舗の運営にSNSをフル活用しています。SNSでの効果的な発信方法や発信をつづけるためのコツについて、noteプロデューサーの徳力がお話をおうかがいしました。
▼イベントのアーカイブ動画はこちら
登壇者紹介

緒方 恵さん
中川政七商店(なかがわまさしちしょうてん) 取締役CDO(取材当時)
株式会社東急ハンズにてバイヤー、ビジュアルマーチャンダイザーを経てWEBチームに異動。ECサイト運用からはじまり以後、東急ハンズのWEB/デジタル施策すべての開発及び運用を統括しながらデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進。2016年、株式会社中川政七商店にWEB/デジタル領域すべてを統括する執行役員CDOとして入社。2018年、取締役就任。現職。
緒方 恵(おがた けい)|中川政七商店 取締役|note
大日本市 by 中川政七商店
中川政七商店公式サイト|通販サイト

牟田口武志さん IKEUCHI ORGANIC 営業部長
映画製作会社を経てCCC、AmazonでマーケターやWebプロデューサーとして活躍。2015年IKEUCHI ORGANICに入社。広報、法人営業、実店舗や直販(ECサイト・店舗)などすべての販売戦略づくりをになう。タオルソムリエ資格をもつ。
牟田口武志|note
IKEUCHI ORGANIC|note
今治タオルのイケウチオーガニック|IKEUCHI ORGANIC 株式会社
複数プラットフォームの特性を活かしつつ、均一に活用
——顧客との接点としてさまざまなSNSを活用されていると思いますが、特に重視しているものはありますか。
牟田口さん SNSに限らずですが、Twitter、 Instagram、LINE、Facebook、noteにYouTubeも使っていて、どのプラットフォームもここ1、2年は特に注力しています。加えて、10年以上配信しつづけているメールマガジンには昔からのお客様も多く、いまも非常に力を入れていますね。メルマガ先行でお知らせをしたり、新商品のモニターを募ったりと、SNSは流れが早くてついていけない方でも、週に1度のメルマガを読むことで、IKEUCHI ORGANICの考えや情報がある程度わかるようにしているんです。
緒方さん LINEとメルマガをセットにして使っていて、これが最重要です。弊社には「接心好感」という造語がありまして。「お客さまの心に接し、好感を得る」という意味で、これは社内のコミュニケーション基準において最も重要視している考え方です。LINEとメルマガはこの「接心好感」を象徴するツールだと思っています。

たとえば、実店舗でよい接客を受けて中川政七商店に好感を抱いてくださったお客さまが、「引きつづきあなたの情報がほしいわ」とLINE登録をしてくださる。そして私たちからLINEを通じてお手紙をお届けする。こちらから無許可に送りつける・画面に表示されるのではなく、お客様が希望してから初めて届けられるという流れは「接心好感」の精神からしても望ましい在り方だと思います。
弊社にはブランドのアカウントとは別に、全店舗の個別LINEアカウントもあります。お客さまの多くが必要としているのは、自分がいつも行く店舗の具体的な情報であることが多いからです。それに、お客さまはその店の店員が気に入って、通っている場合もあります。個店のLINEアカウントをご登録いただくことで、いつもの店から、いつもの店員から「お手紙がくる」と感じていただき、ブランド全体と個店の好感度をそれぞれ高めていければと考えています。
——Twitterや Instagramなどのプラットフォームはどのように使っていますか。
牟田口さん Twitterでは毎日、商品情報やイベントの報告など幅広い情報を発信しています。弊社の商品について投稿してくださった方には「いいね」するなど、お客さまとのコミュニケーションがしやすいプラットフォームだと思いますね。公式のアカウントはもちろんですが、私はもちろん、代表の池内や店頭スタッフ、職人さんもお客様の投稿は必ず見ていてコミュニケーションをとることも多いです。
Instagramは、雑誌のような感覚でつくっています。タオルだけでなく、ひとを登場させたり、季節を感じさせる花の写真をのせたり。1枚の写真でバズらせるのではなく、9枚12枚とタイルのように並べた写真全体で、ブランドの雰囲気を伝えるようにしています。

緒方さん TwitterとFacebookは、販促として主にプロダクトについて投稿します。弊社では、お客さまのブランド理解をプロダクト、ライフスタイル、ライフスタンスの3つの軸でとらえていまして。それぞれの軸に沿った情報をバランスよくお届けしたいと考えています。これをSNSでの投稿に置き換えると、プロダクト=商品情報、ライフスタイル=その商品がある暮らしの提案や職人の思いなどの商品背景、ライフスタンス=企業哲学となります。プラットフォームの特性をふまえて、Instagramは主にライフスタイル、ライフスタンス軸で発信しています。
牟田口さん SNSは併用するのが大事ですよね。noteで公開したことをTwitterで拡散してメルマガでも紹介するように、1つの公開で終わらせないということをつねに意識しています。
緒方さん そうですね。SNS上の情報を受け取ることもお客さま体験の一つですから。サービスの質をすべてのプラットフォームで均一化することが重要だと思います。
牟田口さん どれか一つでも抜け落ちたら、お客さんをがっかりさせてしまうことになるんですよね。ただ、同じ情報をそのまま流すのではなく、プラットフォームに合う形で編集しています。例えばnoteで「イケウチとオーガニックの20年間」という2万字の記事をTwitterで毎日紹介していましたが、140字以内でTwitterの文脈に合うよう調整して投稿していました。
ブランドのたましいを伝える文章に必要なのは「うまさ」よりも「熱さ」
——おふたりとも、コンテンツの制作は社内の人員だけで全部行っているんですか?
牟田口さん 入社してすぐに行った社員たちへのインタビューは、写真以外すべて内製しました。ものづくりをしている職人や社員たちの思いを伝えるには、伝える側の熱量も必要だからです。

しかし、2年前にはじめたnoteは当初から外部のスタッフに関わっていただくようにしました。外部の視点で、よりお客さんに共感いただける言葉を使って表現することも大切だと考えたからです。ただその場合も、方針はもちろん私たちが決めますし、ライターもIKEUCHI ORGANICのファンである方にお願いをしていて。商品に対する社員の熱い思いをそのまま伝えられるようにしていますね。
緒方さん うちの場合は、制作体制をコンテンツで分けています。公式サイトのコアコンテンツである「はたらくをはなそう」や職人やデザイナーのマインドを伝える読み物、社員が自社商品への愛を伝える「わたしの好きなもの」は、写真撮影もふくめて完全に内製しています。
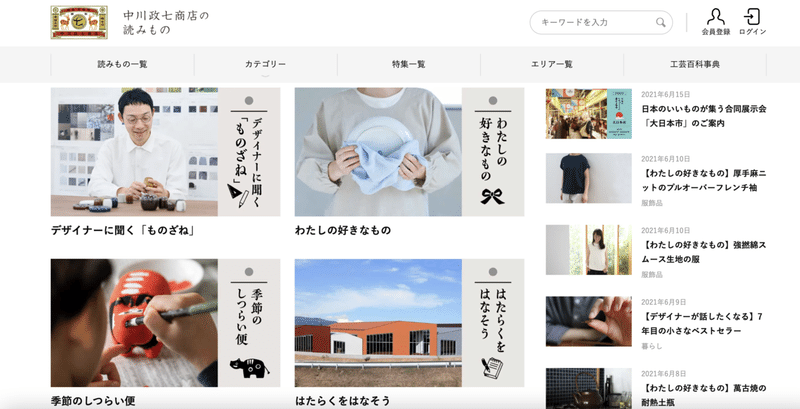
なぜ完全内製するかというと、自分たちの職人に対する熱いリスペクトをそのままお客さまに伝えて、分かち合いたいと思うからなんです。職人はみな試作に試作を重ね、血と汗を流して商品をつくっています。私たちはその姿を見ている。彼らがつくった商品が悪いものであるはずがないという確信があるんです。私たちが抱く職人や商品への愛情と熱量がこもったコンテンツが充実してはじめて、Webのブランディングが成立すると思っています。
一方、公式サイトで展開している「工芸百科事典」というコンテンツは外部のライターにお願いしています。古今東西の工芸について網羅的に紹介していて記事の量も多いので。このように外部の方にお願いする場合は、牟田口さんと同じで自社のビジョンに共感してくださる方とパートナーシップを結んで制作することを大切にしていますね。
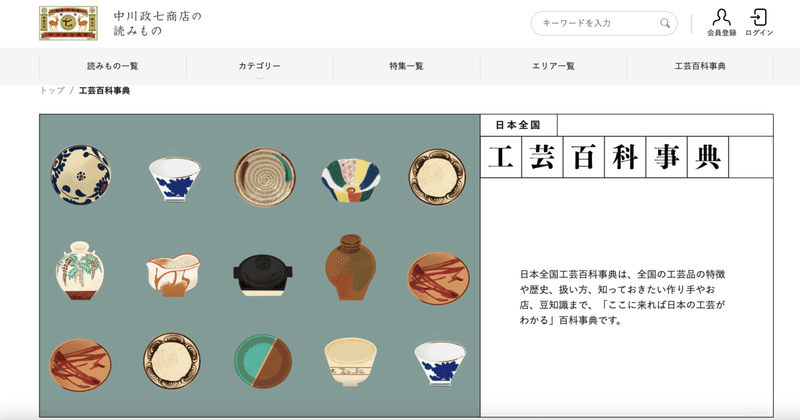
SNSではよき「発信者」ではなく「受け手」になること
——企業のSNS利用がつづかない理由に「SNSのなかのひと」がしんどくなってしまったとか、同じような内容の投稿ばかりになってしまうという声をよくききますが。
牟田口さん よい発信をしようと考えるからしんどくなるのかもしれませんね。情報の発信者ではなく、よい受け手になろうと考えることが第1だと思います。SNSは何よりお客さまとのコミュニケーションの場なので。クチコミに対してお礼を言い、会話を積み重ねていくというのは、SNSに限らず接客業のきほんですよね。
——ほかにも「売上的な成果につながっているかわかりづらい」といってSNSでの発信に二の足を踏んだり、つづけるのがむずかしくなったりする企業もありますね。
緒方さん お客さまとコミュニケーションして好感が積み上がることで共感が生まれ、やがて信頼されるようになると思っていまして。当社の哲学として、この関係性の構築がなされた結果が、売上につながっていくことが大事だと考えています。
牟田口さん 私も、SNSやオウンドメディアで正しい振る舞いをして、企業が愛されれれば売上は結果としてついてくると思っています。必要なのは、長期的な視点で効果をみることですね。
それと、SNSの効果は売上だけでは測れないところもあります。SNSの投稿きっかけで取材いただいたり、法人の問い合わせや採用に結びついたりすることもあるからです。いつどこでどんな効果が生まれるかわかりません。だから、ふだんから社内のいろんな役割の人を巻き込んで、多くの社員に自分ごととしてとらえてもらうことが、SNS運用においては大事ですね。
——SNSは特別なものではなく、人間同士の多様なコミュニケーションのなかに存在しているものだということにあらためて気づかされました。リアルな世界同様に相手に対して誠実にコミュニケーションすることが大切ですね。本日はありがとうございました!
***
次回の「ビジネスに役立つnoteやSNSのつづけ方」は8月12日(木)19時からヤプリの島袋さんとロート製薬の柴田さんにお話しをお聞きします。
ぜひご参加ください!
interviewed by 徳力基彦 text by いとうめぐみ
*この連載は、日経クロストレンドにも寄稿しています。
