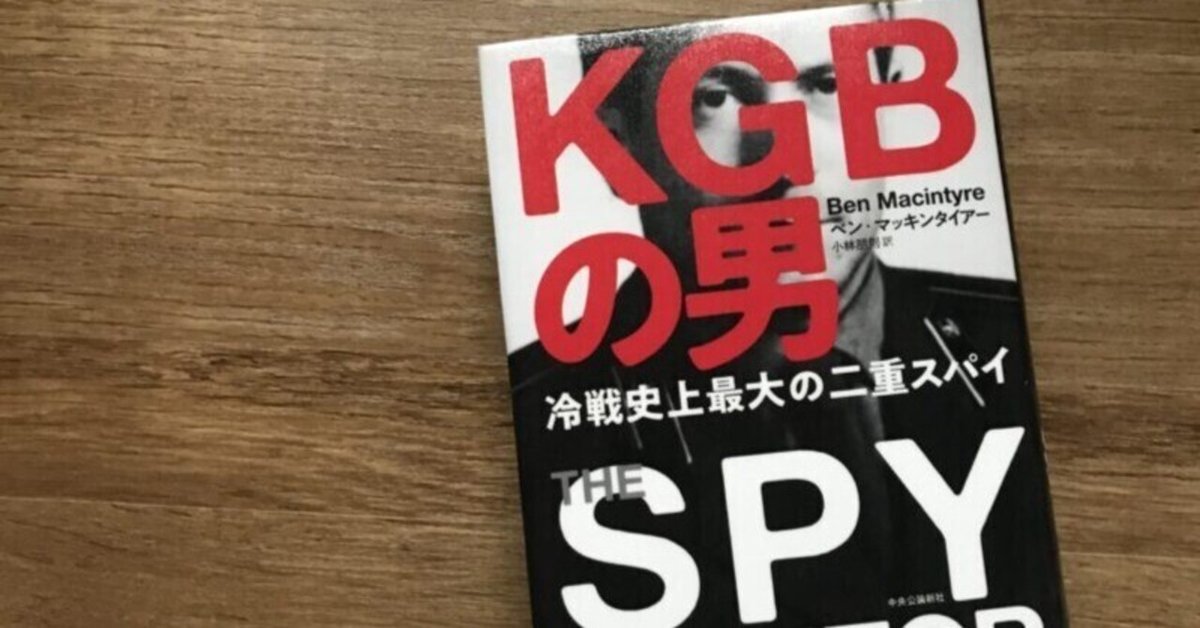
『KGBの男』 ベン・マッキンタイアー 冷戦史上最大の二重スパイ スパイも人なり
1985年7月のとある晩、ひとりの中年男性が、モスクワ中心部の通りで、英国のスーパー「セーフウェイ」のレジ袋を持って立っていた。このレジ袋は信号であり、彼を密かにソ連から出国させる、驚くべき脱出計画スタートの合図だった。
『KGBの男』の内容紹介
『KGBの男』は、冷戦時代にソ連から西側に寝返った実在の諜報員オレーク・ゴルジエフスキーを描いたノンフィクションです。
KGB(ソ連国家保安委員会)の一家に育ち自らも職員となったゴルジエフスキーは、外交官としてデンマークに赴任。そこで西側社会に触れ、祖国ソ連の政治姿勢に疑問を持つようになります。イギリスの情報機関MI6やデンマークの公安警察PETと接触し、やがて二重スパイとしての活動するゴルジエフスキー。が、あるところからKGB内に二重スパイがいるという情報がー。
容疑者の一人としてソ連に引き戻されたゴルジエフスキーに待っていたのは、KGBによる厳しい尋問と監視。このままでは処刑か、少なくとも二度と国外に出ることはできない状況に。
が、こうした事態を予測していたゴルジエフスキーとMI6(の一部) は、事前に計画していたソ連からの脱出を実行するー。
スパイも人なり
スパイといえば映画『007』や『ミッション:インポッシブル』『キングスマン』のようにシュッとしてスタイリッシュ。これら西側のスパイに対し、東側のスパイは冷酷無比でやたら強いといった(あくまでの個人の)イメージです。
ところがこの本に描かれている実在のスパイはそうではありません。盗聴や尾行といった映画でもおなじみのスパイ活動を黙々とこなし、隠れ家で短い打ち合わせを繰り返す地味なもの。ゴルジエフスキーの国外脱出に映画のような派手な銃撃戦なんてありません。
なのにスリル満点。最後の最後までハラハラさせられます。ノンフィクションなので、はじめから「無事に脱出できる」とわかって読んでいるのに、ですよ。
そのハラハラを引き起こしているのは、スパイたちの人間臭さです。ゴルジエフスキーほか、登場するスパイや関係者たちはみな人間味あふれる普通の人間なのです。
ゴルジエフスキー自身に大きな影響を与えたとされる1956年のハンガリー革命に対するソ連の武力鎮圧、さらには1961年のベルリンの壁の建設。ゴルジエフスキーがKGBで活動した背景には「冷戦」という社会情勢があります。
その中で、ゴルジエフスキーはなぜ2重スパイになったのか。一方、崩壊に至るKGBはどのように腐敗していったのか。MI6、CIAはー。
映画とは一味違う人間臭いスパイたちの実態と、歴史を動かした驚きの脱出計画を、ぜひ。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
