
営業マンは数字を語るな。それじゃあAIに勝てない
数字で評価はやめろ。AIに勝てなくなる
図らずもシリーズになってしまった(笑)今回のTVCMマーケティングですが、ポイントは「評価」ということだと思います。CMの目的に対しての貢献度という評価です。前回はテーマがアドレッサブル、つまりターゲットにどれだけフィットしているかという尺度でCMの効果を測ったわけです。
評価は数値化がつきものです。例えば、あるCMの効果測定、つまり評価を試みるとしましょう。
一番簡単なのは、クライアントが望む結果がどのくらい得られたか、ということでしょう。
CMの要素がどれだけ結果に貢献しているか、を要素別に計算、トータルで数値化するのが一般的です。
例えば、
○出演者の好感度
○長さ
○セリフ
○コンセプト
○変化適合性(例:NHKで「腸内細菌」やったので、ビフィズス菌ヨーグルトバカ売れ)
○ターゲットとの適合性
○時間帯
○同じ時間帯で流れる他のCMとのバランス
などなど色々あると思います。
これをえいやっと、これまでの実績や経験で貢献度を数値化し、数式化すれば、そのCMの効果性測定はできないことはないでしょう。
消費者は変化してやまないという真理
しかしね、これは一見いいように見えて、ダメだ。なぜならばこの考えは、消費者つまりCMを見る視聴者は不変、ということが前提だからです。
これは過去にあるCMが、ある条件で放映されたときの効果をもとにしているので、今の視聴者が同じ反応をするとは限りません。
そもそも、この貢献度云々だって、常に視聴者は一定ではないのです。気分だったり、何かの大きな事件があったらCMに集中ができなかったり、そもそも消費者は、The Wall Street Journalの言葉を借りれば、elusive(気まぐれ、とらえどころがない)のです。
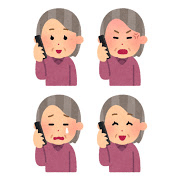
実はこの消費者はelusiveであるということが、マーケティングの本質で、常に我々はそれを忘れがちなのです。
マイルドヤンキーはもう存在しない?
やれF2(女性20代)はこういうプロフィールだから、とか、マイルドヤンキー(下図)とか、特定層を定義したがります。しかし、人間は変わるものです。特に消費者という呼び名に変わると、その気まぐれがひどくなります。
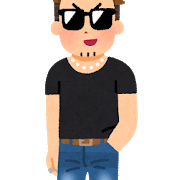
だから数値化など意味がないのです。
それがわかっているんじゃないかな、今回コンソーシアムという別組織を用意して、TVCMをテレビ放送業者に売り込もうと必死な8社のマーケターたちは。
彼らのプリシジョン・マーケティングは要するにアドレッサブル、ターゲットとCMの合致を金科玉条とするものですが、それはあくまで彼らの立ち位置を外部にわかりやすくしたものに過ぎません。
いずれにせよ、その企業の目的にあったCMコンテンツは、プログラミングなどに落とし込むことができないのです。
それが証拠に、企業にCMを売り込むべきコンソーシアムでは、最適CMの方程式やプログラミングを創るわけじゃないのです。
データで語るな、話し合え
月に一度話し合いをするだけなのです。最適CMとは、常にクライアントと営業マンたるマーケターが話し合って、落とし所を決めるものなのです。
マーケターと企業のTVCM担当者との話し合いはこんな感じ
架空のやりとりを実況してみます(笑)
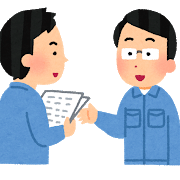
企業担当者:弊社は新製品の口紅を売ろうと思っており、ターゲットは30代女性ですが、なにかアドバイスをいただけたら

マーケター:火曜サスペンスドラマが比較的30代女性が多いので、アドレッサブルではあるのですが、CMは正直ザッピングされる傾向にあります。だから、冒頭に30代に人気のあの女優を起用するしかないと思うんですよ
企業担当者:女優Aは社長が嫌っているんですよね、新製品は無添加の口紅で、ナチュラル、無垢のイメージを出したいので、素人でいくのはどうでしょう
マーケター:最初の絵でオーディエンス(視聴者)をつかめないと難しいんで、視聴者を費引っ張る絵を弊社クリエイティブに厳命しましょう
企業担当者:予算は1000万円ですが、バックアップ版も行けますか
マーケター:リザーバー、バックアップは出演者の不祥事、離婚その他のイメージダウンの際の応急処置として、環境保護をテーマに動物主演(笑)で作らせていただきます。弱いですが。(苦笑)どの企業様もバックアップなしではご契約いただけないご時世ですので、1000万コミコミでさせていただきます。
企業担当者:火曜サスペンスのCM枠の組み合わせは弊社に有利にできますか
マーケター:私共の経験則ですと、化粧品の場合、洋服と食品の間に挟むと最大の効果が得られることがわかっています。ユニクロ様と丸大ハム様にCM作成のオファーをこの枠で頂いてますので、その間に御社のを入れられたらと思います。しかし、あくまでそれはこの10年の傾向ですので、いまの30代女性が同じ反応をしてくれるか・・・
企業担当者:わかりますよ、1年経つとターゲットのプロフィール、って全然変わっちゃいますものね
マーケター:実はまったくそのとおりなんですよ、こうやってコンテンツを、時間帯をどうするか、アドレッサブルどうのこうのなんてお話をしていても、視聴者の傾向が変わってしまうので、意味がないと言えば、ぶっちゃけそうなんですよね。むしろ、とにかくネットを見ない層に向けて、御社及び御社製品のイメージアップのため、時間帯無視の安い枠で、月100回というパッケージをおすすめしているんですよ
企業担当者:オリンピックじゃないけれど、参加することに意義があり、ってことですね。身もふたもない話だけれど、説得されちゃうなあ。
一同(笑)
こんな感じのやりとりが想像されます(笑)
AI(人工知能)からHI(話しアイ)の時代へ
要するに、マーケターは数字を出して説得するよりも、企業担当者と細かいニーズごとに話をして、説明して納得してもらうというのがいいんじゃないでしょうか。
このパターンだと確実に御社の目的達成率は90%ですなどとできないこともありません。
過去のデータからAIに計算してもらえばいい、DXでプログラミングしてもらえばいい。
でも、お客さんはelusiveで環境変化も激烈。今回のオリンピックみたいに2週間で世論が激変することだってある。
そうすると、今後マーケターの新しい売り方は「AIじゃなくHI(話し合い)ってことになる(笑)。
誰かが言ってましたよ最近。AIってのは、人間のごく限られた能力を補完するだけの存在に過ぎないって。賛成です。
それは、前回紹介したように、アメリカTV界のそうそうたる連中が、会社作ってそこで毎月話し合いをしているって事実が証明していると思うんですよ。
もう「AIが答えを数字としてもっている」、なんていう考えではダメなんです。AIは、はしょり過ぎなんです。いろいろ。それを埋めるのが、人間の言葉であり、説明なんです。
それを可能にするのは、マーケターに知識とコミュニケーション能力が備わっているだけじゃ十分じゃなく、企業側も勉強してなきゃダメだってことですよ。
AIに学習させて、ディープラーニングどうのこうのの時代は終わりました。これからは生身の人間が改めて勉強しなくちゃいけない時代です。
その基礎にあるのが、読み、書き、話し、聞き、プレゼンの5つの能力じゃないでしょうか。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました
また明日お目にかかりましょう。
野呂 一郎
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
