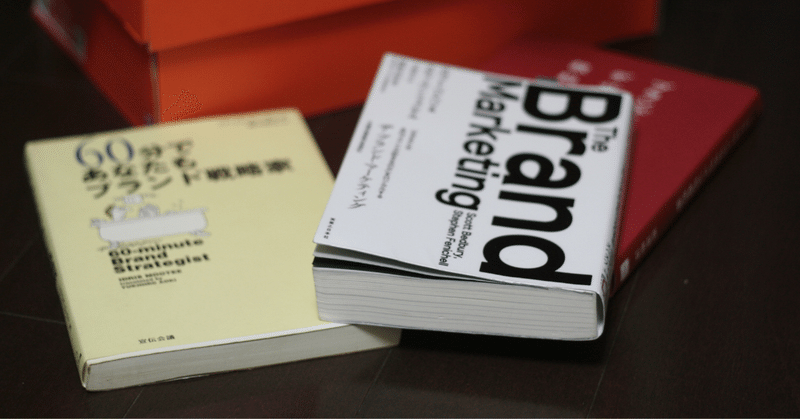
ブランディングとは企業の理念が生み出す独自性や強みを表面化させる活動|46冊目『ザ・ブランド・マーケティング』
スコット・ベドベリ&スティーブン・フェニケル(2022, 実業之日本社)
高校生起業ゼミでブランディングを考える
勤務先高校のゼミ(科目名:プロジェクト)の活動で、高校生と一緒にビジネスプランを考えています。
高校生が小さなビジネスを実際に行うのですが、高校生のビジネスを学校で行うので当然、資金力がありません。
また、短期間に完結させなくてはならないので、ビジネスといっても、斬新なビジネスモデルを考えるというのではなくて、シンプルにモノをつくって販売するというビジネススタイルがほとんどです。
さらに、教育活動として授業で行っているので、めざしているのは、利益ではなくて、ビジネスを通して社会課題の解決をめざすこと、すなわち社会起業家、ソーシャルアントレプレナーです。
「誰のどんな課題を解決するのか?」すなわちニーズから考えるべきなのですが、しかし実際は「何を売ろう?」と商品から考えていることが多くなっています。
その際に、内部環境分析とまではいきませんが、一応、自分のリソースを洗い出して、商品化できそうなものを考えています。
大凡の商品構想ができたら、どんな顧客をターゲットにするかを含めて、マーケティングについてアドバイスしています。
取り扱う商品は、コーヒーやお茶、ドレッシングなどの加工食品の場合が多いです。
高校生のビジネスでは大量ロットで商品を生産できないので、どうしても商品単価は高くなります。
競合となるのは大手食品メーカーで、とても価格で太刀打ちはできないですから、商品に付加価値をつけて差別化していくしかありません。
そうした中でブランディングという意見が出ました。
じゃあ、ちょっとみんなでブランディングについて考えようよ、ということになって、僕もブランディングについて少し学んでみることにしました。
ブランディングはマーケティングか?
ブランディングといったとき、よく考えるのが、ブランディングはマーケティングの手段の一つなのか?それともマーケティングがブランディングの手段なのか?ということです。
マーケティングの手段としてブランディング的なことをすることはあると思います。
でもそれは意図的にブランドを作ろうとする、ブランディング的マーケティング戦略といったものです。
まあ、それこそがブランディングだといわれれば、そうなのかも知れません。
逆にブランディングのためにマーケティングの手法を使うことはあるかといえば、おそらくそういうこともあるでしょう。
4P、すなわちプロダクト、プライス、プレイス、プロモーションをブランド商品寄りにすることはできます。
コストよりも品質を優先して、あえて高い価格をつけて、売る場所を限定的にして希少価値を生み出し、富裕層を顧客としてアプローチする、ということで、あるいはブランド的なものをつくることができるのかも知れません。
マーケティングの一手段としてのブランディング的戦略と、意図的にブランディングをめざすマーケティング戦略とは言い方の順番は違いますが、手法に落とし込んでみたら、どちらも同じような手段になると思います。
そしてその手段とは上に書いたようなことです。
しかしそれは、ブランディングを実現させるための方法ではあるかも知れませんが、ブランドの本質が何かを説明するものではありません。
ブランドとは何かを正しく理解していないならば、本当のブランディングはできないのではないでしょうか。
では、ブランドとは一体何なのでしょう?
この本にその答えが直接書いてあるわけではありません。
しかし、ブランドとは「ミッションやパーパス、バリューが示す組織(企業・団体)の独自性、強み」のことであり、それを表面化させるための活動がブランディングであると、本を読み終えて、ブランディングの定義を僕はそう捉えました。
つまり、ミッション、ビジョン、バリューが組織に浸透して、それが商品や文化、組織の制度や環境、そして従業員の行動など、企業のあらゆる場面に滲み出てくるものがブランドなのです。
そうであるならば、もちろんブランドとなるにふさわしい、素晴らしいミッション、ビジョン、バリューが存在することは大前提です。
「利益第一主義」なんてバリューの企業では、ブランディングはとても叶わないと思います。
ブランディングは帰属欲求への働きかけ?
マズローのピラミッドの真ん中に帰属の欲求というものがあります。
人には自分よりもっと大きな集団に帰属したいいう心理があるのです。
そして集団への帰属は、自分自身を表すアイデンティティにもなります。
例えば、ビジネススーツはNEW YORKERしか着ないとか、休日に身につけるものは全部NIKEに決めているとか、ブランドの持つイメージを利用して、それを自分のアイコンにしてアイデンティティを確立させようとすることは、マズローの”帰属欲求”の上位にある”承認欲求”、”自己実現欲求”につながっていきます。
組織をブランドにするのは従業員のふるまい
著者がこの本で終始主張し続けているのは、ブランドは人であり、組織における従業員教育は極めて重要であるということです。
ブランドの構築は基本的に時間がかかるものです。
マーケティングレベルのブランディング的なんちゃって戦略で一朝一夕にできるものでは本来はないのです(方向性を決めることはできますが、ブランドの本質は別のところにあります)。
従業員のふるまいは組織の価値に大きな影響を与えます。
従業員の一流のふるまいがその組織をブランドに育てていきます。
そして従業員のふるまいを決めるのは、他でもない、そう、組織のミッション、ビジョン、バリューなのです。
例えば自分が勤務する学校には、よくわけのわからない営業の電話がかかってきます。
「通信料を安く抑えるご提案をしたいのですが、理事長先生はいらっしゃますか?」
「・・・。」
誰に何の電話をしているのかわかっているのでしょうか?
学校とは何であり、理事長の仕事は何か、もう少し想像力を働かせて電話してこいよ!と内心腹立たしく思いますが、だからといって、上から目線で無礼な対応をして良いということではありません。
僕もよくそういう態度をとってしまうので反省しています。
けんもほろろに冷たくあしらわれたお兄ちゃん、お姉ちゃんは、やがて自分に子どもができたとしても、この学校に自分の子どもを入学させたいとは決して思わないでしょう。
そして、たぶんこの学校を、他の誰にお薦めすることもないと思います。
営業の提案は的を外していますし、不作法であると思いますが、こちら側も、もっと別のふさわしい対応の仕方はあると思っています。
自分が学校の看板を背負って電話の応対をしているということを、学校の全教職員が理解をして対応できたとしたら、それは立派なブランディングになるのではないでしょうか。
ブランド・マントラ
ブランド・マントラという言葉が登場します。
例えば、ナイキのブランド・マントラは「本物のアスレチックパフォーマンス」です。
スタバのブランド・マントラは「満足を味わう日常のひととき」です。
そして、ディズニーのブランド・マントラは「楽しいファミリーエンタテイメント」です。
マントラとはサンスクリット語で、日本語に翻訳すると「真言」のことです。
ですからブランド・マントラとは、ブランドを示す真言ということですね。
企業のミッション、ビジョン、バリュー、パーパスとの一貫性が必要ですが、ブランドがうまく構築されたなら、それを持続していくために、ブランド・マントラとして言語化しておくことは良いことだなと思いました。

最後までおつきあいいただきありがとうございました。
スキ♡の応援よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
