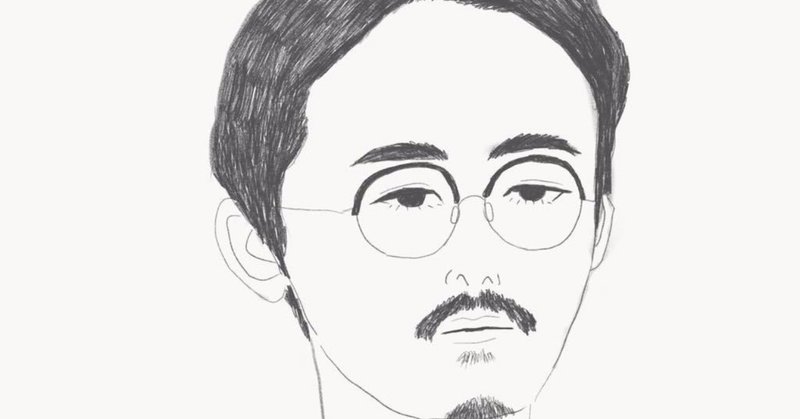
まちづくりは「ズルい」のかもしれない、というお話
以前、とある講座でお話をさせていただいた際、フロアから興味深い問題提起があったのを思い出したので、忘れないように書いておこうと思います。その問題提起をされた質問者は、長年、困窮者支援に携わっておられた方で、その立場からの発言でした。
氏曰く、困窮者支援というのは、なかなか市民の理解を得られないテーマであるというんですね。いわゆる自己責任論に典型的ですが、諸事情から経済的に困窮したひとたちというのがいるとして、そういう人々に公金を投じて支援をしようとすることに対して、市民の理解が得にくいというわけです。「あいつらが困窮なのは、本人の怠慢が原因であって、俺たちが苦労して稼いで支払った公金をそんな連中に投入するなんて許せない。自己責任だろ」というような論理です。困窮者支援反対派とでもいいましょうか。
そういう事情があるので、困窮者を支援しようとする人々は、困窮者支援反対派を説得、あるいは論破するために、様々な科学的なデータを必死で集めてきたし、理論武装もしてきたのだというんですね。そうしないと、支援反対派を退けて、公金の分配を受けられなかったというわけです。
で、興味深いのはここからで。一方でまちづくりに目を転じてみるとどうか。氏からすれば、公金の分配という点について、まちづくりは、困窮者支援に比べて、ひどくおおらか、もっといえば、甘々なのではないか?というんですね。僕なりに言い換えれば「まちづくり、なんかズルくない?」というわけです。
無論、氏の主張は自身も言うように多分に印象論ですから、この主張が正しいかどうかということは議論の要点ではありません。重要なのは問題提起であると僕は思いました。まちづくりに関わる側の印象から言っても、確かに、まちづくりに関わると、公的な援助制度は相応に整備されているというのはもっともであると感じます。少なくとも、僕がまちづくりに関わってそこそこ飯が食えている、という状況ひとつとっても、一定層の従事者が食える程度には配分があるということができるでしょう。そしてそれが困窮者支援の分野に比べて、配分の基準がイージーに見える、という、その「見え方」がここでは大事であると感じたわけです。
仮にですが、ここでの問題提起にしたがって、まちづくりが、困窮者支援に比べて公金の配分がイージーに行われている、としてみましょう。じゃあなんでそうなんだ、というと、端的に思い浮かぶ理由があります。
サポートされると小躍りするくらい嬉しいです。

