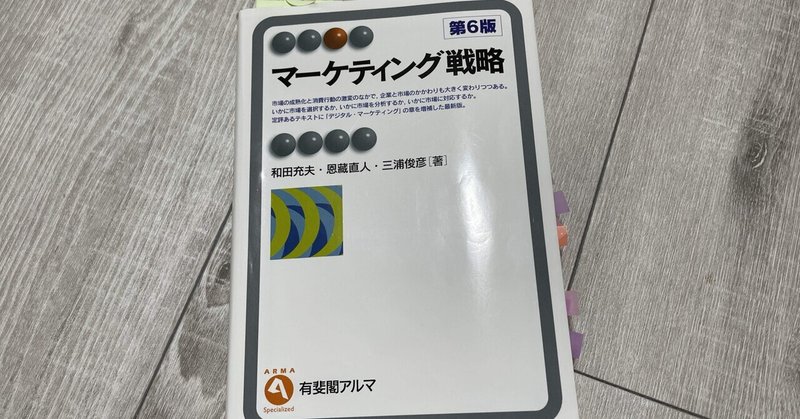
マーケティングの理論を学ぶ 全14回の連続講座がスタート #マープス
無料のオンラインマーケティング講座「マープス」
マーケティングのゴールは、「売れること」「お客様に買っていただくこと」ですが、これは結果です。結果を直接コントロールすることはできません。だからコントロールできる入力を変えます。
そこで、マープスの講座では、
・どこがうまくいってないのか? を『売上の地図』で確認し、
・どの施策をいつ、どのタイミングやるのか? を『ファネルマップ』で確認します。
そんなマープスで、本格的に理論を体系立てて学ぶ14回の連続講座がスタートしました。今回は、全14回の連続講座の第一回です。
みんなでマーケティング理論を学び直すこちらの講座、申込者数がZOOMのライセンス限界500名まで近づいてまいりました…!お早めに!>有斐閣アルマ『マーケティング戦略』を教科書にした連続講座のご紹介|マーケティングが無料で学べるMARPS(マープス) https://t.co/fGrxchbC0X #MARPS #マープス
— 池田紀行@トライバル代表 (@ikedanoriyuki) May 31, 2024
このnoteではどんなことがわかるか
第一回では、
・(マーケティング)理論を学ぶ理由
・教科書の最初に書いてあること、全体像
がわかります。
理論を学ぶ理由(オリエンテーション)
なぜ、理論の学習、基礎的学習が必要なのか?
マーケティングの学習でよく出てくる意見として、
「理論を学ぶメリットがわからない。」「学んだことで成果がでるのか?」があるそうです。
理論を学ばず、事例(具体)を学ぶとどうでしょう? 環境も、製品も、条件も、制約も違うので、そのまま手法だけ真似てもうまくいきません(具体→具体)。必要なのは、そこから抽出した抽象化した概念が必要です。しかし、抽象化したものを抽象化したまま施策を考えても、ただの机上の空論です(抽象→抽象)。うちの会社だったら? うちの商品だったら? を考えて、実際の問題に適用して、実際の施策に落とし込む必要があります(抽象→具体)。学んだ理論を具体的な現状と施策に落とし込まないと活きてきません。これが実践力です。
優秀なマーケターはこの抽象化できているから、他の商材にしても適用できます。良書は、だいたい、妥当な抽象化されたものが載っています。抽象化した概念を束ねたものが理論です。
学習(インプット)について
インプットの仕方については、過去の講座で教えていただきました。
理論を学びメリット3つ
・「理論」は結果の予測性を高める
・「理論」は、目の前の減少や事実を説明・解釈・整理する手がかり
・「理論」は、仮説を生み出す基盤
「理論」にまつわる誤解
・理論は「答え」や「正解」である
→「答え」や「正解」ではない。事実から抽出して、抽象化した概念の束。考えるフレーム
・理論を学べば、売上が上がる
→理論を学ぶだけで売上は上がらない。理論は、概念の束。具体的な施策に落とすマーケターが必要
・理論を学べば、すぐに成果が出る
→理論的学習は、費用的な効果はない(費用をかければ効果が出るものではない)。投資的な効果。
『マーケティング戦略』序章
マーケティングは、1900年ごろ、アメリカで誕生。需要が膨らんだ後、生産(製造)が大きくなり、供給が需要に並ぶ、もしくは、超えるようになって、作るだけでは売れなくなりました。こうした状況で生まれたのが、マーケティングです。日本では、アメリカからマーケティングを取り入れたのが、1955年。日本はこの頃、高度成長期で、製造(生産)が膨らみ、作れば売れる時代が到来しました。(「三丁目の夕日」の時代)
マーケティング・コンセプトの変遷
マーケティング・コンセプト:
「企業経営にあたって必要とされる企業の市場に対する考え方もしくは接近法」
・プロダクト志向(シーズ志向):作れ!作れ!
(企業が売るべきものを知っていて、顧客が買うべきものを知っている)
⇒マーケティング不要
・販売志向:売れ!売れ!
(企業は売るべきものを知っている。顧客が買うべきものを知らない)
⇒マーケティングプロモーション
・顧客志向(ニーズ志向)
(企業が売るべきものを知らない。顧客は買うべきものを知っている)
⇒マーケティングリサーチ
・社会志向:CSR、バブル期にはメセナ、CSV /SDGs/ESG
現在は、顧客志向 & 社会志向の時代です。
※「マーケティング」と「セールス」の違い
・セールス:買って!(商品→顧客)
・マーケティング:お客様がほしい・買いたい、と思う状態を作る(顧客→商品)
顧客志向のマーケティングコンセプト:お客様が求めている未充足なニーズを満たすこと
『マーケティング戦略』の構成
第Ⅰ部 市場の選択
第1章 事業機会の選択(企業成長のための市場需要の探索)
第2章 事業領域の選択(企業アイデンティティの形成)
第3章 標的市場の選択(成熟市場における市場細分化戦略)
第Ⅱ部 市場の分析
第4章 市場データ分析(消費者に関するデータの収集と分析)
第5章 消費者行動分析(消費者の行動を理解する)
第6章 競争分析(競争環境と競争相手の分析)
第7章 流通分析
第Ⅲ部 市場への対応
第8章 製品対応(マーケティングの中核としての製品戦略)
第9章 価格対応(価格設定のマーケティング戦略)
第10章 コミュニケーション対応(消費者への効果適菜情報伝達)
第11章 流通チャネル対応(流通環境の変化に対応したチャネル戦略)
第12章 競争対応(競争優位のための戦略対応)
第Ⅳ部 市場との対話
第13章 サービス・マーケティング(サービス業のマーケティング戦略)
第14章 ソーシャル・マーケティング(マーケティングと社会のかかわり)
第15章 関係性マーケティング(相互作用重視のマーケティング)
第16章 デジタル・マーケティング(デジタル・コンシューマーに対応するマーケティング)
※提出義務のない宿題
『課長 島耕作』を読んでみよう
※マーケティングの変遷と現場感を知ることができます
サイン本を残して売っちゃったんだけど、買い直すかなぁ

いい歌を詠むため、歌の肥やしにいたします。 「スキ」「フォロー」「サポート」時のお礼メッセージでも一部、歌を詠んでいます。
