
Collaborative & Proactive Solutions (CPS) について - CPSシリーズ1
ニュージーランド在住で、総合診療科医、ライフコーチ、Havening technique ®️プラクティショナーなどをしています。
今まで何回も、私の記事の中でDr. Ross Greeneのcollaborative & proactive solutions (CPS) について触れたのですが、日本では彼の本は翻訳されておらず、日本語での資料もないため、ここに概要をまとめておこうと思います。
(その為、かなり長文になります。)
興味がある方は (英語ですが) 彼の本やビデオに目を通していただけるといいなと思います。
(彼の仕事を紹介することで、私に金銭的メリットはありません。
私は個人的に、このCPSモデルに純粋に共感しており、
この方法を、私がやりたい事を達成する一つの方法として採用していきたいと思っています。)
また同じくCPS と略されている「Collaborative Problem Solving」というプログラムもあります。こちらのコースも近い将来取ろうと思っているのですが、考え方、やり方はほとんど同じ様です。同じ研究結果を採用して、2人が別々にプログラムを作ったのでしょうかねえ。
Dr. Ross Greene とは
アメリカの臨床心理学者で、小児を専門にしています。
(以前の記事で「小児科医」と書いたかと思うのですが、医師ではありませんね。)
特に犯罪を起こすような「問題児」のケアに関与してしています。
多くの本も書いています。(ただ日本語訳はない様です。)
「問題児」が起こす「問題行動」を大人が強制的に変えようとしても、「問題行動」を起こさざるを得なかった原因が解決しないことには、根本的な解決にはならない。
刑務所を出たらまた犯罪を起こすし、学校からは追放されてから学校で「問題行動」をしなくなっても、社会で「問題行動」は続きます。
CPSで「根本的な問題の解決」を大人と子供が一緒になってする、という観点を採用した事は、(知ってみると、当然と思える事ですが) 素晴らしいなあと思います。
CPS の根本的なフィロソフィー
CPSはエビデンスに基づいたアプローチで、子どもや若者の「問題行動」そのものでなく、「問題行動」の大元になる原因の解決に目を向けています。
“Children do well if they can” 子供は、できるなら上手くやるのだ
という言葉が重要な原理、原則としてあります。
子供の「問題行動」はモチベーションの欠如とか、親を操ろうとしているとか、大人の注意が欲しいから起こるわけではない。
子供の「lagging skills 発達が遅れているスキル」の為に
大人が期待する行動を取れない結果、「問題行動」が起こる。
じゃあ「unsolved problem 解決されていない問題」自体は何なのか、に目を向け
それを大人と子供が一緒に解決する。
CPSには以下に説明するプロトコールがあり、
それに従っていきます。
大切な要素は、大人と子供の間の共感、コミュニケーション。
そして大人が権威を使って解決策を押し付けるのでなく、
プロアクティブに(つまり問題が起こっている最中でなく、その前に)
解決策を話し合う事。
CPSは、大人の押し付けでなく、子供も納得する解決策を取るため、
長い効果が期待できます。
CPS を使うことによって、「問題児」が拘束されたり、学校や施設で懲罰会議に送られるのがかなり減ったそうです。
CPSのプロトコール
CPSの流れについて、書きます。
1.発達の遅れているスキルは何かを明らかにする
これは通常、その子供をよく知っている大人が集まってやります。
(子供抜きです。)
学校なら、担任と校長先生とか、教科の先生とか。
家なら両親とか。(ただ、親の1人はCPSを使いたいけれど、もう片親は使いたくないという事はよくあるので、その場合はCPSを使いたい親が1人でやります。)
この時使うのが 「Assessment of skills and unsolved problems
スキルと未解決の問題のアセスメント」(ASUP 2024)
です。
(2024年にバージョンアップがあり、ALSUP2020からASUP2024になりました。)
一つ前のバージョンALSUP 2020の日本語訳は以前の私の記事に載せてありますので、宜しければそちらを参照してください。)
よくある「遅れているスキル」には
感情のコントロール
(考えの)柔軟性
コミュニケーション
衝動の制御
問題解決思考
があります。
大人もよくこういったスキル、発達が遅れてますよね。(笑)
ただ、このステップの一番大切な点は、「どんなスキルが遅れているか」を見つけ出す事でなく
「子供の問題行動を、遅れているスキルと結びつけて見る」という
「新しいレンズを使って、大人が子供を見るきっかけを作る」ことにあります。
2. 「未解決の問題」は何か、を子供の話を聞いて、見つけ出す。
通常、ある特定の状況や問題が、子供の「問題行動」に繋がっており
殆どの「問題行動」は予測可能です。
まず、この子供を悩ましている「状況や問題」が何であるかを、子供に訊いて見つけ出します。
よく我々大人がするのは(あの子は、親が離婚したから落ち着きがないし、友達の輪に入って行けないのだ)とか、勝手に推測して、その子の問題を定義する事です。
Dr. Greene は「No assumption 推測しない」事の大切さを説明しています。
「子供に訊いてみなきゃわからないでしょ」と言う事です。
大人が自分の意見を挟む事なく、子供がどんな事を感じて、
どんな行動に出ているのか、純粋に好奇心を持って聞く。
できる限りの情報収集をします。
3. 大人の心配している事を説明する
ここで初めて、私達が大人の見地から何を心配しているのか(例えば、宿題しなかったら必要な知識がついたかどうか確認できない、とか。自分の部屋のゴミを処理しなかったら、衛生的に健康に問題を起こす可能性がある、とか) を子供に説明します。
ステファン コヴィーの「7つの習慣」を読まれた方は多いと思います。
その習慣の一つに
「まず相手を理解する事に徹し、その後自分が理解される様にする」と言うのがありますよね。
まさにそれです。反対の順番では上手くいかないことが多いです。
またこの過程を経ることで、大人が自分の懸念が「本当に意味があること」なのか、を顧みることができます。
4. 子供に解決法を考える場を与え、大人と子供が一緒に話し合い、双方が納得する解決法を導く
これが大まかな流れです。
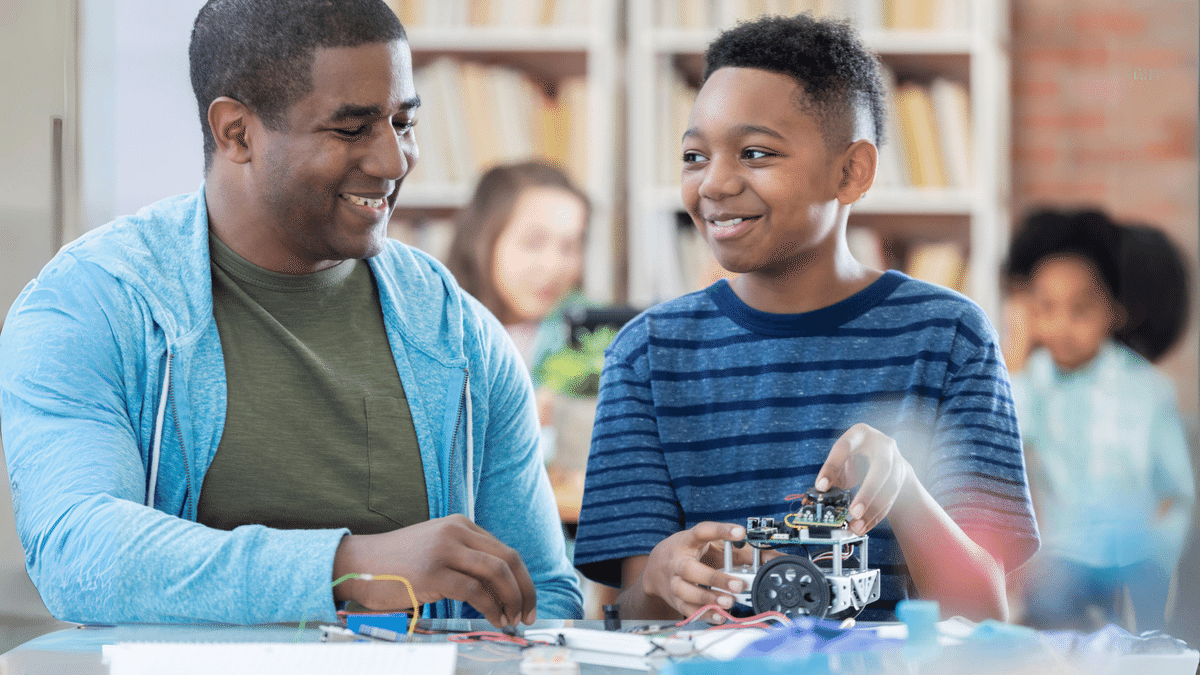
プランA、B、Cとは
CPS ではプランA、B、C と言う言葉を使います。
プランBはCPSの方法を使い、大人と子供の双方が納得する解決策を、問題が起こる前に話し合って決める事を言います。
プランA は、大人が自分の解決策を押し付けるやり方。
たとえ大人が子供の話を聞いて話し合っても、最初から大人が「どんな解決策を使うか」が分かっていたら、それはプランA です。
「子供と話し合いをしたふり」、「子供を尊重するふり」をして、結局は自分(大人)の解決策を押し付けているからです。
プランC は、親が自分の期待を取り敢えず置いておく事。
「諦める」と言うのとは違います。
でも、現時点で他にもっと大切な事があれば、まずそれをプランBする事に時間とエネルギーを注ぐ。
例えば
「学校で算数の時間中に隣の友達にちょっかい出して、友達の勉強の邪魔をする」という問題と「遊んだ後に部屋の片付けをしない」という問題があったら、どちらか一つの問題をプランBして、もう一つはプランCする訳です。
最後に
かなり長くなったので、今日はここで終わりにしたいと思います。
もちろんここに書ききれていない事が多くありますし、
いつも全てのステップがスムーズに行く訳ではありません。
また個別の記事で、いろいろ補足していこうと思います。
もしもCPSに興味があって、もっと知ってみたいという方。
是非Dr. Greene の本を読んでみて下さい。
(英語はちょっと)という方で、「CPSに興味がある」「CPSを始めてみたい」「学校で取り入れてみたい」という方がいらっしゃったら、直接私に連絡していただいても構いません。
note経由でも、私のウェブサイト経由で
でもオッケーです。
長文を読んで頂き、ありがとうございました。
「親も育つ子育て」を広めるために、私の持っている知識、経験、資料をできるだけ無料で皆さんに届けたいと思っています。金銭的サポートが可能な方で、私の活動を応援していただける方は、サポートをしていただけると嬉しいです。
