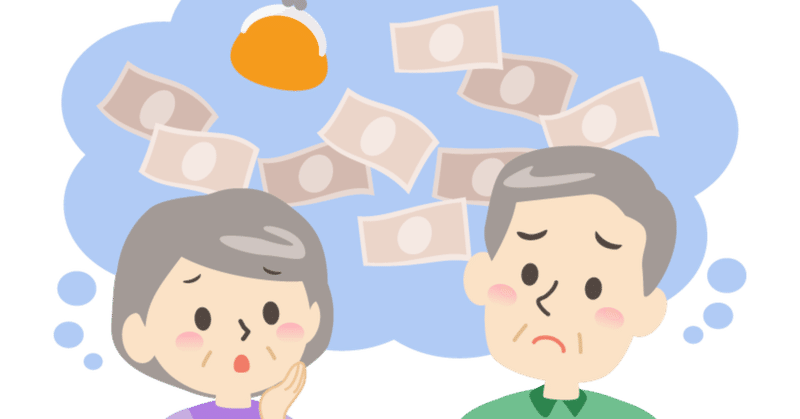
定年後のお金問題と働く目的
前回のブログにも書きましたが、昨年2022年11月末で41年8ヶ月間勤務した会社を一旦定年退職し、12月からは再雇用の嘱託社員として週3日の勤務をしていますが、今回は定年後のお金問題と働く目的について書いてみたいと思います。
お金のことを真剣に考えるきっかけとなった出来事
私は今から7年前の58歳の時点までは家計は妻に任せっぱなしで、毎月の給与額や賞与の金額は把握していましたが、支出や預金を含めた家計がどうなっているかについては無頓着で、ほとんど把握していませんでした。
そして、預金通帳などはどこにしまってあるのかも知らず、妻が見せてくれることも一切ありませんでしたし、支出の詳細についてはほとんどわかっていませんでしたが、妻が毎月のように自分自身と2人の娘たちの洋服を中心に、食料などもたっぷり買っていたこともあり、結構使っているんだろうなとは思いつつも、そこそこの年収がありましたので、貯金もある程度の額にはなっているだろうと思っていました。
そうしているなか、その58歳の時のことでしたが、妻の歯の治療がうまくいかず、そのことから妻は眠れなくなくなり、ひいてはメンタルダウンを起こして食欲不振で体重が激減し、結構大変な状況になりまして、歯医者を変えたりしながら、その通院に加えて心療内科への通院がしばらく続き、治療費も結構かかっていました。
そういう状況のなか、妻がある日突然に「貯金がほとんどなくなってるんやけど、どうしよう」と言い出しました。
それを聞いて、「えぇ~!!!ほんまかいな???」と思わず言ってしまいましたが、もっともその2年ほど前に次女が自宅から通っていた大学を卒業して、私は行かなくてもいいのになぁと思っていましたが、東京の赤門とかがある大学の大学院に入学しましたので、かなりの教育費が追加でかかっていることはわかっていたものの、まさかそこまでになっているとは思っていませんでした。
そして、妻に預金通帳を見せてもらうと、確かに残高は100万円を切るぐらいになっていて呆然としましたが、ここは妻を安心させようと「何とかなるから大丈夫や」と言いました。
しかし、内心はこんなことになっているとは思っていなかったので、非常に焦りましたが、このことがきっかけで、私はお金と家計のことについて、真剣に考えるようになりました。

まずは支出の把握からスタート
それで、家計簿なんかつけていない家計の支出がどうなっているのか、まずは現状把握からスタートしようと思い、預金通帳をにらみながら、支出項目とその金額をエクセル表に入れていきました。
幸か不幸か、妻の買い物もほとんどがクレジットカードを使っていましたので、詳細まではわからないこともあるものの、支出金額については概ねわかりましたので、半年分ぐらいを記録していったところ、支出の全体像がある程度把握できるようになりました。
また、あわせて住宅ローン返済や所得税、住民税などの税金、そして厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料についても金額をエクセル表に入れていきました。
そうしますと、わかったことは単独でもっとも大きな支出は住宅ローン返済で年収金額の約16%を占め、あと税金と各種保険料をトータルすると約31%、マンション管理費や水道光熱費、新聞、電話、インターネット接続、NHK受信料などの定期的な支出のトータルが13%強となっていて、それらを合計すると年収金額に占める割合が、ちょうど6割程度となっていることがわかりました。
あと住宅ローン返済の次に大きかったのは実は私の小遣いでして、それはそっとしておきましたが(笑)、残りは衣食を中心とした消費支出ということで、支出の全体構造が把握できるようになりました。

支出のダウンサイジングへの取組み
そのような支出状況の把握をもとに、ここからは家計のマネジメントをしようと考えまして、経営の基本である「入るを量りて出ずるを制す」のうち、まずできることは「出ずるを制す」ことだと考え、生命保険や傷害保険は必要以上の契約内容を見直すようにしたり、定期購読していた複数の雑誌や業界新聞等で止めてもいいものは購読を中止していくなどし、どうしても減らせないもの、やめられないものは別にして、定期的に支払っているもので減らせるものは減らすようにしていきました。
そして、60歳になる時点でさらに給料が大幅に減ることがわかっていましたので、60歳時点で受け取れる確定拠出年金を全額一時金で受け取り、73歳まで組んでいた住宅ローンの残金すべてを返済しましたので、娘たちも就職して独立していたこともあり、人生の三大資金といわれるなかの住宅資金と教育資金を60歳時点で不要とすることができました。
ちなみに確定拠出年金の運用は下手くそで、大幅なマイナスからほぼプラマイゼロまで戻したところでしたが、住宅ローンの残額一括返済で本来支払うべき金利を支払わずにすんだことで、その分は運用益と同等だと考え、自分を慰めました(涙)
定年後は年金だけで生活できるのか?
そういうふうに「出ずるを制す」を中心に58歳から約7年やってきましたが、いよいよ65歳の定年退職を迎えるにあたり、定年後のお金の問題をどうするか決める時がせまってきました。
それは具体的には、定年退職時点で老齢厚生年金と確定給付年金をどう受け取るのかを選択することでしたが、老齢厚生年金は繰り下げ受給をすると割り増しがあり、確定給付年金は実質は退職金なので、退職一時金で受け取ることもでき、その場合勤続年数に応じて一定金額までは「税金の免除」というメリットがあるということで、それらを踏まえて意志決定しなければならなかったのです。
特に確定給付年金については、その時点ですっかり元気になって、体重が元通り以上に戻っていた妻からは、「全額一時金で受け取って半分は私がもらう!」と主張していたんですが、すったもんだの末「終身保障なので一時金でもらうよりも、亭主が85歳以上まで長生きすれば増額になる」という私の主張をやっとのことで通し、全額を企業年金として受け取ることに落ち着きました(汗)
また、老齢厚生年金については、繰り下げで増額されても手取りベースではそれほど増えるわけではないこと、そして専業主婦の妻が5歳年下であるので妻が65歳になるまでは1年あたり約39万円の加給年金がもらえること、また自分自身が何歳で死ぬかわからないことなどから、もらえるうちからもらえるだけもらっていこう、ということで65歳から基礎年金も含めて全額受給することにしました。
その上で、支出のダウンサイジングも更にすすめ、例えば自家用車もそれまで乗っていたRV車から軽ワゴン車に買換えて、自動車税、ガソリン代などの維持費を減らすようにしましたし、一方で定年に伴い健康保険については任意継続でも保険料がアップしたものの、それより金額が大きかった厚生年金保険料が無くなったことで支出を更に減らすことができました。
そうやってダウンサイジングしてきた支出と、老齢厚生年金+企業年金の収入を計算してみると、私の小遣いを無しにすれば、なんとか生活はできることがわかりました。ということで以前に妻から「小遣い無し」と言われたことは、結果的には正解だったんだと、この時点でわかりました(汗)
また、預金残高についても、確定拠出年金の残りと、わずかですが一時金で受け取るのが必須部分の退職金と、少ないながらも社内株の売却金の手取り分などで、最低限の夫婦2人分の老後資金に加え、想定外の支出にもある程度対応できるぐらいの預金残高が確保できました。

定年後も働く目的は?
では老後資金などもある程度確保でき、年金で生活ができるなら働かなくても悠々自適で生きていけるのではないか?ということになりそうですが、私は2つの目的をもって生涯現役として仕事を続けようと考えています。
その2つの目的とは、「暇つぶし」と「小遣い稼ぎ」です。
それは、以前のブログにも書きましたように、65歳から85歳までの20年間の生活必需時間を除く自由になる時間は約10万時間で、それは40年あまりの会社員としての労働時間とほぼ同じということで、時間はたっぷりあることと、年金でも生活自体はできるものの、自分だけの趣味を楽しんだり、飲み会をはじめとしたコミュニティに参加したりする、つまり自分の好きな遊びをするための小遣いは自分で稼ぐ必要があるからです。
そして、冒頭にも書きましたように定年後も再雇用で働いているのですが、再雇用は最長でも70歳までということもあり、70歳以降も続けられる仕事を模索中ですが、年金のみでも生活できるメドが立ったことで、焦る必要もなく、脳天気プランで流れに身を任せればいいと思えるようになりましたし、高尚な目的でもないこの2つを定年後の働く目的とすることで、自分でもウケて(笑)、肩の力が抜けとても気が楽になりました。

その上で、ただ単に稼げればいいということではなく、アイデンティティ(自分らしくあること)を大切にしながら、生涯現役で働き続けることを前提に「簡単で、楽で、余裕でできる、自分がやりたい仕事だけをやる」というスタンスのもと、シニアモデル・タレントなど今までやったことのないことにもチャレンジしながら、本当にやりたい仕事を見つけていき、ある程度の安定した小遣い稼ぎができるようになれば、自分の夢でもあり、2つの働く目的も同時に果たすことができる、自分の居場所&秘密基地としての会員制サロンバーを実現したいと考えています。
以上、少し長くなりましたが最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
