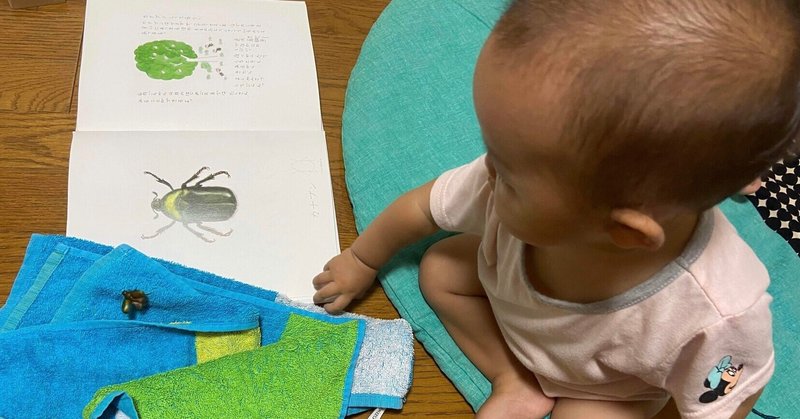
教育熱心と教育虐待の違い
自分が子どもに熱心にしていることは教育虐待ではないか、と心配している親が少なからずいるという。教育熱心と教育虐待の線引きはどこにあるのかという問い合わせをメディアから次々といただく。
教育虐待ではないかと不安になる親、子どもが将来、問題を抱えたらどうしよう、自分が虐待をしている親というレッテルを張られたらどうしようと不安になっている親は、子どもがこれではかわいそうとうすうす思っていることを現にしているのだろう。でも、これは子どものためと思って一所懸命にやってきたことだ、だから止められないし、それが子どもにとって良くないことだとしたら、今まで自分がやってきたことはまずかったのか、いや、大丈夫だと言ってほしい、これでいいと認めてほしいということだろう。
それに、子どもに無理やりと思えることをやってきて、子どもが結果的に社会的成功をなし遂げた(受験に合格したとか、社会的評価の高い会社に入ったとか、オリンピック選手になったとか)というような例が巷で宣伝されているから、それにあこがれる親は、子どもに多少の無理はさせなければそうはならないと思っている。
無理をさせてもいいと思っている親は不安にはならない。子どもはさておき、自分が満足する結果を得られることが第一なのだから。そして、頑張れば短期的に良い結果が得られてしまうこともあるから厄介だ。何十年か後にどうなっているかは、多くの人は知らないから。
一方で、不安になる親は子どものことを本当に心配している。人生というスパンで気にかけている。もし違っているのならやり方を変えたい、知りたいという気持ちを少なからず持っている親だ。
それで、教育虐待という言葉を学会大会で取り上げた私に、教育熱心と教育虐待の違いを教えて下さい、ここからが教育虐待というラインを示して下さいというメディアからの取材が入る。ついついその問いに答えようして「教育熱心にやっていても、子どもの受忍限度(耐えられる限界)を越えたら、教育虐待です」と言っている自分がいて、苦笑する。
次の質問は、「子どもの受忍限度の基準を教えて下さい」だから。
顔色が悪い、寝起きが悪い、親の顔をうかがう、隠しごとをする、誰かに意地悪やいじめをしている、物にあたる、いらいらしている、急に泣きだす、ゲームがやめられない、自傷行為がある…。
いろいろと指標はあげられるだろう。
上記のように、子どもの体や心や脳の発達を阻害する行為は虐待にあたる。
でも、基準は他人の私が作ることではない。
子ども本人に聞いてみればいい。
「私は一所懸命にあなたを育てているつもりだけれど、あなたにとっては辛すぎるかな」
「私がこれを強要するのは、子どもの立場からするとどうなんだろう」
「厳しいお母さんなんていなくなればいいって思うことがある?」
「どの位までだったら、大丈夫?」
そもそも子どもが本音でそれに答えられる関係でないとしたら、日頃の接し方を考え直した方がいい。
正直に答えた子どもを叱るかもしれないと微かにでも思うなら、聞いてはいけない。
とても聞けないけれどそこを何とかというのであれば、直接聞かないで、まずは「自分が誰かから全く同じこと(寝ないでこれをやりなさい。これをやるまでおやつはあげません。休憩は10分だけね。ぼーっとする時間があったら勉強しなさい、等々、普段から自分が子どもに言っていること)をしばしばされたら耐えられるだろうか」と考えてみる。自分と子どもはしばしば感覚が違うから、自分にはより厳しい基準にしておいた方がいい。
このとき、自分の教育熱心さが虐待になっているかどうかの「他者からの評価や基準」を気にしているとしたら、それはそもそも自分中心の考え方であるということに気づきたい。
一番気にしなければならないのは、「子どもがどう感じているか」である。「子どもがどう思っているか、考えているか」ではなくて、子どもが身体感覚として、親からされることに対して、どう感じているか、ということである。子どもが感じていることは、「えーそんな、親の気持ちをわかってくれないなんて」ではなくて、いいとか悪いとか判断するものでもなくて、子どもがそう感じているのだから、親はそのまま受け止めなければならない。
そうして、子どもに共感してもらいたいと思う前に、自分が子どもに対する共感性を持てているかどうか、振り返って考えてみる必要がある。同じことを自分の子ども以外の誰か(例えば、親や友達、先生)にできるかどうか考えてみてもいい。子どもだから多少の無理を言うことは許されると思っているとしたら、子どもを人として尊重できているかと考えてみる必要がある。虐待というのは、力のある者が、暴力的に相手を扱うことである。
と、いうわけで、教育熱心と教育虐待の違いは、こういうことになる。
「教育熱心」は親の一所懸命な状態を表すことば。対象者としての子どもの状態とは関係がない。
「教育虐待」は親の不適切な行為を表すことば。対象者としての子どもは親の行為に巻き込まれて耐えがたく辛い状態にある。
でもね、うちの子はやらせないと勉強しない、子どもは親がコントロールしないといけないものでしょう?という親はやっぱり多い。
それについては、ややこしくなるのでまた改めて書くことにしましょう。
#教育虐待 #教育熱心 #コントロール #子どもの人権 #尊重 #受忍限度 #社会的成功 #子どもの体と心と脳の発達の阻害
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
