
フィクショニズム File03
5歳の時に姉と母親が死んだ。
トラック運転手の居眠り運転で当時7歳だった姉が横断歩道を渡る際に猛スピードではねた。庇って守ろうとした母親も同時にはねられ死亡。
小学生。
いじめにあう。
毎日ものを盗まれる。
毎日誰かに殴られる。教師の目をかいくぐって。
彼ら曰く、物語にはスパイスが必要らしい。
彼らは賢く、証拠を残さない。故に、言っても誰も聞いてくれない。
「嘘はだめだよ。先生は忙しいからね」と言われる。先生は本当に忙しそう。先生に嫌われたくない。みんなに嫌われたくない。
父親には言えない。
父は優しくしてくれる時とそうでないときがあり、そうでないときには暴力を振るわれた。
そんな父に転校したいと伝えたら、父はどんな顔をするだろう。人並みに学校に通わせてくれる父にそんなことは言いたくない。言えない。
中学校
いじめは続く。
でももう慣れた。
いじめる子もいつもヘラヘラする自分に飽きたのか、いじめの回数は減少した。
やがていじめは無くなった、というよりかはターゲットが僕ではなくなった。
僕は孤立する。もう、誰も構ってくれない。
話しかけることはできない。嫌われたくないから。
高校
一生懸命勉強した。第一志望である公立高校は偏差値の高いところを目指した。第二志望は私立だったがそれでも偏差値は高かった。
落ちた。
第二志望には受かった。
父親に殴られた。私立はお金がかかるから。
「なにやってんだこの馬鹿野郎!」
ごめんなさい。
努力はした。精一杯やった。でも。合格できなかった。僕は馬鹿なんだ。
部活には入らなかった。怖い。誰かと必要以上に関わるのが。
もういじめられたくない。殴られたくない。ものを盗まれたくない。
僕は孤立する。声をかけられてもそっけない対応をする。
「あいつって喋れないの?」と陰で言われる。
授業中、教師に当てられて答えたら
「あいつって喋れるんだ」
と誰かが小声で言うのが聞こえる。
怖い。
寝る前になんども思う。
明日起きなかったらどれほどいいだろうかと。
目を閉ざしたまま自分という存在がどこかに消えてしまったらどれほどいいだろうかと。代わってほしい。
でも僕は必ず2つの条件をつけてしまう。
誰も傷つけないこと。
できるだけ多くの人を幸せにすること。
どうしても、いつもこの条件をつけてしまう。だから誰も代わってくれないのだろう。
朝最悪な気持ちで起きる。父親に嫌われたくないからちゃんと学校に行く。
真面目に勉強する。
助けを求めている自分を何度も頭の中で殺す。
何度も何度も殴り殺す。
食欲はそんなにない。
高校には給食がない。
昼食の時間になると僕は決まって外に出る。
誰もいない公園に行ってベンチに座って空を見る。
雨の日は図書室で過ごす。
優しい時の父は食事のお金を渡してくれる。父は決して料理しない。僕は料理した方が安上がりなことを知っているから出来合いの物は買わない。
数年前までは父に料理を振舞っていたが、「不味い」と言われてからはつくっていない。父親はもう何も言ってこなかった。近頃の父親は忙しく深夜に家に帰ったかと思うと朝にはいなくなっている。もう何か月、何年も顔を合わせていないかもしれない。
あまり食べすぎると吐いてしまうから自分はそんなに食べないようにしている。
何度も死にたいと思う。でも死んだら父親に嫌われてしまうかもしれない。加えて死ぬ勇気は今のところない。故に死ねない。
18歳。
何とか大学に進学した後に父親が死んだ。
首吊り自殺。
父親が持っていた金をすべて使い切った後に死んだ。
僕の成績は優秀ではなく、入った大学も私立であったことから奨学金を借りても学費を払いきれなかったことから退学を余儀なくされた。
僕は近くのハローワークへ行き、就職口を捜す。
ようやく決まった就職先は工場の作業員。ひとりで生きる分には困らない給料だが、学校の勉強と同じくらいの苦痛。しかしもう耐えることには慣れている。ひたすら耐える。耐える。反復作業。反復作業。
4年が経つ。
起きる。食べる。職場に向かう。作業を終える。帰る。食べる。寝る。その繰り返し。休日は暇を持て余し、散歩をしてみるが結局何も起こらない。
起きる。食べる。職場に向かう。作業を終える。帰る。食べる。寝る。
起きる。食べる。職場に向かう。作業を終える。帰る。食べる。寝る。
起きる。食べる。職場に向かう。作業を終える。帰る。食べる。寝る。
…何のために。
…誰のために。
それを考えるのはもうやめたはずだった。それを真面目に考えられる人はきっと幸福な人だろうから。過去の自分は精一杯生きていた。最近の自分はそうではない。
余裕が生まれたことによる苦痛。

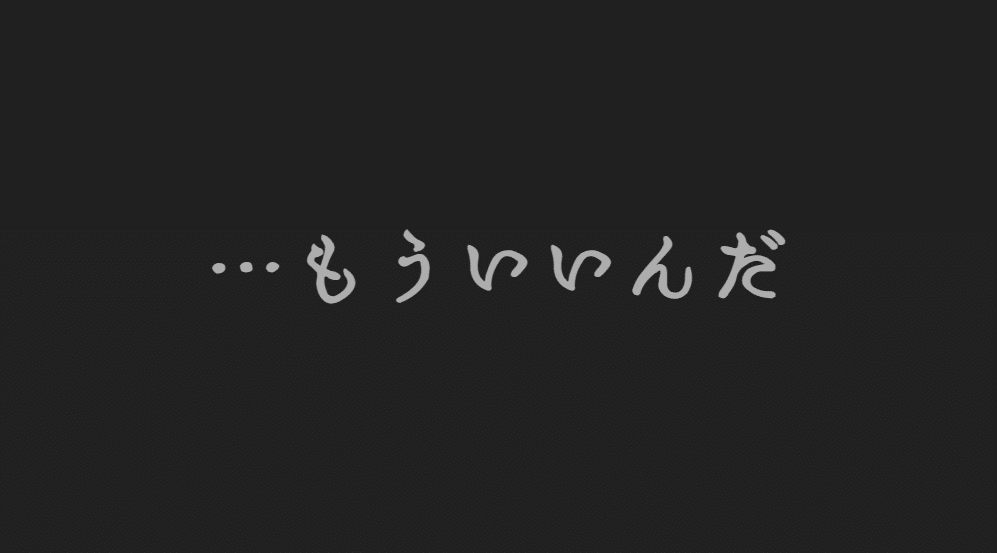
そろそろもう…いいよな。
十分やったさ。
今死んでも、誰にも迷惑かけないだろう。
工場の作業員なんて代わりはいくらでもいる。
終わりにしよう。
でも最期に…何かしたいな。
そう思い、頭に浮かんだのは、富士山。
なぜかは分からない。しかしその時富士山が頭に浮かんだのだ。
登ろう。
登って死ぬことにしよう。
迎えた休日。
新幹線で富士山へと向かう。バスで五合目まで登る。
登山の道中、いろんな人を見る。子供、若者、高齢者。
誰も死ぬために登山なんかしていない。
みんなはなぜ生き続けられるのだろう。
なんでそんなに笑っていられるんだろう。
死ぬために登るなんて、僕だけなんだ…
当たり前のことかもしれないけど、その時僕は初めてそのことに気が付いた。
今日、地下駅で見覚えのある人物を見かけた。
そいつは中学校で僕をいじめていた奴とよく似ていた。
勿論人違いかもしれない。
中学生のころの顔と大学生の顔なんて成長して似ても似つかなくなっている可能性が高い。
でも、喋り方や歩き方がどことなくあいつと似ていた。
隣には女性がいて、二人は手をつないで歩いていた。
僕とすれ違う。僕は彼らのことを覚えているけど、向こうは覚えていないみたいだ。
二人は笑顔で楽しそうに話していた。
その時僕は、よかったと思った。
楽しそうな二人を見て、よかったと思った。
いじめられていた時、自分のことなんて忘れて、早く幸せになってほしいと思っていたから。
途中の旅館で一泊する。明日で頂上まで行き、帰りにロープでも買ってどこかの山で首を吊って死のうかと考えている。多分、以前のように躊躇うことはないだろう。そういう意味ではもう吹っ切れている。
うん。山頂に登れたなら、何となくできる気がする。
翌日の天気は雨だった。風が強く吹き、嵐のように荒れ狂う雨が降っていた。それでも僕は気にせず登ることにした。どうせ死ぬのだ。僕は荷物をまとめ、できるだけの防水対策をして山頂へ向かった。
さすがにこの悪天候の中登ろうとする人は他に居なかった。
あぁ。ここで死ねるならそれもいいな。とそんなことを考えながら登っていたがとてもここで死ぬとは思えなかった。
気付けば周りが全く見えなくなっていた。数メートル先しか見えない。それでも進む道だけはわかっていたから、遠慮なしに進んだ。
出発から3時間ほどかけてようやく山頂にたどり着く。
何回か休憩をはさんで来たものの足場が悪かったのでかなり疲れてしまった。
山頂というと、雲の上にあるので永遠に晴れなのかと勘違いしていたが、全くそんなことは無く、天気は曇りだった。
しかし山頂に登った事には変わりない。これで心置きなく死ぬことができる。そう思った僕は下山を開始した。
下山の途中、天気は回復し、太陽が顔をのぞかせた。
山頂が晴れていたら、良い景色に感動して死ぬのが馬鹿らしくなっただろうか?
いや、多分そんなことは無い。
とある人が純粋に生きたいと思うのと同じように
僕は純粋に死にたいんだ。
この気持ちが変わることはいい景色を見たくらいじゃあな…
下山した後、僕は近くのホームセンターでロープを買った。
今夜、人気のないところに行って死ぬことにしよう。誰もいないところで首を吊る。
首吊りにしたのは自分が逃げられないようにするためだ。痛いのは嫌だが、仕方ない。確実に死ぬためだ。
夕方、僕はコンビニで最後の晩餐を買う。おにぎり二個とプリンとシュークリームを買った。加えてティラミスも買った。悔いは残さないように。判断が鈍ってしまうだろうから。
終わりが近づく。
この人生も今日で終わりだ。
自分はずっといらなかったんだ。
もう自分は楽になりたいんだ。
これが正しい選択だっ――
「あの!」
声が聞こえる。街中で人がまばらにいたので、まさか自分ではないだろうと思いそのまま歩く。
「あの!大丈夫ですか。」
え?
声の方を見やる。大学生だろうか?私服を着た女性が立っている。
「…僕?ですか」
「『僕』、ですね」
「…」
「…」
驚きのあまりどぎまぎしてしまう。
「だ…大丈夫では…ないですね…でも、もういいんです。声をかけていただいて、ありがとうございます」
そう言って立ち去ろうとした。
「すごく、悲しそうな顔、してますよ」
思わず足を止めてしまう。
どうしよう…なぜこの人はこんな人間に話しかけるんだ?
声をかける人なんて他にもたくさんいるじゃないか…!
「話を、聞かせてくれませんか」
迷う。自分はどうすればいい?
いや、でもここで断ったらこの人を傷つけてしまうかもしれない。もし傷つけてしまったら悔いが残る。そしてそれは死への判断を鈍らせる。
「……わかりました。いいですよ」
「よかった!じゃあ行きましょう」
「…どこへ?」
「あなたの家へ」
「…いや、自分の家ここから遠くて、新幹線で来たので…」
「え?そうなんですか。じゃあ私の家でいいですよ」
「…わかりました。…え?」
僕は駅のロッカーから預けてあった荷物とロープを取り出して彼女について行った。
話を聞くところによると、彼女の名前はエリサで大学生で自分と同い年らしい。
僕はコンビニで買った、最後の晩餐を食べながらエリサに尋ねる。
「なんで僕に話しかけてくれたんですか?」
「それは…さっきも言ったでしょ――」
「嘘ですよね」
「嘘じゃないよ」
すぐに予想外の返答が返ってきた。
「いや…自分はあまり感情を顔に出さない人間なので…多分それはないかと思いまして…」
「…敬語使うのやめてよ」
「ごめん…あんまり同世代の人と話すの慣れてなくて」
「でも理由はもう一つある。悲しそうな顔してたっていうのが一つ。もう一つは…話したらユイは怒るかも…」
「絶対怒らないよ。言ってください」
「イベントが欲しくて…」
「イベント?」
「うーんとね。もっと簡単に言うと刺激が欲しかったんだ。人生に。ほら、たいていの人生ってつまらないでしょ」
僕はここ最近の生活を思い出す。
「まぁ…」
「だから適度なスパイスを入れてあげなきゃいけない」
「…!スパイス…」
脳裏にちらつくいじめの光景。
「そういえばなんでタケはそいつを殴るんだ?」
面白半分に僕を殴る奴の隣にいる奴が言う。その子は
「人生が物語ってことはよう、こういう漫画やゲームみたいなアクションの要素が必要なんだよ。俺の親父も言ってたぜ。人生にはスパイスが必要だって」
苦しい。呼吸が荒くなる。
「君も…僕を痛めつけるの?」
「え?痛めつけ――」
「嫌われたくない…嫌われたくないけど…やっぱり痛かったし…辛かったんだ。ごめん。やっぱり帰るよ…」
僕は立ち上がって帰ろうと――
「待って!」
手をつかまれる。
「…」
「また悲しそうな顔、してるよ。傷つけないから」
「いやでも…」
「ずっと苦しかったでしょ。私、分かるんだよ。表情からその人がどんな生活を過ごしてきたか。それもあって心理カウンセラー目指してて…
ごめん。人生変えるような出来事が欲しかったっていうのは本当。けどもう一つ理由がある。それはさっきも言ったけどあなたが本当に悲しそうな顔をしてたから。話してよ。ユイのこと。話すことで楽になることもあるかもしれない。それに」
エリサは僕の眼をじっと見つめる。
僕は思わず目を逸らしてしまう。
「私はあなたの話を聞きたい」
気付かなかった。最近、人の顔をまともに見ていなかったことに。
人は自分か他人の二種類だと思っていた。
でも、この人は違う。
少なくとも僕のことを気遣って話しかけてくれた。
今まで誰も助けてくれなかったのに。この人は今日会ったばかりの僕を部屋にまであげてくれた。
何をするかわかったもんじゃないのに。
「…僕は――」
僕は自分の生い立ちを話した。
両親が既に他界していること。父親から虐待を受けていたこと。それでも父親に褒められたかったこと。努力が実らないことが多かったこと。
そして、今夜死のうとしていたこと。
彼女は不思議な存在だった。これまでに会った事のない存在。僕が全く人と話してこなかったからかもしれないが。不思議と話したくなってしまう。心の鎖がひとつひとつゆっくりと取れていく。心が軽くなってくる。
僕は…殺していた。
嫌だと拒否する自分自身を殺していた。
エリサはもう殺さなくていいといった。
「君を傷つけてしまうかもしれない」
「ユイが傷つくくらいなら自分が傷ついた方がいい」と言った。
僕は決してそうは思えなかったけど、そう言ってもらえるだけで嬉しかった。
エリサが泊ってもいいといったが、僕は迷惑をかけたくないから宿でも探すよと言ったら、いいから言葉に甘えときなさい。と強く勧められた。
僕は断ると彼女を傷つけてしまうかもしれないと思ったから言葉に甘えることにした。
自分はソファで、エリサは布団で眠る。眠りにつこうとするとエリサは言った。
「ユイに話しかけて本当によかった。フィクショニズムには感謝しなくちゃね」
「フィクショニズム?」
「うん。うーんと。簡単に言うと人生は物語と捉えることによって幸福を見出す…みたいな。ほら、だいぶ前だけど『虚構理論』ってのが有名になってたじゃんニュースとかに取り上げられてすごい賞を取って」
「ニュースはあまり見てこなかったから…」
「まぁいいや。とにかくユイに話しかけられたのはそれのおかげだったんだよ。人生が物語なら私もできるかぎり面白い物語を生きたいって。まぁフィクショニズムはもはや流行語だからね~大学の人もみんな言ってるよ。たまにそういうのちょっと怖いとも思うけど。けど、『物語は人を幸せにする』っていうあの一連の話を聞いた時、なんか感動しちゃったんだよね」
「…なるほど。そんな風に考えたことなかったよ」
人生は物語。
物語は人を幸せにする。
自分は考えすぎていたのかもしれない。
僕は翌日フィクショニズムについて調べた。
すると今や物語は大半の人には欠かせないものとなっているらしく、時には物語が高値で売買されることもあるということがわかった。
エリサに自分の人生を物語として売ることを相談した時、彼女は賛同してくれた。
不純な動機としてまだ返しきれていない奨学金を返済したいというのもあったが、何より自分の物語で自分と同じ環境下にある人が死なずに生きてくれることを願っての行動だった。
出版社に物語の構想、というか自分の人生を話した際、
「いいね!いかにもノンフィクションらしいフィクションだ!売れるよ!」とサングラスをかけた怖そうなおじさんは言ってくれた。
そうして僕の人生は物語として売られることになった。
映画、小説、漫画。あらゆるコンテンツで僕の物語は大ヒットし、これまでの人生で見た事のないような金額が懐に入り込んできた。自分は頭の良いエリサにもらったお金の管理を任せることにした。彼女はお金に関しては厳格な性格らしく、実に巧みにお金を減らさずむしろ増やすよう管理をしていた。自分には興味もなく理解することもできない分野だったので、エリカに感謝した。
物語は人を幸せにする
いいことも悪いことも全部含めて。
いや、含むからこそ物語は美しいんだ。
多分、僕はずっと幸せだったんだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
