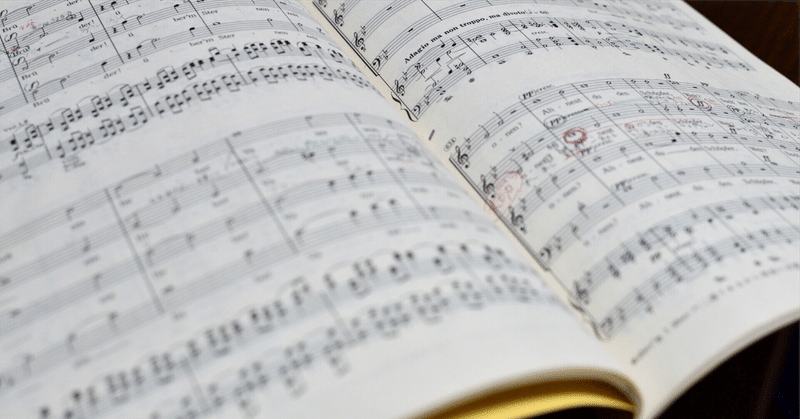
生まれてこの方音楽推しですっ!!〜音楽を推すとは〜 その2
↑↑前回の記事はこちらからお読み下さい↑↑
音楽を構成する要素1…作曲
作風=推しメン?
さて、音楽が成り立つための最初の要素である「作曲」について考えてみよう。
一般的には作曲を専門に行う作曲家と呼ばれる人がいる。音楽にはある程度ルールがあって、そのルールに則って新たな作品を生み出すことは素人にとって簡単なことではない。
ここに音楽を「推す」ことと一般的な「推し」との共通点があるように思う。それはファンにとって好意の対象となるものはそう簡単に手出しできない領域である点である。
これだけでは「推す」理由にはなりづらいが、ただ一般的な「推し」は対象となる事物が自分にはないもの、または自分より優れているものを持っていることはほとんどのものについて共通だろう。
では少し話を進めてみよう。
作曲家が生み出す旋律は時代、地域、作曲者の置かれた環境など様々なバックグラウンドが混ざり合って作られる。
しかしこのように音楽は複雑に構成されたとはいえ(普段から音楽によく親しむ人なら分かると思うが)、作曲家、作曲された時代・地域によってある程度系統や癖、特徴などが表れる。
これを読んでくれる方も、「このバンドが書く曲って全部一緒に聞こえるんだよな〜〜」という経験はないだろうか。これらの系統や特徴というものが音楽オタクからすれば楽曲の好みに繋がるのである。
ここで気をつけて頂きたいのが、今「推し」の対象になっているのは「作曲家本体」ではなく【作曲家の作曲した曲の雰囲気】であるという点である。(広義で考えたら「作曲家」=「作風」になりそうではあるが。)
なぜなら、「作曲家本体」はつまり3次元の人間であるから一般的な「推し」と変わらないからである。
音楽の推し方も多様なので一概には言えないが、少なくとも私はこの世に溢れた音楽の中にも、アイドルグループの「推しメン」にあたる作曲家や流派などがある(がここで語り出すと日が暮れるので割愛する)。
楽曲=メディア?
その上で、同じ作曲家、時代によっても勿論楽曲によって表現したいものや趣向が変わってくる。
あまり例えが上手ではないが、ある作曲家の作品たちを一人のアイドルとした場合、それぞれの楽曲はアイドルの見せるかっこいいところ、可愛いところ、セクシーなところ、といった表情にあたるのである。その表現の仕方は作曲家の腕にかかっているのだが、例えば長調か短調か、速さ、強弱、そしてどのような楽器を用いるかなどで作品の雰囲気は大きく変わるのである。
これらの特徴だけでも勿論雰囲気が変わるのだが、さらに言えばこのような楽曲の構成要素を用いてある種のメッセージを送っているのである。
哲学者マクルーハンは「メディアはメッセージである」と述べたが、ここではメディア、すなわち伝達手段も既に発信者からのメッセージであるということである。
例えば誰かに謝りたい時にLINEで済ませるか、自筆の手紙を書くか、対面で直接伝えるかで謝罪の意味合いが変わってくるのは日常生活を送っている上で身をもって実感していることだろう。これら楽曲の構成要素はメディア(=伝達手段)であり、ここで敢えてこの楽器を使うということは作曲者が演奏者に対して、ひいては鑑賞している我々に対してどういうことを表したいかを十分に伝えうるのである。
最後の方は話がずれてしまったが、つまり、作曲された音楽、旋律には実体はないが、様々な楽曲に作風などの特徴を見出し、それぞれの楽曲に作曲者からのメッセージを感じ取ることで音楽や旋律そのものにも十分魅了されうるのであり、これが推しの対象になりうるのだと思う。
次回の記事もお楽しみに
note初心者なので最初の記事を見てあまりに見にくくて絶望しました。。。工夫しつつも全然上手な書き方が分からないのですが、もしまた時間があれば読んでくれる人がいたら嬉しいです涙
次回は「演奏」について語るつもりです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
