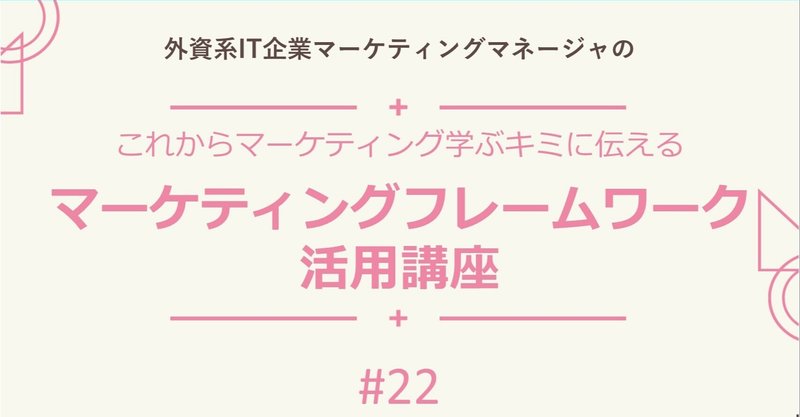
#22. 3C分析におけるVRIO分析の活用:マイケル・ポーター教授のフレームワークは正しくない!?
マイケル・ポーター教授は、経営戦略論やマーケティング理論を勉強した人なら誰でも知っている著名な経営学者です。フィリップ・コトラー教授、ピーター・ドラッカー教授と並ぶ、ビックスリーの一人だとボクは思っています。
そのマイケル・ポーター教授の考え、理論、フレームワークは、ボクの「マーケティング・フレームワーク・フロー(MFF)」で多く取り入れさせて頂いており、絶対的なものだと認識していました。また、僕自身、ポーター教授を尊敬するとともに、そのフレームワークの実践者、信者と言ってもいいぐらいその有効性を信じてやまないぐらいでいました。
そんなポーター教授のフレームワークは、「ポジショニング派」と呼ばれ、ジェイ・B・バーニー教授の「ケイパビリティ派」と、1990年代に論争になっていた。そして、ポーター教授の「ポジショニング派」が破れた。と、いう記述をここ1週間で立て続けに読みました(聴く読書をしました)。
マーケティングフレームワークの連載noteを書いているのに、1990年代のこの論争のことを今更ながらに知るという間抜けさは否定できません。しかし、ボクにとって有効としか思えないフレームワークが「使いモノにならない」というのは聞きづてなりません。ボクのMFFの有効性にも影響を及ぼしかねない問題です。
そこで、バーニー教授の著書を読むとともに、この論争の内容を早速調べてみました。本noteでは、このことについて書いていきたいと思います。
ーーー
本noteは、ポートフォリオワーカー*になった、外資系IT企業マーケティングマネジャーによる、『初めてマーケティングを学ぶキミに伝える マーケティングフレームワーク活用講座』の連載企画です。
*「ポートフォリオワーカーって何?」は、こちらを参照下さい。自己紹介とともに説明しています。
前回はこちら、最初から読まれる場合はこちらからどうぞ。
ーーー
ポーター、バーニー論争
調べていくと、このサイトが端的に論争の内容をまとめているようでした。
本サイトのまとめをさらに、ピンポイントでまとめてみると、
ポジショニング派
ファイブフォース分析/マイケル・ポーター
「業界内の競合他社と比べて、自社がどのような製品・サービスを顧客に対してどのように提供していくかが重要」
ケイパビリティ派
VRIO分析/ジェイ・B・バーニー
「企業の競争優位に重要なのは、製品・サービスのポジショニングではなく、企業の持つ経営資源をどのように活用するかが重要」
「どちらが、企業業績に対して持続的な競合優位を構築する寄与度が高いか?」調査結果
✔約15%:ポジショニング派
業界ごとに異なる何らかの要素(例えば、業界構造や規制環境等)が寄与
✔約45%:ケイパビリティ派
特定の企業や事業に固有の何らかの要素(例えば、経営者の能力、保有技術、営業チャネルなどの内部資源の違い)が寄与
✔40%:不確実性
要は、どちらとも断定できない、という意味
とのことでした。ポーター教授の「ポジショニング派」の敗退ですね。。。
そもそも不勉強なボクは、ジェイ・B・バーニー教授も、教授が提唱したVRIO分析も、その著書「企業戦略論」も全く知りませんでした(VRIO分析は単語として見たことはありました)。早速、書籍を購入して、新たな考えに触れてみました。
バーニー教授はバリューチェーンを評価している!?
この論争をコメントした本(後述)やサイトでは、バーニー教授はとことんポーター教授の「ポジショニング派」を否定しているように感じました。しかし、読み進めていると(聴く読書をしていると)、「あれ?ちょっと予想と違うな」という感じをいだきました。バーニー教授はポーター教授のバリューチェーン分析をとても評価しています。
ファイブフォースのポジショニングについては、それよりも「ケイパビリティが重要」と主張されていますが、バリューチェーンは有益なツールと書かれているのです。その部分の引用です(太字はの~ち追加)。
なお、バーニー教授は「経営資源という語とケイパビリティという語は同義語として扱う。」と明記されているので、この定義でお読み下さい。
企業にとって競争優位を生じさせる可能性がある経営資源やケイパビリティを特定する方法の1つは、バリューチェーン分析(value-chain analysis)を行うことである。たいていの製品やサービスは、垂直的に連鎖する事業活動によってつくり出されている。すなわち、原材料の獲得、中問製品の製造、最終製品の製造、販売と流通、販売後のサービス等である。
バリューチェーンを構成する各ステージそれぞれに、財務資本、物的資本、人的資本、組織資本が関わっているのが一般的である。
バリューチェーン分析を行うことにより、企業の経営資源やケイパビリテイが非常に細かいミクロレベルで考察されることになる。経営資源やケイパビリテイをより概括的な大きなレベルでとらえることもむろん可能である。しかし、ある企業が営む個々の活動が、その企業の保有する財務・物的・人的・組織資本の組成にいかなる影響を与えるかを仔細に検討することのほうが、えてして有効な分析を提供してくれる。より細かなレベルで分析を行えば、企業の競争優位をもたらす源泉をより詳細に考察できるようになる。さらに言えば、この後明らかにするように、上述の細かなレベルの分析により、その企業がバリューチェーン上のある活動に関しては競争優位を保持していると同時に、他の活動では競争均衡に、さらにある活動では競争劣位に甘んじている、といったことも理解できるようになる。これは、企業の経営資源やケイパビリティをミクロレベルで理解すべきことのみならず、競争優位という概念がこのレベルでも適用可能であることを意味している。
特に最後の太字部分「その企業が~理解できるようになる」は、ポーター教授と全く同じ意見です。各バリューチェーンにおいては優位や劣位があっても、バリューチェーン全体で競争優位が構築される、という意味です。
この引用部分のみで、バーニー教授の主張をまとめ上げるのは少々強引かもしれません。しかし、ボクは、ビジネスからプライベートまで戦略立案を日々実践しているいちプロダクトマネージャーとして、次のように解釈するのが有益だと考えました。
バリューチェーン分析において、ケイパビリティ視点であるVRIO分析の考えを取り入れるべき
はい、これだけです。
本連載で説明している通り、バリューチェーン分析は、3C分析のCompetitor/Company分析において、なくてはならないフレームワークです。それを業界特有の形にカスタマイズすべきことは、ポーター教授も主張しているところです。それをあえて4P視点を予め入れ込んだ形にして、後々のSWOT分析や4Pにおいても活用しやすいようにしてしまえ、というのがボクが提唱するカスタマイズド・バリューチェーン(CVC)です。
そう、フレームワークなんて、なにかに固執することなく、臨機応変にいいとこ取りすればいいのです。
ここでバーニー教授のVRIOの有効性、それをバリューチェーンで実施することで、その精度がより高まることを知ったなら、それを採用してしまえばいいのです。
リソース・ベースト・ビュー(RBV)/VRIO分析
「リソース・ベースト・ビュー(Resourced Based View:RBV)」は、企業のケイパビリティに基づき戦略立案をするアプローチ」とのことです。そのフレームワークが、VRIO分析だそうです。
VRIOは、経済価値( Value )、希少性(Rarity)、模倣困難性(Inimitability)、組織( Organization)の4つの評価区分の頭文字をとり、名付けられています。

要は、「”希少性があり、模倣が困難で、組織的にそれを実現できて、経済価値、つまり利益が出ていれ”ば、その競争優位な状態を持続的に維持することができる」可能性が高いということです。
ここまで書いていて、ふと、疑問がよぎります。
「VRIOは何のために行うの?」
図の「競争優位の状態」を見てみるとわかります。「持続的競争優位」が最上位の評価基準です。また、ポーター/バーニー論争の調査結果をみていると、「企業業績に対して持続的な競合優位を構築する寄与度」を判断しています。
そう、VRIO分析は、「持続的な競争優位の構築の分析」のために行います。
「なにを今更! 昨日今日知った内容を書いているから、訳のわからないことをいい出している。。。」と、思われたあなた!
「昨日今日知った」は正しいのですがw、VRIO分析をボクのマーケティング・フレームワーク・フロー(MFF)のどこに入れるか、つまり、どのタイミングで実施するかを考えた際、もしかしたら、このVRIO分析は使えないかも、とも思い出しているのです。
なぜかというと、VRIO分析は「持続的な競争優位の構築の分析」のために行うものです。競合優位性を構築するために行うのではなく、それが出来上がった後に、その状態が持続的に維持できるかを分析(判断)するためのフレームワークと解釈できるからです。
そう、つまり、「売るためのフレームワークではなく、売れている状態を維持できるかを判断するためのフレームワーク」なのです。
この視点は、企業がゴーイングコンサーン、継続し続ける前提であるために必要な視点です。また、製品/サービス開発、あるいは企業発足時からこの視点をもつことは重要です。
しかし、まずは、製品/サービスを売るためにどのように戦略構築するかを考えることが重要、とボクは考えます。
顧客は、製品/サービスを購入する際に、このCompany(自社)の競争優位の持続性は考慮しません。「この会社の製品/サービスを買って大丈夫かな? 潰れないよね?」は当然考慮されます。サポートなどのアフターサービスの”重要度/重み”が多い場合は、なおさらです。
しかし、その判断は、顧客から見えるバリューチェーンを構成するひとつの検討項目でしかなく、「競争優位の持続性」だけでは判断されないはずです。
顧客は、「意識する、しない」はおいておいて、無意識のうちに複数のカスタマイズド・バリューチェーン(CVC)で取り上げた各VCの内容を、競合製品/サービスと比較しながら吟味します。そして自社、競合のCVC全体を総合的に判断し、「買う、買わない」の判断を行っています。
そう考えると、このVRIO分析の視点は、明示的に「”持続的な”競争優位」と使用目的が限定されているように、競争優位を確立させる方策を見出した後、あるいは、その方策を見出そうとしている際の、チェック項目として使用した方がよさそうです。
マーケティング・フレームワーク・フロー(MMF)の中においては、SWOT分析のSW(強み/弱み)を分析、判断する際と、Cross-SWOT分析の際に、持続的な競争優位が確立できるかを判断すると良さそうです。
実際に、Cross-SWOTでは、現状(As-is)の状態を理想の状態にするための施策を検討します。その判断基準として、VRIOの自社ケイパビリティ、希少性、模倣困難性、さらには実際にそれを実現できる企業体力があるか、を判断するのがよさそうです。
ボクのMFFでは、Cross-SWOT分析時に、明確には行っていなかったVRIO分析を追加しようと思います。
3C分析のおけるVRIO的視点
VRIO分析はCross-SWOT分析時に行うのに、3C分析を解説している途中で、このnoteシリーズに挟み込んできたのには実は理由があります。
自分が新たに知ったことなので考えをまとめておきたかった、という理由もあるのですがw、それよりも、VRIO的視点は競合分析をする際にも常に持っておくべきと考えたからです。「希少性」、「模倣困難性」の視点は、3C Competitor/Company同時分析においても、考慮すべきポイントなのです。
具体的には、Competitor/Company同時分析を行う時点で、競合あるいは自社が、各バリューチェーン項目で、希少性、模倣困難性があるかを判断すべきです。
実際に、数回前からの3C分析の解説の「ノートPC」および「B2Bソフト」で、無意識でこの「希少性」と「模倣困難性」を判断ポイントとして使用していました。しかし、重要なポイントであるにも関わらず、無意識で行っており、解説は行っていませんでした。ダメですね。。。
そこで、このnoteで追加解説を行います。
前回noteでは、Competitor/Company同時分析を行う際のポイントとして、「自社と競合がとっている施策の差を忠実に書く」と指摘しました。ここが、「希少性」と「模倣困難性」を無意識に使っているところでした。
「B2Bソフト」のCVCで解説したいと思います。CVCの「競合」コメントの囲み部分に注目して下さい。
k

赤い囲みの「知名度バツグン」「代理店100社」は、「希少性」と「模倣困難性」両方がある例です。自社が競合と同じような状態を得ようと思った場合、時間的、資金的コストは相当掛かることが予想できます。この部分は、真似しようと思っても簡単には真似できません。競合が長い時間をかけて獲得した経営資源です。
一方、青い囲みの「本社が日本にあり充実」は、外資系ITベンダーが多くを占める中で、「日本に本社がある」というのは「希少な価値」ではあります。しかし、「日本にある」だけでは、価値とはなりえないので、注意が必要です。「日本にある」ことによる、なんらかの価値を提供していなければなりません。例えば、「競合が英語サポートだけしか提供していない」のに「日本語によるサポートを提供している」とかです。
明示はできていませんでしたが、この「希少性」と「模倣困難性」が、想定顧客の「重要度/重み」と合致した時は、製品/サービス購入決定において、大きく寄与をすることになります。

「流通」VCの「代理店100社」は、「販売の強さ:93.5」における約25%の寄与度があります。
「競合」と「自社」の販売量は、単純に「販売の強さ」の比率ではありません。「流通」の「顧客」にとっての「重要度/重み」が高いだけに、「自社」と「競合」のスコアである”10”と”25"という、2.5倍の差の方が、より現実の販売量の差に近いように感じます。
そういう意味においても、「希少性」と「模倣困難性」は、明確に取り上げるべき内容であったと反省し、今回のnoteで書かせて頂きました。
VRIO分析自体は上述したように、Cross-SWOT分析の際に再度登場させたいと思います。
参考文献(本議論をボクが知った本)
いずれも2021年5月現在Kindle Unlimited対象!
名古屋商科大学のMBA実況中継は、なかなかいいですね。4月にこの01、02がKindle Unlimited対象でしたが、スルーしておりました。5月にはKU対象外になってしまったので、ちょっと悔しい思いです。この流れで行くと、現在KU対象の03と04も6月にはドロップしてしまう可能性があるので、ボクの「Kindle Unlimited合法的保存法」で保存するのをオススメいたします。
「3000年の叡智を学べる 戦略図鑑」はパラパラ見て、認識していない「戦略」を確認するのはいいかもしれません。ボクはおかげさまで、バーニー教授の考えと「ファイブウェイポジショニング戦略」なるものを新たに知りました。
バーニー教授の本はすでに「聴く読書」とポイント部分は精読。下巻は、大企業向けなので、ボクには不要と判断し、購入せず。ファイブウェイポジショニング戦略は、これから「聴く読書」をする予定です。
念の為、Kindle Unlimitedのリンクを貼っておきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

