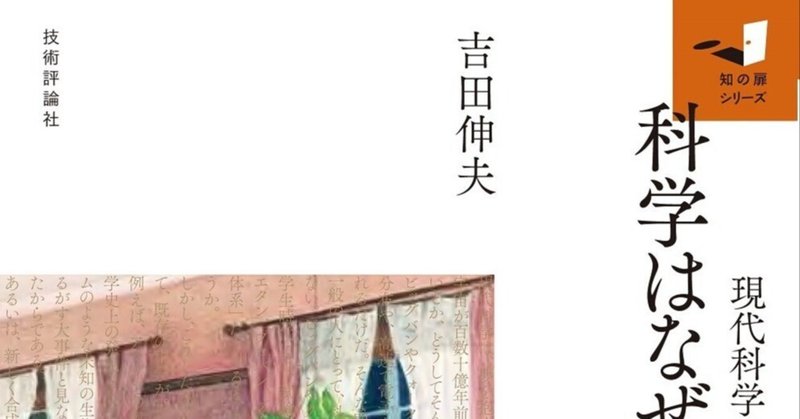
【書評】科学はなぜわかりにくいのか【基礎教養部】
科学はなぜわかりにくいのかというタイトルであるが、そこは全く本質ではない。小さく書かれているサブタイトル、現代科学の方法論を理解する、が本質的な内容である。とはいえ、タイトルを決めるのは本人ではないことが多いので、筆者に何かを言いたいのではない。単にタイトルが内容の本質を示していないということを言いたいだけである。サブタイトルをタイトルにしてもらいたいが、それでは売れないのかどうか。
肝心の内容は、恐竜の絶滅に関する論文、アルヴァレズらが提出した小惑星衝突説の論文を追うことで、現代科学の手法、その手法をとることによって得られる科学の信頼性、妥当性を示そうとするものである。論文の論旨、データ、そこから派生する歴史的な議論を丁寧に読み解いているので、示そうとしたことは成功していると言っていい。内容としては小惑星衝突説を扱った第1章と第2章の前半部分でほとんど完結している。あとは具体例、補足、科学の限界、科学の付き合い方などが続く。
書評はこのくらいにして、後は科学について考えたことを述べる。科学とは何か。遠い昔、大学で物理を学ぼうと思っていた頃、そして大学で物理を学んでいた頃、科学とはこの世の真理を追求する学問であると思っていた。当然、今はそれが勘違いであることは知っている。しかしなぜ当時はそう思ったのか。
科学とは、ある限定された空間内部での妥当性を示す学問である。重要なのは「限定」と「妥当性」だ。限定から外れれば効力を失う。また、妥当性であるがゆえに、科学は真実ではない。多分、おおよそ、きっと、ある程度の信頼性がある。大体において正しい。科学はそこまでしか言えない。絶対に100%正しい。それは科学ではない。別の何かだ。なぜ科学は100%正しいとは言えないのか。まずこの世に100%正しいことなど、脳みその中で作った世界にしかないのだが、それは置いておくとしても、科学に関して、絶対正しいと言えない理由はなにか。科学の根本には証明不能な「原理」がつきまとっているからである。原理とは、何か知らんけど成りなっている、この世の決まり(と人間が勝手に思っているもの)だ。原理は観測事実、実験事実に基づいてはいるが、それ自体は経験則であり、証明できないがゆえに、絶対正しいとは言えない。絶対正しいとは言えないものから、各種の法則を導いたとしても、各種の法則が正しいとは言えない。演繹は前提が100%正しい時にだけ結論が100%正しくなる。科学はその前提が経験則の原理である。原理は100%正しいとは言えないのだから、当然あらゆる結論も100%正しいとは言えないわけだ。妥当性とはそういうことだ。科学の限界である。
この考えに従うと、当時の勘違いの理由が浮かび上がってくる。勘違いの理由は、我々が普段「限定」と「妥当性」の中に閉じ込められて生きているからだ。いや、自分がその空間内に勝手に閉じこもっていた、という方が正しい。空間の内部において、科学はほとんど神の如き力を持つ。神の下で生きていれば、全てが自分の思い通りになるような錯覚する。安心できるのだ。楽に生きられるとも言える。しかし、世の中、科学が支配する空間の外の方が広い。私はそれを知らなかった。
科学は強力な武器である。限定された空間では神に近い。人は神を支配して、全てを神の予測可能な空間に押し込めようとした。その正体が、私の文章では何回も何回も言及している、「都市化」、あるいは「脳化」である。神が支配できないものは全て排除していけば、神はより全能となる。都市とはそういうものだ。かつての私の姿でもある。世界考察で取り扱っている能力主義なる概念の設計図も、この神の設計図に近い。ゆえに能力主義の問題点は、都市の問題点でもある。
科学と正しく付き合う方法は、科学が限定された空間内の妥当性を示すツールにすぎないことを常に意識することだ。私は、それらが意識されていない言説は、疑ってかかるようにしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
