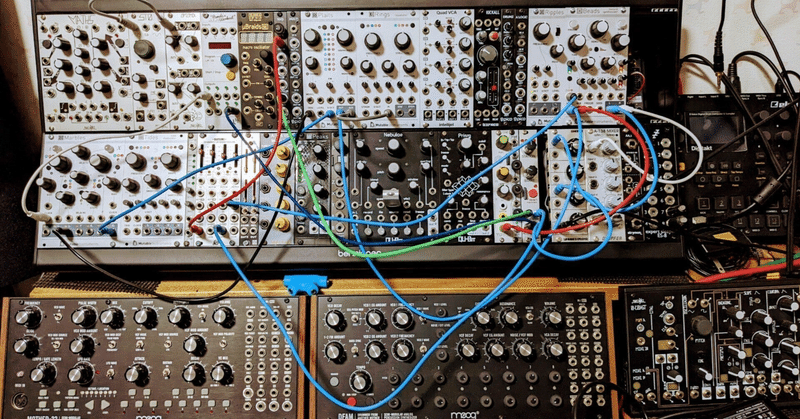
404 NOT FOUND(サンプル)
2023/9/10の文学フリマ大阪11でお披露目する作品の冒頭です。
会場は大阪府OMMビル2F。(最寄駅大阪メトロ谷町線・京阪電車天満橋駅)
弊サークル「蓮花」はK-29でお待ちしております。
A5版112ページで予価1000円です。
お手にとっていただけることを心から願っております。
いつものように僕はステージ下手の奥に陣取った。規則的なマシン・ビートが舞台を満たす。クラフトワークの「コンピュータ・ラブ」。僕らのバンドのオープニングを飾るいつものSE。僕は相棒の調子を確かめるように鍵盤を叩く。闇に場違いなきらきらした音が、Gの音程で鳴った。
ギターのトモがすぐそばで眉をひそめるのが、暗がりでもわかった。わざわざアンプを切ってチューニングしている彼からすれば面白くないだろう。小さな舌打ちが聞こえた。
そんな小競り合いは我関せずとばかり、ボーカルのタクミはご機嫌だった。リハのときから浮かれてたもんな。新しい彼女ができたって。さて、今度の子はいつまでもつかな。
ドラムのサクヤがバスドラとクラッシュ・シンバルを鳴らすと、ベースのリヒトが応えて指で弦を叩いた。
万全ではないけど、僕らの準備は整った。
オーディエンスと僕らを隔てていた黒いカーテンが、さあっと左右に引かれる。もろに歓声を浴びたタクミはご満悦だ。
「こんばんは、『タブラ・ラサ』です!」
サクヤがスティックでカウントを取る。リヒトが合わせてうねるベースラインを刻む。僕とトモも負けじと旋律を重ねてゆく。
タクミの声が放たれるやいなや、最前列の女の子たちが嬌声をあげる。
さあ、ここからは僕らの時間だ。
夜はまだ始まったばかりだった。
やっぱりアルコールは得意じゃない。
飲めないわけじゃないけど、好きでもない。無理にハイになるのは、次の日にこたえる。
なんて弱音を吐く僕はまだ二十五だ。いや、もう二十五なのかな。どっちだっていい。
僕の名前は碓井誠。「タブラ・ラサ」ってバンドでシンセサイザーを担当している。まあ、まだインディーズでくすぶっているけど。これでも、小さなライブハウスくらいなら、そこそこ埋められるくらいの動員はある。
華々しいことを言っても、世間的には僕はまだ何者でもない。ただのミュージシャン未満だ。
上京して七年、いろんなバンドを渡り歩いた。中にはメジャーデビュー寸前までいったところもあるけど、僕の方の辛抱が切れたなんてこともあった。今のバンドは……そこそこ気に入ってる。答えに間があったって? 鋭いな。
音楽性は及第点だけど、人間関係がめんどくさい。特にボーカルのタクミとはうまくいってない。どうしてって? またききにくいことをきくなあ。はっきり言えば、タクミはとびきり女癖が悪い。ファンを食う暇があるなら、ボイストレーニングにでもいけばいいのに。
タクミみたいなのがいるから、バンドマンの信用がなくなるんだよな。僕? 僕はただのひねくれ者だ。ひねくれ者だけど、そこそこ音楽はできる。と思いたい。
僕はかすむ頭を振って、中古のVAIOを立ち上げる。依頼メールが来てないかチェックしないと。
前の前のバンドに在籍しているときに、ある音楽プロデューサーと出会った。ありがたいことに僕を見こんでくれて、ちょっとした仕事を回してくれる。おかげで、CMやゲームの音楽で食いつないでいる。
「『演歌調』⁉」
だが、僕の薄っぺらい感謝の気持ちは、クライアントからの注文で消し飛んでしまった。
日本酒のCMの仕事で、メールにはまぎれもなく「演歌調で十五秒ほどお願いします」とある。これはYMOチルドレンの僕には荷が重い。でも、できないとは言えない。NOイコールクビだ。僕の代わりなんて掃いて捨てるほどいる。あわててSPOTIFYで演歌のプレイリストを呼び出す。特徴さえつかめば何とかなる。
要するに新手のペンタトニック・スケールだと思えばいい。僕は狭い部屋の中、イヤホンを突っ込んだまま、「北国の春」やら「箱根八里の半次郎」を聴き続けた。
こんな僕を、ギターのトモは「小器用」だと皮肉る。あいつ、ギタリストなのに曲が書けないから、やっかんでるんだろう。対照的に、ベースでリーダーのリヒトは僕の仕事を快く思っているらしい。
「何事も経験だからね」
ちょっと老成した感のあるリヒトは、僕より二つ上だ。
バンドマンの裏側なんてこんなもんだ。僕は昼食代わりのカロリーメイトを頬張って、音の海に沈んでいった。
だるい。
毎日つまんない。
はやりの動画見て、はやりのマンガ読んで、はやりのブランドに身を包む。
そういうの、正直疲れた。
私はそっとお気に入りのプレイリストを呼び出した。ホントのとこ、なんでこの音楽が気に入ってるのかもわかんない。だって、メロディらしいメロディはないし、ビートだってはっきりしてない。ただ、自然の音がごうごうと流れてる感じがする。
スマホでそっとそのひとのサイトを開く。
「ルナティック・シンドローム」
意味なんてわかんない。ただ、そのひとが残した音の歴史が、淡々とした文章で綴られている。
「ねー、何やってんの? 早く行かなきゃ売り切れちゃうよ!」
月一の限定フレーバー。アイスって季節でもないだろうに、なんであのコはこだわるんだろう。
友達じゃないのかって? ただの知り合い。
私に友達なんてひとりもいない。
みんなそう思ってるよ。友達なんていない、ただ私たちはゆるくつながってるだけ。
ほんとうにひとりになるのが怖いから。
「うららぁ! バス出ちゃうよ!」
ああ、うるさいなあ。私はもう少しこの音にひたっていたいだけなんだ。
「ルナティック・シンドローム」
今度辞書で意味調べてみよう。
「今行くから! ちょっと待って!」
なんで言えないんだろう。
私なんておいていっていいよって。
進路指導。
きくだけで憂鬱な四字熟語。
でも後回しにしてもそいつはずっと私の後をついてくる。わかってるよ、ただ時間をかせいでるだけだって。
とりあえず名前を書く。
中瀬うらら。
就職か進学か。ずいぶんざっくりと分けてくれるじゃん。極端なんだよね。
私は周りを見回した。みんなプリントを薄っぺらいカバンにしまっている。なんだ、馬鹿正直に今書くことはないんだ。とりあえず私もプリントをカバンに押し込んだ。
みんなはここに書くことは見つかってるんだろうか。聞きたいけど聞けない。結局、私もこわいんだ。何かにひたむきになるのが。
「うららぁ」
背中から声がかかった。
「なんだ、カノンか」
「なんだはないでしょ」
すぐ後ろの席は、いつもつるんでるグループのアタマ、三枝佳音だ。
「午後の体育、ブッチしない?」
「出とく。出席足んないから」
「変なトコで真面目だねえ」
カノンは心配じゃないのかな。自分のこと。将来のこと。多分、聞いてもはぐらかされるだけだ。
私は、カバンに詰め込んだCDウォークマンにそっと触れた。スマホでも音楽は聴けるけど、これはお守りだ。
いつも持ち運んでるこの音を創ったひとは、若くで遠くへ旅立っていった。ちょっと華奢ではかないそのひとと私の人生はほんの少ししか重ならなかったけど、私はその思い出だけで生きていける。
こんなせっぱつまった思いは、誰にも打ち明けられない。それでいい。私はこの気持ちと生きていく。
ねえ、あなたは知ってる? 「ソウ」のこと。
「トリムールティ」の「ソウ」。
ううん、私が彼を知ったときは、たったひとりで未知の音にむかっていった、ただの「ソウ」。
私も彼のようになれたら。
たったひとりで向かい風にあらがうように生きていけたら。
唱えても唱えてもしかたのないことを、私はいつまでも唱えている。
そのひとに届きますようにと、今も祈っている。
「ねーえー、うららぁ! うららぁ!」
私はまだ、ひとりになる勇気も持てないで、せいいっぱい日常を生きている。
我思う故に我あり。
フランスの哲学者、デカルトの言葉らしい。
我思う故に我あり。
僕はそれを反芻する。
デカルトという人は変わり者だと思う。神の存在証明までやったらしい。それによると、僕たちは完全者を想起できるから、完全者は存在しているということになっている。
でも、僕は思う。完全者っていうことは、その不完全性においても完全でなければならないんじゃないかって。完全に不完全な存在、矛盾している。だから僕は神を信じない。かと言って、無神論者でもない。
またつまらないことを考えている。
「柚月、問一の答え教えてくれよ」
堂々とカンニングの相談とはおそれいるね。
僕はさっきから背中をつついているシャーペンを無視した。
「こら、そこ何やってる!」
巻き添えを食うのはごめんだ。僕はひたすら目の前の解答用紙に没頭する。
その間にも、僕の頭からあの旋律は離れてくれない。
母がブックマークしていたホームページから流れてきた音のかたまり。まるで空気のように僕を包んだあの音。
その日から僕の世界に音楽は消えない。
どうせ、百点なんだろうな。
中間テストの答案を裏返しにして、僕は席を立つ。担任が見直しはしたのかとか何とか言っている。したさ。暇つぶしにもならなかったけど。
僕は鞄に筆記用具を詰めて、悠々と帰り支度を始めた。
こんにちは。
僕は柚月悟という。
都内のある私立中学に通う、中学二年生だ。
自分で言うのもなんだけど、勉強はけっこうできる。スポーツも得意だ。つまり、今いる学校という名の金魚鉢の中じゃ、あまり困ることがない。そのせいか、毎日が退屈で仕方ない。贅沢な悩みなんだろうな。
でも、僕はときどき無性に不安になる。僕は異常なんじゃないかって。同い年の連中は、ことあるごとに女の子の話ばかりしている。それにひきかえ、僕ときたら。
やめよう、こんな話。僕の話なんて面白くもない。
自分に拘泥するのは思春期の少年らしいって?
そういう考え方もあるね。でも、やっぱり面白くないよ。自我の肥大した人間の自分語りなんて。代わりに趣味の話でもしようよ。
すてきな音楽を見つけたんだ。きっかけは家のデスクトップパソコンだった。学校の課題をまとめるために、ネットで調べ物をしていたときだった。
ブラウザにブックマークが無造作についていた。多分母のだ。父なら自分のノートパソコンで用は済ませる。
とにかくそこに、変な名前のフォルダがあったんだ。
「TRIMURTI」
妙な単語だ。トリムルティって読むのかな。僕はグーグルにその文字列をそのままタイプした。
出てきた英和辞典には「三神一体」と表示されていた。
「三神一体:後期ヒンドゥー教の三神格」
ちょっと心配になってきた。うちの母親はありふれた平凡な主婦だ(と思う)けど、おかしな宗教にハマっているのかもしれない。怖いもの見たさでブックマークフォルダをクリックした。フォルダには三つホームページが格納されている。その一つに目が止まった。
「ルナティック・シンドローム」
「狂気症候群」とでも訳せばいいのかな。なんだか香ばしい。僕は意を決してそのページに飛んだ。どうやら、あるミュージシャンのホームページらしい。洗練されたデザインの中に、動画が一つ埋め込まれていた。
痩身の年齢不詳顔の青年が小さい窓の中で鍵盤に囲まれていた。ままよとばかりに動画をクリックする。
そこからあふれてきた音楽は、僕の知っているどんな音にも似ていなかった。とても抽象的で、それでいて大気のように穏やかで、自然で。十分以上もある動画だったけど、僕は時を忘れてそれに吸い込まれていった。
動画の終わりに「作曲・編曲:SOW」と短い字幕が現れた。「ソウ」って読むんだろうか。
以来、僕は電信の海をさまよって、「ソウ」のことを調べ続けている。得たのは、彼が「トリムールティ」というユニットにいた情報と、いくつかの音源だけだった。
もしあなたが「ソウ」のことを知っているなら。
どうか僕にも彼のことを教えてほしい。
「取材、ねえ」
「そう構えることはないよ」
「ギャラは?」
「ない。載せてもらえるだけありがたいと思わないと」
真っ昼間の喫茶店の一角で、「タブラ・ラサ」の緊急ミーティングが開かれている。野郎五人が固まって座っている絵面は、なかなかに熱苦しい。
リヒトがブラックコーヒーを冷めるに任せて切り出したのは、とあるミニコミ誌からの取材のオファーについてだった。
正直、僕はあんまり乗り気ではない。きっと時間のわりには大した記事は載らないんだろう。反対に、がっついているのはタクミだ。目立てれば何でもいいってやつだからな。トモとサクヤはそんなに自己主張しない。
「マコトはどう思う?」
リヒトはよく僕に意見を求める。仕切っているのはリヒトだから、彼が決めればいいだろうに。
「リヒトがいいならいいよ」
「本当に?」
見透かしたように僕の目を覗く。参ったな。
「うーん、今時ミニコミねえ。配布数どれくらい?」
「五百は下らないって話だけど」
「リヒトらしくないなあ。そんな眉唾な話に乗るの」
「はい、出たよ、マコト先生の慎重論が」
僕とリヒトにタクミが割って入る。
「その『先生』っていうの、やめてくれないかな。僕は今リヒトと話してるんだ。邪魔しないでくれる?」
「まあ、二人とも落ち着けよ」
まったく、リヒトがいなけりゃ、とっくに空中分解してるぞ、このバンド。
「今、『タブラ・ラサ』は正念場を迎えてる」
リヒトが神妙な口調で告げると、僕もタクミも聞き入るよりほかなかった。
「動員は横ばい、レコーディングのめども立ってない。正直、資金繰りも厳しい。ライブのギャラを次のライブに充てるので精一杯だ」
皆黙り込んでしまった。マネジメントだのブッキングだの、こみ入ったことはリヒトにおんぶにだっこだったからな。
「石油王でもスポンサーについてくれないかなー」
「茶化すな」
軽口を叩いたタクミがたしなめられる。
「使えるものは何でも使いたい」
「じゃあ俺たちにきくまでもないじゃん。リヒトの中じゃ、とっくに答えは出てるんだろ?」
タクミの言い分ももっともだけど、リヒトの性格上、高圧的に決めたくはなかったんだろう。こいつ、そんなこともわからないかな。
「さっきも言ったけど、僕はリヒトが決めたんなら、それでいいよ」
はなはだ主体性を欠くが、僕はリヒトに助太刀した。トモとサクヤもぼそぼそと同意した。
「俺も反対しないよ」
なぜかタクミは僕をにらんでいる。
「今まで通り、SNSでの拡散も続けてほしい」
「そっちは大丈夫」
「マコト先生はツイ廃だからな」
なんでそう突っかかるんだ。喧嘩したいのか?
きな臭い空気を察して、リヒトが僕に視線を送る。僕は喉元まで出てきた啖呵を飲み込んだ。
神経がすり減るようなミーティングはお開きになって、僕らは三々五々店を後にする。帰りかけた僕をリヒトが呼び止めた。
「タクミのことだけど」
「ん?」
「大目に見てやってくれないか。妬いてるんだ」
「妬いてる?」
「君には華があるから」
「冗談言わないでよ」
「自意識過剰も困るけど、無自覚なのも考えものだな」
リヒトは小さく笑った。
「『タブラ・ラサ』は、今最高の布陣なんだ。誰が欠けても駄目だ。腹の立つこともあるだろうけど、こらえてほしい」
リヒトにこう言われちゃな。
「わかってるよ。善処する」
リヒトの大きな手が、ぽんと肩に置かれた。
彼はさりげなく伝票をつかんで、立ち上がった。
「僕も払うよ」
「たまにはリーダー面させてくれよ」
本当にリヒトにはかなわない。
僕は苦笑すると、彼と一緒に雑踏の中へ飛び込んでいった。
人生初の取材は、ほどなくして実現した。と言っても、フリーペーパーに毛の生えたような代物だけど。
訪れたのは、僕らと同年代の若い女性一人だった。ナチュラルメイクとカジュアルなパンツの似合う、快活な子だ。
彼女は、リヒトに手の切れそうな名刺を渡して、ぴょこんとお辞儀した。
「『コスモポリタン』の矢萩です。よろしくお願いしまーす」
はきはきと小気味よく名乗る。
「こちらこそよろしくお願いします」
リヒトが矢萩さんにメンバーを紹介しようとすると、彼女はにこっと破顔した。
「あ、知ってます。あなたがベースでリーダーのリヒトさん。シンセのマコトさんに、ボーカルのタクミさん。ギターのトモさんに、ドラムのサクヤさん」
胸を張って彼女は宣言する。
「実は、今回の取材、言いだしっぺは私なんです」
「もしかして俺たちのファン?」
タクミがおどけて矢萩さんをうかがうと、彼女は真顔で「はい」と答えた。
「好きな曲ある? リクエストに応えちゃうかも」
「タクミ」
リヒトがやんわりとタクミを牽制する。
「んー、『ビーイング・アン・イリーガル・エイリアン』とか」
その曲はまずい。浮かれていたタクミの顔がこわばるのが僕にもわかった。タクミはそっけなく「そう」とだけ告げた。
「ビーイング・アン・イリーガル・エイリアン」は僕の曲だ。何が問題かって? この曲はタクミ抜きでも成立する。この曲のボーカルは僕なんだ。まあ、素では歌えないから、ボコーダー使うけど。あ、ボコーダーっていうのは、声を歪ませてマシン・ボイスみたいに加工できる機械のこと。とにかく、タクミが気に食わないのは間違いない。
急にまとわりつくのを止めたタクミの機嫌も知らず、矢萩さんはリヒトにこれからのスケジュールを尋ねている。
取材はリヒトに任せておこう。僕は機材の調子を確かめに、ステージの隅に置かれたプロフェット・ファイブに歩み寄ろうとした。
「マコトさん」
「はい?」
矢萩さんに突然話しかけられて、僕の声は見事に裏返る。振り返れば、満面の笑みをたたえた彼女がいた。
「お話、いいですか?」
ええ、と答えてタクミの方をチラ見する。やっぱりわかりやすくむくれている。
「さっき、リヒトさんに音楽のルーツを聞いてたんです。マコトさんのルーツも聞かせてください」
僕は天を仰いだ。先にタクミを済ませてくれたら、角が立たずに済むのに。でも、あからさまに矢萩さんにそれは言えない。僕はぼそぼそと質問に答える。
「えーっと、小さい頃はYMO聴いてました。その流れで、クラフトワークとか」
「テクノキッズだったんですね。だから『タブラ・ラサ』でも打ち込み系を?」
「はい」
早くタクミのところへ行ってくれという僕の願いも虚しく、彼女は質問を重ねる。
「おすすめのアルバムがあったら、教えてくださぁい」
「あー、アート・オブ・ノイズの『ジ・アンビエント・コレクション』」
「邦楽で何かありませんか?」
「トリムールティの『セントラル・ドグマ』とか」
「トリムールティ! 私も好きなんです!」
タクミだったら、これにかこつけて矢萩さんを口説いてたかもしれない。けど、僕はバンドのフロントマンの気分の風向きを気にするただのシンセ弾きだ。生返事でごまかしておいた。
矢萩さんはやっとタクミのところへ行ってくれた。
僕は胸をなでおろして、サウンドチェックを始めた。
今日のライブ、荒れなきゃいいけど。
僕の不安は膨れあがる一方だった。
「お願い! おーねーがーい!」
放課後、バス停につながる道で、カノンが盛大に頭を下げている。
「無理。ウチ、親が厳しいし」
「一緒にウチで勉強してることにすればいいし!」
「カノンの家は? 親は何にも言わないの?」
「ウチは平気! 放任主義だから」
私はため息をついた。
カノンのわがままは今に始まったことじゃない。カノンは息をするように他人を振り回す。しょっちゅう誰かに「お願い」している。
「なんで私なわけ?」
大きな目をくるくるさせてカノンは言った。
「だって、うららいつも音楽聴いてるし。そういうの好きかなって」
私の胸のあたりが、急に冷たくなった。
私の好きなバンドは、もうこの世界に存在していない。私の好きなひとも、もうこの世にいない。
「悪いけど、つきあえない」
ちょっと冷たすぎたかな。視界の端でカノンを見たら、泣きべそをかき始めた。
「うらら、ひどぉい」
こうなると手がつけられない。私も突きはなしきれない。カノンの「お願い」をきかないと、グループからハブられるかもしれない。
「わかったから! それで、いつなの? ライブ」
くるっとカノンは笑顔になった。
「来週!」
「何時から?」
「開場が六時半。開演は七時!」
「音源は? あるんでしょ? サブスクで聴ける?」
「まだインディーズだし、配信はないけど。なんで?」
「一応ライブ行くんだし、最低限の礼儀」
説明してもカノンにはわからないかな。
そんなこんなで、私は次の日、カノンからCDを借りた。「メメント・モリ」……何語だろ。
「タブラ・ラサ?」
よくわかんないまま、私はいつものCDウォークマンから、「ソウ」のアルバムを外した。
ボーカルのクセが強い。よく言えばエッジがきいてる。でも、私向きじゃない。
トリムールティの「シン」は、もっと低音で渋かった。「シン」の声に慣れた私には辛いものがある。
バックはそこそこ聴ける。ベースが歌ってるし、シンセかな、音がきらきらしてる。打ち込みも「ソウ」の音楽にどっぷりの私には好感が持てた。
私はぼんやりとそのアルバムを聴いていた。
今死んだら、「ソウ」と同じところへ行けるかな、なんて馬鹿なことを考えながら。
五分がたった。
不意にイヤホンから、ちゃかちゃかと気ぜわしい音があふれる。え、これ何?
かけっぱなしのCDだ。私が気持ちを立て直すより早く、鼓膜をマシン・ボイスがひっぱたく。
これはボコーダー? 「ソウ」も時々使ってた。ゆがんでるせいで、何歌ってるかはわからない。
幽霊曲だ。たまにアーチストが遊びで、クレジットに載せない曲をアルバムの最後に収録したりする。
私はスマホで「メメント・モリ ゴーストトラック」と検索した。
「ビーイング・アン・イリーガル・エイリアン」
曲名がわかったころ、耳元でマシン・ボイスが、「ハロー・ウィー・アー・『タブラ・ラサ』」と告げる。
びっくりした。でも、なんだかおかしかった。せっかくボーカルの人が歌いあげた世界観みたいなものが、最後の曲でぶち壊しになってる。なんか面白い。
来週のライブ、楽しもう。
私はちょっとスキップして、家路についた。
次の金曜日、私はカノンと待ち合わせて、ライブに出かけた。中間テストの点がイマイチだったせいで、親を納得させるのに時間がかかった。
「あれー、うらら、そのカッコ……」
私が着ているのは、地味地味なブラウスにジーンズだ。カノンはここぞとばかりに着飾ってる。動くたんびに、フリルがわさわさ揺れる。
「仕方ないじゃん、友だちのウチに勉強に行くって言ってんだから」
トモダチという単語に違和感を覚えながら言った。
「そっかぁ、残念だねー」
どうせカノンはすぐに忘れる。
私はあたりを見回した。やっば、同年代のコはほとんどいない。ゴスロリ、黒系、仕事帰りのスーツの人、まとまりのない客層だ。
「整理番号一桁なんだよぅ! タクミと目が合うかも!」
タクミ、タクミ……確かボーカルだ。
ライブハウスのスタッフが出てきて、入場列を作り始める。整理番号は5番と6番。最前列行けるけど、押されるのはイヤだなあ。
「最前、いくの?」
「あったりまえでしょ!」
「押されたりしない?」
「真ん中は結構激しいかも。押されるのイヤなら、ちょっと脇にズレてたらいいよ。リヒトさんとマコトさんのファンは、そんな激しくないから」
そう、と答えて、会場に入る。空っぽのステージに、無造作に機材が置かれてる。
私は下手に並べられてるシンセに気を取られた。
あれはプロフェット・ファイブだ。「ソウ」も使ってたビンテージ・シンセ。引き寄せられるように、私はその前に立った。カノンは真ん中、人が密集してる場所から動かない。
いったん、ステージのカーテンが引かれて、プロフェット・ファイブも隠れてしまった。少し心細い。そのまま、三十分ほどたった。
不意に周りが真っ暗になる。肌寒いのは、たちこめたスモークのせいだ。つめかけている女の子たちが色めきたつ。カーテンの向こうに、人の気配を感じる。
「タクミ!」
カノンが真っ先に叫んだ。それをきっかけに、めいめいがばらばらの名前を呼びだす。
カン、カン、カン、カン、と乾いた音が鳴る。
カーテンがさあっと引かれた。
光と音が、いっせいにあふれだす。
「こんばんは、『タブラ・ラサ』です!」
ステージの中央に、細身のオニイサンがいた。金髪で、うっすらとメイクしてる。あれがカノンの「推し」か。
私はなぜか冷静になって、正面に向き直った。誰があのプロフェット・ファイブを弾くんだろうって考えて。
鍵盤の向こうに、さらにやせっぽちのオニイサンがいる。黒髪、大きな目、ちょっとあどけなさの残る顔立ち。左耳だけにルーズリーフの金具みたいに、いっぱいピアスをつけてる。数えてみたら、七つあった。彼が長い指で鍵盤を叩くと、のびやかな電子音がフロアにこぼれる。小刻みに頭でカウントをとりながら、その人は機材に囲まれて忙しそうにしている。シルエットが「ソウ」に似ていて、涙が出そうになった。
いけない、楽しまなきゃ。
カノンの言ったとおり、ここはセンターほど殺気だっていない。でも、楽しもうとすればするほど、トリムールティのことが頭から離れない。
「ソウ」はもういないんだ。
わきたつオーディエンスの中で、私だけが下を向いて、沈みこんでた。
何が演奏されているのかもわからないまま、何曲かが過ぎた。
異変が起きたのは、ライブ中盤だった。
最初は、歌声がざらざらし始めただけだった。だんだんその声がつらそうになって、ついにボーカルが咳きこんだ。彼は急いでアンプの上のドリンクをあおったけど、ひび割れた声は戻らなかった。
上手にいるベーシストが彼に駆けよって、何か話してる。ボーカルは答えてるけど、首を横に振った。ベーシストがさらに早口で話しかける。それから逃げるようにして、ボーカルはステージから楽屋口に消えた。
今度はベーシストは、シンセ弾きに近づいた。一言くらい何か告げると、ベーシストも楽屋口に走る。
ステージにはシンセとギターとドラムが残された。どうなっちゃうんだろう、これ。
会場はどよめいてる。不安が周囲をおおう。
私はすがるように、プロフェット・ファイブ使いを見ていた。
彼は静かに、マイクのついた装置を引き寄せた。
底抜けに明るいトラックが闇に鳴る。この曲、覚えてる。「ビーイング・アン・イリーガル・エイリアン」だ。
マシン・ボイスが響きわたった。私の近くにいた女の子たちが、たちまち揺れる。話が違うよ、カノン。「激しくない」んじゃないの?
みんなが歌ってた。ステージのその人に合わせて。
彼がシンセから手を離した。両手を両耳の後ろにあてて、聞き耳を立てるみたいにした。とたんに、会場が大合唱する。
「ハロー! ウィー・アー・『タブラ・ラサ』!」
彼はにっこり笑って、ひとつ大きくうなずいた。ループする電子音を聴きながら、また鍵盤を叩く。
きらびやかな旋律がやんで、再びステージが静かになる。
「マコトさぁーん」
口々に彼の名前が呼ばれた。彼はガチャガチャとボコーダーのスイッチをひねりまわしてる。
「えー」
滑舌の悪い声が響く。
「ちょっと待ってください。タクミは少し休んでます」
「マコトさん、しゃべって!」
彼は面白いほど動揺していた。助けを求めるように、ギターとドラムの方を見る目が泳いでる。
ギターの人がほがらかに「マコト、話せ!」とはやしたてた。バスドラもドンドンと合いの手を入れる。彼はいっそう困った顔をした。
「あのー、もう少し待ってください……えっと、タクミは……」
この人、無理に話さない方がいいな。でも、私はなんだかとてもおかしくなっていた。同じプロフェット・ファイブを弾いていても、「ソウ」と全然違う。当たり前のことが、すごくあたたかい。
しどろもどろになっていた彼を助けるようにスポットライトが輝いた。その光は彼ではなく、舞台の中央を照らしている。
「タクミ!」
女の子たちの視線が真ん中に集まった。
すねたような表情のボーカルが、ステージに復活している。ベーシストにうながされて、彼はぴょこんとお辞儀した。ドラムのスティックが、私たちに考える暇も許さずに、カウントを取る。
私は、もう一度真っ正面を見た。
心底安心したようなシンセの人が、そこにいた。
「タブラ・ラサ」のマコト。
覚えておいてあげてもいいと思った。
手っ取り早いのは母に直接尋ねる方法だ。
でも、ご多分に漏れず、僕の家もディスコミュニケーション気味ときている。それに、よくあることだと思わない? 思春期の息子が両親を避けるってさ。
塾からの帰り道、僕は「ソウ」のことをどうやって調べようか思案していた。
ああそうだ。父が今度の中間テストのご褒美は何がいいってきいてたな。スマホ……は意外に鬱陶しいから、ノートパソコンにしよう。
都合良く子どもの顔を使い分けるのは、僕だけの特権じゃないよ。親だって、自分に得にならないときには、大人面しない。
駅前に若い女の子たちがあふれていた。
ふーん、ライブハウスか。「トゥデイズ・アクト……『タブラ・ラサ』」。名前だけは立派なバンドだな。意味わかって名乗ってるんだろうか。まあ、僕には関係ない。
勘違いしないでほしいけど、馬鹿にしているわけじゃない。むしろ羨ましいと思っている。バンドが? 違うよ。女の子たちの方だ。なぜか彼女たちにくらべて、僕ら男は意欲がない。仕事に生きるから? 詭弁だね。
雑踏を人にぶつからないように気をつけながらやり過ごして、いつもの電車に乗りこむ。疲れ果てた顔、顔、顔、うんざりだ。早く家に帰りたい。矛盾してる? そうだね。僕も疲れ果てた群衆の一部なのは認めるよ。
「ただいま」
もう十時だ。ご飯とお風呂を済ませて、調べ物してたら、十二時をまたぐな。
僕はぼんやり食事をとって、風呂に入った。ぼうっと「ソウ」のことを考えながら。
「ソウ」。本名は明かしていない。十年ほど前に、トリムールティというユニットだかバンドだかに在籍。トリムールティは五年ほど活動して、キャリアの最盛期に突然活動停止した。正確には今も「活動停止中」だ。ボーカルの「シン」とシンセサイザーの「アキ」と「ソウ」で構成されている。「シン」と「アキ」は、トリムールティの活動停止後、静かに音楽界から去った。「ソウ」だけが音を紡ぎ続けた。
彼の音楽性は幅広い。トリムールティの時代は、ダンスミュージックに近い曲も書いていたけど、ソロになってからはアンビエントやチルアウトに傾倒した。
僕が偶然出会ったのは、ソロ時代の曲だ。
残念ながら、彼は一年と少し前にこの世を去った。
もっと早くに出会いたかった。今思うのは、ただそれだけだ。
トリムールティの映像は動画サイトを検索すれば、それなりに残っている。でも、「ソウ」のソロはあまり評価されていないのか、公式サイトのものくらいしかない。
僕は貯金を切り崩して、オークションサイトでいくつか「ソウ」の音源を入手した。
何かにのめりこむのは生まれて初めての経験だ。危ういんだろうな。死者を追って、ネット漬けになるなんて。
本当に「ソウ」には生きていてほしかった。僕の前に未来を見せてほしかった。過去の亡霊を追わせないでほしかった。
ごめん。ただの愚痴だ。忘れてほしい。
僕がごねようがごねまいが、日はまた昇って明日は来る。学校だってある。のぼせる前に風呂を出よう。
僕は洗面所へ出ると、鏡の前で笑顔を作った。
多分、きっと明日も大丈夫だ。
「柚月くん」
圓総一郎くん。僕の唯一の友達。
彼はいつものようにおずおずと、放課後の僕に話しかける。長いまつげ、おとなしい物腰、まだ高い声。
「よう、オカマ。また『柚月くーん』か?」
「圓が誰と話そうが、彼の自由だろう。それに、今時『オカマ』なんて言ってたら、どこでもやっていけないのは君の方だ」
「こわいこわい」
きつい口調で釘を刺すと、同級生はすごすごと撤退する。ああいう手合いにはこれくらいでちょうどいい。
「ありがとう」
「事実を言っただけだよ。あんなの、ほっとけばいい」
「柚月くんは強いね」
「そうかな」
圓くんが感じる僕の強さは、大人社会に担保されたものだ。成績が良くて、従順な模範生。だから大人たちは僕に味方してくれる。まっとうなことをまっとうに主張するふりをしている僕に。
「あの、今日の数学の最後の問題だけど」
僕らの中学は普通クラスと特進クラスに分かれている。特進クラスは中学二年生の範囲をとっくに終えて、中三で習う二次方程式や幾何学に足を突っこんでいる。中三に上がれば、受験対策一本だ。この不毛な競争は、僕らが高校に上がっても続く。首尾良く目当ての大学に進学できたとしても、今度は就職のための勉強だ。資格試験に課外活動……それでやっと社会に出たとして、どうなるんだろう。終身雇用なんておとぎ話、とっくの昔にはやらなくなってる。
僕たちの行く手は暗い。
「柚月くん?」
「ごめん。最近寝不足で」
圓くんに言い訳しながら、大あくび。我ながら、無駄なことをしているのかもしれないと思っている。もういなくなった人間や、その周辺のことを調べまわっているだなんて。
特進クラスに行けば、さっき圓くんに暴言を吐いた馬鹿みたいなのはいないと思ったんだけどな。あいつ、名前はなんていったかな。覚えてない。まあ、群れを作れば必ず落ちこぼれはできる。
僕だって、もっと優秀な群れに投げこまれたら、今みたいに涼しい顔はしていられないだろう。僕の立場なんて、そんな危ういものだ。
「ソウ」はどうだったのかな。
二次方程式を解く僕のシャーペンの芯がぽきりと折れる。ほうけていた僕を、心配そうに圓くんがみていた。
「大丈夫? 疲れてない?」
大丈夫、と答えながら、僕は圓くんに視線を合わせる。彼こそ尊ぶべき人間だ。優しくて、他人のことを思いやれて、困っている人間を放っておけない。しばらくそうしていたら、照れくさいのか、彼はついっと目をそらす。
「ごめんね。もう帰ろうか」
終業のチャイムから三十分以上もたっていた。
帰っても家に鞄を放りこんで塾に出かけるだけだ。
でも、僕に他に行くあてはない。やることも、やりたいこともない。
逃げなのかもしれないな。
それでもいいんだ。
今は、今だけは「ソウ」のことを追わせてほしい。
ツナイデ。
確かにリヒトはそう言ってた。
つないで。意味がわかるのに時間がかかった。その間に、リヒトはタクミを追って楽屋口に消えた。
あとには僕とトモとサクヤが残された。
シンセとギターとドラム。何をするにも中途半端な編成だ。これでつなげって? 無理だ。MCするにしても、それはほとんどタクミの役目だったし、たまに喋るのはリヒトだった。
僕らはパニクってた。トモもサクヤも固まってる。
フロアがざわつき始めた。まずい。流れが止まる。
何とかできないのか? 僕は麻痺した脳で考える。指先が震えてる。
あ。
一曲だけある。今できる曲が。あの曲のオケはほぼ打ち込みだ。でも、やっていいのか? トモとサクヤをうかがうと、二人もきょろきょろあたりを見回しているだけだった。救援は望めそうにない。
僕は腹をくくってVAIOからシーケンスソフトにアクセスした。
同期プログラムを回せ。
頼む、回ってくれ。
ボコーダーを引き寄せる指はまだ震えている。
回れ……回れ……回った!
やたらポップで鮮やかな音が爆音で響く。永遠に感じられる数秒、鼓動が耳元で聞こえた。
「ビーイング・アン・イリーガル・エイリアン」。歌詞は適当に書いたデタラメな英語だ。僕はボコーダーに向かって必死で歌った。そのとき。
声が聞こえた。誰? 誰が歌ってるんだ?
オーディエンスだ。みんなが歌ってくれてる。僕の書いた、意味も何もないような言葉の羅列を。
胸が熱かった。僕の近眼でぼやけた視界に、たくさんのオーディエンスがにじんだように映る。ああ。
ありがとう。助けてくれて。
だからもっときかせてほしい。君たちの歌声を。
キーボードから指が離れた。
「ハロー! ウィー・アー・『タブラ・ラサ』!」
うん、これでいい。
いきなりトモが僕の脇腹をこづく。
「ちょっと、何?」
「『何?』じゃないよ!」
ライブがはねて、ステージにつながる楽屋口のカーテンが引かれた瞬間、トモとサクヤがにやにやと笑いだす。
「すっごい度胸」
サクヤが一言。
「今日のMVPはマコトで決まりだな」
僕は合点がいかずに首をかしげた。
「あんまり覚えてない」
「あれも覚えてないの? 『歌え!』ってやったやつ」
トモが両手を両耳の後ろにあてて、聞き耳を立てるようなポーズをとった。心当たりがない。首を横に振る。
「嘘だろ、おい」
「てっきり冷静だとばかり……」
「めちゃくちゃテンパってた」
覚えているのはそれだけだ。どうしようどうしようって思ってて、なぜかボコーダーのスイッチを切って、自分の間抜けな声で我に返ったところからしか記憶がない。
リヒトもにこにこ笑っている。
彼は僕に手を差し出した。握手? なんでだろう。わけのわからないまま手を取ると、ぎゅっとハグされた。それを遠巻きにながめているタクミの顔が蒼ざめているのが気になった。
打ち上げは終始変な雰囲気だった。普段饒舌なタクミは黙りこくって、トモとサクヤが盛んに僕に話しかけてくる。リヒトはいつものように、マイペースでビールを口にしている。
「お疲れ様です!」
お客さんに埋もれて取材していた矢萩さんが、大きなデジカメを首にぶら下げて現れた。
「一時はどうなることかと思いましたよ!」
「いい写真、撮れましたか?」
サクヤが矢萩さんに紙コップを手渡す。彼女は会釈するとウーロン茶を一気飲みした。
「はい、ばっちり!」
彼女が差し出した液晶画面には、僕がさっきのトモのポーズできれいにおさまっている。
「なに、これ」
「こいつ、テンパりすぎて、覚えてないんだって」
「またまたぁ」
今夜はいったいなんなんだ。
「じゃ、俺は先に帰るわ」
そう言えば、目立ちたがりのタクミがおとなしいな。
「喉」
リヒトがタクミに声をかける。
「医者に診てもらっておけよ」
タクミはあいまいに返事をすると、夜の街に消えた。
「僕も帰ろうかな」
「マコト」
リヒトが焼きたてのDVDディスクを僕に手渡した。
「今日のライブ。ちゃんと見ておいたほうがいい」
僕らのバンドは、毎回記録用のデジタルビデオカメラを回している。なんで今回に限って、打ち上げでディスク渡すのかな。次のミーティングでもいいのに。
リヒトの真意が気になった僕は、帰宅してすぐにそれをチェックしたのだが。
「最悪……」
僕が作業場で悶絶したのは言うまでもない。
今更ながら、顔から火が出た。恥ずい。
ライブの後はいつもツイッターでつぶやくんだけど(タクミが僕のことをツイ廃だと言ってたのは本当だ)、どんな神経でつぶやけばいいんだ。それでもツイ廃の悲しさで、「本日はご来場ありがとうございました」とだけつぶやいたら、即座にリプがたくさんぶら下がって、いたたまれなくなった。習慣になってる自己検索も、とてもじゃないができたもんじゃない。
頭を冷やそう。
僕は眼鏡をかけて、サブ機のディスプレイに向かった。
久しぶりに「ソウ」のサイトにでもアクセスするか。
古いパワーブックのトラックパッドに指を這わせ、ブックマークを探し当てる。こいつとも長い付き合いになっちゃったな。大分型落ち感は否めないけど、この頃のアップルのセンスは良かったな、なんてぼやきながら。
「ルナティック・シンドローム」
僕は何も考えずに、ブックマークをコンコンと人差し指でダブルタップした。
見慣れた風景が立ち上がるはずだった。
でも。
404 NOT FOUND
あれ。
スマホ、調子悪いのかな。昨日まではなんともなかったのに。
私は「ルナティック・シンドローム」のページを上から下へスワイプした。やっぱりダメだ。謎のメッセージが画面で頑張ってる。
屋上でクリームパンと牛乳をかわりばんこに口にして、しばらく格闘した。他のページは表示されるんだけど。
これって、「ソウ」のページだけなのかな。
試しにユーチューブに飛んでみる。ごちゃごちゃとサムネがひしめきあういつもの絵が表示された。
まあ、いいか。きっとちょっと待てば戻るし。
私はユーチューブの検索ボックスに、「SOW」と打ち込んだ。いくつか動画が浮かびあがる。
私はまだ気づいていなかった。
その謎のメッセージの本当の意味に。
昼休みの終わりのチャイムが鳴る。
じゃあね、「ソウ」、またあとでね。
「あとで」なんて、私はとことんのんきだった。
見慣れないエラーメッセージにデスクトップパソコンが占拠された。
僕は息を吸ってF5キーを叩く。エラーは居残ってる。
キャッシュクリア。これでも直らないな。回線の問題だろうか。
いつも使ってるグーグル検索は生きてる。回線の不具合じゃないな。
「404 NOT FOUND」で検索してみる。
「クライアントの要求に対応するページが既に存在しないことを意味する」エラーコードだって?
ゆっくり頭で三度考える。そして、僕は理解した。
「ルナティック・シンドローム」はもう存在していない。
心臓がいったん冷える錯覚にとらわれて、そのあと全身の血が逆流しているのかと思えるほどのめまいに襲われる。
消えた? 「ソウ」のホームページが?
待ってくれ。まだ消えないでくれ。
もっと彼のことが知りたいんだ。
手の甲に涙が落ちる。僕はひとりすすり泣いた。
午前四時。
僕は一睡もできなかった。あれからずっと、パワーブックの画面は404エラー表示のままだ。頭の中からなにもかもがはじけ飛んでた。僕が僕であることさえ。
来るべきときがきただけなのかもしれない。「ソウ」が不在では、いつまでもホームページを保てないのかもしれない。
でも、今じゃないだろ?
僕は「ルナティック・シンドローム」を削除した誰かに猛抗議したかった。
今「ソウ」の痕跡を消してしまったら、僕らはどうやって彼にたどり着けばいいんだ?
こわかった。そりゃ、僕と彼とじゃ格が違うけど、同じミュージシャンを名乗るものとして、あまりにあっけなく彼と彼の音楽が消し去られるのがたまらなかった。
彼がいなくなってから一年とちょっとだ。まだ僕らには、いや、少なくとも僕には彼が必要だ。
なんで「ルナティック・シンドローム」を記録しておかなかったんだろう。けど、たとえそうしていたとして、彼が緩慢な死を迎えるのを食い止められるか?
答えはNOだ。
彼がこの世を去った瞬間から、風化は始まってる。人の記憶なんてそんなものだ。
音楽なんてそんなものだ。
僕の心を雲が覆う。あの「ソウ」でさえ消えゆくんだ。まして、僕なんか。
いつの間にか立ち上がって、狭い部屋をうろうろしていた。落ち着け。落ち着くんだ。
何か彼を残す方法はないのか?
またパワーブックを前にして、ない知恵をしぼる。
あてもなく機械的にキーボードを叩く。「SOW」だとか「TRIMURTI」だとかとりとめもなく。公式が消えたばかりだから、まだ検索エンジンには「ルナティック・シンドローム」が浮かびあがってくる。あとは、オークションサイトとか、ファンアートだとか……
ファンアートか。
そうか、「ソウ」は僕らの心の中にまだ生きてる。
あんまりうまいやり方じゃないけどな。
僕はとあるサイトを訪れて、行動を開始した。
おかしいって気づいたのは、三日もたってからだ。
いつまでも「ルナティック・シンドローム」から意味不明な文字が消えない。
アタマよくない私でもわかる。何かがヘンだって。
私はスクショを撮って、同じクラスの小林って男子に見せることにした。ホントは、あんまかかわりたくないんだけど。小林って、典型的オタクっていうか。
「ちょっと顔貸してくれる?」
私が声をかけたら、眼鏡の裏までテカテカな小林が、さらにテカテカしてる。
「何かな、中瀬くん?」
妙な期待してるんじゃないだろうな。うー、ヤだなあ。
「これ、何かわかる?」
さっさと切り上げよう。私はスマホの画面を小林の鼻先に突きつけた。
「404エラーがどうしたの?」
「そんだけじゃ意味わかんない。もっとわかるように説明しろ」
小林が眼鏡を直す。かっこつけんな。
「端的に言うと、『お探しのページは存在しない』ってことになるかな」
「存在しない……」
すうっと教室の風景がフェイドアウトした。
え、どういうこと? 存在しない? ないってこと?
「三日前まではあったの! いい加減なこと言うな!」
私は気力をふりしぼって小林にどなる。
「三日『も』前じゃねえ」
小林が何を言っているのか、私には理解できなかったし、もしできたとしても、理解したくなかったと思う。
「ふざけんな!」
そのとき、私は小林じゃない誰かをどなりつけたかったんだろう。
こんなにかなしいのは二度目だ。
また「ソウ」が消える。私の目の前から。
あのときと同じ、ううん、それ以上の痛みが体の中をかけぬける。ある日突然「ソウ」が消えた日。いつもと同じ毎日がこなくなった日。
ぽろぽろと涙がこぼれた。
晴れた日の朝、ホームルームの後、私は泣きつづけた。
「悟、塾は?」
母がドアの向こうで呼んでいるのが聞こえる。
「気分が悪いから休む」
大丈夫、とおざなりな質問が飛んだけど、僕の耳には入らなかった。僕はベッドにもぐりこんでた。
たかがホームページと思うだろう。だけど、僕にとってはそれが彼の大半だった。「ソウ」は既に鬼籍の人となり、情報はほとんどホームページに蓄積されていた。動画、過去のライブ、彼の言葉……失われたものはあまりに大きい。
籠城を続けていたら、知らないうちに日が暮れていた。寝入ってしまったらしい。あたりはすっかり暗い。
僕はのろのろとベッドから這いでた。新興住宅地の夜はひどく静かで、静かすぎていて、自分の足音が聞こえた。ぺたぺたと素足が不快な音を立てる。
デスクトップパソコンはリビングの隅に置かれてる。
もう「ルナティック・シンドローム」はない。
わかっているのにパソコンを起動する。半ば習慣で、僕はブックマークフォルダをダブルクリックする。
「404 NOT FOUND」
何度更新しても、その文字列は消えない。
どうすればいいんだ。
どうすれば、また「ソウ」にたどり着ける?
記憶の断片を求めて、気がつけばユーチューブにいた。無意識に「SOW」と叩いて、いくつかの動画を確認する。公式に埋め込んでた動画もユーチューブ使ってたからな。ここはまだ存在している。水たまりに巣くったボウフラのように、僕はそこに留まりつづけた。クリックするたびに、馬鹿みたいに明るいネットCMが流れて、そのあと「ソウ」がいつものように演奏を始める。
一通り動画を再生し終わったら、また最初から始める。僕はループの中に閉じこもってた。
でも、どこかでわかっていた。いつまでもここにいてもどうしようもないってことが。CMが始まるたびに、否応なく現実がのしかかってきて、僕の首筋をちりちりさせる。
どこか。ここではないどこか。
まだ「ソウ」の存在している世界はないのだろうか。
僕はあてもなく電信の海をさまよいつづけた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
