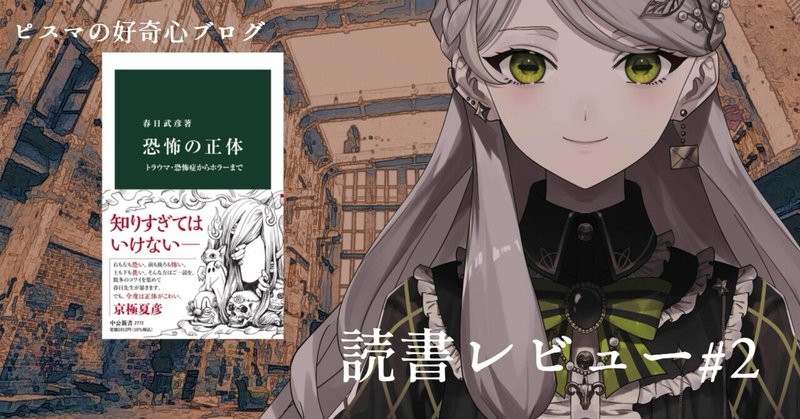
【読書レビュー②】春日武彦「恐怖の正体」
こんばんは。PisMaです。
本日も「恐怖の正体」の続きを読んでいきます。第2章「恐怖症の人たち」。
第1章にて恐怖症の人について触れましたが、今回はそれの深掘りになります。
恐怖症。架空の危機感から発生する恐怖。
恐怖症は多種多様で、学術用語になっているだけでも200は超えるのだとか。
雨、笛、万物、毛、色。人はすべてのものに恐怖を覚えることが可能だといえますね。
この書籍の著者は重度の甲殻類恐怖症なようで、システマチックなところが生物のように感じないとか、外骨格はあんなにも硬そうなのに、中身がぷにぷにしているところも気持ちが悪い。如何にして甲殻類が気味が悪いか、どう生理的に受け付けないかを熱弁していました。
特別なきっかけがあってもなくても発症することがある点などを、集合体恐怖症の話も交えながらさまざまな恐怖症の事例を取り上げられていました。
閉所恐怖症やパニック障害の記述では恐怖症が発動する状況や公式があり、状況が揃えば揃うほど悪化していくようでした。
最後の人形恐怖症では大きめな人形と何日も一緒にいた人がおかしくなってしまい、「対象との距離感をうまく取ることができず人と人形の関係性が崩れてしまう」という考察で締め括られています。
「距離感を測れなくなって関係性が崩れる」というのはなるほどと思いました。あまりにも近すぎると、その大きな人形と自分の境界が分からなくなり、恐怖につながる。距離を保つことで、自分とそれ以外の輪郭を認識できるのだと思います。
また甲殻類恐怖症の著者が「甲殻類はどこが受け付けないのか」を書いていましたが、あまりにも具体的に甲殻類のここがよくない!というのを何例も書くので、もはや興味があるの類に足を突っ込んでいるようで大変興味深く拝読いたしました。
私に特徴的な恐怖症は無いのですが、少しだけ先端恐怖症と怒られること恐怖症があるような気がします。目の近くに尖ったものを見つけると急いで撤去したり、怒られる可能性がある事柄について1日中ずっと考え込んでは心臓がドキドキしていたりします。
本日はここまで。
「怒られるかもしれない」という恐怖は立派な恐怖症になるのか。次の章もゆっくり読んでいきたいと思います。
お相手は黄緑の魔女PisMaでした。
恐怖の根源はどこかな。
ご機嫌よう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
